澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、「賃料増額請求における事情変更の法的根拠と実務ポイント」について、詳しくご説明します。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。
登録はこちらから
![]()
所有する賃貸物件の賃料が、契約当初から据え置かれたままで、そろそろ増額したいと考えるオーナー(賃貸人)は少なくありません。しかし、お客様である賃借人にとっては思わぬ負担であり、なかなか合意が得られないものです。
建物の賃料の増額若しくは減額については、借地借家法32条に規定されています。
本記事ではオーナーが増額請求する場合に、どのような事情があれば増額を求められるのか、増額請求の進め方について解説していきます。
解説動画 : 賃料増額請求は法的にどう進める?基本的な流れを弁護士が解説!
賃料増額請求の「事情変更」とは

借地借家法32条では、経済的な事情変化を理由とした建物の賃料の増額や減額を認めています。(※なお、借地権については借地借家法11条。)
条文上、以下の2つの条件を満たしている場合に請求することが認められます。
②一定期間、賃料を増額しない旨の特約がないこと
特に①の、契約締結時の状況から経済的な事情が大きく変化していることが重要です。
また、②の賃料を増額しない特約があっても、例外的に賃料増額が認められるケースもあります。
従来通りの契約内容を無理に継続すると、当事者間の公平が害されるほどに事情が激変している場合、たとえ前回の合意から時間がそれほど経過していなくても、増額が認められる可能性が大きくなります。
このように、事情変更の有無が増額請求には大きなポイントとなります。
賃料が不相当となった場合には、当事者の合意により、新しい適正額の賃料を決定します。
法的には口頭でも構いませんが、実務上は証拠が残るように内容証明郵便にて通知するのが一般的です。
合意がまとまらなければ、裁判所にて調停や訴訟の手続きにより決定します。
賃料増額請求の基本的概念
賃料増額請求とは経済的な事情が変更したことにより、現在の賃料では経済的に不相当となった事情を抱えた場合に、賃貸人が賃借人に対して賃料の増額を求める請求です。
法律上、賃貸人が賃借人に賃料増額の意思表示をした日から、増額した適正額を請求したものとみなされます。
他方、賃借人から減額請求を求めた場合も同様です。
不動産の賃貸借契約は、長期間にわたる契約も多いです。時間の経過に伴い、物価や税金の上昇・下降など、経済事情の変動が予想できます。
賃貸借契約時の賃料が適正額より低い場合、そのまま無理に賃貸借契約を続けると賃貸人としての経済的利益が得られず、他方で賃料が適正額より高い場合には賃借人の負担が重くなり、当事者間に不公平が生じてしまいます。
そこで借地借家法では、契約期間中であっても経済的な事情変更による賃料の増額もしくは減額の請求をお互いの権利として認めています。
法律上の事情変更の定義
借地借家法32条では、以下の3つの要素を事情変更の例として示しています。(※なお、借地権については借地借家法11条。)
- 土地または建物に対する租税その他の負担の増減
- 土地または建物の価格の上昇または低下その他の経済事情の変動
- 近傍同種の建物の借賃と比較
このように例示された3点等を含め、当事者間の具体的事情を総合的に判断し、従前の賃料を維持することが公平か否かという見地から、賃料が不相当となったといえる場合に、増額請求または減額請求が認められます。
ただし、この3点はあくまで例示であり、この要素があるだけで直ちに増減の請求が認められるわけではありません。これらの要素以外の諸事情が検討されることもあります。
具体的には、契約締結の経緯や建物の条件(商業用か居住用など)、当事者の個人的な関係性などを総合的に考慮して判断されると考えられています。
不相当性の判断要素
先述の通り借地借家法32条で例示された以下の3つは、賃料の不相当性の判断要素として重要です。
- 租税その他の負担の増減
- 土地や建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動
- 近傍類似の賃料水準との比較
これら3つはあくまで例示的なものですが、租税等の必要経費といえる負担の増大により賃貸人としての純利益が著しく減少しているような場合や、開発が進み急激に周辺の土地や賃料が上がったことで相対的に賃料が安くなったといえるような場合は、従前の賃料が不相当になったものと考えることができます。
不相当と認められた場合には、適正賃料の範囲内に是正して相当といえる新しい賃料を決定していきます。
公平性の観点
不相当性の判断における当事者間の公平は、賃貸借契約という継続的な取引の安全が期待できるか、賃貸人と賃借人のお互いの利益を保護できるかという意味で捉えて差し支えありません。
とはいえ、何を理由に「公平」とするのかは判断が難しいところです。ただ、少なくとも賃料の増減額請求においては主観的に考えるのではなく、客観的基準に基づいた請求が必要です。
事情変更が認められる具体的な理由

これまで、賃料の増額請求が認められるには、経済的な事情の変更により、賃料が不相当になっていることが条件であると解説してきました。
現在の賃料のままでは、賃貸人の純利益が激減してしまうほどの支出や負担の増加があると証明するための具体例をこれまでの判例等にもとづき、経済指標も含めて、詳しく解説していきます。
租税その他の負担の増減
賃料増減請求が認められるための要素のひとつとなる「土地または建物に対する租税その他の負担の増減」における「租税」として、固定資産税や都市計画税などが挙げられます。
また、「その他の負担」とは、建物の使用に伴う必要費用を指し、管理費や共益費という名目になっていることが多いです。具体的には、火災保険料や維持修繕費、点検費、空室等の損失を補填する費用などが挙げられます。
この点、ビルの修繕積立金の増額を「その他の負担の増減」に該当するとし、賃料の増額を認めた裁判例があります。
ビル全体の老朽化に伴う大規模修繕のために、従前の3倍相当の修繕積立金を各区分所有者から徴収した件について、その修繕積立金は当該建物を賃貸するための必要経費であるとし、「その他の負担の増減」に該当すると判断しました(東京地判平成29年12月7日)。
土地または建物の価格の上昇・低下
そもそも賃料というのは、土地や建物の価格に期待利回りを乗じた金額(純賃料)に必要経費を含めて決定します。そのため、土地や建物の時価の変動は当然、賃料に大きく影響することとなります。
土地・建物の価値が変動した場合をそれぞれ考えていきます。
上昇の場合には、現在の賃料では市場価値に対して安すぎるとして、増額請求が活発となります。低下の場合には反対に、現在の賃料では価値に対して高すぎると判断され、減額請求が多くなります。
土地の評価方法は、公示地価や路線価など国が発表する価格や、近隣の類似した土地での取引事例を参考にした方法、土地から得られる賃料収入を参考にした方法が用いられます。
建物にも同様の評価方法が用意されており、これらの客観的な数字を参考にして賃料へと反映されます。
その他の経済事情の変動
「その他の経済事情の変動」は土地や建物の価格以外の経済的な変動を指しています。
具体的には物価指数、国民所得、通貨供給量、賃金指数といった指標です。
指標の数値だけで賃料額の決定の決め手となるわけではありませんが、賃料が不相当といえるかどうかの参考として役立てられています。
この点、新型コロナウイルスとそれに伴う経済情勢の悪化は、賃料の減額請求の際の事情変更といえるかどうか争われた事案がありました。
当該事例で裁判所は、借地借家法に基づく賃料減額を相当とすべきような恒久的な経済事情の変動に該当するかについては疑問がないとはいえず、対象建物の価格や物価・地価が中長期的に下落したとは認められない等とし、賃料増額請求を認めませんでした(東京地判令和3年9月30日)。
物価指数や国民所得の変動
物価指数、特に消費者物価指数(CPI)は賃料を決定する際に参考となる指標です。
たとえば、消費者物価指数が上昇した場合には増額請求、下落すれば減額請求の根拠に使われる傾向にあります。
また、国民所得(NI、国民の所得の総額)も賃料の増減額請求の根拠の1つであり、国民所得が上昇すると賃料が上昇する傾向となり、賃料の増減請求が予想できます。
通貨供給量や賃金指数の変動
通貨供給量とは、経済全体に流通するお金の量を指し、物価や家賃にも影響する指標です。
一般的に供給量が増えると、物価が上がり、それに伴い賃料の増額も活発になると予想できます。
賃金指数とは、個人の収入や支払能力に影響しています。
支払能力に応じて賃料も変動していくものと考えられているため、賃金指数が数%上がれば、それに応じた賃料の増額も考えられます。
新型コロナウイルス感染症の影響
コロナ禍による経済的悪化を理由に賃料減額を求めた事案があります。
しかし、裁判所は、コロナ禍による経済的悪化は建物や地価、物価の中長期的な下落の要因とまではいえず、事情変更に当たらないと判断しました。
コロナ禍は経済的な事情変更が発生したといえるほどの長期的な事情とは言えず、現行の賃料が不相当に高額になったとまで認めるのは難しいという結論に至ったのです。
「事情変更」と認められるためのポイント
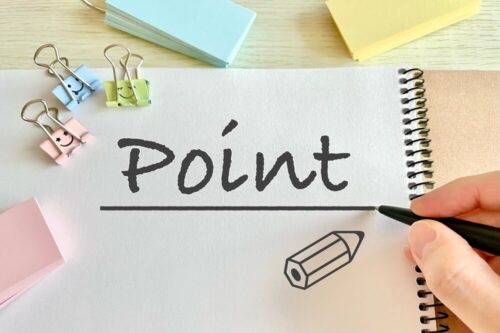
事情変更があったと認められるためには、具体的にどの程度の変更が必要と考えられるでしょうか。
目安としては、周辺の賃料相場との差額が20~30%ほど差が付いているようであれば、事情変更として認められるケースが多いようです。ただし、物件の特徴や契約内容を個別に見ていく必要があります。
周辺の賃料相場との差の程度
賃貸借契約の対象となっている建物と、付近にある類似の建物や地域全体の賃料相場などから導き出される本来あるべき相当な賃料と差がある場合、従前合意した賃料が「不相当となったとき」(事情変更があった)と認められる場合があります。
本来あるべき相当な賃料は、大まかにいえば近隣の相場を参考にします。近隣の相場は、付近の類似の建物や地域全体の賃料相場から導き出されます。付近の類似の建物と比較する場合には、比較対象として相応しい物件であるかという点から証明する必要があります。
建物の構造、用途、階数や南向き、北向きといった位置関係、居住面積といった様々な要素で考えなくてはなりません。また、物件の用途が商業用か居住用かは重要な要素となります。
乖離率の目安(20%・30%基準)
賃貸借契約を締結する際、当事者は不動産市況等により賃料の相場がある程度変動することは想定した上で賃料の合意をしているはずです。そのため、一般的には、少なくとも10~20%の差がなければ、賃料増減額請求の行使は認められないものと考えられています。
過去のバブル期やリーマンショックの際の価格変動は、20~30%を超える価格変動がありました。
この2つの時期では賃料に大きな影響を与える程度の変動を記録したため、それ以降20~30%という乖離は賃料の増減額請求が認められるかどうかの目安として考えられるようになりました。
ただ、2~3%程度の増減であっても増減額請求を認めた裁判例もあります。そのため、単純な数値だけにとらわれていません。
乖離率がそこまで高くなくとも賃料が不相当と認められるだけの事情がないか、当事者と物件の特徴も含めて個別に判断する必要があります。絶対的な基準ではなく、あくまでも目安、参考の1つとして考えます。
物件用途による判断の違い(商業用・居住用)
では、物件の用途によって乖離率の目安は異なるのでしょうか。
この点、収益を目的とする賃貸借であれば20%ほど、居住目的の賃貸借であれば30%ほどが目安になると考えられています。
もちろん、当事者と物件の状況等、個々の事情によって前後するので個別に検討していく必要があります。
裁判例にみる事情変更の認定
事情変更の認定基準や判断の傾向について、実際にあった2つの裁判例から考えていきます。
いずれの裁判でも、現在の賃料が不相当であり、相当賃料と乖離しているという点を客観的証拠によって立証しなければなりませんでした。
東京地判平成19年7月26日の事例
裁判所による鑑定の結果、相当賃料は約3.3%減額となる月額6850万円が認められました。
3.3%という数値だけ考えれば、賃料改定が認められるほどの変動といえませんが、裁判所は、借地借家法32条について、賃料の著しい変動がある場合にのみ賃料の改定ができるものと制限しているわけではないと判断したのです。
東京地判平成22年12月7日の事例
裁判所は、通常であれば賃料が不相当といえる状態であり、賃料増額請求が認められるとしつつ、この事案では、賃貸借契約において賃料改定について「著しく不相当となったときは、改定することができる」と加重されていたため、適正賃料と現行賃料の差がいまだ「著しく不相当となったとき」とはいえないとして、賃料増額請求を否定したのです。
本件では、現行賃料額と適正とされた賃料額には、月額44万6000円、年間にして535万2000円の差額があり、賃料が「不相当となったとき」の要件は満たすものの、「著しく不相当となったとき」の要件を満たしていないと判断されたのです。
事情変更の認定に必要な実務上の視点

事情変更の認定を受けるためには、下記のような視点・理由に注意する必要があります。
② 直近の合意時点からの変化の必要性
③ 物件ごとの特性と個別の事情の考慮
要するに、「現行の賃料が、相当といえる賃料と比べてどれだけの差があるのか」を客観的に証明する必要があります。
厳格なチェックが求められますので、抜けがないようにひとつひとつ見ていきます。
近くの似た物件との賃料比較の方法
近傍類似の賃料とは、近隣の類似した賃貸事例における賃料という意味です。面積や用途ができるだけ近く、同じ区内の何件かの物件を見つけて比較して、賃料を算出します。
できるだけ正確に比較するためには、賃料だけではなく、敷金や管理費、駐車場代など、賃料以外の条件も含めて判断しなければなりません。不動産鑑定評価書等を用意することも考えられますが、データは最新のものであること、事情変更が認められるだけの根拠を充分に用意する必要があります。
なお、単に近傍類似の賃料相場より対象物件の賃料が高かったり安かったりするだけで賃料増減額請求が認められるというわけではありません。「直近合意時点」以降の「事情変更」により、従前合意した賃料が事後的に不相当になっていることが必要である点、注意が必要です。
直近の合意時点からの変化の必要性
賃料増額請求は、「直近合意時点」以降の事情変更により、賃料が不相当になっていることが必要です。つまり、最初の契約締結時点から近隣の相場よりも割安な賃料で合意している場合には、後から近隣の相場よりも割安であることを理由とした増額請求は認められません。
最後に合意をした時点から、経済的な事情変更により増額が必要だと判断されなければなりません。
物件ごとの特性と個別の事情の考慮
通常、賃料の適正額を考慮する際には、一般的な不動産の市況が参考にされます。しかし、例外的に特殊な事情が考慮されるケースもあり、個別の事情を見ていく必要があります。
具体的には、立地や築年数、設備等の物件の特性によるものです。中には用途や中途解約に制限がかかっている物件なども存在します。
用途の制限と社会的事情の重視
通常、事情変更というのは税その他の負担や、土地・建物の価格の上昇など一般的かつ経済的な理由によります。しかしながら、稀に用途制限がある物件においては、当該用途についての社会的な事情の変動を重視するケースもあります。
たとえば病院やクリニックなどの建物の賃貸借では、用途が医療・福祉関係に限定されていたり、比較的長期間の契約しかできず、中途解約には大きな制限が課せられていたりする場合があります。
このような場合、一般的な地価・建物価格の上昇などといった事情より、当該用途についての社会的な事情の変動が重要となる場合があるのです。
老人ホーム運営の事例にみる判断例
裁判所は、建物の使用目的が老人ホームの運営等に限定され、中途解約等の場合には違約金が必要とされ、さらに賃借人の事業を、賃借人の負担で、賃貸人が指定する業者に引き継がせる義務があるなど、賃借人からの契約解消は制限されていたことから、借地借家法32条に定められているような一般的な不動産市況に関わる事情の変動よりも、老人ホームの経営に係る社会的な事情の変動を重視すべきであると判断しました。
当該地域での老人ホームの運営が、時代の変化で契約締結時よりも競争が厳しくなっているという背景を経済的な事情変更として認め、賃料が不相当に高額になったとしています。
賃料増額請求における事情変更の主張と立証
増額請求では多くの場合、賃借人からの合意が得られないことが多いかと思われます。このような場合、賃料増額請求について、裁判所の利用を検討しましょう。
ただし、原則として、いきなり訴訟を起こすことはできません。
まずは調停を申立て、調停の場での話し合いを通じて解決を目指します。調停手続の中で、当事者双方から鑑定結果に従う旨の同意書をとった上で相当な賃料額の鑑定申請をすることもあります。この場合、鑑定の結果に従う形で紛争は解決します。
しかし、調停での解決が見えない場合、調停を不成立として終わらせるか、調停に代わる決定がなされます。調停に代わる決定は、当事者から異議がなければ確定し、紛争は解決しますが、異議があれば紛争は解決しません。
調停不成立または調停に代わる決定に異議が出た場合、紛争を解決するためには、訴訟を提起することになります。
事情変更の立証責任は誰にあるか
民事裁判での立証責任とは、原則として請求を通すために訴えを起こす側(原告)が負うものです。つまり、増額を求める場合は賃貸人、減額を求める場合は賃借人が原告となって立証責任を負います。
それ以外には増額と減額に違いは特になく、共通の手続きで進めます。ただし、立証のハードルが高く、希望の額まで増額(または減額)が認められるだけの根拠を示さなくてはなりません。
実務上、当事者間で何度も増減額請求で揉めており話し合いによる解決が困難で、最初から訴訟による解決を視野に入れて調停を申し立てているケースも多く、合意が成立する例は少ないとされています。
合意賃料と相当賃料の差をどう示すか
ここで、従前に合意した賃料と、希望する相当賃料までの差を裁判でどう示すかが重要となります。
まずは、賃料相当の算出方法を決定する必要があり、以下の方法が一般的です。
- 利回り法
- 賃貸事例比較法
- スライド法
- 差額配分法
実務では、複数の方法を組み合わせています。近隣の土地・建物ではどのような方法で賃料をいくらと算出したのか、データをよく収集する必要も出てきます。
増額請求では当事者がそれぞれ不動産鑑定士に不動産鑑定評価書の作成を依頼し、評価書に基づき、適正賃料を主張することが多いです。元々の賃料が高い場合や、増額の幅が大きくなるような場合には、最初の時点で不動産鑑定士に依頼することをおすすめします。
不動産鑑定評価の活用方法
不動産鑑定評価書は、事情変更の立証において重要な証拠となります。裁判所に増額請求が認められるほどの賃料の不相当性と事情変更を、正確な知識や情報に基づいて説得力のある鑑定書を作成することが大切です。
なお、不動産鑑定士同士で意見が分かれるような事案も多いため、注意が必要です。
当事者が不動産鑑定士に依頼して作成する鑑定評価について、根拠となる情報やその相当性や合理性などによって不動産鑑定評価書の証拠としての価値が変わってきます。裁判になった場合、原告及び被告双方から鑑定評価書が提出されることも多く、その場合、裁判所によって詳細に合理性が判断され、裁判所による鑑定の結果等も併せて、相当賃料額を認定することが多いです。
不動産法務に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで
賃貸人が個人で増額請求をするにしても、希望通りの金額へ引き上げることは難しいことが多く、賃借人との信頼関係、ひいては今後の賃貸借契約を続けるために慎重な対応が求められます。
そこで、不動産分野を取り扱える弁護士に相談することが大切です。調停や訴訟になった場合にも、代理で手続きを進めることが可能です。また、信頼できる不動産鑑定士との連携も期待できます。賃料が高額で、契約内容が複雑であるほど、正確な知識を持つ弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】【関連記事】
賃料を上げたい大家必見!家賃値上げの正当理由と交渉術
賃料増額請求における「直近合意時点」の重要性と判断基準
賃料増額請求の必要書類は?根拠資料の種類や選び方・交渉戦略を解説
直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。
その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。
アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。

