澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、「賃料増額請求における調停不成立後の訴訟対応と実務ポイント」について、詳しくご説明します。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。
登録はこちらから
![]()
賃貸物件のオーナーとして、収益性の向上を目指し、賃料増額交渉に臨んだものの、賃借人との折り合いがつかず、途方に暮れていませんか?「交渉が平行線」「内容証明を無視された」など、オーナー様の悩みは尽きません。
法律に基づいた賃料増額請求が認められる場合があり、最終的には訴訟という選択肢も存在します。賃貸経営の安定を図るために、正しい選択を見つけていきましょう。
賃料増額請求の基本|借地借家法32条のおさらい

土地建物への税負担の増減、土地建物価格の上昇その他経済事情の変動により賃料が不相当となった場合や、近隣の同種の建物と比べて賃料が不相当になった場合は、賃料増額請求を行うことができます(借地借家法32条1項)。
条文上、以下の2つの条件を満たしている場合に請求することが認められます。
- 経済的な事情変更により、現在の賃料が適正額と比べて不相当となっていること
- 一定期間、賃料を増額しない旨の特約がないこと
特に、1の契約締結時の状況から経済的な事情が大きく変化していることが重要です。
また、2の賃料を増額しない特約があっても、例外的に賃料増額が認められるケースもあります。
従来通りの契約内容を無理に継続すると、当事者間の公平が害されるほどに事情が激変している場合、たとえ前回の合意から時間がそれほど経過していなくても、増額が認められる可能性が大きくなります。
このように、事情変更の有無が増額請求には大きなポイントとなります。
また、当事者の思うままに賃料額を決めていいわけではありません。賃料増減額請求が認められるのは客観的に「相当」な賃料額です。そのため、賃料増減額請求における対立では、「相当」な賃料額がいくらかが主な争点となります。「相当」な賃料額について、入居者との合意が得られない場合、最終的に調停や訴訟という手段を検討することになります。
この「相当」な賃料額は、物件の価値、周辺地域の相場、市場動向などに加えて物件の特性や個別事情も総合的に考慮して判断されますが、裁判でどのような点を重視して相当な賃料額を認定しているのかを確認し、必要な資料を収集して適切な手法を用いて増額する賃料を算定することが重要です。
当事者間で合意できない場合は裁判所が判断
賃借人と賃貸人双方で、増額幅等について合意できない場合、最終的に裁判所に判断を仰ぐことになります。裁判所は、不動産鑑定士による鑑定評価書、特に裁判所が選任した不動産鑑定士の鑑定評価(裁判所鑑定)を参考に、相当な賃料を決定することが多いです。
交渉・調停を経て訴訟へ|手続の流れを確認

賃料増額請求は、法的根拠に基づいて行う必要があることを理解し、適切な手続きを踏み、増額の根拠資料等を揃えて説得力ある交渉を進めることが重要です。
賃料増額請求の手続きは、以下の4つのステップで進みます。
① 増額請求の通知(内容証明等)
賃料を増額したい場合、オーナーはまず入居者に賃料増額請求の意思表示を通知します。
賃料増額請求の効果は、賃料増額請求の意思表示が相手方に到達した時点に生じます。
そのため、いつ、誰に、何を通知したかを証明することができる配達証明付内容証明郵便を使うのが一般的です。このような形で通知することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
② 任意交渉
通知を送った後、オーナーは入居者と直接話し合いをし、賃料増額についての合意を目指します。
この段階では双方の理解を深め、納得のいく条件で合意に達することが理想です。この段階で合意できれば、裁判になるのを避けることができ、調停・訴訟の費用や時間・労力も節約できます。
③ 賃料増額調停 (任意/裁判所)
任意交渉で合意できない場合、次のステップとして調停に進みます。
調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければなりません(調停前置、民事調停法第24条の2第2)。
そのため、原則として賃料増額請求の訴訟は調停を経た後でなければ提訴できません。
調停は、調停主任裁判官と民間人から選任される2名の民事調停委員から構成される調停委員会の仲介によって当事者間のトラブルを話し合いで解決する手段です。
賃料増額請求の場合、賃料増額請求などに詳しい専門家として弁護士1名と不動産鑑定士1名が民事調停委員に選ばれることが一般的です。その調停委員である不動産鑑定士が、簡易的な鑑定を行い、専門的な立場で意見を述べることもあります。
④ 調停が不成立の場合 → 訴訟提起
もし調停でも合意ができず調停が不成立となった場合、最終手段として訴訟に進むことになります。
訴訟では裁判所が証拠をもとに賃料の妥当性を判断します。
この段階においては、当事者が依頼した不動産鑑定士による不動産鑑定評価(当事者鑑定)が証拠として提出されることも多いです。双方から提出された場合には、双方の鑑定評価に対して反論や裁判論がなされます。そして、裁判所が選任する不動産鑑定士による不動産鑑定評価(裁判所鑑定)がなされると、多くのケースでこれを基準とする判断がなされます。
調停不成立の意味と法的効果
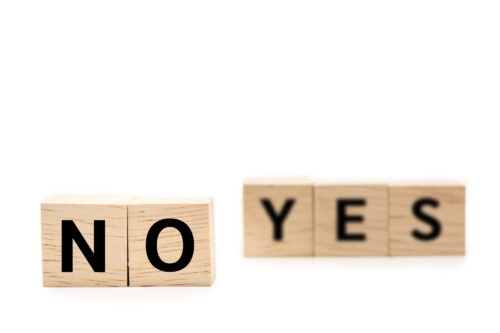
賃料増額請求の調停が不成立となるのは、賃借人と賃貸人の主張が平行線をたどり、調停委員の尽力にもかかわらず、合意に至らなかったような場合です。
民事調停法14条では、調停委員会は調停が成立しないものとして調停事件を終了させると定められています。
調停不成立は、当事者の権利義務に直接的な影響を与えるわけではありません。つまり、賃料増額請求権そのものが消滅したり、賃借人が賃料を支払わなくてもよくなるわけではありません。
しかし、調停不成立は、賃料増額請求の権利を行使するための次のステップを踏む必要があることを意味します。
調停不成立後は、賃料増額を請求する側は、訴訟提起という選択肢を取ることができます。
民事調停法19条では、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起した場合、調停を申し立てたときに訴訟提起があったものとみなされるとされています。
これらの点を、以下で詳しく解説していきます。
調停不成立の定義と終了プロセス
調停不成立は、調停委員会が調停が成立しないものとして調停事件を終了させることをいいます。
調停委員会の試みと不成立の判断
調停委員会は当事者間の意見や提案を検討し、仲介を試みますが、合意の可能性が見えないと判断した場合には調停不成立を宣言します。
調停不成立の要件
① 当事者間に合意が成立する見込みがないこと、又は、成立した合意が相当でないと認められること
(ア) 合意が成立する見込みがない場合
・ 当事者の双方又は一方が説得に応ぜず、その態度が強固で、期日を重ねても合意が成立する見込みがない場合
例) 賃料の増額を求めるオーナーと、これを拒否する賃借人の間で、要求や条件に大きな隔たりがある場合、両者が各自の立場を譲らなければ、合意形成が非常に難しい状態となります。
・ 当事者の双方又は一方が調停期日に出頭しないため合意が成立する見込みがない場合
(イ) 成立した合意が相当でない場合
・ 合意の内容が法律や条理等に照らし違法又は著しく妥当性を欠き、調停員会が承認しえないような場合
② 裁判所が17条の決定をしないこと
調停委員会の調停が成立する見込みがない場合に、相当と認めるときには裁判所が調停委員の意見を聞き、当事者双方のために公平になるよう、職権にて当事者双方の申立ての内容に反しない限度で、解決のための決定を行うことができます。これが「調停に代わる決定」で、「17条決定」ともいわれます。
③ 調停条項の裁定の合意がないかあっても申立てがないこと
調停委員会は、当事者同士の話し合いについて合意が成立する見込みがない場合、もしくは成立した合意が適正でないと認める場合で、当事者間に調停条項に服する内容の書面による合意があるときには、申立てによって解決のために適当と思われる調停条項を定めることができます。そして、この調停条項は裁判上の和解と同じ効力があります。
ただ、賃料増額請求の調停申立ての時点で訴訟に発展することを視野に入れているケースも多く、「調停条項の裁定」が利用されるケースはあまりありません。
終了プロセス
民事調停法第14条及び民事調停法施行規則第22条1項によると、調停委員会が状況を考慮し、成立の見込みがない旨を判断した場合、調停事件を終了させます。
調停が不成立となった場合、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
なお、調停の不成立については、不服申し立てをすることはできません。
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
引用:e-GOV法令検索|民事調停法(調停の不成立)第十四条
法第十三条若しくは第十四条(これらの規定を法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了したとき、又は法第十八条第四項の規定により決定が効力を失ったときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
引用:裁判所|民事調停規則
このように、調停が不成立となった場合、賃料増額請求の権利を行使するための次のステップとして、当事者は訴訟を選択することが一般的です。
2週間以内の提訴によるみなし効果
調停不成立の後、2週間以内に訴訟を提起した場合、「みなし効果」が発生します。
これは、民事調停法第19条に基づく法的効果で、訴訟が調停申立時に提起されたものとみなすというものです。
賃料増減額請求に関するみなし規定は、以下の2つの実益があります。
① 消滅時効の完成を阻止
訴訟提起には、消滅時効の完成を阻止する効果があります。
賃料請求権は、発生から5年で消滅時効が完成しますが、訴訟を提起することで、時効が中断され、権利が保護されます(民事調停法19条)。
例えば、賃料請求権について、2020年4月以降の民法改正では、一般消滅時効として発生を知った時から5年で消滅しますが、2週間以内に提訴すれば、時効の完成を防ぐことができます。
ただし、改正前の民法による場合は調停不成立から1か月以内に提起すれば時効を中断でき(改正前民法151条)、改正後の民法による場合は調停不成立から6か月以内に提訴すれば時効は完成しないものとされている(民法147条)ため、訴訟提起によるみなし効果の実益はあまりないかもしれません。
なお、賃料増額請求と時効の関係については別記事にて解説しておりますので、是非ご参照ください。
参照 : 「賃料増額請求と消滅時効~改正民法で変わる適用基準と対応策~」
② 訴訟手数料の減額
調停申立て時に納付した手数料を、訴訟提起の手数料に充当することができます(民事訴訟費用等に関する法律5条1項)。
第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
引用:e-GOV法令検索|民事調停法(調停不成立等の場合の訴の提起)第十九条
調停不成立後の訴訟提起の実務ポイント

調停が不成立となった場合、訴訟提起という新たな段階に入ります。
以下では、スムーズに訴訟を進めるための重要ポイントを説明します。
消滅時効の完成と訴訟提起の関係
調停申立や訴訟提起により消滅時効の完成を阻止したい場合に注意すべき点を説明します。
なお、賃料増額請求と時効の関係については別記事にて解説しておりますので、是非ご参照ください。
参照 : 賃料増額請求と消滅時効~改正民法で変わる適用基準と対応策~
賃料請求権の消滅時効
まず、賃料増額請求に関して消滅時効が問題となるのは、増額分の賃料が支払われておらず、長年経過したような場合、賃料増額請求によって増額した分の賃料請求権についての時効消滅です。
賃料請求権の消滅時効は、2020年4月1日の改正前の民法では5年とされていましたが、改正によって「権利を行使できることを知った日から5年」もしくは「権利行使をできるときから10年」となりました(民法166条1項)。
ただ、賃貸借契約によって賃料の支払時期が決められており、賃貸人がそれを知らないことは考えられないため、基本的には賃料の支払時期限から5年で時効が消滅すると思ってよいでしょう。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用:e-GOV法令検索|民法(債権等の消滅時効)第百六十六条
訴訟提起と時効完成の阻止
改正前の民法では、時効の完成前に訴訟を起こせば時効が中断することになっていました。
改正後は消滅時効が完成する前に訴訟を提起することで、訴訟継続中は時効の完成が猶予され、訴訟にて権利関係が確定すれば、消滅時効が更新されます。
賃料増額請求における差額分の賃料の時効を阻止するための訴訟としては、差額分の賃料の支払を求める訴訟だけでなく、一定期間以降の賃料増加を確認する訴訟でも問題ありません。
調停による時効完成の阻止
さらに、調停についても調停係属中は時効の完成が猶予されます。
調停不成立後の訴訟提起による時効完成の阻止
また、調停不成立の場合に、時効完成を阻止するために訴訟を提起する必要があります。
改正前の民法151条では、調停不成立から1か月以内に訴訟を提起すれば、時効が中断し、完成を防ぐことができます。
2020年4月から施行された民法改正後の147条では、調停不成立から6か月以内に提訴すれば時効は完成しないものとされています。
これにより、調停不成立後の訴訟提起までの期間が長くなり、より慎重かつ準備を整えて対応できるようになっています。
訴訟提起期限内対応の重要性とリスク
期限内に訴訟を提起することは、消滅時効の完成を防ぎ、賃料請求権を保全するために不可欠です。
訴訟提起は時効を中断する効果があるため、賃貸人の権利を守るために期限管理が非常に重要です。
もし期限内に訴訟を提起しない場合、消滅時効が成立する可能性があり、賃料請求が法的に認められなくなるリスクがあります。このため、訴訟提起は早めに準備を進め、期限内に確実に行うことが求められます。
訴訟提起の期限を守ることは、法的権利を維持し、債権者としての地位を守るために重要です。
訴訟提起時の手続きと必要書類
調停不成立後の訴訟提起に関しては、次のような手続きや必要書類の準備をすることが重要です。
① 訴状の作成
訴状とは、請求内容や法的理由、証拠書類を明記した文書です。訴状には、当事者双方の氏名・住所等、請求の趣旨や原因等を詳しく記載します。
② 必要書類の準備
ケースによって必要書類は異なりますので、状況に応じた必要書類の判断が難しい場合には弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらいましょう。
調停が不成立であることを証明する書類です。これを取得することで、調停を経た上で提訴したことを示すことができます。
また、この書類により2週間以内の提訴であることがわかれば、調停申立時に納付した手数料を訴え提起の手数料に充当できます。
・ 証拠書類
賃料増額に関する裏付けとして、(あれば)不動産鑑定書、過去の賃料支払い履歴、契約書等を用意します。
・ 手数料納付に関する書類
調停申立時に納付した手数料の転用に関する証明書類も必要になります。場合によっては手数料算定のため固定資産評価証明書が必要になります。
・ 資格証明書
法人が当事者であれば代表者事項証明書
③ 訴訟提起手続き
訴状と必要書類を裁判所に提出します。この際、法定の手数料や郵便切手を納付しなければなりません。
手数料の流用方法
調停不成立から2週間以内に訴訟を提起することで、調停申立時に納付した手数料をそのまま訴訟提起時に流用することが認められています。
このため、実質的に訴訟提起の手数料が減額され、二重の負担を避けることができます。
具体的には、調停不成立証明書を取得し、手数料転用の手続きについて裁判所側で確認を取ります。
実務上の対応
調停不成立の場合、速やかに行動することが推奨されます。
✓ 調停不成立証明書の取得
調停終了後、直ちに書記官室に行き、調停不成立証明書を請求しその場で発行を受けます。この書類がないと、訴訟手続きを円滑に進められない場合があります。
✓ 訴訟提起の準備
訴状の作成や必要書類を整え、2週間以内に提出することを目指します。
✓ 手数料や郵便料金の確認
調停時に納付した手数料に関わる確認事項があれば、裁判所の担当窓口で確認し、適切に手続きを進めます。
手続きの流れを理解し、適切に対応することが、調停不成立後のスムーズな対応に繋がります。
訴訟で何が争点になるのか?主張・立証のポイント

賃料増減額請求の訴訟における主な争点は、増額請求した賃料額が相当であるか否かです。
そして、当事者間で継続している賃貸借関係において生じるべき相当の賃料額を継続賃料といいます。
これは、過去に賃料の合意がされた事情を踏まえ、現時点における賃料を算定するものであって、単に現在の適正な賃料を求める新規賃料と異なるものです。
継続賃料の算定方法には、賃料増額の根拠となる要素としての消費税の導入や不動産価格変動などを踏まえた「差額配分法」「利回り法」「スライド法」「賃貸事例比較法」の4つがあります。
また、国土交通省も「不動産鑑定評価基準」において、この4つの方法を用いて計算することと合わせ、「賃貸借契約の締結や賃料改定の経緯などの事情を総合的に考慮して算定すること」としています。
不動産鑑定士は、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準に従って、継続賃料の算定をすることができる専門家です。継続賃料の算定は非常に専門的で専門家である不動産鑑定士以外の者が行うのは困難です。そのため、裁判所はこの継続賃料について不動産鑑定士の鑑定評価に重点を置いて審理をすすめます。
鑑定評価書の提出
不動産鑑定士による鑑定書は、相当な賃料額を客観的に示す証拠として非常に効果的です。
鑑定評価書は、不動産鑑定士が国土交通省が定める基準に沿って、専門家の視点から市場分析や物件評価を行った結果として作成されるため、その信頼性は高いとされます。
裁判所はこの鑑定書を参考に、賃料の妥当性を判断する材料とします。
なお、鑑定については別記事にて解説しておりますので、是非ご参照ください。
参照:「賃料増額請求の鍵を握る不動産鑑定評価の基礎知識」
その他の資料の例
・ 路線価図、固定資産税評価証明書
租税公課の変動を示すなどによって、前回賃料について合意した時点から経済的な事情が変動したことを示すことができれば、増額が必要な根拠を示すことが容易となります。
税金等は賃借人が直接負担するわけではないものの、維持コストが増えたと主張することで理解を得られやすいと考えられます。
・ 宅建業者に現在募集をかけている物件の資料やチラシ、相場が分かるデータ
「近傍同種の賃料相場との比較」による賃料増額請求となった場合には、これらを用意する方法が最も手軽です。
・ 総務省統計局が出している消費者物価指数 (CPI)
物価の変動を示す指標です。従来の賃料が、物価上昇や物件の維持費にかかる費用に対して割安であることを証明できます。
・ 国道交通省が発表している地価公示データ
地域ごとの土地の価格の変動が把握できます。
これらの主張と立証を通じて、裁判所に対して賃料変更の正当性をしっかりと説明することが求められます。このプロセスは訴訟の中で賃料増額を成功させるために決定的な役割を果たします。
証拠は、可能な限り詳しく、鑑定書や相場資料などの客観的かつ信頼性があるものを揃えることで、賃貸人としての主張を強固なものにできます。
オーナーが訴訟を起こすメリット・デメリット
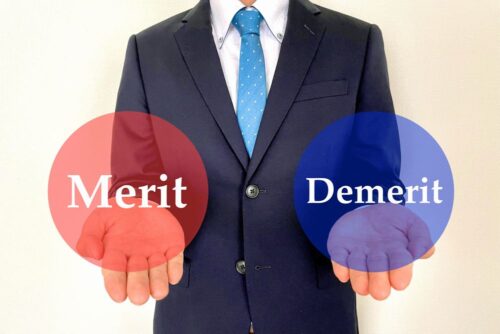
オーナーが賃料増額請求の訴訟を起こす際には、いくつかのメリットとデメリットが存在します。
これらを踏まえて、慎重に判断することが求められます。
メリット
・ 裁判所の判断を受けられる (強制力)
訴訟を通じて、裁判所による公正な判断を受けることができます。
裁判所は、中立的な立場から証拠や主張を検討し、相当な賃料額等を判断します。
裁判所の判決は法的な強制力を持つため、請求が認められれば、賃料増額請求によって求めた賃料額での支払いを求めることが可能になります。
・ 未払い分についての確定判断が得られる
賃料増額請求の効力が生じた時点から判決までの間に未払いとなっている賃料についても、裁判で請求をしていれば、裁判所が最終的な決定を下すため、認められれば未払い分を回収する確定した法的根拠を得ることができます。
デメリット
・ 時間と費用がかかる
訴訟手続きは通常、時間がかかります。また、訴訟費用や弁護士費用、不動産鑑定費用などの金銭的コストも負担となります。
・ 賃借人との関係悪化リスク
訴訟を起こすことで、賃借人との関係が悪化する可能性があります。
特に、長期的な賃貸関係を維持したい場合には、慎重に考慮する必要があります。
・ 判決までの支払われる賃料額は「従前額」の場合が多い
訴訟中は、改訂賃料が認められるまで賃借人が従前の賃料しか払ってくれないケースが多いです。
そのため、収入面での不安定要因となる可能性があります。
借地借家法32条2項では、賃料増額請求について当事者の協議が調わないときは、裁判が確定するまで、相当と認める額の賃料を支払えば足りるとされており、相当と認める額の賃料は少なくとも従前の賃料額とされています。
そのため、原則として賃借人は従前の賃料額を支払っていればよいことになっているのです。
しかし、賃料改定が認められた場合、未払い分の賃料について賃借人は年1割の利息を付して支払わなければなりません(借地借家法32条2項ただし書き)。
そのため、判決が確定して実際に未払賃料の回収ができるまでは減収しますが、確定した場合には年1割の利息がついて支払われることになるので、これを含めてメリット・デメリットを考える必要があります。
まとめ
訴訟を起こすことは、法的に明確な解決策を得るためには非常に効果的ですが、必ずしも最善の手段ではありません。コストや時間、関係性への影響など多くの側面を考慮する必要があります。
最適な判断を行うためには、交渉や調停といった他の解決手段とも比較検討し、トータルでの利益と損失を慎重に計算することが重要と言えます。
また、専門家である弁護士や不動産鑑定士の意見を取り入れながら、状況に応じた最良の方針を決定することも重要です。
訴訟に必要な準備と証拠の整え方

訴訟を通じて賃料増額を求める際には、資料を収集することや、専門家のアドバイスを求めるなどの綿密な準備が重要です。
以下では、準備を検討すべき資料について具体的に解説します。
鑑定書 ・ 近隣相場表 ・ 改修履歴 ・ 地価変動資料
・ 鑑定評価書
不動産鑑定士による鑑定評価書は、専門的な視点から算出された継続賃料(相当な賃料額)を証明する重要な資料です。裁判所は、鑑定評価書を客観的かつ信頼性のある証拠として重視します。
ただし、コストがかかるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
・ 近隣相場を示す資料
周辺地域の類似物件の賃料相場を示す資料を用意します。これにより、要求する賃料が市場において妥当であることを示すことができます。
・ 改修履歴
物件の価値を維持または向上させるために行った改修があれば、その履歴を用意します。
これにより、物件維持のための投資を示し、賃料増額の正当性を補強することができます。改修内容、時期、費用などを具体的に記録し、費用を証明する領収書を保管しておきます。
・ 地価変動資料
地価の変動に関する情報を提供できる資料です。
周辺地域の地価の上昇は、賃料の適正価格の引き上げの必要性を主張することができます。
賃貸借契約書 ・ やりとりの記録 (メール・通知書)
・ 賃貸借契約書
これまでの賃貸借契約の内容を確認し、契約条件、賃料額、更新条件などの確認資料として使用します。
契約書に一定期間建物の家賃を増額しない旨の特約がある場合は原則として賃料増額請求ができない(借地借家法32条1項ただし書き)ため、このような特約がないことを示す資料ともなります。
・ 賃借人とのやりとりの記録(メール・通知書)
賃借人との間で行われた賃料変更に関する連絡の記録を準備します。
メールや内容証明郵便による通知書などを示すことで、交渉履歴や相手方の対応を明示し、主張の根拠を強化します。
訴訟は、主張を証拠によって立証していくため、しっかりと準備をすることが重要です。
これらの証拠を準備して有効に活用することで、賃料増額要求の合理性と適正性を裁判所に効果的に示すことができます。
よくある質問(Q&A)

Q1. 賃料増額請求後、賃借人が増額分の賃料を払わない場合、遡って請求できますか?
過去に支払われなかった増額分の賃料についても遡って請求することは可能です。
賃料増額自体に賃借人が納得していない場合、調停や訴訟で賃料改定の確認を求めることになりますが、その際にあわせて未払い分の賃料の請求もするのが一般的です。
ただし、消滅時効が完成している場合、賃借人が援用すれば請求できないので、時効にかからないよう行動することが重要です。
賃料改定が認められた場合、未払い分の賃料について賃借人は年1割の利息も支払わなければなりません(借地借家法32条2項ただし書き)。
交渉段階でも、賃借人にこのような点を説明して早期の未払いの増額分賃料の支払いを求めるとよいでしょう。
Q2. 裁判に負けたらどうなりますか?
裁判で敗訴した場合は、賃料の増額が認められないことになり、従前の賃料のままになります。
ただし、賃借人が同じ訴訟で賃料減額の確認を求め、減額が認められた場合には賃料が減額する場合もあります。
また、敗訴の場合には裁判費用の一部または全額を負担する可能性があります。ほかにも、賃借人との関係が悪化するリスクもあります。
さらに、控訴・上訴をする場合にはさらなる費用と時間がかかります。
Q3. 少額でも訴訟する価値はありますか?
少額の賃料増額でも、原則的には訴訟を起こすことは可能です。
少額であっても、賃貸借契約が将来的にも長期に及ぶ可能性がある場合、積み重なれば大きな金額になるため、費用をかけても訴訟をする意味がある場合もあります。
ただし、時間、労力や費用の負担があることは否めず、また、賃借人との関係が悪化する可能性があることなどを総合的に考慮する必要があります。
不動産法務に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで
賃貸増額請求の訴訟は、交渉が難航し、調停でも合意に至らなかった場合に選択される手段です。訴訟では、裁判所が証拠や主張を検討し、適正な賃料を判断します。
訴訟を有利に進めるためには、不動産鑑定士による鑑定評価書や周辺の賃料相場についての資料などの客観的な証拠を準備することが重要となります。
また、訴訟は時間と費用がかかるため、適切な準備をした上で手続きを進めることが大切です。訴訟は、オーナーにとって最終的な手段となるため、慎重に判断する必要があります。
適切かつ効果的な準備をし、円滑に手続きを進めるべく、賃料増額請求を検討する場合は早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】【関連記事】
賃料増額請求の弁護士費用~相場と抑える方法を徹底解説~
賃料増額請求における調停前置主義の意味や根拠・実際の注意点を解説
賃料増額請求の調停完全ガイド~手続きの流れから結果による対応まで~
直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。
その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。
アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。

