澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、「賃料増額請求と消滅時効~改正民法で変わる適用基準と対応策~」について、詳しくご説明します。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。
登録はこちらから
![]()
賃料増額請求権を行使したものの賃借人が従前の賃料しか支払ってくれない場合、増額賃料分の請求権は原則として各増額賃料の支払時期から5年で消滅時効にかかります。
消滅時効が完成し、賃借人がこれを援用した場合には、増額分の賃料を請求できなくなるため、消滅時効期間の考え方や計算方法について知っておくことが大切です。
今回は賃料債権の消滅時効について詳しく解説するとともに、具体的な増額賃料の請求権の時効に関する事例も紹介しますので、賃料収入のある不動産を所有しており、これから賃料増額請求を行おうと思っている人や既に賃料増額請求をしたものの、賃借人が従前の賃料しか払ってくれないまま放置してしまっている人はぜひ参考にしてください。
賃料増額請求で「時効」が問題になるケースとは?
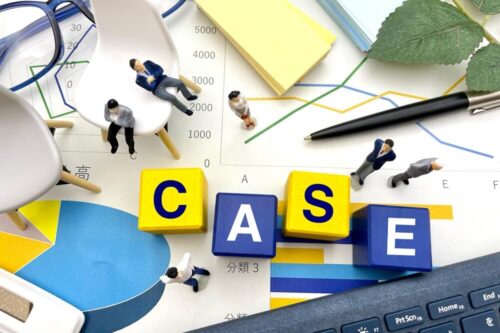
実際に、賃料増額請求をしたものの、賃借人が従前の賃料しか支払ってくれず、協議も進まないまま何年も経ってしまったが、いままでの賃料増額分を請求できるのかといった相談はよくあります。
賃貸人としても、従前の賃料が支払われているため、ついつい増額賃料の請求を後回しにしてしまいがちなのです。そしていざ、増額賃料を請求しようとしたとき、問題になるのが時効です。
なお、賃料増額請求権自体が時効で消滅するということは考えられません。
賃料増減額請求は、建物の賃料が不相当になった場合、賃貸人または賃借人のうちどちらか一方が、もう片方に一方的に賃料増減額請求の意思表示をすることで賃料の増減ができる権利であり、意思表示が相手方に到達した時点で「相当」な額において賃料が増減したという効力が発生するものだからです(借地借家法32条1項)。
改正前民法と改正後民法の時効期間の違い
2020年4月1日改正前の民法では、一般の債権の消滅時効は10年、商事債権は5年とされていました。ただ、賃料債権については、定期給付債権(1年または1年よりも短い期間で定めた金銭その他のものの給付を目的とする債権)として扱われ、5年間という「短期消滅時効」が定められていたのです。
そのため、賃料債権については、一般の債権および商事債権を問わず、請求できるときから5年が時効という認識でした。
2020年4月1日改正後は短期消滅時効の考え方がなくなり、賃料債権は一般の債権として取り扱われます。
なお、一般の債権の場合の消滅時効の考え方は以下のとおりです。
- 権利を行使できることを知った日から5年
- 権利行使をできるときから10年
このように、一般の債権の時効については5年もしくは10年の消滅時効が設定されていますが、賃料債権については賃貸借契約によって賃料の支払時期が決まっており、賃貸人がそれを知らないことは考えられないため、基本的には賃料の支払時期限から5年で時効が消滅すると思ってよいでしょう。
賃料債権の消滅時効の起算点
賃料債権の消滅時効は、前述のとおり、通常は「権利を行使できることを知った日から5年」です。
では、賃料債権の消滅時効の起算点は、いつなのでしょうか。
賃料債権の「権利を行使できる」のは、一般的には各月の賃料の支払時期です。そして、契約で賃料の支払時期が定められていれば賃貸人は支払時期を知っているはずなので、各月の賃料支払時期当日が「権利行使できることを知った日」になります。
しかし、民法140条にて「消滅時効の期間の計算において、初日は算入しない」と定められているため、消滅時効の起算点は、支払時期の翌日になります。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
賃料増額請求を行っても入居者が従前の賃料しか払ってくれない場合、増額分の賃料について、各月毎の支払時期の翌日から、当該月の増額分の賃料債権の消滅時効が進行していきます。
賃料増額請求と時効の関係
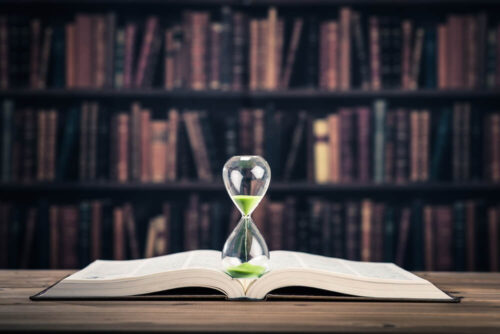
このように、増額分の賃料請求権は基本的に5年で時効消滅します。そのため、増額分の賃料を請求するためには、支払時期の翌日から5年以内に法的措置を講じなければなりません。
時効直前になって慌てることがないように、賃料増額分の請求についての法的措置を講ずる予定を立てておくことが大切です。
その際の法的措置としては、次に説明するような時効の完成を阻止する制度も利用します。改正後の民法の適用基準と合わせて理解しておきましょう。
時効完成を阻止する制度
改正前の民法では、時効の完成前に訴訟を起こせば時効が中断することになっていました。
改正後は消滅時効が完成する前に訴訟を提起することで、訴訟継続中は時効の完成が猶予され、訴訟にて権利関係が確定すれば、消滅時効が更新されます。
賃料増額請求における差額分の賃料の時効を阻止するための訴訟としては、差額分の賃料の支払を求める訴訟だけでなく、一定期間以降の賃料増加を確認する訴訟でも問題ありません。
さらに、調停についても調停係属中は時効の完成が猶予されます。また、調停不成立の場合に、時効完成を阻止するために訴訟を提起する必要がありますが、その訴訟提起までの期間について、改正前の民法では調停不成立から1ヶ月以内となっていたものが、改正後では6ヶ月以内に延長されています。
また、催告(裁判外での請求)を送り、それから6ヶ月以内に訴訟を起こすことでも、時効の完成猶予を(改正前であれば時効の中断)ができます。
催告は、どのような内容でいつ配達されたかが重要となるため、一般的には配達証明付内容証明郵便で行います。
催告文 (内容証明) の例
賃料の増額請求後の差額分賃料の支払について
令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇ー〇〇〇〇〇県〇市〇区〇丁目〇番〇号〇室
〇〇 〇〇 様
〒〇〇〇ー〇〇〇〇
〇県〇市〇区〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇 印
私は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に締結した賃貸借契約書に基づき、貴殿に対し下記物件を居住目的として賃料〇〇万円(1ヶ月)で賃貸しております。
しかし、近年の物価上昇や固定資産などの税負担増加もあり、近隣の類似の借家と比較しても、本賃貸契約の賃料を増額するのが妥当だとの判断に至り、貴殿に対して賃料増額請求を行い、貴殿はその通知を〇〇年〇〇月〇〇日に受領しました。
その結果、賃料を〇〇〇〇年〇〇月分から〇〇万円(1ヶ月)に値上げしております。
しかし、現在にいたるまで、値上げ分の賃料について支払いがありません。
貴殿におかれましては、〇〇〇〇年〇〇月分から〇〇〇〇年〇〇月分までの値上げした分の賃料各月〇〇万円をお支払いくださいますよう、お願いいたします。
記
物件:〇県〇市〇区〇丁目〇番〇号〇室
なお、入居者(賃借人)が増額分の賃料の支払の猶予を求めたり、一部だけ支払ったような場合、債務を承認したことになり、時効が更新されます。
時効の更新とは、これまでの時効期間の経過が無意味となり、新たに時効が進行することをいいます。賃料債権について消滅時効が完成した後に承認があった場合も、その時効の完成がなかったことになり、承認の時点から新たな時効が進行します。
また、賃料債権について時効が完成していた場合でも、相手が時効を援用しなければ、裁判所は当賃料債権が時効消滅したという裁判をすることができません。
時効の援用とは時効の利益を受けるという意思の表明であり、裁判所は、当事者が時効の援用をしなければ、時効に基づいて裁判することができないとされています(民法145条)。
そのため、相手が時効を援用していない場合は、相手がそのまま時効を援用しない可能性や、債務の承認をする可能性に期待して、時効期間が経過した分の賃料も請求することも検討しましょう。
改正民法の適用基準
増額分の賃料請求をする場合の消滅時効については、改正前の民法が適用される場合と、改正後での民法が適用される場合があります。
具体的には賃貸借契約の締結時期が2020年3月31日以前なら改正前の民法、2020年4月1日以降なら改正後の民法が適用されます。
2020年3月31日以前に締結した賃貸借契約を2020年4月1日以降に法定更新などにより入居者の合意なしで更新した場合、改正前の民法が適用され続ける点に気をつけましょう。ただし、2020年4月1日以降に再契約された場合や当事者の合意による更新がなされた場合、自動更新条項による更新などの場合は、改正後民法が適用されます。
冒頭のQ&Aのように、2018年4月1日に締結された賃貸借契約が2年ごとに自動更新されている場合、2020年4月1日に自動更新がされ、この時点から改正後民法が適用されます。とはいえ、消滅時効については、前述のとおり改正前でも改正後でも通常は支払時期から5年と考えられます。
賃料増額分の請求と時効の具体例
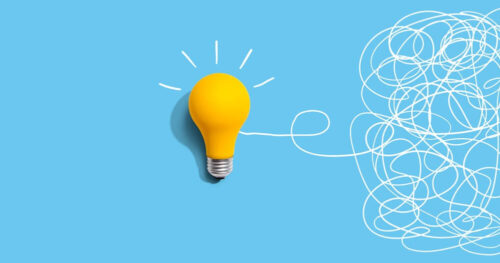
賃料「増額」請求の場合
2010年4月1日に賃貸借契約が締結され、その後3年ごとに自動更新されており、2015年3月1日に賃料増額請求をしたケースを考えてみましょう。
賃貸借契約は契約に基づき、民法改正前の2013年、2016年、2019年のそれぞれ4月1日に自動更新され、2022年3月31日までは改正前民法が適用されます。しかし、2022年4月1日の自動更新によりそれ以降は改正後民法が適用されます。
2022年3月31日以前の賃料債権に適用される改正前民法では、賃料債権については請求しうるときから5年で消滅時効にかかるとされており、支払時期の翌日から5年で消滅時効にかかります。
賃料増額請求の後、従前の賃料額しか支払われていない場合、支払時期から5年経過した差額賃料については、時効の中断事由や完成猶予事由などがなければ消滅時効が完成しています。
ただし、入居者側が差額賃料についての支払義務があることを認めたりした場合は、その認めた時から新しい時効期間が進みます。
賃料「減額」請求の場合
入居者に対して賃料減額請求を行ったにもかかわらず、賃貸人との協議が調わないなどの理由で入居者がそれまでの賃料を払い続けている場合、入居者側は賃貸人に対して差額賃料の返還を請求できます。この場合の請求権は、「不当利得返還請求権」であり、増額分の賃料請求とは法的性質が異なるので注意が必要です。
不当利得返還請求権の消滅時効は、改正前民法が適用になる場合は賃貸借契約が商行為に該当するか否かを問わず10年、改正後民法が適用される場合は5年です。
時効完成後でも請求できるケース
増額分の賃料債権について消滅時効が完成したら諦めるほかないのでしょうか。
いえ、時効期間が経過していても、増額分の賃料を請求できる可能性はあります。
それは入居者側が消滅時効を援用しない場合です。賃料債権について時効が完成していた場合でも、入居者が時効を援用しなければ、裁判所は当賃料債権が時効消滅したという裁判をすることができません。
「時効の援用」とは、時効の利益を受けるという意思の表明であり、裁判所は、当事者が時効の援用をしなければ、時効に基づいて裁判することができないとされているのです(民法145条)。
また、入居者(賃借人)が増額分の賃料の支払の猶予を求めたり、一部だけ支払ったような場合、債務を承認したことになり、時効が更新されます。
「時効の更新」とは、これまでの時効期間の経過が無意味となり、新たに時効が進行することをいいます。
賃料債権について消滅時効が完成した後に承認があった場合も、その時効の完成がなかったことになり、承認の時点から新たな時効が進行します。
このように、相手が時効を援用していない場合は、相手がその時効を援用しない可能性や、債務の承認をする可能性に期待して、時効期間が経過した分の賃料も請求することも検討しましょう。
賃料増額請求を行う前にすべきこと【実務対応のポイント】
実際に賃料増額請求を行うにあたっては、以下の点に注意しましょう。
1.現行賃料の相場との乖離を確認
近隣相場の賃料を確認し、現行の賃料とどれだけ離れているかを確認しましょう。
不動産会社のサイトなどで類似物件がどのくらいの価格で貸し出されているかなど調べられます。
2.証拠(路線価・近隣物件賃料・鑑定など)の整理
路線価は国税庁のサイトで確認できます。路線価が上がっていれば土地の価格が上昇しています。国税庁の路線価図は過去6年分まで公表していますので、過去との比較に役立ちます。
近隣物件賃料などは、類似物件の賃料を複数チェックしておくことをおすすめします。
また、相当な賃料の資料として不動産鑑定士に鑑定してもらう方法もあります。その際には、簡易的な評価である不動産調査報告と、正式な評価と言われる不動産鑑定のどちらかを選択する必要があり、費用も発生するため、費用対効果を考慮したうえで利用しましょう。
3.内容証明の送付と訴訟リスクの把握
賃料増額請求は入居者にその内容が到達した時点で効果が発生します。そのため、配達証明付内容証明によって賃料増額請求の意思を伝えることはとても重要なポイントです。
入居者が納得して増額した賃料額を支払ってくれればよいのですが、反対された場合には調停または訴訟という流れになるため、日頃から入居者との関係を良好に保つとともに、入居者が納得できるような資料をそろえることも意識しておきましょう。
仮に訴訟に発展すると資料の準備や裁判費用、さらには弁護士に依頼する費用なども発生します。賃料増額請求がうまくいけば、賃料増額による効果は継続するため、出費分はカバーされることも多いのですが、出費の方が多くなる可能性もあり、注意が必要です。
不動産法務に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで
本記事では賃料増額請求後の増額分賃料債権の消滅時効について解説しました。
賃料増額請求をしたものの、入居者との協議がうまくいかず、従前の賃料を漫然と受取り続けているオーナーも多いのではないでしょうか。後になって増額分の賃料を請求しようと思っていたのに、増額分の賃料債権が時効で消滅してしまったということにならないよう、消滅時効を意識して対策することが必要です。
催告だけで入居者が増額分賃料を支払ってくれない場合には調停や訴訟に進むことになりますが、自分だけでは資料の準備や調停への対応ができない可能性も考えられます。時効完成間近であれば、ただちに申立等の手段を講じる必要があり、専門家の力を借りたほうがよい場合が多いでしょう。
そのため、賃料増額請求後に放置していた増額分の賃料請求を考えているなら弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】【関連記事】
賃料増額請求書の書き方と内容証明郵便の活用についてわかりやすく解説
賃料増額請求の弁護士費用~相場と抑える方法を徹底解説~
賃料増額請求と供託対応~賃貸オーナーのための法的知識と実務戦略~
直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。
その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。
アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。

