澤田直彦
監修弁護士 : 澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、「内部通報事例から学ぶ企業の失敗と適切な調査・対応方法」について、詳しくご説明します。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら【無料】サービス資料を受け取る当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。
登録はこちらから
![]()
内部通報制度は、組織内の不正行為や法令違反を事前に発見し、防止するための重要な仕組みです。しかし、通報に対する対応を誤れば、制度への信頼失墜を招き、結果として重大なコンプライアンス上のリスクを生み出す可能性があります。
この記事では、内部通報の具体的な事例を参考にしながら、企業が犯しがちな対応ミスを分析し、効果的な調査プロセスと改善措置の実施方法について詳しく説明します。
内部通報制度における典型的な失敗事例と対策

企業が不正防止や法令遵守のために導入する内部通報制度は、本来、組織の健全性を維持するための重要な仕組みです。しかし、制度の設計や運用が不適切であったり、通報者に対する保護が不十分であったりすると、かえって深刻なコンプライアンスリスクを引き起こしてしまいます。
内部通報を受けたものの、社内調査が不十分で真相解明に至らなかったり、証拠の隠匿や社員の非協力によって実態が把握できないケースも見受けられます。通報内容が事実無根であった場合でも、調査が不十分だと真の不正行為を見逃すリスクがあります。内部監査部門が経営陣の意向やリソース不足から調査を形だけで終わらせ、「問題なし」と結論付けた事例もあります。
ここでは、内部通報制度を適正に機能させるために企業がどのような対策をとればよいのかを、典型的な失敗事例をもとに解説します。
元請会社の通報窓口利用による不利益取扱い事例
A社の取引先のB社の役員や従業員は、A社の従業員や役員についての通報対象事実を、B社内の通報窓口に通報した場合、公益通報として保護されます。
しかし、A社が取引先の従業員等も通報者に含むという内部規程を定め、B社でもA社の通報窓口をB社の通報窓口として定めている場合、B社の従業員は、A社の通報窓口にA社の従業員等の不正について通報をすることができ、これも公益通報として保護されます。
※2022年6月の改正公益通報者保護法により、「事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前一年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者」や「事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合」における当該事業に従事する役員が、「当該他の事業者」やその役員、従業員等についての通報対象事実を通報することも、公益通報として保護されることになりました(同法2条1項3号・4号)。
内部通報の実効性を高める上では、内部規程でも「取引先の従業員や役員」を通報者に含めることも検討すべきでしょう。ただし、取引先の従業員や役員を通報者に含める場合、通報者の保護などにおいて十分な措置や配慮を行わないと、取引先内部で通報者が不利益な取扱いを受ける恐れがあります。
例えば、元請会社が設置する通報窓口を利用した下請会社の従業員が、下請会社内で不利益な取扱いを受けた事例があります。この従業員は、元請会社と自社による下請法違反を通報したところ、社内の役員から非難され、担当業務から外され、周囲から「給与泥棒」と揶揄されるようなったという事案です。
元請会社が通報窓口を取引先にも開放している場合、通報者を保護する規定を明記し、関係者に制度の趣旨を周知する必要があります。
厚生労働省の「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説」(以下「指針の解説」といいます)では、関係会社・取引先からの通報を受け付けている場合において、公益通報者が当該関係会社・取引先の労働者等又は役員である場合には、通報に係る秘密保持に十分配慮しつつ、可能な範囲で、当該関係会社・取引先に対して、例えば、以下のような措置等を講ずることが望ましい、としています。
- 公益通報者へのフォローアップや保護を要請する等、当該関係会社・取引先において公益通報者が解雇その他不利益な取扱いを受けないよう、必要な措置を講ずること
- 当該関係会社・取引先において、是正措置等が十分に機能しているかを確認すること
通報を理由とした報復があれば、公益通報者保護法違反に該当するおそれがあり、損害賠償や取引停止といった重大なリスクに発展します。内部通報制度への信頼を損なうことは、企業のコンプライアンス体制そのものを揺るがす問題であると言えます。
こうした事態を防ぐには、事実関係を適切に調査し、必要に応じて業務の是正措置や処分を行うとともに、通報者の保護を徹底し、内部通報制度の再整備や情報管理体制の見直しが不可欠です。また、取引先へ通報者の保護の徹底を求めるなども必要です。
内部通報者への報復行為(不利益な取扱い)がもたらすリスク
内部通報者に対する報復行為(不利益な取扱い)は、企業にとって重大なリスクをもたらします。具体的には、「損害賠償リスク」「内部告発リスク」「元請会社との取引解消リスク」「公益通報者保護法違反」の4つのリスクが考えられます。
【内部通報への不適切な対応がもたらす企業リスク】
| リスクの種類 | 具体的な内容 | 想定される影響 |
|---|---|---|
| 損害賠償リスク | 通報者が心身に支障をきたした場合、内部規程違反・公益通報者保護法違反を理由とした損害賠償請求 | 高額な損害賠償責任の負担 |
| 内部告発リスク | 内部通報制度への信頼崩壊により、公益通報者保護法3条3号の要件を満たし、マスコミ等への内部告発が法的に保護される | 企業の不正行為の公開、レピュテーション損失 |
| 取引解消リスク | 元請会社が情報管理や教育の不徹底を非難し、取引解消の動きに出る | 重要な取引先との関係悪化・喪失 |
| 公益通報者保護法違反 | 同法5条等違反として法的責任を問われる | 行政指導、訴訟リスク |
通報者に対する報復行為が行われると、通報制度そのものへの信頼が失われます。
その結果、本来は社内で是正可能だった不正が放置され、通報者や第三者によって外部に告発される可能性が高まります。これは企業にとって、コンプライアンス上の致命的な損失につながりかねません。
また、報復によって通報者が精神的または身体的に深刻な影響を受けた場合、企業が負う損害賠償責任は非常に重いものとなります。特に小規模な組織では、職場環境の分離が難しく、通報者が離職に追い込まれることも多く見られます。こうした事態は他の従業員にも強い萎縮効果を与え、内部通報への信頼を根本から損なうことになります。
企業は報復のリスクを正しく認識し、通報者保護の徹底と制度の適正運用を通じて、信頼されるコンプライアンス体制を築く必要があります。
公益通報者保護法違反による企業の損害
公益通報者保護法は、一定の条件を満たす通報者に対して不利益取扱いを禁止し、通報者の権利を守る法律です。通報が保護対象となるためには、要件を満たす必要があります。
なお、内部通報は、役務提供先(代表者や通報対象事実について権限を有する管理職、通報者の業務上の指揮監督に当たる上司等の従業者を含む)または役務提供先があらかじめ定めた者に行う必要があります。役務提供先が取引先の通報窓口を通報窓口と定めている場合、取引先の通報窓口も「役務提供先があらかじめ定めた者」となります。
これらの要件を満たす通報に対して、企業が不利益な取扱いをした場合、同法5条に違反することとなります。
【内部通報と外部通報の保護要件の違い】
| 内部通報 | 外部通報(行政機関) | 外部通報(報道機関等) | |
|---|---|---|---|
| 保護要件 | 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する」(主観的要件) | ①通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 または ②通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ氏名等を記載した書面の提出 |
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ特定事由(内部通報等では効果がない等)に該当 |
同法5条では、通報を理由とした解雇や降格、業務外しなど、あらゆる不利益な取扱いを禁止しており、違反が認定されれば企業は損害賠償請求の対象となるだけでなく、違法行為として社会的非難を受けることになります。
さらに、違反事実が公にされれば、企業の評判は大きく損なわれ、取引先や顧客、株主からの信頼も失墜します。加えて、監督官庁による行政指導や是正勧告を受ける可能性もあり、企業の経営・コンプライアンス体制全体に深刻な影響を及ぼします。
企業は同法の趣旨を正しく理解し、通報者保護を徹底することが不可欠です。
内部通報を端緒とした不正発覚事例の調査手法

内部通報をきっかけに企業内の不正やハラスメントが発覚するケースは少なくありません。適切な調査体制と手順を整備しておかなければ、真相の解明が困難になり、対応の遅れや誤りがさらなるリスクを招くおそれがあります。
ここでは、通報受付後の調査において、誰が調査を行うべきか、どのように証拠を集め、関係者に聴取するべきか、そして調査結果をどう評価し、対応につなげるかといった実務上のポイントを解説します。
調査主体と調査体制の構築方法
通報者保護の観点から、通報を理由とした不利益取扱いは禁止されており、通報者のプライバシーや名誉にも十分配慮する必要があります。
通報者による内部通報制度の濫用や不誠実通報が疑われる場合でも、当初から排除せず、通常の通報として調査を進めることが推奨されます。また、調査の結果、通報者による内部通報制度の濫用と認定できる場合でも、安易な懲戒処分はレピュテーションリスクを高めるため、慎重な対応が必要です。
なお、役員の不正が疑われる通報を受けた場合、誰が調査担当となるべきか問題になります。
通報の対象となる者が役員の場合、適切に調査を行うためには、当該役員より上位の立場の者が調査主体となる必要があります。適切に調査できなければ会社に様々なリスクが生じ、また、取引先からも徹底した調査を求められる可能性もあります。そのため、基本的には経営トップ、つまり代表取締役社長を調査責任者とするべきです。
また、その補佐役も当該役員より上位の立場の者が望ましいですが、いない場合は弁護士などの専門家を活用します。
重大な案件等ケースによっては、弁護士等の専門家を調査責任者とする調査委員会を設置して調査をすることも検討しましょう。
証拠収集と関係者ヒアリングの手順
調査は、いきなり対象役員から事情を聴くのではなく、真実を語らざるを得ない状況を整えることが重要です。
基本的には以下の順に進めましょう。
- 通報者へのヒアリング
- 客観的資料の確認
- 関係者ヒアリング (通報対象者の言動を知る立場にある従業員等)
- 対象者へのヒアリング
前述の事例(元請会社の通報窓口に元請会社と自社の下請法違反の事実を通報したことを自社の役員に非難され、仕事を外され、給与泥棒などと揶揄されている旨の通報事案)における調査の場合、次の事実について認定が必要となります。
| 認定すべき事実 | 調査のポイント |
|---|---|
| 役員から元請会社の通報窓口を利用したことを非難された事実 | 当事者以外の従業員や役員で、直接又は間接的にこの言動を認識していた者がいればその認識。 認識していた者がおらず、通報者と通報対象者(役員)の説明の食い違いがある場合、両者の信用性。 |
| 仕事を外された事実 | 通報者の仕事が変わった時期と内容 |
| 内部通報を理由に不利益取扱いがされた事実 | 通報者の仕事を変更する合理的な理由が通報以外にあるのか |
このように、客観的な記録や当事者や関係者の証言をもとに、通報者が元請会社への通報により不利益な取扱いを受けているといえるのかを見極める必要があります。
証拠に基づいた丁寧な調査をすることにより、会社の内部通報制度への信頼と納得感を確保することが求められます。
調査結果の法的評価と対応方針の決定
調査によって通報内容が事実と認定された場合は、前述の事例のケースでは役員の行為が社内の内部通報制度規程違反や公益通報者保護法違反に該当するかを評価します。不利益な取扱いが確認されれば、社内規程や法令に違反するものとして、厳正な対応が求められます。
違反が明らかになった場合、通報者の業務内容を適切に見直す、加害者との上下関係を回避する人事異動、役員に対する降格・減給・解任などの是正措置が必要です。もし、就業規則が適用されない役員であれば、取締役会で解任する又は報酬の減額をするなども考えられます。
対策が不十分でも過剰でも、内部通報制度の信頼性を損なう恐れがありますので、処分の内容や軽重については慎重に検討しましょう。
また、将来的に内部通報を理由とした不利益な取扱いの発生を防ぐために実施すべき再発防止措置としては、以下のようなものがあります。
- 経営トップによるメッセージ発信
- 規程整備
- 規程 ・ 制度の中値のための教育研修
- 自社の通報窓口設置
- 運用担当者の選定と教育
- 自社や元請会社の調査体制や情報管理体制の点検
是正措置の実効性を検証し、必要に応じて見直すとともに、内部通報制度の利用状況に関する記録や運用実績の開示、定期点検を通じて制度への信頼性を高める取り組みが重要です。経営陣が内部通報制度の意義を理解し、周知徹底を図ることが求められます。
食品表示偽装に関する内部通報事例と景品表示法

食品の原産地や品質を偽る「食品表示偽装」は、消費者の信頼を損ない、企業にとって重大な法的責任やレピュテーションリスクをもたらします。内部通報により発覚しても、通報に対する最初の対応を誤った場合や事実調査の不備によって、後に企業の信用失墜を招くことや、行政処分がなされる事態につながりかねません。
ここでは、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます)における「優良誤認表示」の考え方を踏まえつつ、過去の違反事例や消費者庁の対応、企業側の調査・是正の実務対応について解説します。
優良誤認表示の典型的なケース
景品表示法5条1号が禁じる「優良誤認表示」とは、一般消費者に対し、実際の品質・内容よりも著しく優良であると誤認させる表示を指します。判断基準は、特定の言葉や図柄だけでなく、表示全体から受ける印象によって決まります。
例えば、レストランで「松阪牛ステーキ」とメニュー表示しながら、実際には松阪牛ではない通常の和牛を提供していた場合、優良誤認表示に該当します。消費者庁も過去に、和牛と誤認させる地元牛使用の宿泊プランや黒毛和牛と偽った料理名に対して、優良誤認表示と判断し処分を行っています。
ブランド産地や品種は、消費者にとって品質の重要な判断要素であり、それを偽る行為は、消費者の合理的な選択を妨げる重大な問題とされます。したがって、表示の一部が正確でも、全体として誤認を与える場合は違反に該当することに注意が必要です。
措置命令と課徴金納付命令への対応
食品表示に優良誤認表示があった場合、消費者庁は事業者に対して措置命令や課徴金納付命令を行うことがあります。
それぞれの制度と対応策は以下のとおりです。
【優良誤認表示に対する行政処分と対応】
| 処分の種類 | 内容 | 要件・適用除外 | 企業の対応 |
|---|---|---|---|
| 措置命令 | ① 違反行為の差止め ② 再発防止に必要な事項 ③ 公示 ④ その他必要な事項 |
違反行為が既になくなっていても命令可能 | 速やかな表示の取りやめ、再発防止策の策定 |
| 課徴金納付命令 | (最大3年の)売上額の3%相当額 | 【適用除外】 「相当の注意を怠った者でない」と認められる場合 |
① 原材料の仕様・規格確認 ② 認証制度の利用 ③ 成分検査の実施 |
| 課徴金減額措置 | 50%減額 | 消費者庁の調査開始前に自主的に報告した場合 | 早期の事実調査と報告判断 |
| 返金による減免 | 課徴金の減免 | 弁明の機会後、認定された消費者に対する返金計画に基づき4カ月以内に実施 | 消費者に対する返金計画の策定と消費者庁長官の認定取得 |
課徴金は、違反行為を「知らなかったかつ、相当の注意を怠っていない」と認められれば、命令の適用除外となります(景品表示法8条1項但書)。「相当の注意を怠っていない」と認められるには、当該事業者が課徴金対象行為に係る表示をする際に、当該表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意をしていたか否かにより、個別事案ごとに判断されることとなります。
そのため、以下のような措置を講じていたことが重要です。
- 原材料の仕様 ・ 規格 ・ 表示内容の確認
- 原産地や品質に関する認証制度の活用 (例:ブランド食材の証明書)
- 無作為抽出による成分検査の実施
なお、措置命令・課徴金命令のどちらにも対応するためには、違反の事実確認に加え、表示開始の経緯・販売実績・組織的関与の有無などを調査し、的確な対応方針を定める必要があります。
消費者庁調査前・後の自主的対応の重要性
不当な食品表示をしている旨の内部通報をうけた場合、早期に是正措置を講じて正確な情報を公表することを検討する必要があり、迅速かつ適正な事実調査を実施することが不可欠です。特に、消費者庁による調査が始まる前の自主的な対応が極めて重要です。
初動としては、速やかに問題の表示を取りやめ、社内で事実調査を実施することが求められます。具体的には、表示と商品の実態が異なるものになってしまった経緯や原因、偽装表示の開始時期と継続期間、その間の販売数や金額、材料の入手経路や商品の販売経路などについて調査する必要があります。
その結果、課徴金対象行為が確認された場合、所定の形式で事実を自主的に報告すれば、課徴金額が50%減額されます(景品表示法9条)。ただし、この減額措置は消費者庁から調査開始の通知を受ける前に報告した場合に限られるため、報告のタイミングは非常に重要です。
また、措置命令や課徴金納付命令の前には、必ず消費者庁による調査があります。消費者庁による調査が開始した場合、「確約手続」をとることで、措置命令や課徴金納付命令を回避することもできます。
確約手続とは、優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が、是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととする手続です(景品表示法26条乃至33条)。原則として、消費者庁が確約に付す必要があると認める場合に、違反の疑いがあるというところまで認定し、事業者に確約通知をし、これを受けた事業者が60日以内に確約計画を策定し、申請するものとされています。
しかし、消費者庁が確約手続通知を行う前であっても、調査を受けている事業者は、確約手続の対象となるかどうかを確認したり、確約手続に付すことを希望する旨を申し出たりするなど、確約手続に関して消費者庁に相談することができるとされています(消費者庁「確約手続に関する運用基準」)。
このように、確約手続をとることができればメリットが大きいのですが、確約通知を受けてから60日以内に確約契約を策定しなければならないという時間的制約があることから、内部通報などで事前に事業者が違反状態を確認したのであれば、独自に調査を進めてしっかりと是正計画を立てていくことが大切です。
さらに、課徴金のさらなる減免措置として「返金制度」があります。これは、①返金計画の策定と長官の認定取得、②計画の実施は4か月間以内、③完了後1週間以内の報告という手続に従って行われます。
こうした自主的な対応は、法的責任の軽減だけでなく、消費者や取引先からの信頼回復にも直結します。早期の是正と情報公開が、企業のリスクマネジメントとして不可欠です。
経費の私的流用に関する内部通報事例と対処法
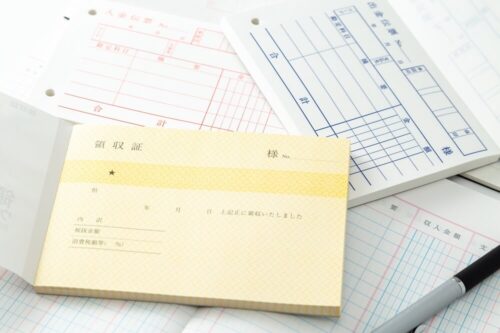
経費の私的流用は、企業内部からの通報によって発覚する典型的な不正の一つです。特に接待交際費や出張旅費といった経費は、制度の隙を突いて不正に使用されやすく、役員等の上位者が私的流用していたような場合、組織全体のモラル低下を招くおそれもあります。
ここでは、役員による経費流用に関する通報事例をもとに、不正のパターンや調査・法的対応のポイント、そして再発防止に向けた内部統制の構築方法について解説します。
接待交際費の不正使用パターン
接待交際費に関する不正には、大きく2つのパターンがあります。1つは、「架空請求型」で、実際には支出されていないにもかかわらず、領収書などを偽造して経費として申請するケースです。もう1つは、「実支出型の私的流用」で、実際に飲食費等が発生しているものの、業務とは関係のない私的用途である場合です。
いずれのケースでも、申請内容に不自然な点や整合性の欠如があることが多く、客観的な資料や状況証拠をもとに丁寧に確認する必要があります。不正を見抜くには、領収書の形式や日付の整合性、接待の業務関連性、実際の支出の有無など、複数の観点から調査を進めることが重要です。
以下に、接待交際費の調査で着目すべき主要なポイントとその確認方法をまとめます。
【経費流用調査における確認ポイント】
| 調査項目 | 確認内容 | 具体的な調査方法 |
|---|---|---|
| 領収書の体裁 | 不審な点の有無 | 役員の筆跡との照合 ・ 書式の確認 |
| 日付の整合性 | 不自然な日付の有無 | ① 休日の接待の有無 ② 日付空欄領収書の利用 ③ 役員スケジュールとの矛盾 |
| 支出の実在性 | 実際の飲食の有無 | 店舗への聴取 (ただし情報漏洩リスクに注意) |
| 接待の業務関連性 | 接待相手と業務の関係 | ① 接待相手の特定 ② 申請内容との照合 ③ 必要に応じて接待相手への反面調査 |
| 頻度 ・ 場所の妥当性 | 不自然なパターンの有無 | 役員の自宅近くの飲食店での頻繁な利用など |
役員の横領行為に対する法的措置
役員が接待交際費を私的に流用した場合、会社に対して重い法的責任を負うことになります。
まず、会社に対する民事責任として、会社法423条1項に基づく損害賠償責任が問われます。会社に損害を与えた役員は、故意・過失の有無を問わず、その全額を賠償する義務を負います。
さらに、刑事責任としては、会社に損害を与える意図で虚偽の経費申請等を行っていた場合には背任罪(特別背任)、虚偽の領収書等による請求であれば詐欺罪が成立する可能性もあります。
役員の解任については、株主総会の決議によっていつでも行うことが可能ですが、「正当な理由」なく解任した場合には、残存任期に相当する報酬等の損害賠償責任を会社が負う可能性があります。そのため、経費流用の証拠を整理し、解任の「正当な理由」を明確化することが必要です。
実務上は、調査結果をもとに役員本人との面談を行い、自発的な辞任を促す対応をとることもよくあります。この際に、辞任を強制されたなどと主張され紛争となるおそれもあることから、手続の正当性を担保するために、面談時のやり取りを録音・録画し、証拠として保全しておくことが重要です。
役員の不正は企業の信頼性を根本から揺るがす問題であるため、法的措置と実務対応の双方から、慎重かつ確実に進めることが求められます。
再発防止に向けた内部統制の構築
接待交際費の私的流用が発生する背景には、経費精算における内部統制の甘さがあることが多く、制度上の不備が不正を助長する温床となり得ます。とりわけ、役員等の上位者の経費については、チェック機能が形式的になりやすく、内容の妥当性が精査されないまま承認されるケースも少なくありません。
こうした構造的な問題に対処するためには、制度改善が不可欠です。具体的には、経費申請時に接待相手・目的・内容の詳細記載を義務付ける、承認プロセスに複数の確認者を設ける、一定額以上の支出について定期的な内部監査を実施することなどが有効です。
また、経営トップが不正に対して毅然とした姿勢を明示し、適切な処分を行うことは、組織全体に対する強い抑止力となります。
一時的な対応で終わらせるのではなく、企業内秩序の維持と再発防止を目的とした継続的な取組みとして、教育・監督体制の見直しを含めた改革を進めていくことが重要です。
内部通報事例における報告のポイント

内部通報を受け、当該報告事案についての調査責任者を経営トップとした場合、調査結果をどのよう経営トップに報告するのかは、とても大切な課題です。
不正行為に毅然とした考えをもっていない経営者であれば、不正行為やこれに毅然とした対応をしない場合に会社にどのような悪影響があるのかを伝えるなどして、経営者の考え方を改めてもらう必要があります。つまり、どのように報告するかは、是正措置や再発防止策の立案・実行に直結するものなのです。
なお、内部通報への対応について、報告書が必要か否かはケースバイケースです。
報告書の記載内容 (構成例)
調査責任者である経営トップに対する報告書には、調査の経緯や結果を正確かつ簡潔に記録し、今後の是正や再発防止に資する資料として活用されるべきものです。
以下のような内容を記載することが多いです。
- 通報の概要 (通報日、通報方法、通報対象事実の要旨)
・ 通報の対象となる行為 (法令違反、社内規則違反、企業倫理違反 等)
・ 通報者の範囲 (正社員、パートタイマー、派遣社員 等)
・ 通報方法 (書面、メール、FAX等の手段と匿名の可否) - 調査の経過 (調査開始日、調査方法、関係者ヒアリング 等)
- 調査結果 (認定事実、証拠の整理)
- 是正措置 ・ 再発防止策 (必要な場合は具体的措置や実施状況)
- 通報者 ・ 関係者への通知内容 (プライバシーや名誉に配慮した範囲で)
事実認定と法的評価の記載方法
調査報告書では、調査対象となった事実について認定の有無を整理し、法的観点からの問題点も明確に記載することが重要です。
経費の私的使用が疑われる事案の場合、各経費申請ごとに、私的使用の可能性についての評価を記載する方法が考えられます。
例えば、「○(可能性高い)」「△(疑義あり)」「×(認められない)」等の評価区分を設け、判断理由を簡潔にまとめます。評価は、証憑の整合性・業務との関連性・接待の実在性などを基準に行います。
また、認定された事実については、社内規程違反・公益通報者保護法違反・景品表示法違反などに該当するかどうかを明示し、関連する条文や基準を踏まえた簡潔な解説を添えることが望ましいでしょう。
さらに、役員の関与が認められた場合には、「正当な理由」による解任の可否や、損害賠償・刑事責任の可能性について、弁護士等の専門家の見解を添えることで、報告書の実効性を高めることができます。
是正措置と再発防止策の提言
報告書には、認定された不正や違反行為に対し、必要かつ相当な是正措置を明記することが重要です。
例えば、対象者の業務内容の変更や異動、不正の程度に応じた懲戒処分(役員であれば減給処分や解任など)など、違反状態の解消を目的とした具体策を記載します。処分が過剰・不十分となれば制度への信頼を損なうため、妥当性の説明も添えるとよいでしょう。
加えて、再発防止のための施策として、以下のような7つの取り組みを提言するのが有効です。
- 経営トップによるコンプライアンス重視のメッセージ発信
- 内部通報制度に関する規程の明確化 ・ 整備
- 管理職を含む従業員への教育研修の実施
- 社外の通報窓口の設置と周知
- 調査 ・ 対応記録の保存体制の構築
- 通報制度の運用状況の定期的な評価と改善
- 運用実績の労働者 ・ 役員へのフィードバックと開示
なお、食品表示偽装が認定された場合には、是正措置に加え、消費者庁への報告や自主的な対外公表などといった特別な対応も記載する必要があります。これにより、消費者・取引先からの信頼回復につなげることが可能です。
経営トップへの報告
経営トップに対する報告に際しては、以下の点を留意することが重要です。
まず、内部通報対応に問題があった場合は、それがコンプライアンス体制全体の脆弱性や機能不全の兆候であることを明確に伝える必要があります。
調査結果の背景に潜む構造的な課題も含めて、組織全体のリスクとして認識させることが求められます。
また、不正行為が確認された場合には、関係者への適切な処分と再発防止に向けた制度改善を同時に提言する必要があります。
単なる制裁にとどまらず、制度の信頼性回復や職場風土改善の視点を含めた提言とすることが大切です。
さらに、対外的な公表や行政対応の要否についても判断を仰ぐ必要があります。
例えば、下請法違反が認定された場合は、監督官庁への報告が必要となる場合があり、景品表示法違反がある場合には、消費者庁による措置命令が出される前に自らプレスリリースを行うことが信頼回復につながることがあります。
こうした対応方針も、経営判断を仰ぐ前提として、報告書に明記しておくことが重要です。
通報者保護と情報管理
調査終了後は、通報者に対し調査結果や是正措置の有無を速やかに通知することが原則です。
その際は、関係者のプライバシーや名誉を損なわない範囲での情報提供とし、個別の処分内容などの開示は慎重に判断する必要があります。
通報者の氏名や通報内容など、本人の特定につながる情報は、本人の同意なく第三者に開示しないことが原則です。
正社員かパートタイマーかなど、就労形態を記載によって特定されるおそれがある場合には、就労形態を記載しないなどの対応も必要です。また、調査や処分の過程で一定の情報開示が必要な場合であっても、最小限の範囲にとどめ、事前に本人の意思を確認する対応が望まれます。
さらに、匿名での通報が可能な制度を設けている場合には、通報者が特定されることを防ぐために、調査や報告書の記載にも細心の注意を払う必要があります。
通報者の属性や関与範囲が文面から推測されるおそれがある場合には、記載方法や表現に工夫を凝らし、特定回避の配慮を徹底することが重要です。
なお、調査報告書や関係記録については、社内規程に基づき適切な期間保管し、外部への情報流出を防ぐためのアクセス制限や管理措置を講じることが求められます。
また、制度の透明性を高める観点から、通報件数・対応方針・再発防止策などの運用実績の概要を、通報者が特定されない形で社内に開示することも推奨されます。これにより、通報制度への信頼と利用率の向上が期待されます。
内部通報制度に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで
内部通報の運用は、企業の法令遵守体制や企業倫理の真価が問われる場面です。
対応を誤れば、通報者からの信頼喪失だけでなく、損害賠償や行政処分、社会的信用の失墜といった重大なリスクを招きかねません。事実調査の在り方から是正措置の適否、報告書の記載内容に至るまで、すべてをコンプライアンスの一環として慎重に行う必要があります。
特に、下請法違反や景品表示法違反に関する通報、公的機関への通報があったような場合、早期に専門家の助言を得ることが、被害拡大の防止にもつながります。
社内対応に不安を感じた際は、早めに専門家にご相談されることを推奨します。適切な法的対応が、企業の信頼と将来を守る最善の一手となります。
直法律事務所においても、ご相談は随時受けつけておりますので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。
\初回30分無料/
【初回30分無料】お問い合わせはこちら【無料】サービス資料を受け取る【関連記事】
【2026年施行予定】公益通報者保護法改正で企業に求められる対応とは
内部通報で把握したハラスメント疑義への適切な調査と対応方法
顧問弁護士とは?法律顧問契約を結ぶメリットや費用・相場について解説!【企業向け】
IPO準備企業は必読!IPOに適した内部通報制度の整備を弁護士が解説
直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。
その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。
アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。

