
columns
弁護士コラム
遺贈や死因贈与がある場合、遺留分侵害額請求の順序はどうなる?
- 遺留分のトラブル
- 投稿日:2023年07月21日 |
最終更新日:2024年05月17日
- Q
- 遺贈と死因贈与では、遺留分侵害額請求をした場合にどちらから対象になるのでしょうか?
- Answer
-
学説には、遺贈から遺留分侵害額の負担をする遺贈説と、死因贈与から遺留分侵害額の負担をする贈与説があります。
この学説の対立は民法改正によって解決されず、解釈にゆだねられています。
民法改正前の遺留分減殺請求について、東京高判平成12年3月8日は、死因贈与は遺贈に次いで、生前贈与より先に遺留分減殺の対象とすべきとしています。
これに従えば、①遺贈、②死因贈与の順で遺留分侵害額請求の対象となります。
本記事で詳しく説明していきます。
目次
遺贈と死因贈与
前提として、遺贈と死因贈与の違いを確認します。
遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産を他人に与える行為をいいます(民964条)。物権や債権の移転のみならず、使用収益権や担保権の設定、債務の免除なども遺贈の対象となります。
遺贈は契約ではなく、無償の単独行為です。
また、遺言の中で行われる、法規の定めた一定の方式に従って行わなければ、不成立または無効となる法律行為(要式行為)です。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。
具体的には、贈与者の生前に、贈与者が死亡することを条件として効力が生じる契約を締結し、贈与者が死亡することで贈与の効力が生じます。
このように、死因贈与は、贈与者の意思表示に加えて、相手方の受諾を要件とする契約です。
死因贈与は、遺贈に関する規定が準用されます(民554条)が、遺言の方式に関する規定は準用されず、また、遺言能力や遺贈の放棄・承諾に関する民法の規定(民法961条、同986条以下)は準用の余地がありません。
遺留分侵害額請求
他の相続人の遺留分を侵害する遺贈がなされた場合、遺留分権利者は、遺留分侵害者に対して、侵害額の金銭請求が可能です(遺留分侵害額請求、1046条1項)。
改正民法では、旧民法下における「減殺」という文言は用いられず、「減殺の請求権」は「遺留分侵害額の請求権」に改められました。
旧民法下では、通説・判例によれば、遺留分減殺請求権が行使されると、減殺される範囲で遺贈・贈与の効力は消滅し、減殺の対象となった財産に対する権利は当然に遺留分権利者に復帰すると解されていました。そのため、原則として、遺留分権利者は、減殺の対象となる財産の、遺留分に相当する持分の返還を求める必要がありました。
しかし、改正により、遺留分侵害額請求により、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が発生する(民1046条1項)ものとされました。
事例
では具体的事例をみてみましょう。
事例
| Xは、自己が所有する宝石を長女Aに相続させる旨の遺言をしました。 この遺言以前に、Xは長男Bと、自己が所有する土地についての死因贈与契約を締結し、Bは所有権移転の仮登記を具備しました。 Xの相続人には、A、Bのほかに次男Cがいます。 Cが、A及びBに対し遺留分侵害額請求を行った場合、Aに宝石を相続させる旨の遺言とBに対する土地の死因贈与では、どちらが先に遺留分侵害額を負担するのでしょうか? |
検討
学説では、被相続人が遺贈と死因贈与をしている場合に、遺留分を侵害された一部の相続人が遺留分侵害額請求をしたとき、遺贈と死因贈与は同じ順位で遺留分侵害請求を受けるとの見解があります。
他方、まず遺贈を受けた者が遺留分侵害請求を受け、それでも遺留分に不足があればさらに死因贈与を受けた者が遺留分侵害請求を受けるとする見解もあります(「宝石をAに相続させる」旨の遺言は、相続分の指定による遺産の取得ですが、これも遺留分においては遺贈に含まれます)。
本事案の場合、いずれの見解をとるかによって結論が異なります。
民法改正前の下級審の判例では、遺贈が先に遺留分侵害請求を受けるという説に従うものがあり、この場合、Cはまず、遺贈を受けたAに対し遺留分侵害額を請求し、それでも自己の遺留分額に不足があれば、その不足分について死因贈与を受けたBに対して遺留分侵害額の請求をすることになります。なお、A及びBそれぞれの負担額は、遺贈ないし死因贈与された財産の評価額が限度となります。
令和2年の民法改正では、遺留分について全面的に改正されましたが、遺留分を侵害している者が複数いる場合の請求順序については改正前と変更ありません。民法1047条1項では次のように規定されています。
受遺者又は受贈者は、次の①から③に従い、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として遺留分侵害額を負担します(1047条1項)。
- 1受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します(1047条1項1号)。
- 2受遺者が複数いるときは、遺贈の目的の価額に応じて遺留分侵害額を負担します(1047条1項2号)。
- 3③受贈者が複数いるときは、新しい贈与を受けた者から遺留分侵害額を負担します(1047条1項3号)。
なお、贈与が同時にされた場合について明示の規定がありませんが、一般に贈与財産の価格の割合に応じて遺留分侵害額を負担すべきであると考えられています。
では、死因贈与についてはどうでしょうか。この点、明文で規定されておらず、解釈の問題となります。
死因贈与は「遺贈に関する規定を準用する」(554条)と規定されていますが、改正前の1033条は「贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。」と規定していたため、死因贈与を遺贈と同列に考えるべきか否かについて、学説が対立しています。
遺贈と死因贈与がある場合の遺留分侵害請求の順序(遺贈説と贈与説)
民法改正前から、死因贈与の遺留分侵害請求の順序に関する学説は対立しており、死因贈与の遺留分侵害請求は、遺贈に準じこれと同順位であると解する学説(遺贈説) と、死因贈与は遺贈の後になされると解する学説 (贈与説)があります。
さらに贈与説のなかでも、生前贈与と同順位で遺留分侵害請求されるという説と遺贈の後になされるが生前贈与より先に遺留分侵害請求をされるとの学説があります。
遺贈説(遺贈と死因贈与が同順位)
遺贈説は、死因贈与は遺贈と同じく贈与者の死亡によって効力が生ずることを根拠の一つとしています。また、遺贈は遺留分権者を害する最後のものであり生前贈与と区別されるべきことを理由に1033条が遺贈を贈与より先に遺留分侵害請求すべきものとしたと解されます。そして、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与は遺贈と同様に扱われるべきであるとしています。
贈与説(①遺贈→②死因贈与の順、多数説)
贈与説は、死因贈与契約により成立し権利義務関係が確定することで拘束力が生ずることを根拠としています。死因贈与は契約であり、権利義務関係が確定し、拘束力が生じていることから、遺留分侵害請求を受ける相手方の権利義務関係確定による利益の保護を図るべきであることなどを理由としています。
かつては、遺贈説が多数説でしたが、現在では贈与説が多数説となっています。
民法改正前の裁判例をみると、遺贈説によるものも贈与説によるものもありますが、最高裁では判断されていません。
裁判例
遺贈説をとるとした裁判例は、死因贈与が贈与者の死亡に効力を生ずる点で遺贈と同じことであることや、民法554条が死因贈与について「遺贈に関する規定を準用する」と規定していることを根拠としています。
他方、贈与説に立脚した裁判例は、死因贈与が生前贈与と同じく契約締結によって成立する点で贈与としての性質を有することから、贈与として取り扱うのが相当であるとしています。もっとも、改正前民法1033条及び1035条の趣旨にかんがみ、通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与として、生前贈与より先に遺留分減殺請求の対象とすべきであるとしています。
なお、東京高判平成12年3月8日は、死因贈与は遺贈に次いで、生前贈与より先に遺留分減殺の対象とすべきとしており、贈与説をとっています。
民法改正によっても、死因贈与について明文で規定されませんでした。この点、従前の学説の対立を立法的に解決すべきとの意見もありましたが、判例または学説上も確実に定まっているといえる状況でないため、解釈に委ねられることになりました。
遺贈説に立つ場合
遺贈説に立つと、遺贈と死因贈与は同順位で遺留分減殺請求されることになります。
そして、遺留分減殺請求の割合は遺贈の目的となっている財産と死因贈与の目的となっている財産のそれぞれの価額に従って定められます。
贈与説に立つ場合
贈与説に立つ場合は、まず遺贈に遺留分減殺請求することになります。
そして、遺贈に遺留分減殺請求してもなお遺留分額に不足がある場合にはじめて死因贈与に遺留分減殺請求できることになります。
このようにどちらの考えを採るかによって結論が異なります。
事例への解答
先述の事例のXは、宝石をAに相続させる内容の遺言をしています。
このような特定の財産を特定の相続人に「相続させる」遺言については、民法改正前は、これを遺贈と考える説と、遺贈ではなく遺産分割方法の指定と考える説が対立していました。
もっとも、最高裁は、これを原則として遺産分割方法の指定であると判断しました(「「相続させる」旨の遺言の効力は?判例とともに解説」の記事をご参照ください)。
そして、令和2年の民法改正で遺産分割方法の指定による遺産の取得も遺贈に含まれると定められました(1047条1項)。
遺贈説からの結論
遺贈説からは、遺贈と死因贈与が同順位で遺留分侵害請求を受け、次に生前贈与が遺留分侵害請求を受けることになります。
贈与説からの結論
贈与説からは、先にAが遺留分侵害請求を受け、足りない場合にはBが遺留分侵害額請求されることになります。
贈与説に立つ場合、
- 1死因贈与と生前贈与を同順位と解する説
- 2死因贈与を受けた者が遺留分侵害請求を受け、次に生前贈与を受けた者が遺留分侵害請求を受けるとする説
があります。
前述のとおり、高裁判決では、贈与説を採用し、死因贈与は遺贈の後、生前贈与より前に遺留分減殺請求すべきであると判断しました。
現時点の多数説・高裁判決にしたがい贈与説をとると、Cは、XのAに対する遺言について、Aの取得した遺産について、その評価額からAの遺留分等の評価を控除した限度で遺留分侵害額請求をし、それでも自己の遺留分額に不足するときにはじめてBへの死因贈与を減殺することができるという結論になります。
まとめ
現在の多数説・高裁判決によると、贈与説をとるとされています。
つまり、まず、遺贈対象の財産について遺留分侵害請求をし、それでも遺留分額に不足する場合には死因贈与対象の財産について遺留分侵害請求をすることとなります。
遺贈にあたるのか死因贈与にあたるのかの判断が困難な場合や、遺留分侵害請求の順序が分からない場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
お困りの際は、直法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺留分についてお悩みの方へ
遺留分額の計算から協議、まとまらない場合は遺留分侵害額請求訴訟まで、ご依頼者様の意向を汲み取りながら、プロの弁護士が適正に解決を図ります。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
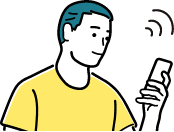
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


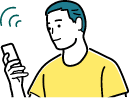


 メールで
メールで