
columns
弁護士コラム
特別受益にあたる生前贈与は、遺留分侵害の対象になる?具体例も用いて解説!
- 遺留分のトラブル
- 投稿日:2022年09月29日 |
最終更新日:2022年09月29日
- Q
-
相続開始の1年以上前に、特別受益にあたる生前贈与を受けました。
この場合、遺留分侵害の対象となるのでしょうか?
- Answer
-
特別受益にあたる生前贈与が相続人以外の第三者に対してなされた場合には、相続開始前の1年間に当該贈与がなされたときに限り、遺留分侵害の対象となります。
他方で、特別受益にあたる生前贈与が相続人に対してなされた場合には、相続開始前の10年間になされたときに限り、遺留分侵害の対象となります。
このように生前贈与の相手方によって期間や対象となる贈与の範囲(特別受益にあたる場合に限られるのか否か)が異なってきますので注意が必要です。
本記事では、この遺留分侵害の対象となる生前贈与の期間制限について、解説していきます。
目次
はじめに
被相続人が生前に、自身の財産を相続人などに対して贈与すること(生前贈与)は広く行われています。
生前贈与は、被相続人が自身の財産を生前に処分できる点で 、便利な法制度です。しかし、法定相続とは異なる割合や相続人以外の人に対して全財産を譲るといった生前贈与がなされた場合には、その財産を相続できると期待していた法定相続人に不測の損害を与えかねないため、そのような相続人を保護する必要性があります。
そこで、民法は「遺留分」という制度を設けています。これは、相続財産の一定割合につき、遺留分権利者に対して、被相続人の相続財産に対する分け前(遺留分といいます)を求める権利を認めるものです(民法1042条以下)。
そして、遺留分算定のための基礎となる財産を基礎財産といいます。
基礎財産は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除」することにより算出されます(民法1043条1項)。
生前贈与によって贈与された財産は、上記民法1043条1項の「贈与した財産」に該当するため、遺留分権利者は、受贈者に対して自身の遺留分に相当する金銭の支払いを要求することができるのが原則です。
この権利を、「遺留分侵害額請求権」といいます。
もっとも質問のように、生前贈与といっても亡くなる相当前になされることも多くあります。
このような場合に、大昔になされた生前贈与等、あらゆる生前贈与が遺留分算定の基礎とされてしまうと遺留分を侵害することもないと信じた受贈者に不測の損害が生じるおそれがあります。
そのため、特別受益にあたる生前贈与を受けた場合でも、常に遺留分侵害の対象とはならず、遺留分侵害の対象となる生前贈与の期間について一定の制限が設けられています。
遺留分算定の対象となる生前贈与の範囲
相続開始の1年以上前に、特別受益にあたる生前贈与(後述します)を受けた場合に、遺留分侵害の対象となるかどうかは、生前贈与を受けた者が相続人以外の第三者か法定相続人か、また、生前贈与を受けたのが相続開始の何年前なのかで結論が異なってきます。
以下では、それぞれの違いについて解説します。
法定相続人以外の第三者
法定相続人以外の者に対する贈与については、原則として、相続開始前の1年間になされた贈与に限って、基礎財産に算入されます(民法1044条1項前段)。
「相続開始前の1年間にした」とは、相続開始前の1年間に贈与契約が締結されたことをいいます。相続開始前の1年より前に贈与契約が締結され、相続開始前の1年間に当該贈与契約の履行がなされた場合では、「相続開始前の1年間にした」とは認められないので、注意が必要です。
なお、遺留分算定の基礎財産の評価については、相続開始時を基準に評価されます。
これは、遺留分権が具体的に生じるのは相続開始時であることなどの理由に基づいています。
相続人
相続人については、対象となる贈与の期間が原則として、相続開始前10年間とされていますが、他方で、対象となる贈与の範囲が「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」(特別受益ともいいます)に限られているのが特徴です(民法1044条3項)。
法定相続人が、このように法定相続人以外の者に対する贈与と異なる取扱いを受けているのは、相続人間の実質的公平を図る必要がある点、そして、法定相続人以外の第三者である受贈者に対しては相続人以上に相続財産に対する期待がなく、過度に昔の生前贈与について遺留分侵害を認めてしまうと、不測の損害を与えることになり、法的安定性を著しく害するおそれことにあります。
なお、「婚姻若しくは養子縁組のため…受けた贈与」とは、持参金や嫁入道具、支度金などのことをいいます。
他方で、「生計の資本として受けた贈与」とは、独立して世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、営業資金を出してもらったりした場合がこれに該当します。
また、普通教育以上の学費についても、当該学費を支出するのが被相続人の資力等から当然と認められない限り、受贈者にとって将来の生計の基礎か生活能力の取得の基礎になるものといえ、「生計の資本として受けた贈与」にあたるとされています。
※特別受益については、下記記事もご参照ください。
★【特別受益について徹底解説!】持戻免除の意思表示・計算方法
★生命保険金は、遺産分割の対象・「特別受益」になる?わかりやすく解説!
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合
上述のように、基礎財産に算入される贈与財産の範囲は、民法上一定の制限が設けられています。しかし、例外的に相続開始前の1年間(法定相続人の場合には10年間)より昔になされた生前贈与であっても、基礎財産に算入される場合があります。
それが、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」(民法1044条1項後段)です。
このような場合には、受贈者等に不測の損害が生じるおそれはなく、相続人間の実質的公平性を優先しても問題ないため、期間制限が撤廃されています。
ここでいう「損害を加えることを知って」いるとは、損害を加える意図や誰が遺留分権利者であるのか認識していることまでは要求されず、遺留分権利者に損害を加えるべき事実を知っていることで足りるとされています。
たとえば、受贈者が「被相続人のすべての財産を譲り受ける」との贈与契約を締結した場合には、相続人の取り分が全くなくなることを認識しうるため、「損害を加えることを知って」いるといえるでしょう 。
負担付贈与及び不相当な対価による有償行為について
民法1045条1項は、負担付贈与については、その目的の価額から負担の価額を控除した額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入することとしています。
また、民法1045条2項は、不相当な対価をもってした有償行為についても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなし、前項と同様に、目的財産の価額から負担の価額(当該対価)を控除した残額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入することとしています。
受遺者又は受贈者の負担額
受遺者・受贈者による遺留分侵害額の負担
民法1047条1項は、受遺者又は受贈者の遺留分侵害額の請求に係る債務につき、
- 1遺贈と贈与があるときは、受遺者が先に負担する(1号)
- 2遺贈が複数あるとき、又は同時期の贈与があるときは遺贈が複数あるとき、又は同時期の贈与があるときは、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合を除き、その目的価額の割合に応じて負担する(2号)遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合を除き、その目的価額の割合に応じて負担する(2号)
- 3贈与が複数あるときは、後の贈与を受けた者から順次前の贈与を受けた者が負担する(3号)
ということになります。
留分侵害額の算定における債務の取扱い
民法1047条3項は、
- 1受遺者又は受贈者が「遺留分権利者の負担する相続債務(遺留分権利者承継債務)」につき、弁済、免責的債務引受、その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、遺留分権利者の遺留分侵害額請求権の行使により負担する債務を消滅させることができること
- 2この場合に、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅すること
を規定しています。
この規定は、実際上、受遺者又は受贈者が被相続人の事業を承継したなどの理由で相続債務を弁済する場合があると思われますが、この場合に受遺者又は受贈者が遺留分権利者の承継する相続債務の支払をした上で、遺留分権利者にこれを求償することは迂遠であることなどを理由とするものです。
具体例で遺留分侵害額を算定してみましょう
では、以下の具体例を素材にして、実際に遺留分侵害額を算定してみましょう。
| 夫、妻、息子、娘の4人家族で、夫が亡くなりました。 夫が亡くなった時点で有していた財産が2000万円であり、夫が亡くなる20年前に息子に対して医学部の学費として1600万円の生前贈与、夫が亡くなる5年前に息子に対して病院の開業資金として2000万円の生前贈与をしていました。 遺言書においては、妻に1000万円、息子に対して500万円、娘に対して500万円を譲る旨が記載されていました。 この場合において、娘は、息子に対して遺留分侵害額請求をすることができるのでしょうか。 また、できるとして、いくら請求することができるのでしょうか。 |
配偶者である妻の遺留分は4分の1、子である息子と娘の遺留分はそれぞれ8分の1です。
遺言書の記載は、相続時に夫が有していた財産2000万円のうち2分の1に相当する1000万円を妻に、4分の1に相当する500万円を息子と娘に譲るというものであるので、遺留分を侵害せず、遺言書における相続分の指定は問題がないとも思えます。
しかし、開業資金は、病院経営のための営業資金である以上、「生計の資本として受けた贈与」に該当します。そして、開業資金2000万円の生前贈与は「相続開始前の10年間にしたもの」に該当します。
そのため、開業資金2000万円は「贈与した財産の価額」として基礎財産に算入されます。
また、医学部の学費として生前贈与された1600万円についても、夫及び妻の資力からは1600万円という高額の学費を支出することが当然であるとまでは認められないので、当該学費1600万円も「生計の資本として受けた贈与」に該当します。しかし、生前贈与されたのが相続開始の20年前であり、「相続開始前の10年間にしたもの」に該当しないため、基礎財産に算入されないのが原則です。
ただ、医学部の学費の贈与を受けた時点で、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」いた場合には、医学部の学費として贈与された1600万円も基礎財産に算入されることとなります。
以上より、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」いなかった場合には、基礎財産は4000万円(2000万円+2000万円)となり、娘の遺留分は500万円(4000万円×8分の1)である以上、遺言書における相続分の指定は娘の遺留分を侵害しません。そのため、娘は息子に対して遺留分侵害請求をすることはできません。
他方、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」いた場合には、医学部の学費1600万円も基礎財産に算入されることになるため、基礎財産は5600万円となります。この場合、娘の遺留分は700万円(5600万円×8分の1)となるため、遺言書における相続分の指定は200万円の限度で娘の遺留分を侵害していることになります。そのため、娘は息子に対して200万円の限度で遺留分侵害額請求をすることができます。
※遺留分の割合については、記事「法改正で遺留分制度はこう変わった!~例を用いて算定方法も解説~」で詳しく解説していますので、参照してみてください。
遺留分で迷ったら、弁護士に相談を
本記事でご説明したように、特別受益にあたる生前贈与が、相続人以外の第三者に対してなされた場合には、相続開始前の1年間に当該贈与がなされたときに限り、遺留分侵害の対象となります。他方で、特別受益にあたる生前贈与が相続人に対してなされた場合には、相続開始前の10年間になされたときに限り、遺留分侵害の対象となります。
このように生前贈与の相手方によって期間や対象となる贈与の範囲(特別受益にあたる場合に限られるのか否か)が異なってきますので注意が必要です。
また、本記事では、遺留分侵害の成否や特別受益の範囲については、テーマとの関係上、必要な範囲で簡潔に言及するに留まりましたが、遺留分制度や特別受益との範囲とも密接に関係するので、※部分で記載した他の記事も参照してみてください。
遺留分額の計算方法がわからなかったり、協議がまとまらない等のトラブルでお困りの際は、当事務所のプロの弁護士が、一括でサポートさせていただきます。
お困りの際は、お早めにお問い合わせください。
遺留分に関するご相談は、こちらのページから弁護士費用をご確認いただけます。
遺留分についてお悩みの方へ
遺留分額の計算から協議、まとまらない場合は遺留分侵害額請求訴訟まで、ご依頼者様の意向を
汲み取りながら、プロの弁護士が適正に解決を図ります。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
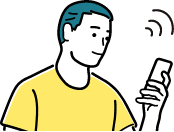
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


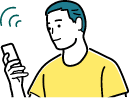


 メールで
メールで