
columns
弁護士コラム
法改正で遺留分制度はこう変わった!~例を用いて算定方法も解説~
- 遺留分のトラブル
- 投稿日:2022年09月13日 |
最終更新日:2022年09月13日
Q
相続法改正における遺留分制度の見直しとは何ですか?
遺留分の割合や、算定方法についても教えてください。
相続法改正における遺留分制度の見直し
はじめに
民法上、それぞれの相続人の相続財産に対する分け前の割合(相続分といいます)について定められており、これを法定相続分といいます。しかし、相続においては被相続人(亡くなった方)の意思を尊重するべきであるため、被相続人の意思が遺言書等に表れているときは、被相続人の意思が法定相続分(民法で定められた相続分)に優先します。
もっとも、夫の死後に妻が相続した財産を自身の生活費に充てるといったように、相続は相続人の生活保障の意義を有することなどの理由から、民法上、相続財産の一定割合につき、後述の遺留分権利者に対して、被相続人の相続財産に対する分け前を認める権利を認めています。
これを遺留分制度といいます。
相続法改正において、遺留分制度のうち、以下の点が見直されました。
- 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ変更されました。
- 受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部または一部の支払につき相当の期限を許与することができるようになりました。
- 遺留分算定の基礎となる財産(基礎財産)の算定方法が明確化されるとともに、範囲が変更されました。
本記事では、上述の変更点について詳しく解説します。
遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権への変更
従来、遺留分が認められる相続人(遺留分権利者といいます)は、遺留分が侵害された場合、遺留分の額を保全するために、必要な限度で遺贈や生前贈与の一部の効力を失効させ、相続財産に戻すことができました。これを、遺留分減殺請求権といいました。
しかし、遺贈等の対象が不動産である場合に遺留分減殺請求がされると、不動産の所有者が受贈者と遺留分減殺請求をした者の2人になる、すなわち、共有関係が生じることとなり、共有関係を解消するために新たなトラブルが発生することがありました。
そのため、相続法改正において、遺留分が侵害された場合において、遺留分権利者に認められた権利が、受贈者等に対して、遺留分が侵害された額に相当する金銭の支払いを求めることができるものに改められました。これを、遺留分侵害額請求権といいます。
この遺留分侵害請求権を受けた受遺者・受贈者は、所定の負担ルールに従い、遺留分侵害額につき債務を負担することになります。
基礎財産の算定方法の明確化・範囲変更
相続人に対する生前贈与の範囲
改正前民法の下において、判例・実務上、相続人に対する生前贈与は、期間制限なく各相続人の遺留分を算定する際の基礎となる財産(基礎財産といいます)に含まれるものと取り扱われてきました。その結果、何十年前の贈与であっても、遺留分の基礎財産に算入されることになり、遺留分減殺請求権(現在は遺留分侵害額請求権)の対象となるため、受遺者に不測の事態が生じることがありました。
このような事態が発生することを防止するために、相続法改正では、相続開始前10年間になされた、婚姻若しくは縁組のため又は生計の資本として受けた贈与(これらをまとめて特別受益といいます)に限って、基礎財産に算入すると改められました(改正民法1044条3項)。
なお、特別受益の範囲については、別記事「「特別受益」とは?具体的な事例とともにわかりやすく解説!」をご参照ください。
負担付贈与
負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除した額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入します(改正民法1045条1項)。
不相当な対価による有償行為
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすことになりました(改正民法1045条2項)。
支払いに対する相当の期限の許与
遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変更されたことにより、受贈者は遺留分権利者に対して金銭を支払うことになりましたが、現金不足などの理由により、受贈者が即時に支払えない事態も考えられます。
そのような事態に備えて、相続法改正では、受遺者又は受贈者の請求により、裁判所が、支払いの全部又は一部につき相当の期限を許与することができるようになりました。
遺留分の割合
遺留分権利者
遺留分はすべての相続人に認められているものではなく、以下の相続人に限り遺留分が認められています。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(父母または祖父母)
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、配偶者や子が相続人の場合には法定相続分(下表参照)の2分の1となります。また、相続人が直系尊属(父母または祖父母)の場合には、遺留分の割合は法定相続分の3分の1となります。
なお、子や直系尊属が複数いる場合には、遺留分の割合は上記の割合を頭数で割ったものとなります。
| 法定相続分 | |
| 配偶者のみ | 相続財産の全部 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
| 子のみ | 相続財産の全部 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
| 直系尊属のみ | 相続財産の全部 |
計算例
被相続人である夫Aに、妻Bと子C、Dがいる場合には、相続人が複数いるため、妻の遺留分の割合は相続財産の4分の1(法定相続分2分の1×2分の1)となります。
他方、子C、Dの遺留分の割合は相続財産の8分の1ずつになります(法定相続分4分の1(子の法定相続分2分の1÷子の人数2人)×2分の1)。
遺留分の算定方法 遺留分算定における基礎財産の範囲の変更
遺留分の算定方法
遺留分は次の計算式により算定されます。
| 遺留分 = 遺留分を算定するための財産の価額 × 遺留分の割合 |
なお、遺留分「侵害額」は、改正民法1046条2項により、上記「遺留分額」から「遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与(特別受益)の価額」及び「第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額」を控除し、これに「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額」を加算して算出します。
| 遺留分侵害額 = (改正民法1042条の規定による遺留分額) -(遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の価額) -(900条から902条まで、903条及び904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額(寄与分による修正は考慮しない。)) +(899条の規定により遺留分権利者が承継する相続債務の額) |
遺留分を算定するための財産の価額
遺留分の割合をもとに、各相続人の遺留分を算定する際の基礎となる財産を基礎財産といい、以下の計算式(1043条1項)で算定されます。
| 基礎財産 = 被相続人が相続開始の時において有した財産 + 贈与財産 - 相続債務の全額 |
「被相続人が相続開始の時において有した財産」
相続人が承継したプラスの財産をいい、ここには遺贈された財産も含まれます。
ただし、祭祀財産や被相続人の一身に専属する権利はこれに含まれません。
贈与財産
基礎財産に算入される贈与財産は、下記の4つです。
- 1相続人以外の者に対する贈与については、原則として、相続開始前の1年間にされた贈与財産
- 2相続人に対する相続開始前の10年間にされた贈与財産
- 3当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与財産
- 4当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした不相当な対価の有償行為の対象となった贈与財産
以下、それぞれについて解説します。
相続人以外の者に対する相続開始前の1年間にされた贈与財産
贈与された財産であればどんなものでも含まれるものではなく、原則として、「相続開始1年前にした」贈与に限り、基礎財産に算入されます(1044条1項前段)。
ここでいう「相続開始1年前にされた」とは、贈与契約が相続開始前の1年間に締結されたことを意味します。
なお、財産の価額は、相続開始時点の財産価値を基準とします。
相続人に対する相続開始前の10年間にされた贈与財産
上述のように、相続人に対する贈与財産は、相続開始前10年間になされた、婚姻若しくは縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に該当する場合には、基礎財産に算入されます。
※「自分の子の学費を負担してくれる場合には不動産を贈与する」などといった負担付き贈与については、贈与財産の価額から負担の価額を控除した額を、遺留分を算定するための基礎財産に算入します。たとえば、学費として支出しなければならない負担額が500万円であり、譲り受けた不動産価額が1000万円である場合には、1000万円から500万円を控除した残額である500万円が基礎財産に算入されることになります。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与財産
上述のように、基礎財産に算入される贈与財産は、相続人以外の者に対しては、相続開始前の1年間にされたもの、相続人に対しては、相続開始前の10年間にされたものに限られるのが原則です。
しかし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与財産は、基礎財産に算入されるとしても当事者双方に不測の損害を加えることにならないため、基礎財産に算入されます。
なお、「損害を加えることを知って」したとは、当事者双方が、贈与が遺留分権利者の遺留分を侵害すると認識しており、かつ、被相続人の財産が将来少なくとも増加しないことを認識していたことを意味します。当事者双方が遺留分権利者を害しようとする意思まで必要とされていません。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした、不相当な対価の有償行為の対象となった贈与財産
贈与財産を譲り受ける際に、対価を支払ったとしても、「1000万円の財産を100万円で譲る」といった不相当な対価の有償行為である場合には、遺留分権利者を侵害するおそれがあります。
他方、当事者双方が認識していない場合には、当事者双方に不測の損害が生じるおそれがあります。
そのため、「損害を加えることを知って」した場合に限り、不相当な対価の有償行為の対象となった贈与財産は基礎財産に算入されます。「損害を加えることを知って」の意味は、上述のものと同様です。
| 【持戻しの免除の意思表示と遺留分について】 相続人が特別受益(生前贈与)についての持戻し免除の意思表示をした場合に、当該特別受益の額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算定することができるか問題となります。 当該特別受益の額は、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合には、当然「遺留分を算定するための財産の価額」に算入されるものと解されます。 この点につき、改正民法1044条3項は、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の額に限る。)を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入する旨規定していることから、このことを当然の前提とした規定と解されます。 つまり、持戻し免除の意思表示は、旧民法と同様に、遺留分侵害額の算定には関係しないと解されます。 |
債務
相続債務については、遺留分制度が、相続人が現実に取得する財産を基礎にして遺留分権利者に一定割合を留保する制度である以上、消極財産(価値がマイナスの財産)である相続債務は基礎財産から控除されます。
計算例
ここまでで、遺留分制度における遺留分の割合及び遺留分の算定方法について解説してきました。
ここまでの内容の確認として以下の例を素材に、実際に遺留分を算定してみましょう。
【例】
| 被相続人Aには、妻B、子C・Dがおり、相続財産は2000万円である。 またAは、死亡する3か月前に、弟であるEに対して、子C、Dの学費(1000万円)を負担してくれる場合には、所有するマンション(評価額3000万円)を贈与するという負担付き贈与をしている。 この場合における子Cの遺留分はいくらか。 |
【解説】
まず、基礎財産に関して、相続財産として2000万円があり、当然に基礎財産に算入されます。
そして、上記負担付き遺贈は「相続開始前の1年間」にされたものといえるので、贈与財産の価額3000万円から負担の額1000万円を控除した額である、2000万円が基礎財産に算入されます。
そのため、基礎財産は4000万円となります。
次に、遺留分の割合については、まず子全体の遺留分の割合は2分の1です。
そして、上記の例の場合、子Cの他に子Dがおり、子は2人であるので、子の法定相続分は4分の1(2分の1×2分の1)となります。
つまり、基礎財産4000万 × 子の遺留分の割合8分の1(子Cの法定相続分4分の1×2分の1)
=子Cの遺留分500万円となります。
遺留分の質問やお悩みは、弁護士に相談を
本記事でご説明したとおり、相続法改正により遺留分制度が大きく変更されました。
遺留分に関する問題には、遺留分侵害額請求と時効の問題、具体的な遺留分侵害額の計算方法等、様々なものがあります。
遺留分額の計算方法がわからなかったり、協議がまとまらない等のトラブルでお困りの際は、当事務所のプロの弁護士が一括でサポートさせていただきます。お困りの際は、お早めにお問い合わせください。
遺留分に関するご相談は、こちらのページから弁護士費用をご確認いただけます。
遺留分についてお悩みの方へ
遺留分額の計算から協議、まとまらない場合は遺留分侵害額請求訴訟まで、ご依頼者様の意向を
汲み取りながら、プロの弁護士が適正に解決を図ります。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
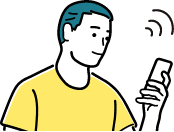
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


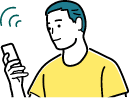


 メールで
メールで