
columns
弁護士コラム
【相続税対策】家族名義の預金は相続財産になる場合がある!
- 相続税・事業承継対策
- 投稿日:2022年08月26日 |
最終更新日:2022年08月26日
- Q
- 子ども名義の定期預金は、相続財産になるのでしょうか?
- Answer
-
結論からいえば、子ども名義の定期預金は、相続財産になる場合があります。
したがって、相続財産にあたるとされる「子ども名義の定期預金」であるにもかかわらず、相続財産に含めずに申告を行うと、過少申告となってしまうおそれがあります。
本記事で詳しく解説します。
目次
家族名義の定期預金
原則的な取り扱い
子ども名義の定期預金は、言い換えれば「家族名義の定期預金」です。
では、家族名義の定期預金は、相続財産なのでしょうか?
原則的な取り扱いは、次の通りです。
そもそも、定期預金は、預貯金等の一種です。そして、預貯金等は、一般的にはその名義人に帰属します。したがって、ある家族名義の預貯金等は、原則的にはその名義人である家族本人に帰属するのです。
例えば、子ども名義の定期預金は、その「子ども」に帰属するということになります。
よって、被相続人本人(例えば、名義人である子の父母)の預貯金等ではありませんから、相続財産にも当たらない、というのが原則的な取り扱いとなります。
だからこそ、本来的には、相続税の課税対象ともなりません。
※相続税の課税対象は、相続により取得した財産の全てです。逆に言えば、相続財産に含まれない(相続していない)財産は、課税対象とはなりません。
| (相続税法第二条・第一項) 第一条の三第一項第一号…の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 (相続税法第一条の三・第一号イ) 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 一 相続又は遺贈…により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 一時居住者でない個人… |
例外的な取り扱い
しかし、預貯金等については、被相続人以外の、別の名義への預け替えを容易にすることができます。したがって、単純に名義だけを基準として預貯金等の帰属を判断してしまうと、極めて容易な脱税手段を認めてしまうことになりかねません。
そこで、預貯金等の帰属の判断に当たっては、単に名義人が誰なのか、という形式的な基準のみならず、預貯金等の原資である金員の出捐者(出資者)が誰なのか、その預貯金等の管理は誰がどのように行っているのか、などを総合的に検討する必要が生じます。
このような総合的な検討の結果、名義は子供であるけれど、実質的には被相続人である父母に帰属する相続財産である、と判断されることもあり得ます。
そのような場合には、子ども名義の定期預金であっても、「相続…により取得した財産」に含まれるべきであるとなりますから、相続税の課税対象になります。
もしも、このような子ども名義の定期預金を相続税の申告から漏らしてしまえば、過少申告となってしまう、というわけです。
具体的な検討の方法
預貯金等の帰属は総合的に検討することになりますが、具体的には、どのように検討すればよいのでしょうか。
この検討に当たっては、先述の、
- 1預貯金等の原資である金員の出捐者(出資者)が誰なのか
- 2その預貯金等の管理は誰がどのように行っているのか
- 3生前贈与があったのか
の検討が重要となります。
まず、①預貯金等の原資である金員の出捐者(出資者)について見ていきましょう。
預貯金等の名義人本人が原資を出資していれば、その預貯金等は、名義人である家族に帰属することは疑いがありません。
したがって、被相続人の相続財産にもなりません。
他方で、預貯金等の名義人本人は原資を出資しておらず、被相続人が生前に原資を出資していたのであれば、その預貯金等は、名義人である家族には帰属せず、生前の被相続人に帰属していた相続財産であると判断されることがあります。
次に、②その預貯金等の管理は誰がどのように行っているのかについて見ていきましょう。
預貯金等の名義人本人が通帳や印鑑の管理を行っていれば、その預貯金等は、名義人である家族に帰属します。
したがって、被相続人の相続財産にもなりません。
他方で、預貯金等の名義人本人が通帳や印鑑の管理を行っていないのであれば、その預貯金等は、名義人である家族には帰属せず、生前の被相続人に帰属していた相続財産であると判断されることがあります。
【具体例】
例えば、預貯金等の名義人が子供である、子ども名義の定期預金があるとします。
そして、
- その口座開設の届出印が、被相続人の他の預貯金等の届出印と同じで変更がない
-
名義人本人は、その口座や預貯金等を自由に管理・処分できない
(名義人である子ども自身は、通帳や印鑑を管理していないなど)
- 住所変更等の手続を名義人本人が行っていない
など、名義人である子ども自身が管理を行っていると言い切れない場合や、名義人である子ども自身が管理を行っていないことについての合理的な経緯や理由を明らかにできない場合が考えられます。
このような場合には、その預貯金等は、名義人である子どもには帰属せず、生前の被相続人に帰属していた、相続財産であると判断されることがあります。
さらに、③生前贈与があったのかについて見ていきましょう。
確かに、被相続人がその預貯金等の原資である金員を出資しており、あるいはその預貯金等の管理を行っていた場合には、先述のとおり、その預貯金等は被相続人に帰属します。
しかし、仮にそのような預貯金等であったとしても、この預貯金等をその口座の名義人である家族に贈与していた場合には、その預貯金等は、名義人である家族に帰属しています。
したがって、その場合には、その預貯金等は相続財産とはならず、課税対象ともなりません。
このような場合には、
-
名義人である家族が、その口座や預貯金等を自由に管理・処分できるのか、
(名義人である子ども自身は、通帳や印鑑を管理していないなど)
- 名義人である家族が、その口座や預貯金等を自由に管理・処分できないのであれば、名義人本人が管理を行っていないことについての合理的な経緯や理由を明らかにできるのか
が重要なポイントとなります。
(自由に管理・処分できる、そうでなくとも合理的な経緯や理由を明らかにできる、という場合には、その預貯金等は名義人である家族に帰属している、と言えることになります。)
生前贈与と相続税の申告
このように、被相続人が、生前に、その口座の名義人である家族に預貯金等を贈与していた場合、その預貯金等は相続財産とはならず、課税対象ともならないのが原則です。
ただし、相続税の申告の場面では、被相続人の生前の贈与を、相続により財産を取得したものとみなして、申告する必要がある場合があるため、注意が必要です。
※なお、被相続人が死亡した日の属する年に被相続人から贈与を受けていた場合には、原則として贈与税ではなく相続税の申告を行うことになります。
具体的には、
a. 相続時精算課税制度を選択している場合
b. 相続時精算課税制度を選択していない場合
の区別が重要となります。
相続時精算課税制度を選択している場合
まず、相続時精算課税制度の選択を受けている財産は、相続により財産を取得したものとみなされるため、相続税の申告をする必要があります。
確かに、生前贈与を受けた財産については、贈与を受けた年分の贈与税の申告を行う必要があります。しかし、相続時精算課税制度の選択を受けている財産については、相続税の申告の際、相続財産に含めて申告を行うことになります。
したがって、年分に納付した贈与税と、相続税との精算が必要となります。
相続時精算課税制度を選択していない場合
相続時精算課税制度の選択を受けていない財産であっても、被相続人の死亡前三年以内に、被相続人から贈与を受けた財産については、相続により財産を取得したものとみなされるため、相続税の申告をする必要があります。
相続時精算課税制度の選択を受けている財産については、相続で財産を取得した人が、生前贈与を受けていた場合には、原則としてその財産の贈与された時の価格(当時の時価)を相続財産の価格に加算します。
なお、この加算は、暦年課税制度との関係で申告が不要だった場合にも、行う必要があります(相続税法第十九条参照)。
(※「相続時精算課税」については、下記の「*その1 相続時精算課税の制度とは」を、「暦年課税」については、下記の「*その2 暦年課税とは」をご覧ください。)
その1 相続時精算課税の制度とは
相続時精算課税の制度とは、二つある贈与税の課税方法のうちのひとつです。
原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度となっています。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除し、その残額に対して贈与税がかけられることになります。
なお、この特別控除は、贈与税申告の期限内に申告書を提出する必要があります。
その2 暦年課税とは
暦年課税とは、二つある贈与税の課税方法のうちのもうひとつです。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかけられます。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告も不要になります。贈与税の課税は、暦年課税です。
以上については、詳しくは、こちらから国税庁のホームページもご参照いただけます。
過少申告とされてしまった場合
もしも過少申告とされてしまった場合には、どうなってしまうのでしょうか。
被相続人に帰属していたと判断されるべき預貯金等について、子ども名義であることを理由に申告しなかった場合、相続税の過少申告と判断されかねないため、問題となります。
まず、重加算税が科せられる場合があります(国税通則法第六十八条・第一項参照)。
具体的には、次のような場合に、重加算税が課せられます。
納税者(申告を委任された税理士など、納税者と同視できる者を含みます)が、
その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を
- 隠蔽していたとき
- 仮装していたとき
- 隠蔽し、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたとき
このように、重加算税を課すための要件には、過少申告をしてしまったこととは別に、隠蔽や仮装と評価されるべき行為をしていることが含まれています(「隠蔽し、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していた」)。
税理士などに相談するときにも、隠蔽や仮装と評価されかねない行為をしないよう気をつけることが大切です。
| 第六十八条 …(過少申告加算税)の規定に該当する場合…において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、…過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額…に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。 |
まとめ
子ども名義の定期預金は、相続財産になる場合があります。
どのような場合に相続財産と判断されるかは、
- 1預貯金等の原資である金員の出捐者(出資者)が誰なのか
- 2その預貯金等の管理は誰がどのように行っているのか
- 3生前贈与があったのか
を具体的に検討することが重要となります。
仮に、相続財産にあたるとされる「子ども名義の定期預金」であるにもかかわらず、相続財産に含めずに申告を行うと、過少申告となってしまう場合があります。
以上のポイントをふまえて、重加算税を課せられたりすることのないよう、十分注意して申告を行いましょう。
相続税・事業承継対策についてお悩みの方へ
相続税・事業承継においては、ご自身にとってどの方法が効果的な対策となるのか、見極めることがまず大事です。トラブル防止の観点からも最適な対策・進め方ができるよう、プロの弁護士が専門家とも連携して安心のサポートをいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
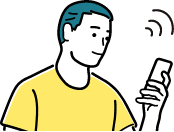
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス

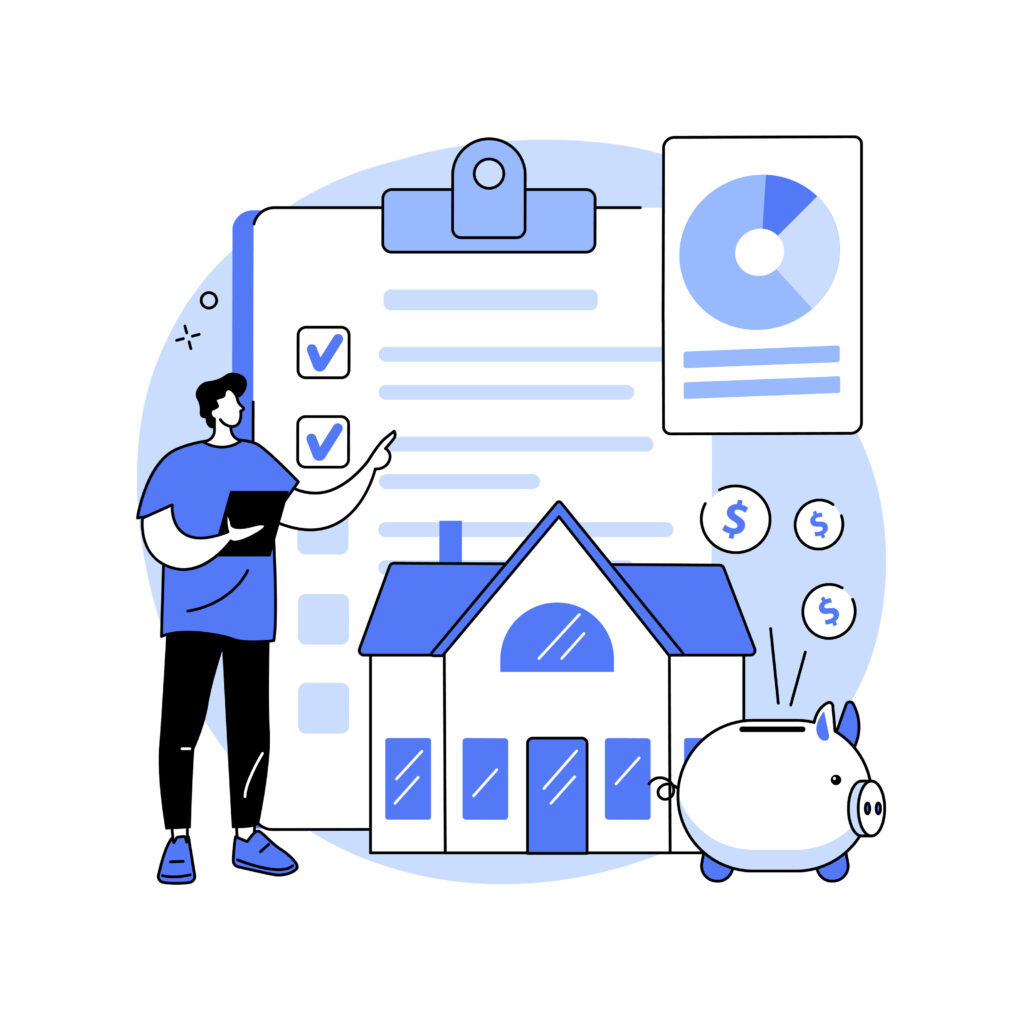
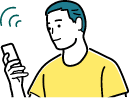


 メールで
メールで