
columns
弁護士コラム
生前の預金引き出しはどこまで許される?相続リスクと税務署が指摘するポイントを解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年11月21日 |
最終更新日:2025年11月25日

- Q
-
最近、母の物忘れがひどくなり、銀行手続きなどを代行することが増えてきました。将来、入院することや葬儀費用を考えると、今のうちに預金を引き出しておいた方が良いのではと漠然と考えていますが、相続税対策になるのか、後で税務署から指摘されないか不安です。また、遠方に住む兄に「勝手にお金を使っている」と疑われるのが怖く、どうすれば正当な管理として認められるのか、具体的な方法が分からず悩んでいます。
そこで、生前に親の預金を引き出す際の税務上の注意点や相続税対策になるのか教えてください。他の兄弟とトラブルにならないために、どのような権限(委任状など)が必要で、どうお金を管理すれば良いのかを具体的に知りたいです。
また、親の認知能力が低下してきた際に、法的に気を付ければ良いことも把握しておきたいです。
- Answer
-
単に親の口座から預金を引き出すだけでは相続税対策にはなりません。むしろ、税務署から申告漏れ、他の相続人からは使い込みを疑われるリスクがあります。このリスクを避けるためには、親との間で委任契約を締結し、可能であれば公正証書を作成して法的な権限を明確にすることが必要です。
さらに、引き出した金銭は領収書を保管するなどして使途を明確にし、後日、何に使ったのかを証明する体制を整えてください。親の認知能力が低下している場合は、委任契約が無効となる可能性があるため、成年後見制度や任意後見契約などの制度の検討が必要な場合もあります。
この記事では、生前の預金管理に不安を持つ方が、税務上・法的なリスクを回避し、後の相続紛争を未然に防ぐための具体的な手法を解説します。
監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
親の入院費や介護費に備え、生前に預金を引き出す行為は、一見親孝行に見えますが、実は税務署からの指摘や、兄弟間から使い込みを疑われるなど、トラブルを引き起こす原因になるリスクがあり、注意が必要です。
この記事では、生前の預金引き出しが相続税の節税にならない理由や税務署のチェックポイントなど、トラブル回避の方法を解説します。
記事を読んでいただくことで、親の財産を適正に管理し、「争族」を回避できるようになります。

目次
生前の預金引き出しは相続税対策として有効か?

「親が亡くなる前に預金を引き出して現金化すれば、相続税がかからなくなる」という考えは、結論として誤りです。
相続税の計算は、被相続人が亡くなった時点(相続開始日)で保有していた財産総額を基準に行われます。預金口座から1,000万円を引き出したとしても、財産が預金から現金に形を変えただけであり、財産の総額自体は一切減少していません。
そのため、亡くなった時点で自宅などに保管されていた現金も、病院の支払いや生活費として実際に使用した分を差し引いた残額は、預貯金と同様に相続財産として申告の対象になります。したがって、生前に預金を全額引き出しておくことは、相続税の節税対策にはなりません。
さらに、節税を目的とした安易な預金の引き出しは、効果がないばかりか、以下のようなリスクを招く原因となります。
- 税務署からの調査リスク
- 預金から引き出された現金の使途が不明瞭だと、税務署から「申告漏れ」や「財産隠し」を疑われ、税務調査の対象となりやすくなります。
- 他の相続人とのトラブルリスク
- 他の相続人から「親の財産を勝手に使い込んだのではないか」という不信感を抱かれ、遺産分割協議が紛糾する恐れがあります。
このように、安易な引き出しは節税につながらず、むしろ税務上・法的なリスクを増大させることを理解しておくことが重要です。
生前に預金を引き出すときの正しい手続き方法

相続を見据えて親の預金を引き出す行為は、後に税務署や他の相続人から不当な行為だと追及されないよう、必ず親の明確な意思と法的な根拠に基づいて行う必要があります。
ここでは、生前に預金を引き出すときの正しい手続き方法を紹介します。
委任状・代理権限の準備
親の預金を子が引き出す際、金融機関の窓口で提示が求められるのは、原則として親本人からの委任状です。
委任状には、「誰(子)に」「どの金融機関の」「どの口座から」「いくらまで」「何のために(例:生活費の支払い、医療費の支払い)」といった委任の範囲と目的を具体的に明記します。
この委任状は権限の証明となりますが、親の意思能力が低下してから作成された委任状は、その有効性を巡って争いになりやすいため、親の判断能力が明確なうちに作成することが重要です。
公正証書による契約にしておくメリット
親の財産管理をより広範囲かつ長期的に行う場合は、単なる委任状ではなく、財産管理委任契約を締結し、公正証書にしておくことが強く推奨されます。
公正証書は、公証役場で公証人が本人(親)の意思を確認して作成するため、契約当時に本人に意思能力があったことを証明する、信頼性の高い資料となります。
また、委任の範囲や期間を明確に文書化することで、他の相続人に対し、管理行為の透明性を示すことができ、後の使い込みトラブルの予防につながります。
税務署は生前の預金引き出しをどう見るか

税務署は、相続税調査において、被相続人本人だけでなく、その家族の預金口座についても、過去数年分(場合によっては10年近く)にわたる入出金の状況を徹底的に確認します。
そのため、特に「亡くなる直前の高額な引き出し」や「使途が不明な引き出し」は、相続財産を隠すための意図的な行為、すなわち申告漏れと疑われやすい行動としてチェックされるため注意が必要です。
税務署から申告漏れと判断された場合、本来の相続税に加えて重い追徴課税(ペナルティ)が課されることになります。
自身の財産を次世代へ円滑に引き継ぐためにも、生前の預金引き出しに関する税務上の扱いとリスクを正しく理解し、適切な証拠を残しておくことが大切です。
「直前引き出し」と「生前贈与加算」のルール
税務上、相続税対策を目的として預金を引き出した場合、「直前引き出し」として相続税を少なくするための行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
生前贈与加算のルールにより、相続人が財産を取得する際、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続財産に持ち戻して相続税を計算しなければなりません。なお、2024年1月1日以降の贈与については、加算対象となる期間が順次7年間へ延長されます。
葬儀費用や亡くなられた方の医療費の清算をするための準備資金として引き出したとしても、原則として相続財産に持ち戻される点には注意が必要です。
ただし、引き出した現金が、亡くなられた方の医療費の精算・生活費・施設の費用など、亡くなられた方が生活を維持していくために必要な金額に充てられた場合は、その分について相続財産から控除することが認められます。
この控除を適用するためには、預金を引き出した理由が明確であることに加え、領収書や請求書などの客観的な証拠を確実に残しておくことが不可欠です。
申告漏れが発覚した場合のペナルティ
税務調査で生前の預金引き出しが申告漏れと判断された場合、本来納めるべき相続税に加え、以下の追徴課税(ペナルティ)が課されます。
意図的に財産を隠したとみなされた場合には、最も重い重加算税が課されるリスクがあるため、生前の預金管理の税務上の扱いを正しく理解しておくことが重要です。
| 追徴課税の種類 | 概要 | 税率 |
| 延滞税 | 納付期限の翌日から完納日までの利息に相当する税 | ・ 納付期限翌日から2ヶ月を経過するまで:令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間年2.4%(原則7.3%) ・ 納付期限翌日から2ヶ月を経過した翌日以降:令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間年8.7%(原則14.6%) |
| 過少申告加算税 | 納付税額が少なかった場合や、還付税額が多かった場合に課される | 10%~15% |
| 無申告加算税 | 申告期限までに申告しなかった場合に課される | ・ 税務調査前:5~25%(事前通知後は10~25%) ・ 税務調査後:15~30% |
| 重加算税 | 意図的に財産を隠蔽するなど、悪質なときに課される | 35%~40% |
生前の預金引き出しが法的に認められる「権限」とは

親の預金を引き出す行為は、相続時に他の相続人から無断の使い込みと指摘されやすいリスクがあります。これを避けるためには、その行為を正当化できる法的な権限を持っておくことが必要です。
その権限は、主に親子の間で結ぶ「委任契約」や、緊急時に親の利益のために行動したと認められる「事務管理」といった民法の規定によって、法的な正当性を与えられます。
ここでは、委任契約および事務管理という2つの法的根拠と、それらを証明する際のポイントについて詳しく解説します。
親子間の「委任契約」による権限
親の預金の引き出しを法的に正当な行為とするための最も一般的な根拠は、親(委任者)が子(受任者)に財産管理を任せる「委任契約」とされています。
この契約は、書面がなくても口頭や黙示的な意思表示によって成立しますが、後のトラブルを防ぐために、委任する事務の範囲(生活費・医療費の支払いなど)を明確にした契約書を作成することが望ましいとされてます。
委任契約書などの客観的な証拠がない状況では、裁判所は主に以下の点を総合的に考慮し、「包括的な委任」があったかを総合的に判断します。
- 親の心身の状態
- 委託時の意思能力の有無・程度
- 自ら財産管理を行うことが困難な状況にあったか
- 委任以前の財産管理の状況
- 親子間の信頼関係・環境
- 同居の有無・期間
- 相続人が被相続人の身上監護(身の回りの世話)を行う状況であったか
- 実際の管理状況
- 子から親への財産管理に関する報告の有無
- 払戻しの頻度・金額・使途など
ただし、親が子に通帳や印鑑を預けているという事実だけでは、直ちに預貯金の引き出しについて無制限の権限を与えたとまでは認められません。預金を引き出した目的や使途の合理性が常に問われ、委任の本旨である「親の利益を図る義務」に沿った支出であったかどうかが重要になります。
委任契約がない場合の「事務管理」による権限
親と子の間で預金管理に関する委任契約がなくても、子が親のために医療費の立て替え払いなど、必要な事務を処理した場合には、「事務管理」(民法697条)が成立する可能性があります。
事務管理とは、法律上の義務なく他人のために事務の管理を始める行為のことです。事務管理は、本人のためにする意思をもって本人の利益に適合する事務を行った場合に成立します。
ただし、本人の意思又は利益に反することが明らかである場合は成立しません。事務管理として本人のために有益な費用を支出した場合、子は、その事務を管理するために支出した費用(立替金)の返還を親の財産に対して請求することができます。
例えば、親が病気や入院により自ら動けない状況にある際、子が親の預金から入院費・生活費・介護費用などを引き出して支払う行為は、本人の利益にかなうため事務管理として正当化され、親の財産に対して費用償還請求が可能となる典型的なケースです。
特に、緊急性を要する医療費の支払いなどは、委任契約がなくても権限が認められやすい行為です。ただし、この場合でも権限は必要最小限の範囲に限られます。
事務管理には、親の財産を増加させる行為や、相続人固有の利益を図る目的で預金を引き出す行為は含まれません。また、引き出した金銭が親のために使われたことを客観的に証明できることが不可欠です。
親の意思能力が低下している場合の注意点
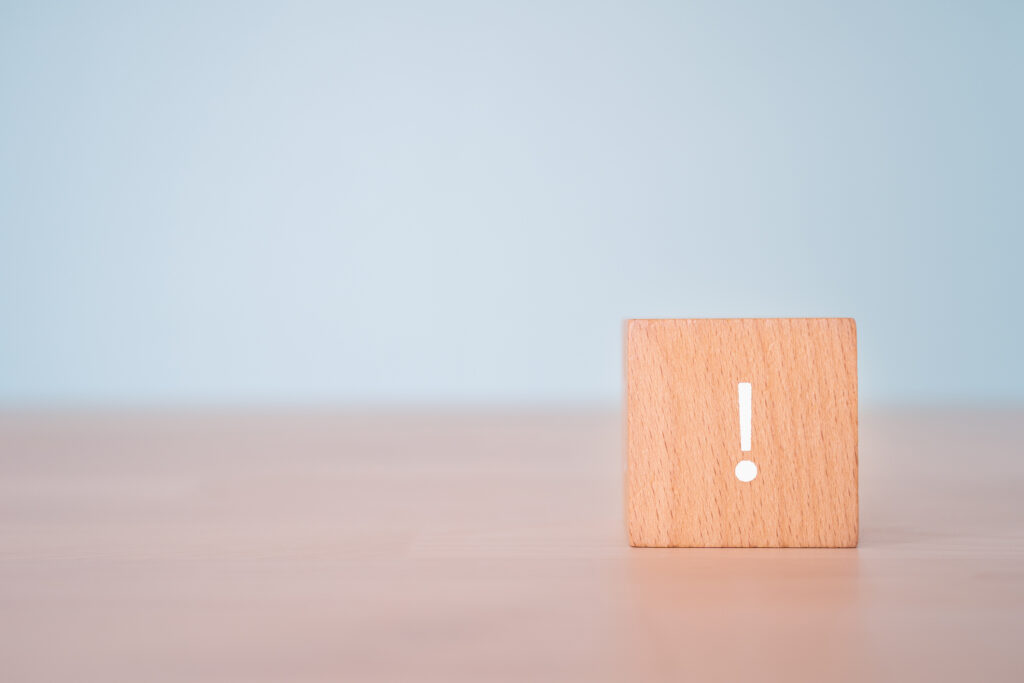
親が認知症などにより、自身の財産に関する判断能力(意思能力)を失っている場合、預金の引き出しや財産管理に伴う法的なリスクは大幅に高まります。
預金の引き出しについて親から委任を受けていたとしても、その委任が有効であるためには、委任をした時点で親に意思能力が備わっていることが必要です。意思能力を欠いた状態で受けた委任は有効とは認められず、後に無権限の行為として責任を追及される可能性が高くなります。
ここでは、委任が無効と判断されうる法的理由と、裁判所が意思能力の有無を判断する際の基準について解説します。
意思能力がない状態での「同意」の無効性
親が認知症などにより、自身の財産の処分や管理行為の意味を理解する能力、すなわち意思能力を欠いている状態で行った承諾や委任は、法的に無効となります。これは、法律行為が成立するためには、行為者がその内容と結果を理解している必要があるからです。
裁判例では、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の点数が1点で、後見相当と判断されるほど意思能力が著しく低下していた被相続人について、子に預金の引き出しを指示したり、承諾を行う能力はなかったと認定されたケースがあります。
したがって、外形上「はい」「いいえ」といった反応や、簡単な身振りで引き出しに同意したように見えたとしても、医療記録などの客観的証拠から、本人が行為の意味や金銭の重要性を理解できない状態であったと認められれば、その承諾は有効と評価されません。
このため、有効な委任が存在しない状態で子が行った預金の引き出しは、無権限の行為として責任を追及される可能性があります。正当性を示すためには、親が十分な意思能力があったことを立証する必要があります。
裁判所における意思能力の具体的な判断基準
相続をめぐる訴訟で意思能力の有無が争点となった場合、裁判所は、長谷川式スケールの点数やカルテ上の「認知症」「認知障害」といった記載のみをもって、直ちに意思能力の有無を判断するわけではありません。
裁判所は、預金の引き出しの指示・承諾(委任)というその行為の意味や結果を本人が具体的に理解できていたかを、以下のような複数の要素から総合的に判断します。
- 行為の複雑さ
引き出しの金額や目的が日常的なものか、もしくは財産全体に影響を及ぼす複雑な処分行為だったか - 日常的な会話の状況
日頃、家族や第三者とどの程度、理路整然とした会話ができていたか - 自身の財産に対する認識
預貯金の残高や収支の必要性をどの程度正確に把握していたか
例えば、裁判例(東京地判平19・10・1)のように、通常の生活費として相当な範囲を超える多額の引き出しについて、その行為の意味を理解する能力(意思能力)がなかったとして、承諾そのものが無効と判断されることがあります。
このように、意思能力は行為当時の理解能力を中心に、客観的証拠によって判断され、その行為の有効性が判断されます。
親の意思能力に少しでも不安がある状態で財産管理を行うと、後に高額な使途不明金として争われ、無効とされる恐れがあります。そのため、安易に預金を引き出すのではなく、成年後見制度・任意後見契約・家族信託といった、より厳格な制度の利用を検討すべきです。
成年後見制度や家族信託との比較

親の意思能力に不安が生じた場合、家族が安易に預金を引き出すことには、法的なリスクがあります。相続トラブルや訴訟を避けるためには、成年後見制度・任意後見契約・家族信託など、より厳格な制度を利用して財産管理を行うことを検討しましょう。
これらの制度は、本人の財産を守るための法的権限を確保する手段ですが、目的・開始時期・柔軟性・費用などに大きな違いがあります。
成年後見制度を利用すべきケース
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になってしまった人を保護し、財産管理や契約行為を支援するための公的制度です。有効な委任契約を締結できない状態にある場合に適した制度といえます。
また、単なる財産管理にとどまらず、介護サービス契約や医療行為への同意などの身上保護に関する法律行為を公的に行う必要があるケースや、家族間の意見対立を避けるために裁判所が選任する第三者へ公正な管理を委ねたいケースでも利用を検討すべきです。
ただし、裁判所が関与するため、管理の厳格さや透明性は高い反面、家族の意向だけで相続対策として不動産売却などの柔軟な財産処分を行うことは難しくなります。
家族信託による管理との違い
家族信託は、委託者(親など)が自身の財産を信頼できる受託者(子など)に託し、生活費の確保など契約で定めた目的に従って財産を管理・運用してもらうための民事信託契約です。
成年後見制度との最も大きな違いは、開始時期と柔軟性にあります。家族信託は、親に十分な意思能力があるうちに契約を結ぶ必要があります。一度契約を結べば、親の判断能力が低下した後も、家族の裁量と契約内容に基づいて柔軟に財産を管理・処分でき、裁判所が介入する成年後見制度より自由度が高い点が特徴です。
ただし、家族信託は、あくまで信託契約の目的に沿った財産管理を行うためのものです。契約書に定められた目的を逸脱した預金を引き出しは義務違反となり、他の受益者から責任を追及される可能性があります。
また、信託の対象とした財産のみが管理下に置かれ、医療・介護の契約など身上保護の代理権は家族信託では付与できず、必要に応じて任意後見制度や成年後見制度の併用が必要になります。
相続時のトラブルを防ぐためのポイント

親の意思能力の有無に関わらず、生前の預金引き出しは、相続発生後に使途不明金として他の相続人から不当な使い込みを疑われ、トラブルに発展するリスクがあります。
意思能力の有無や委任の範囲といった法的問題をクリアしている場合であっても、紛争を未然に防ぐためには、客観的な記録や証拠を残し、他の相続人との信頼関係を確保しておくことが不可欠です。
ここでは、後々の追及や訴訟リスクを最小限に抑えるための重要な2つのポイントを解説します。
使途を明確にし、証拠を保管する
親の預金を引き出した場合、引き出した金銭の使途を明確にし、その証拠となる書類(領収書など)を必ず保管しておきましょう。使途が不明確な金銭は、たとえ親のために使ったつもりでも、相続発生時に使途不明金として扱われ、他の相続人から不当な使い込み(不当利得)として追及されるリスクがあるためです。
引き出したお金を「何に」「いくら」使ったのかを、金銭出納帳などを作成して詳細に記録しておきましょう。そして、親の医療費・介護費・生活費など、本人の利益のために充てた支払いについては、領収書や請求書を必ず保管してください。
これらの記録と証拠は、税務署への説明資料となるだけでなく、他の相続人から使い込みを疑われた際の重要な根拠となり、訴訟においても引き出し行為の正当性を示す有力な証拠となります。証拠がない場合、裁判所が「使途不明金を引き出をした者が勝手に利用した」と判断する可能性が高まります。
他の相続人と情報を共有する
親の財産管理を行う際、その状況を他の相続人にも定期的に報告し、正確な内容を共有しておくことが、後の紛争防止につながります。特に、親の介護や医療に伴い高額な出金が必要になる場合などは、事前に他の相続人に相談して了承を得ておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続開始後に初めて多額の出金を知らされた場合、他の相続人は、たとえ正当な使途であっても、不信感を抱きやすいものです。そのため、日頃から通帳のコピーや出納記録などを共有し、適切なコミュニケーションを図っておくことが、信頼関係を築くうえで極めて重要です。事前に共有しておくことで、使途不明金として追及されるリスクを軽減できます。
弁護士に相談するメリット

相続を見据えた生前の預金引き出しや財産管理は、使い込みを疑われるリスクを防止する法務面だけでなく、相続税リスクを回避する税務面での専門知識も必要となります。
弁護士に相談することで、これらの複雑なリスクを未然に防ぎ、親の財産を安全かつ円滑に次世代へ引き継ぐためのサポートを受けることができます。
税務署からの指摘を防ぐアドバイスが受けられる
弁護士は、過去の相続紛争の判例や税務調査事例の知見に基づいたアドバイスが可能です。
特に、税務署が問題視する「亡くなる直前の高額な引き出し」の金額や頻度、そして使途不明金と疑われないための客観的な記録や証拠の残し方について、具体的な助言を受けることができます。
これにより、意図しない申告漏れを指摘されるリスクを回避できます。
他の相続人とのトラブルの予防策になる
弁護士が関与することで、財産を管理する者の行為が法的に正当なものであることを、他の相続人に対して示しやすくなります。
他の相続人に対し、財産管理の透明性を示す方法や、情報公開の適切な範囲について助言を受けられるため、遺産分割協議で使い込みをめぐる紛争に発展しないよう事前に予防できます。
また、日頃からの、他の相続人とのコミュニケーションについて、具体的なサポートも期待できます。
契約書や手続きの法的整備をしてもらえる
親の意思能力が明確なうちに財産管理委任契約書などの重要な文書を作成する際、弁護士は、後に裁判で争点とならないよう、適切な内容で書面を作成するためのをサポートを提供します。
また、親の認知症が進行した際や、より柔軟な管理を実現するための任意後見契約や家族信託についても、法的な観点から最適な選択肢を提案し、必要な手続きを代行してもらうことができます。
よくある質問(Q&A)

生前の預金引き出しに関するよくある質問と回答をまとめました。
- Q
- 医療費や介護費用なら自由に引き出せますか?
- Answer
-
いいえ、自由に引き出せるわけではありません。
医療費や介護費用など、被相続人本人の利益になる使途であれば、引き出しの正当な権限が認められやすいですが、必ず領収書などの客観的な証拠を保管し、使途を明確にしておく必要があります。
証拠がない場合、たとえ医療費として使ったとしても、税務署や他の相続人から不当な引き出しと疑われるリスクがあります。
- Q
- 相続人全員の同意は必要ですか?
- Answer
-
親が存命中で意思能力があるうちは、親本人からの委任があれば、他の相続人全員の同意は法的に必須ではありません。
しかし、親の意思能力が不安な状態になってきた場合、後のトラブルを避けるためには、高額な引き出しや財産管理の方針について、他の相続人にも情報共有し、理解を得ておくことが強く推奨されます。
- Q
- 税務署に説明する際に必要な証拠は?
- Answer
-
引き出した現金の使途について、客観的に証明できる資料が必要です。
具体的には、被相続人名義の口座からの出金記録に加え、引き出した現金の使途に応じた領収書、請求書、支払先の記録(医療費、介護施設費用、生活費の購入記録など)が不可欠となります。
東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所
生前の預金管理や引き出しの対応は、親の生活費や医療費の確保に直結する一方で、相続開始後にトラブルとなりやすい分野でもあります。特に、意思能力が低下している時期の引き出しについては、後に「委任の有効性」や「使途の妥当性」が争点となり、申告漏れや使い込みの疑いにつながるケースも少なくありません。
そのため、生前の段階で、誰がどの範囲まで預金管理を行うのか、支出の記録をどのように残すのか、といった実務的な整理をしておくことが重要です。財産管理委任契約や任意後見契約の活用を検討する場面もあり、状況に応じて適切な方法を選択することが、後の紛争予防に直結します。
直法律事務所では、生前の預金管理に関するご相談をはじめ、財産管理委任契約・任意後見契約の作成支援、相続トラブルの予防・解決まで、一貫したサポートをご提供しています。「どのように管理を進めるべきか分からない」「家族間のトラブルを避けたい」といったお悩みがあれば、まずは一度ご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで