
columns
弁護士コラム
預金引き出しを相続人が行う際の注意点とは?死亡後のトラブルと立証法を解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年11月11日 |
最終更新日:2025年11月13日
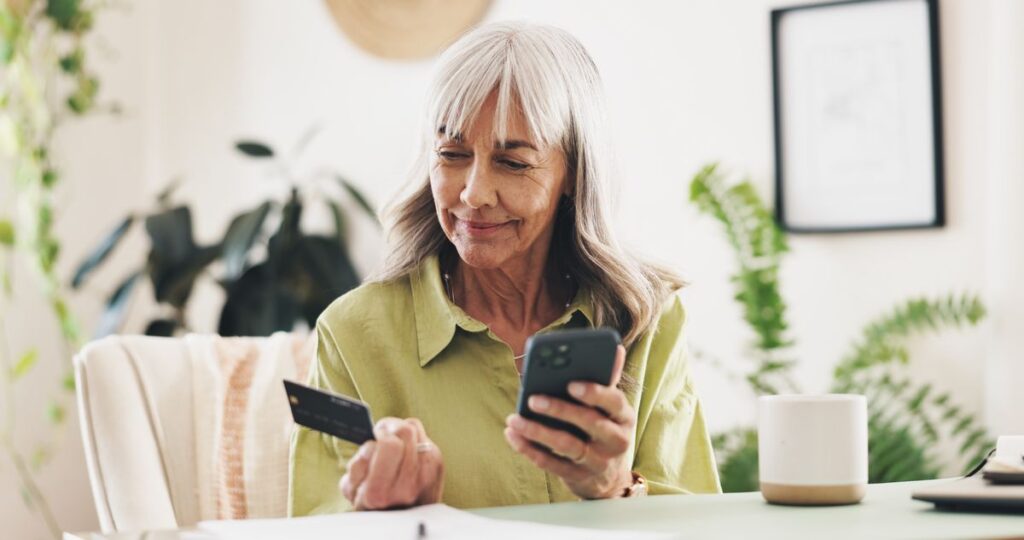
- Q
-
先日亡くなった母の葬儀費用や介護費用の支払いでまとまった現金が必要になりました。母の口座のキャッシュカードは手元にあるため、預金を引き出したいのですが、遠方に住む兄から「遺産分割協議が終わるまでは一切手を付けるな」と強く言われている状況です。
この場合、私の独断で亡くなった人の預金を引き出すと、法的に問題になるのでしょうか。遺産分割の前に、葬儀費用などを引き出すための正式な手続きや、他の親族と揉めないようにするための注意点も教えてほしいです。
- Answer
-
亡くなったお母様の預貯金は、相続人全員の準共有で、財産遺産分割の対象財産となります。そのため、原則として、遺産分割協議が終わるまで、相続人が単独で引き出すことはできません。もし、他の相続人の同意なく引き出すと、後から使い込みを疑われ返金を求められるなどのトラブルに発展する危険性があります。
しかし、遺産分割協議前でも預金の一部を単独の相続人が払戻しを受けることができる「預貯金の仮払制度」を利用することも考えられます。相続人が当面の生活費に困っている場合や、葬儀費用などの支払いなどで資金が必要な場合、この制度を利用すれば、各相続人が単独で、金融機関ごとに最大150万円まで引き出すことが可能です。
この記事では、故人の預金口座から遺産分割協議の成立前にお金を引き出す方法や遺産分割協議成立後にお金を引き出す手続きなど、よくあるトラブルなどについて詳しく解説していきます。
監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
親の死亡後に預金を引き出す必要があっても、どこまで認められるのか不安に感じる方は多いでしょう。実は、一定の条件を満たせば正当な手続きで引き出すことも可能です。
本記事では、引き出しが認められる具体的なケースや注意すべき法的ポイントをわかりやすく整理しています。

目次
死亡後の預金引き出しは違法?適法?

被相続人が亡くなり相続が発生すると、預貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象となり、遺産分割協議成立まで相続人全員の準共有となります。そのため、預金口座からお金を払い戻すことができるのは、相続人全員で話し合う遺産分割協議が成立した後であるのが原則です。なお、金融機関は、預金をした者がなくなると、その口座を凍結するため、それ以降は出金や振込などができなくなります。
しかし、ご家族が亡くなると、葬儀費用や入院費用の精算など、急な支払いが必要になる場面は少なくありません。このような場合に、遺産分割協議が終わる前に預貯金を引き出すことはできないのでしょうか。
この点、横領罪などの犯罪として罰せられる可能性は低いと考えられます。日本の法律には「親族相盗例」という特例があり、一定の親族間での窃盗や横領などについては、刑事罰が免除されることが多いためです。
ただし、たとえ罪に問われなくても、民事上のリスクはあります。例えば、他の相続人から不当に得た利益を返すよう求める不当利得返還請求や、不法行為によって損害が生じたとして損害賠償請求をされるかもしれません。
また、無断で故人の預金口座からお金を引き出して私的に使うと、遺産相続を「単純承認」したとみなされ、多額の負債が発覚しても相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
同意なしで引き出せる正式な手続き

原則として、故人の預金を引き出すには相続人全員の同意が必要です。しかし、遺産分割の話し合いがまとまるまでには時間がかかることも多く、葬儀費用や入院費用の精算、当面の生活費などの支払いに困ってしまうこともあります。
そこで法律では、以下のようなケースに該当する場合、他の相続人の同意がなくても、一部または全部の預金を引き出すことが認められています。
- 遺言書で預金の相続が指定されている
- 預貯金の仮払制度を利用する
- 裁判所で仮分割の仮処分が認められる
ここでは、これらの3つの具体的なケースについて、それぞれの要件や手続き方法などを解説します。
遺言書による指定
被相続人が生前に作成した遺言書に「〇〇銀行の預金は長男〇〇に相続させる」というように、特定の預金を受け取る相続人が明確に指定されている場合があります。
このような遺言書がある場合、指定された人は単独で預金を引き出す正当な権利を持っています。遺産相続において遺言は故人の最終的な意思表示を示すものであり、相続人の全員による遺産分割協議よりも優先されるとされているためです。
指定された人は、遺産分割協議が終了を待つことなく、遺言書とその他の必要書類(故人の死亡がわかる戸籍謄本や相続する人の印鑑証明書など)を金融機関の窓口に提示することで、口座の解約や名義変更の手続きを進めることができます。
預貯金の仮払制度
2019年7月の民法改正によって新しく作られた「預貯金の仮払制度(民法909条の2)」を利用する方法もあります。預貯金の仮払制度は、遺産分割が終わるまでの間、葬儀費用や残された家族の当面の生活費などの支払いに困らないようにするために設けられました。
この制度を利用すると、各相続人は亡くなった人の預金口座(定期預金の場合は明細)ごとに、以下の計算式で求められる額について、金融機関から単独で引き出すことができます。
| (死亡時の預金残高)×(1/3)×(その相続人の法定相続分) |
ただし、同一の金融機関からの払戻しは「150万円」が上限となります。(同じ金融機関の複数の支店に預金がある場合もその全支店で合計します。)
例えば、相続開始時の預金額が900万円、相続人が妻と子1人の計2人であるとしましょう。
この場合、法定相続分は妻1/2、子1/2であるため、各相続人はこの金融機関にある故人の預金口座から「(900万円 × 1/3 × 1/2)= 150万円」まで引き出すことができます。
預貯金の仮払制度であれば、他の相続人の同意や遺産分割協議書が不要であり、家庭裁判所の判断を得る必要もないため、比較的簡単な手続きで利用できる点が大きなメリットです。
なお、必要書類は以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本、または全部事項証明書
- 払戻しを請求する相続人の印鑑証明書
預貯金の仮払制度は、急にまとまった資金が必要になった際に非常に有効な手段といえます。
仮分割の仮処分
預貯金の仮払制度の上限額では必要な金額を支払えない場合、家庭裁判所に対して「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申立てるのも1つの方法です。申立てが認められると、故人の預金口座からより大きな金額を引き出せる可能性があります。
申立てが認められるための主な要件は以下のとおりです。
- 遺産分割の調停や審判がすでに申立てられていること
- 相続債務の弁済や相続人の生活費の支払いなど預金を引き出す必要性があること
- 他の相続人の利益を害さないこと
預貯金債権の仮分割の仮処分は以前からあったものの「差し迫った危険がある場合」でなければ申立てが認められず、適用要件が厳格であり利用が難しい制度でした。
そこで、家事事件手続法が改正され、遺産に属する預貯金債権のみを対象とする場合、「行使する必要があると認めるとき」という要件に緩和され、預貯金債権の引き出しが容易になりました。なお、手続きには1〜2ヶ月程度かかります。
また、仮払い可能な金額は、通常、遺産の中で資産性のある遺産総額の法定相続分が上限となり、相続債務も考慮されて決定されるものと考えられます。
トラブルになりやすい引き出し事例

亡くなった家族の通帳やキャッシュカードの保管場所と暗証番号を知っている場合、葬儀費用や医療費などの支払いを目的として、口座が凍結される前に引き出す人も一定数います。
しかし、正当な目的で故人の預金口座からお金を引き出す場合であっても、他の相続人に不信感を抱かれ、使い込みを疑われるなどのトラブルの火種になりやすいものです。
トラブルに発展しやすい状況や行為の具体例としては、以下の3つが挙げられます。
- 相続分を超えた金額を引き出した
- 引き出した現金の使途を説明できない
- 預金の引き出しを他の相続人に隠していた
上記のようなトラブルを未然に防ぐためには、故人の預金口座から引き出しをすることを事前に他の相続人へ必ず報告し、何にお金を使ったのかを明確にするための証拠(領収書など)を必ず残しておくことが極めて重要です。
相続分超過の引き出し
故人の預金から、自身の「法定相続分」を超える金額を引き出した場合、他の相続人の取り分を侵害してしまうため、トラブルに発展しやすくなります。「法定相続分」とは、民法で定められた、各相続人が遺産を受け取れる割合の目安のことです。
誰が相続人になるかによって、法定相続分は以下のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
| 配偶者と子 | 配偶者:2分の1 子:2分の1(子が2人ならそれぞれ4分の1ずつ) |
| 配偶者と親(子がいない場合) | 配偶者:3分の2 親:3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹(子も親もいない場合) | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
例えば、法定相続人が配偶者・長男・次男であるとしましょう。法定相続分は、配偶者1,000万円・長男と次男が500万円ずつであるとします。
もし、長男が故人の葬儀費用や医療費などを支払うために800万円を引き出した場合、自身の法定相続分を300万円超過することになります。この300万円の預金は、本来であれば配偶者と次男が受け取るはずだった財産です。
そのため、配偶者と次男から「本来の取り分よりも300万円多く引き出した理由を説明してほしい」「取り分を超えた300万円を返してほしい」などと求められ、トラブルになることがあります。
葬儀費用や医療費などの支払いが必要な場合でも、自身の法定相続分を超える金額を引き出すのは避けたほうがよいでしょう。やむを得ず引き出しをする場合でも、預貯金の仮払制度を利用するなどして、社会通念上相当であり、かつ必要最小限の範囲内に留めることが大切です。
使途不明金となっている
故人の預金口座から引き出したお金を何にいくら使ったのかを、他の相続人から質問された際に明確に説明できないと「自分のために使ったのではないか」という疑念を抱かれ、トラブルの原因となります。
後から揉めないようにするためには「葬儀費用として〇〇社に〇〇円を支払った」「入院費を精算するために〇〇病院に〇〇円を支払った」と説明できるようにしておくことが大切です。
また、請求書や領収書も大切に保管し、引き出したお金の支払先や使い道が分かるメモを残しておくとよいでしょう。
引き出しの隠蔽
預金を引き出した事実そのものを他の相続人に隠していると、後で事実が発覚した際に「やましいことがあるから隠していたのだろう」と他の相続人から疑われ、深刻な問題に発展する可能性があります。
また、他の相続人に「生前からお金を勝手に使い込んでいたのではないか」などと余計に詮索されてしまい、不信感がさらに広がってしまうかもしれません。
トラブルを防ぐためにも、遺産の話をする際には、他の相続人に対して故人の預金口座からお金を引き出した事実を正直に伝え、金額や使い道を正確に報告することが重要です。
引き出し行為の立証

実際の遺産相続では、亡くなった人の預金口座に使途がわからない出金の履歴が見つかることがあります。問題が明るみになり、使途不明金の返還を求める請求(使途不明金返還訴訟)を起こす場合、最大の争点となるのが「誰がお金を引き出したのか」ということです。
特に、引き出したとされる相続人が事実を否定している場合、返還を求める側が「指定の相続人が引き出したこと」を証拠に基づいて立証する必要があります。
しかし、払戻請求書の筆跡やATMの防犯カメラ映像など、引き出した人物を特定できる直接的な証拠が必ずしも手に入るとは限りません。その場合、裁判では引き出したと考えられる人物を推認させるために有効となる間接的な事実(状況証拠)を積み重ねることが重要になります。
典型的な反論パターン
使途不明金返還訴訟を提起する立場であるなら、相手がどのような反論をしてくるかを知っておくことが大切です。相手の主張を予測することで、冷静に対応しやすくなります。
使途不明金返還請求訴訟において、被告(引き出したとされる側)からなされることが多い反論の類型は以下のとおりです。
- 関与を否定するパターン
引き出し行為への関与を一切否定する主張です。
「自分は全く関わっていない」と述べ、「故人本人や他の相続人、あるいは全くの第三者が引き出したはずだ」などと反論します。
- 被相続人を補佐したと主張するパターン
自分はあくまで手伝っただけだという主張です。
「払戻請求書は確かに自分のものだが、故人に頼まれて銀行の窓口で代筆しただけで、お金を引き出したのは故人本人だ」というように、自分の関与は補助的なものだったと説明します。
- 被相続人に交付したと主張するパターン
引き出した事実は認めるものの、そのお金は全額故人に渡したという主張です。
「確かにお金はおろしましたが、すぐに全額を本人に手渡しました。その後どう使われたかはわかりません」と説明します。
他にも、被相続人のために有用な用途で使用したと主張するパターンや、被相続人から贈与されたと主張するパターンなどもあります。実際の訴訟では、被告側がこれらの主張を複数組み合わせて反論してくることもあります。
推認につながる間接事実
払戻請求書の筆跡やATMの映像といった直接的な証拠がない場合は、状況証拠を一つずつ集めていくことが重要です。複数の状況証拠を組み合わせることで「特定の人物がお金を引き出した」と裁判所が推認し、主張が認められる可能性があります。
裁判所が引き出し行為者を推認する際に考慮する、間接事実の具体例は以下のとおりです。
- 被相続人の身体状況
医療記録や介護記録を調べ、預金が引き出されたとされる日時に、故人が入院中や寝たきりなどで外出が不可能な状態であったことを証明する。
- 通帳等の管理状況
介護認定の調査票などを確認し、特定の相続人が故人の通帳やキャッシュカードを一括して管理していた事実を明らかにする。
- 引き出しの場所
お金が引き出されたATMの場所が、故人の生活圏から離れており、特定の相続人の自宅や勤務先の近くであることを示す。
- 金銭の動き
故人の口座から出金されたのとほぼ同じ時期に、特定の相続人の口座に不自然な入金があったり、大きな買い物をしたりしている事実を明らかにする。
口座凍結後の正式な手続き

相続に関するトラブルを避けるためのもっとも安全な方法は、ご家族が亡くなられた後、金融機関に死亡の事実を伝えて口座を凍結してもらい、正式な手続きに則って預金を引き出すことです。口座が凍結されることで、一部の相続人が無断で引き出せなくなり、大切な遺産を守ることができます。
しかし、口座が凍結された後でも、法律で認められた方法で預金を引き出すことは可能です。遺言書で預金の相続が指定されていない場合に、遺産分割協議の成立前でも利用できる制度は、前述したとおり、預貯金の仮払制度と裁判所による仮分割の仮処分があります。
ここでは、遺産分割協議成立後にすべての預金を引き出すための手続きはどのようにすればよいのかを解説します。
■ 遺産分割協議書または相続人全員の協力による方法
相続人全員が遺産分割協議に合意した後、預金口座を相続することになった人が金融機関で凍結解除の手続きを行うことで、引き出しができるようになります。
この場合、金融機関の窓口に以下の書類を提出して口座を解約する手続きを進めます。
- 金融機関指定の依頼書
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本、または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
※必要書類は金融機関によって異なる可能性があります。
このように、遺産分割協議が成立していることが前提となっており、相続人全員の印鑑証明書の提出が求められるなど、相続人全員の協力が不可欠です。
必要な費用と期間

預金の引き出しに関する相続トラブルについて、弁護士に相談や対応を依頼する場合は、以下のような費用が発生します。
(以下、金額はいずれも税抜きです。)
弁護士への相談料は、30分あたり5,000円~1万円程度が一般的な目安です。初回相談を30分〜60分まで無料としている弁護士事務所も多くあります。
使途不明金の返還請求訴訟・遺産分割協議の代理交渉などを弁護士に依頼する場合は、通常、案件に着手する際に「着手金」が、事件が解決した際に「報酬金」が発生します。
こうした弁護士費用の合計額は、20万〜70万円程度の場合もあれば、遺産総額が大きい事案や相続関係が複雑な事案では100万円を超える場合もあります。
一方、相続人自身が「預貯金の仮払制度」を利用する場合には、弁護士費用はかかりません。ただし、申請から実際の払い戻しまで1~2週間程度かかるのが一般的であり、期間は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
なお、必要書類となる戸籍謄本等の収集に1か月ほど要する場合もあるため、早めの準備が望まれます。
ケース別の対応ポイント

ここでは、相続預金の引き出しに関してよくあるケースごとの対応ポイントや注意点を解説します。
引き出しを他の相続人から反対されている場合
他の相続人から反対されていても、預貯金の仮払制度を利用して亡くなった人の預金口座からお金を引き出すことは可能です。
ただし、勝手に引き出しをすると相続人間での対立を深める恐れがあるため、事前に「葬儀費用を支払うために、法律で認められている仮払制度を利用したい」などと、理由や使い道などを冷静に説明することが大切です。
生前委任状がある場合
被相続人から生前に預金を引き出すよう委任を受けていたとしても、委任契約は本人の死亡によって効力を失います(民法653条1号)。そのため、原則として、被相続人の死亡後に、被相続人が生前に作成した預金の引出しを委任する委任状を用いて預金を引き出すことはできません。
また、委任内容が、被相続人が自らの死後の事務を委任するものであれば、死後事務委任契約として委任が有効となる場合もありますが、この委任があっても、銀行口座からの引出をすることはできません。前述のとおり、被相続人の死亡後は、預貯金は遺産分割の対象となるため、遺産分割協議が成立するまでは相続人全員の同意が必要となるためです。
被相続人が認知症だった場合
認知症により判断能力に欠ける場合、原則として口座からお金を引き出すことはできません。
被相続人の生前、特定の相続人によると思われる、本人の意思に基づかない多額の出金がある場合は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の対象になる可能性があります。
よくある質問(Q&A)

- Q
- 死亡後、キャッシュカードで引き出すことは違法ですか?
- Answer
-
直ちに犯罪として罰せられる可能性は低いですが、他の相続人との間で深刻なトラブルが発生する可能性があります。
また、相続放棄ができなくなるリスクもあるため、安易な引き出しは避けたほうがよいでしょう。
- Q
- いくらまで引き出せますか?仮払制度の上限はありますか?
- Answer
- 「預貯金の仮払制度」を利用すれば、各相続人が単独で1つの金融機関につき「150万円」の上限以下であれば、各口座について「(死亡時の預金残高)×(1/3)×(その相続人の法定相続分)」の計算式により算出される金額まで引き出しが可能です。
- Q
- 預貯金の仮払制度の必要書類はどのようなものがありますか?
- Answer
-
預貯金の仮払制度を利用する場合に必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
▸ 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
▸ 相続人全員の戸籍謄本、または全部事項証明書
▸ 払戻しを請求する相続人の印鑑証明書
- Q
- 引き出したお金の領収書がないとどうなりますか?
- Answer
-
引き出したお金を何に使ったのかを客観的に証明できず、他の相続人から「自分のために使ったのではないか」と疑われる可能性が非常に高くなります。
トラブルを避けるため、故人の預金口座から引き出したお金を使ったときは、必ずすべての領収書を保管しましょう。
- Q
- どのような行為が単純承認とみなされますか?
- Answer
- 口座の名義人が亡くなったことを金融機関に知らせずに、相続人が預金を引き出したり、そのお金を私的に使用したりすると単純承認とみなされる可能性があります。
- Q
- 相続放棄予定でも仮払制度は使えますか?
- Answer
-
基本的には使わないことをおすすめします。被相続人の医療費等の債務の返済に充てた場合や葬儀費用として使った場合など用途によっては単純承認とはならない可能性もありますが、相続人の私的用途であった場合、相続財産を取得したとみなされるため、相続放棄ができなくなります。
このように用途次第ではありますが、立証できないリスクもあるため、故人に借金が多く、相続財産がマイナスになる可能性がある場合、この制度の利用を控えたほうがよいでしょう。
- Q
- 代理人に依頼したいときはどうすればよいですか?
- Answer
- 代理人が預貯金の仮払制度を利用して故人の預金口座から引き出しを行う場合、原則として依頼する相続人本人の実印が押され、印鑑証明書が添付された委任状が必要です。
東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所
たとえ葬儀費用などに使うためであっても、安易に預金を引き出すと他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求をされる可能性があります。また「単純承認」をしたとみなされ、故人の多額の借金があったとしても相続放棄ができなくなるリスクがあることにも注意が必要です。
トラブルを避けるためには、口座の名義人が亡くなったことを金融機関に伝えて口座を凍結させたうえで「預貯金の仮払制度」をはじめとした正式な手続きを活用することが大切です。また、引き出す前に他の相続人への報告を徹底し、何にお金を使ったのかを領収書や明細書で示しましょう。
ご家族が亡くなられた後の預金の引き出しには多くの注意点があるため、一つの判断ミスが、親族間での深刻な対立に発展してしまいかねません。手続きの進め方に不安がある場合や、親族間でのトラブルが想定される場合は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで