
columns
弁護士コラム
遺言書作成のとき、「相続させる」と「遺贈する」では効力が変わる?
- 家族信託・遺言書作成
- 投稿日:2022年07月22日 |
最終更新日:2024年07月25日
- Q
-
私の死亡後、相続人間で紛争が生じないように遺言書を作成したいと思っています。
そこで、遺言書の書き方を調べていたところ、「相続させる」と書くのと、「遺贈する」と書くのとでは効果が違うと分かりました。
細かい点かと思いきや、重要な違いのようです。
具体的にどの点がどのように違ってくるのか教えてください。
- Answer
-
おっしゃる通り、「相続させる」と「遺贈する」とでは、少し効力が異なります。詳しく説明します。
遺言書に、特定の財産を「遺贈する」という記載があれば、民法にいう“遺贈”であることが文言自体から明らかです。しかし、「相続させる」と記載されている場合、その趣旨としていろいろな解釈ができてしまうのです。
従来、この解釈について、
①遺贈説と②遺産分割方法の指定説とが対立していました。
両者の違いは、
①遺贈説では遺言者の死亡により、相続人間で遺産分割をしないでも直ちに当該遺産の所有権が移転する、というものに対し、
②遺産分割方法の指定説では、遺言に基づく遺産分割が必要、
とされてきました。
しかし、最高裁の判決により、この議論に決着がつきました。遺産分割方法の指定説にたちながら、遺言者の死亡により直ちに所有権移転の効果が生ずるという新しい判断が示されたのです。これにより、両者の違いは登記手続や登録免許税の額といった付随的な点に差異が生ずるということにすぎないという結論になりました。
現在の公証実務においては、遺言によって遺産に属する特定の不動産を特定の人に帰属させる場合、その特定の人が相続人でない場合は「遺贈する」と表現し、その特定の人が相続人である場合は「相続させる」と表現しています。
「相続させる」と表現すると、
・第一に移転登記が相続人単独でできる(「遺贈」とすると相続人全員(あるいはこれに代わるものとしての遺言執行者)と受遺者との共同申請を要する)、
・第二にその特定の不動産が農地である場合でも所有権移転に知事の許可を要しない(農地3条1項12号)、
・第三に遺産が借地権(借家権)の場合でも民法612条の賃貸人の承諾を要しない(民法612条)
以上3つのメリットがあります。
しかし、後述しますように、平成15年の登録免許税率の見直しにより、「相続人に対する遺贈」と「相続」の登録免許税率は同一となる(登税別表1第1号、租税法72条1項)など、もはや差異はありません。
では、詳しく説明していきましょう。
「相続させる」と記載するメリット
遺言の文言として、公正証書遺言を中心に「相続させる」という記載が多くみられます。
遺言に「相続させる」という文言を使用するメリットとして次の4点が挙げられています。なお、受益者である相手方が相続人以外の場合には、いずれの記載でも遺贈と解されるので、以下は相手方が相続人の場合に限定した問題です。
- 1登記手続きにおいて、「遺贈する」の場合は受遺者と全相続人又は遺言執行者との共同申請をする必要があります。しかし、「相続させる」の場合は受益者が単独で申請できるため、簡便です。
- 2登録免許税が、「遺贈する」の場合は不動産の評価額の1000分の25ですが、「相続させる」の場合は1000分の6です。ただし、平成15年以降、両者の登録免許税に違いはなくなりました。(平成18年4月1日以降の登録免許税は不動産評価額の1000分の4です。)
- 3遺産が借地権や借家権の場合、「遺贈する」には賃貸人の承諾を必要となります。一方で「相続させる」には承諾が不要です。
- 4遺産が債権の場合、「遺贈する」の方は対抗要件が必要ですが、「相続させる」には対抗要件が不要です。
その他、従前遺産が農地の場合、県知事の許可の要否も挙げられていましたが、最高裁の判例が、遺贈による農地所有権の移転であっても、相続人に対する場合は県知事の許可は要しないとしました(最判昭52・7・1九金商548・43)ので、この点はいずれであっても変わりません。
また③・④も、相手が相続人の場合、たとえ「遺贈する」としていても、承諾や対抗要件は不要と解されますので、特にメリットにはならないといえます。②の税率は同じになったのですから、そうすると、前記①のみが「相続させる」と記載する実際上のメリットといえるでしょう。
「相続させる」の解釈について
遺言の解釈については、単に当該文言だけを切り放して取り上げるのではなく、遺言書の全ての記載との関連や遺言書作成時の事情等を考慮して、遺言者の真意を探求してその趣旨を確定すべきものとされています(最判昭58・3・1八家月36・3・143)。
そのため、公正証書遺言では、遺言書の中にあえて「相続させる」という記載をした場合、遺産分割をしないで、直ちに所有権が移る趣旨であると書かれてあるという例もあります。
しかし、それでも真意が明確でない場合が問題となり、その解釈については3説に分かれていました。
遺贈説
1つ目は、特段の事情のない限り、遺贈と解釈するのが相当であるとする説です(我妻=唄・相続100、山畠・家体系Ⅵ273等)。
遺産分割方法の指定説
2つ目は、特段の事情のない限り遺産分割方法の指定と解するのが相当とする説です。
この説はさらに2つの説に分かれます。
①遺言者の死亡により遺産共有の状態となり、遺言を基にした遺産分割によって初めて相続人の単独所有となる説
(中川=泉・相続法236、岡垣・新家事調停100講346)
さらにこの場合、同時に相続分の指定を伴うと解するのが一般ですが、相続分の指定を伴わないとする説もあります(右近・判評395・40)。
②遺言者の死亡により何等の行為を要せず、直ちに権利移転の効力が生ずるとする説
(加藤・法釈民法(28)59、永野「相続させる旨の遺言に関する一視点」法時62・7・78等)。
遺言による財産処分説
3つ目は、遺言者の死亡と同時に遺産分割を要せず、相続人に帰属するという遺言による特殊な財産処分であるとする説です。(瀬戸・公証法解釈の諸問題155、倉田・家月38・8・123)。
従来は主として遺贈説と遺産分割方法の指定説のうちの①説が対立し、長い間、裁判実務において先例としての役割を果たしていきた、いわゆる“多田裁判”(東京高裁判昭45・3・30判時595・58)は、遺産分割方法の指定説の①説に立って、遺産分割が成立するまでは遺産の共有持分を有するにとどまるという解釈でした。
これにより、両者の基本的な違いは次の通りとなっていました。
遺贈説では遺言者の死亡により特定の遺産の所有権が直ちに移転するというものです。
一方、遺産分割方法の指定説の①説では、遺言者の死亡後、遺産は相続人らの共有となり、遺言を前提にした相続人間の遺産分割の成立によって初めて所有権移転の効果が生ずるものでした。
しかし、両説とも、遺言作成者の意思に反することになるとして、上記の3つ目の説(遺言による財産処分説)が遺言実務を扱う公証人から強く主張されるようになりました。
もっとも、法務省の登記の実務は、早くから「相続させる」の文言でもそのままで所有権移転登記を受け付けるという扱いがなされていました(昭47・4・17法務省民事甲1441民事局長通達民事月報27・5・165)。
遺言者が改めて相続人間で遺産分割協議をさせたくないような場合でも、実務上は公正証書遺言を中心に「相続させる」という文言が広く使用されてきたのです。
このため裁判所の解釈と登記実務のズレが生じ、これらを巡って議論が続いていたのです。
その結果、近年は、遺産分割方法の指定説にたちつつも、遺言者の死亡により何等の行為を要せずに直ちに所有権移転の効果が生ずるとする、前記遺産分割方法の指定説の②説が主張されるようになり、最高裁もこの説に立った判決をするに至りました(最判平3・4・19判時1384・24)。
このため実務上はこの論争に決着がつけられたのです。
残された問題点
前述の最高裁の判決により、これまで遺産分割方法の指定説の最大の問題点とされていた、遺言者死亡による即時の所有権移転の効力が肯定されたため、実務では現実的なメリットがある「相続させる」が専ら使われることになると思われます。
しかし、遺産分割方法の指定説に立った場合には、最高裁判決では触れられていない、次のような問題点が残されています。
遺留分減殺の順序
遺贈に準じて扱うとする考え方(島津「分割方法指定遺言の性質と効力」)と遺贈・贈与に後れるとする考え方(島津前掲9)があります。
なお、遺産分割方法の指定は、そもそも遺留分減殺の対象とはならないとする説があります(伊藤「相続させる遺言は遺贈と異なる財産処分であるか」法政研究660)。最高裁平成8年1月26日第二小法廷判決が「特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない」と判示しています。
負担付の「相続させる」との遺言があった場合に、その負担が履行されなかった際の法律関係
これについて、
㋐遺贈の規定を準用し、負担の不履行の場合には遺言の取消請求ができるとする考え方(瀬戸『「相続させる」との遺言の効力』金法1210・9)と、
㋑取消はできず履行ないし賠償の請求だけができるとする考え方、さらには
㋒負担に代償性が高い場合には取消請求を認め、代償性が低い場合には履行ないし賠償請求のみを認めるとする考え方(島津前掲9)
がみられます。
「相続させる」による受益者と第三者への登記の要否
この点については登記なくして第三者に対抗できるとする考え方(島津前掲6、大阪高平2・2・28判時1372・83)と、登記がなければ第三者に対抗できないとする考え方(瀬戸前掲9)がみられます。
受益者が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力
遺言は遺贈と同様に効力を失い、その分は相続人に帰属する考え方(瀬戸前掲9)と、受益者が配偶者の場合は失効してしまうけれど、子供の場合は代襲相続が行われるとする考え方(島津前掲7)があります。遺言者の死亡以前に、相続人が死亡している場合に、代襲相続人(民法887条2項,3項)に特定財産を相続させる旨の記載が無い限り、遺言の該当部分は無効であるということを前提に判断をしました。(札幌高決昭61・3・7家月38・8・67参照)
「「相続させる」旨の遺言の効力は?判例とともに解説」もご参照ください。
特別受益や寄与分との関係
「相続させる」旨の遺言が遺産の全部についてなされている場合は、今回の最高裁判決により遺産分割をする余地はありません。
よって、「相続させる」という文言自体からは、特別受益や寄与分は問題となりません。
これに対し、遺言が遺産の一部のみ(預貯金については●●に相続させる、とありますが、不動産については特に記載がない場合等が想定されます)に限定がされている場合は、残った遺産の分割においては、一部の相続人が受けた贈与を特別受益として相続財産に含めて遺産を分配する特別受益や、寄与分の算定に際して受益分が考慮されることになると考えられます(瀬戸前掲9、島津前掲7)。
相続放棄等の熟慮期間終了後ないし相続放棄の申述後に遺言が発見された場合の処理
相続放棄の前に遺言書が発見された場合については、相続放棄が可能とする説と不可能とする説がありますが、今回の最高裁判決は放棄が可能であり、それによりさかのぼって相続とされなかったことになる旨付言しています。
また、放棄後については、財産を取得不可説と可能説に分かれています(伊藤前掲675)。
遺産分割終了後に遺言が発見された場合の処理
遺産分割を無効として遺言どおりに取得させ、遺言外の遺産があれば再分割をするか、あるいは再分割はせず担保責任により解決するとする考え方があります(伊藤前掲676)。
以上7つの問題は、いずれも考え方として主に、遺贈に準ずるとするか相続的に扱うかの問題です。
現在の実務上は未解決ですので、今後の判例の動きに注意することが必要です。
財産目録の活用
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。これにより、民法第968条第2項が新設され、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになったのです(自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならない)。
そして、遺言書には、現在の公証実務においては、遺言によって遺産に属する特定の不動産を特定の人に帰属させる場合、その特定の人が相続人でない場合は「遺贈する」と表現し、その特定の人が相続人である場合は「相続させる」と表現しています。
遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には、例えば、本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。
これを、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることができるようになりました。
うまく財産目録を活用し、遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に、より書く側も読む側も分かりやすくなることが期待されます。
参考サイト
初めての「終活」についてはこちら
家族信託・遺言書作成についてお悩みの方へ
相続においては、「自分が亡くなったあと、どうしたらよいのか」とお悩みの方も多くいらっしゃると思います。当サービスでは、家族信託・遺言書の作成に関しても、ご依頼者様のニーズに沿った、適切な対策・アドバイス・サポートをプロの弁護士がおこないます。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
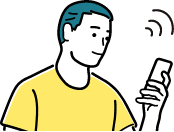
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


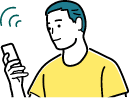


 メールで
メールで