
columns
弁護士コラム
財産を1人にだけ相続させることはできる?遺言の書き方や注意点も解説
- 家族信託・遺言書作成
- 投稿日:2022年08月25日 |
最終更新日:2022年08月25日
- Q
- 財産をひとりに相続させたい場合の、遺言の書き方や注意点を教えてください。
- Answer
-
特定のある人だけに、自分の財産を相続させたい、と思うことは、めずらしくありません。
「縁を切った長男には渡したくない」、「介護をしてくれた姪にあげたい」、というような気持ちは分かりますよね。
では、このような場合、そのひとりだけに財産を相続させることはできるのでしょうか。
よく、「遺留分」という言葉を聞きますが、それとの関係はどうなっているのでしょう。
詳しく説明します。
原則
故人の遺言書を開いてみると、法定相続人の中の1人だけに遺産を相続させる内容が記載されている場合もあります。
例えば、「妻だけに私の財産を渡す」、「長男にのみ残し、次男と三男にはない」というように、特定の人にだけ遺産を相続させるという内容の遺言がこれに当たります。遺言書がある場合には、きちんと遺言書のルールに従って作成されているのであれば有効になりますので、基本的には遺言の内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書のルールは、自筆証書の場合、下記のようなものがあります。詳しくは、法務省のホームページで確認してみてください。
- 財産目録以外は全て自書する必要がある
- 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する
- 戸籍どおりの氏名を記載する
そうすると、遺言書に、「甲にすべての財産を相続させる」と相続人が指定されていた場合には、甲一人が被相続人のすべての相続財産を受け取ることができるのです。
遺留分
では、遺言書によって、たった1人にだけ遺産が相続、もしくは第三者へ遺贈すると記載している場合、法定相続人は遺産を一切相続できないことになるのでしょうか?
法定相続人側から、自分の相続権を主張することはできるのでしょうか?
このような場合にある制度が遺留分(いりゅうぶん)制度というものです。
亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度の目的です。
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
今回でも、法定相続人には遺留分があります。したがって、法定相続人が何人もいる場合には、不満が出ることが考えられますね。「お兄ちゃんにだけ相続があるなんてずるい」、なんていう家族間のもめごとは容易に想像できるでしょう。
遺言で「次男甲にすべての財産を相続させる」などと指定されていた場合、ほかの相続人の遺留分を侵害することになりますね。そうすると、遺留分を侵害された相続人らによって、遺留分減殺請求又は遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。
その場合、上記のような遺言書によって、第三者に全ての遺産を与えると記載されていたとしても、遺留分を有する相続人は、遺言者の意思に反して、いくらかの遺産を相続することができるのです。注意が必要なのは、遺留分に反した遺言も無効ではなく、遺留分権者が遺留分に反した限度で被相続人の処分の効力を失わせる権利行使がされるまでは有効となります。
そして、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅します(民法1048条前段)。
実務上は、遺留分権利者が権利を行使しないまま、時効期間が徒過し、遺留分を侵害する遺言が全て有効として処理される事も多いので、留意してください。
平成30年改正民法による遺留分制度の変更
平成30年改正前民法においては、遺留分権利者の有する権利は「遺留分減殺請求権」という名称でした。
すなわち、被相続人が遺留分を超えて贈与や遺贈を行ったため遺留分が侵害されたときに、受遺者や受贈者などに対して、その処分行為の効力を奪うことを「遺留分の減殺」といい、遺留分減殺を内容とする相続人の権利を遺留分減殺請求権と定義づけていました。
これに対して、平成30年改正民法では、遺留分に関する権利行使により生ずる権利について、「遺留分侵害額請求」の意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じるものとし(民1046条1項)、遺留分に関する権利行使につき、遺留分侵害額請求権の行使と定義しました。
また、遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者が金銭を準備できない場合もあるとして、受遺者等は、裁判所に対して、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限の許与を求めることができると規定しています(民法1047条5項)。
遺言解釈の原則
遺言書は、公証役場に行って公正証書として作成するパターン(公正証書遺言)と、自分で作成するパターン(自筆証書遺言)があります。
※公正証書遺言、自筆証書遺言についての詳細は、「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 それぞれ詳しく解説」の記事をご参照ください
後者(自筆証書遺言)は、弁護士等が介入していない場合、解釈に疑義が生じる書き方がなされていることが散見されます。形式的な面は比較的調べて書けるかもしれませんが、言葉遣いや単語のチョイス次第で、いかようにもとれるという日本語を使用することがあります。これは、とても危険です。以下で詳しく説明します。
例えば、甲さんからこのような質問がきたとして事例で解説していきます。
| 私は亡Aの相続人甲です。Aの死亡に伴い、相続を原因として私名義にAの居住していた土地・建物の所有権移転登記を完了しました。ところが、生前Aと交際をしていたBから、Aの財産を「すべてBにまかせる」と記載された遺言書が作成されていたということを伝えられ、抹消登記を求められました。「まかせる」という文言で遺言書は有効なのでしょうか。 |
Aの財産をすべてBに「まかせる」と記載された遺言書ということですが、「まかせる」の趣旨は一体何なのか、問題となります。
つまり、Bに財産を遺贈する趣旨の遺言として有効であるか否かということです。「まかせる」との文言はそれだけでは、遺贈するとも、それとも管理だけをお願いするという意味とも、そのいずれとも解釈できる余地ありますね。
しかし、遺言書の解釈は単にその文言を形式的に判断するだけではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言書の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し、その遺言書の趣旨を確定すべきである、と解されています。
したがって、こちらの質問については、被相続人亡AとBとの交際状況や、亡Aと甲さんの関係等の事実関係を踏まえて、亡AがBにその全財産を遺贈し、相続人である甲さんに何も財産を相続させないとすることを首肯するに足るだけの具体的事情の有無を判断して、亡Aの真意を探求し、それによって「まかせる」と記載された遺言書の趣旨を確定することになるのです。
(1)
この遺言書の発見により、Bは甲さんに対し、亡Aの相続財産である土地建物につき、甲さん名義の所有権移転登記の抹消登記を求めることになります。その根拠は、亡Aの財産はすべてBに「まかせる」と記載された亡Aの遺言書によってBはその土地建物の遺贈を受けたいということであると思われます。したがって、その「まかせる」と記載された遺言書の文言の解釈が問題となります。
「まかせる」という言葉を辞書で調べてみましょう。「(事物を)他者の行動のままにする。あるいは他者のしたいようにさせる。」(岩波書店・岩波国語辞典(第4版)1048参照)ということを意味します。そうすると、直接には遺贈を意味する「(事物を」他者に与える)という趣旨を含んでいる とはいえないとも解されます(後述する東京高裁の判例はこのように断言しますが、この点はやや疑問の残るところです)。
しかし、事物を他者のしたいようにさせるということは、その物の処分までもまかせた趣旨であると解されることもできます。そうすると、まかせられた者がその物を自身の所有とすることも容認されると考えることもできるし、また、したいようにさせるということの前提には当然その物の所有権を与える趣旨を含んでいると解することもできないわけではありません。
いささか混乱してきましたが、「まかせる」という遺言書の文言だけでは、遺言の趣旨を確定することは困難であると言わなければならないようですね。こうなってしまうと、結局遺言書の解釈はどうあるべきかという点に戻って問題を解決するほかありません。
この問題についての学説判例の考え方をみてみましょう。この点に関しては特に争いはなく、通説判例は以下のように考えています。
すなわち、遺言は相手方のいない単独行為であるから、その解釈に当たって、相手方の信頼を保護し、取引の安全を図るというような配慮は全く不要であり、常に遺言者の真意を探求すべきであり(中川=泉・相続421)、したがって、遺言者の条項の解釈はその文言にのみとらわれることなく、遺言の趣旨の全体的解釈により遺言者の真意を探求すべきだとされています(大判昭14・10・13民集18・1137)。
近時の判例でこの点に関して具体的に判示しているものがあるので、少し長くなりますがその判旨全体を掲げておきます。最判昭58・3・18(判タ496・80)は、
| 「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出してその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」 |
と判示して、遺言の解釈に際しいかなる事情を考慮すべきかを具体的に示しています。そこで、このような考え方に従って「まかせる」という文言を解釈することになります。
(2)
では、解釈する際には、具体的にどのようなことが問題となるかを検討しましょう。
近時、上記のご質問の場合と同様に、相続人以外の者にその全財産を「まかせる」と記載された遺言書の文言の解釈が問題となった事案において、文言の形式的解釈のみではなく具体的事情を考慮してその趣旨を確定した判例がでました。この判例を検討しつつ、質問の場合を考えていきましょう。
東京高判昭61・6・18(判タ621・141)は、まず
| 「『まかせる』という言葉は、本来『事の処置などを他のものにゆだねて、自由にさせる。相手の思うままにさせる。』ことを意味するにすぎず、与える(自分の所有物を他人に渡して、その人の物とする。)という意味を全く含んでいない」 |
としたうえで、更に当該事案の具体的事情を考慮しても「まかせる」という遺言書の記載が遺贈の趣旨であるとは認められないと判断しました。
この判示のうち前半の部分すなわち「まかせる」との文言には「与える」という趣旨が全く含まれていないとする点については、前述のとおりそこまで断言することには疑問があると思われます。しかし、具体的事情を踏まえたうえで遺言書の記載の趣旨を確定すべきであるとする後半部分の判旨は正当であって、この部分はとても参考になります。そして、そこで指摘された具体的事情のうち今回の甲さんからの質問に直接参考になると思われる2点の判断基準を抜き出しました。
- 1遺言者と遺贈を受けたと主張する者との関係
- 2遺言者と相続人との関係
の二点です。
これを甲さんの質問にあてはめて考えてみます。被相続人亡AとBとの交際状況、亡Aと甲さんとの関係等の事実関係を考慮し、そこに亡AがBにその全財産を遺贈し、相続人である甲さんに何らの財産を相続させないとすることを首肯するに足るだけの具体的事情の有無を判断して亡Aの真意を探求し、「まかせる」と記載された本件遺言書の趣旨を確定することになります。
(3)結論
したがって、質問の結論は次のようになります。
まず、「まかせる」との文言は「与える」という意味を全く含まないとして、本件遺言書の記載を遺贈の趣旨であると解釈する余地はないと結論づける考え方があります。しかしこの考え方には前述のとおり疑問があると言わざるを得ないため、採用できません。
そうすると、前述のような具体的事情①②を考慮したうえで亡Aの真意を探求し、本件遺言書の趣旨を確定することになるでしょう。
今回大事なことは、今までの検討から明らかなように、すべての財産を一人に与える趣旨の遺言書を作成するようなときには、「遺贈する」などと明確に記載すべきということです。
「まかせる」というような色々な解釈を許す余地のある言葉の使用は極力避けるようにしなければならないことは、お分かりいただけたかと思います。
家族信託・遺言書作成についてお悩みの方へ
相続においては、「自分が亡くなったあと、どうしたらよいのか」とお悩みの方も多くいらっしゃると思います。当サービスでは、家族信託・遺言書の作成に関しても、ご依頼者様のニーズに沿った、適切な対策・アドバイス・サポートをプロの弁護士がおこないます。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
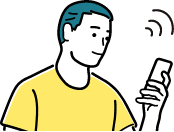
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス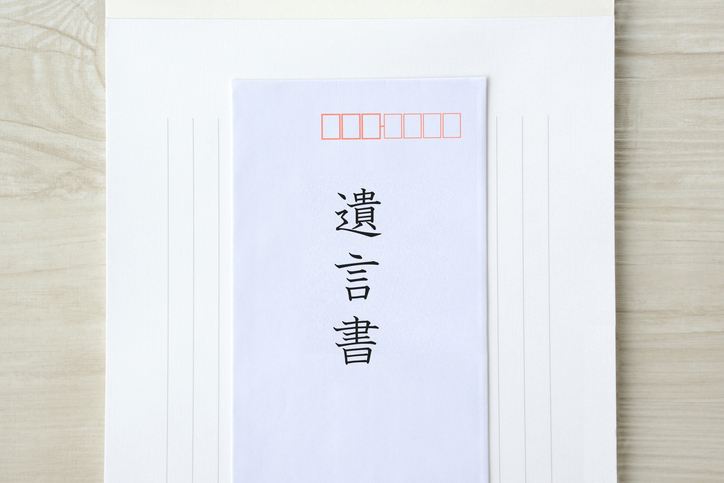


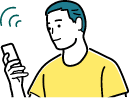


 メールで
メールで