
columns
弁護士コラム
生前に遺留分放棄はできる?
~手続の流れも解説~
- 遺留分のトラブル
- 投稿日:2022年08月22日 |
最終更新日:2024年03月14日
- Q
- 生前に遺留分を放棄する・放棄させることはできるのでしょうか?
- Answer
-
ご存知の通り、相続は、人が亡くなってから発生するものです(民法(以下民といいます)882条~)。
したがって、亡くなる前には何も権利や義務が発生しないのが原則ですね。
しかし、被相続人(例えば親)が亡くなる前に、相続人(子ども)が予め相続をしない、という意思を持つことは少なくありません。その場合、生前に相続しない、一切を放棄する、という意思表示は有効となるのでしょうか。
以下、解説していきます。
| 事例 父は畳屋の経営を長男に譲り、今は隠居しています。母はおりません。私は次男です。 妻とふたり暮らしで、ある程度の収入があり不動産も所有していますので、生活は安定しています。そのため、父の財産を相続する意思はありません。 ただ、私には兄(長男)以外にも弟妹があり、父は常々、長男に畳屋の後を継いでもらい、後々相続のことで問題が生じないようしたいと言っています。父が生きているうちに安心させたいのですが、何か方法はありませんか。 |
目次
遺留分制度とは
まず、遺留分とは何か、というところから解説します。
定義
遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です(民1042条以下)。
「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいいます。
これに対し、遺留分にならずに被相続人による自由な処分にゆだねられている部分を「自由分」といいます。
目的
本来、被相続人は自分の財産を自由に処分できるはずですね。
しかし、相続制度は、残された遺族の生活の保障、遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算という機能もあるのです。民法は、この制度を用いて、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護という対立する要請の調和を図りました。
このため、事例の長男はもちろん、相談者である次男、そして、その弟妹それぞれに、お父様の相続財産に関して遺留分があることになります。
長男に単独相続させるために、被相続人の生前にとり得る方法
現行民法は、家督相続制度を廃止し、諸子均分制度をとっています。とすると、民法は原則、長男が単独で全ての遺産を相続することは予定していません。ただ、他の相続人全員が相続を放棄することにより同じ結果が得られます。注意が必要なのは、相続放棄は、被相続人が死亡し、相続が開始した後でなければできないということです(民915条)。
そうすると、被相続人の生前に、必ず、長男が単独相続できるように方法としては、被相続人が長男に全遺産を遺贈するという遺言をしておくほかないのです。この遺言によって、長男は、一応は、全遺産を承継するということになります。
しかし、このような場合においても、前述したように、遺留分が一定の相続人(事例の次男とその弟妹)に留保されていて、被相続人による自由な処分(遺言・遺贈)に制限が加えられている持分的利益が保障されてしまいます(民1042条)。
2019年の民法改正は、遺留分の制度を遺留分権利者の生活保障や遺産形成に貢献した遺留分権利者の潜在的持分の清算等を目的とする制度であり、その目的を達成するためには、必ずしも物件的効果まで認める必要はなく遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する価値を返還させる(堂園幹一郎=野口宣大『一問一答・新しい相続法・平成30年民法等<相続法>改正、遺言書保管法の解説(一門一答シリーズ)』122頁(商事法務、2019))ことが妥当ということで、改正前の物権的効果と補充的な価格弁償という遺留分の制度を遺留分侵害部分の金銭的給付を認める制度に変更しました。
相続人が全遺産を1人に遺贈すると、当然に、他の相続人(例えば兄弟)の遺留分を侵害することになります。ただ、他の相続人が、生計の資本としての特別の贈与(結婚費用、営業資金、新築資金など)を生前に受け、これが遺留分額に達していれば、遺留分は侵害されていないという結論になります。
したがって、このような生前贈与がされていれば別ですが、そうでない限り、他の相続人が、相続権を主張する場合には、侵害された遺留分を回復するため、遺留分侵害額請求権を行使することになります。
そうすると、遺贈を受けた1人は、他の兄弟の遺留分を侵害している範囲で兄弟に対し金銭的給付をしなければならないということで、遺産について紛争を生じるということになりかねません。
なお、念のため申し上げますと、遺留分侵害請求権は、相続が開始してはじめて認められます。
遺留分権利者は、相続開始前は何ら具体的な請求権を有せず、遺留分の保全行為もできません。
これらの紛争を防ぐためには、他の弟妹に遺留分の放棄をしておいてもらえばよいわけですが、これは、あくまでも、他の弟妹の自由意思に基づくものでなければなりませんから、放棄してもらうためには、話し合いが必要であり、遺留分を侵害しないよう、予め遺留分相当額の生前贈与を行っておく方が簡便な場合もあります(この場合には、トラブル防止のために遺言書にも生前贈与をした旨を記載する必要があります)。
遺留分放棄の手続
遺留分権利者は、相続開始前に、被相続人に対し遺留分を放棄する意思表示でこれを行いますが、その効力発生のためには家庭裁判所の許可が不可欠です(民1049条1項)。
遺留分の事前放棄について家庭裁判所の許可が必要とされているのは、無制限に放棄を認めると、被相続人や他の共同相続人らの威圧によって、遺留分権利者が遺留分の放棄を強要されるおそれがあるからです。相続放棄をするには、家庭裁判所へ申述をしなければならない(民938条)とされているのと同様の理由です。
旧民法は、相続開始前の遺留分放棄については、明文を置かず、判例としては、放蕩者である家督相続人について、放棄契約を家督相続の精神に合するとして有効と認めた大審院判例(大判昭9・4・30法学3・1196)がありましたが、これは特異な事案についてのものであり、一般的には、消極説がとられていました(加藤・家審法講座Ⅱ262〔岡垣学〕)。
これに対して、現行法は、家庭裁判所の許可を条件としてではありますが、明文でこれを認めました。
しかし、この点については、均分相続を原則とする現行法の基本理念に反し、遺留分制度そのものの存在意義を失わせるに等しいものですし、また、相続放棄が相続開始前には許されないこととの対比から理念が一貫しないという批判もあります(槇怫次『相続分および遺留分の事前放棄』家大系ⅶ301項(有斐閣、1960))。
家庭裁判所の審理
遺留分放棄の許可は、被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は、遺留分放棄許可の申立てがあると、家事審判事件(家事法216条1項2号、家事手続別表1の110項)として審判をします。
権利者の自由意思、放棄理由の合理性・必要性、放棄と引換えの代償の有無などを考慮して許否を判断し、相当と認めるときは、許可の審判をします。
実務上、申立てが不相当な場合には、取下げ勧告がなされることが多いので、審判例は多くありませんが、却下された事例もあります(東京家審昭35・10・4家月13・1・149等参考判例参照)。
許可事例として、次のようなものがあります。
- 1死後の遺産紛争を懸念して、婚外子に財産を贈与して遺留分を放棄させる場合
- 2老親扶養のために親と同居する子以外が放棄する場合
不服の申立て
旧家事審判法下においては、遺留分の放棄について許可・却下いずれの審判に対しても不服の申立てが認められていませんでしたが、家事事件手続法の制定により、申立てを却下する審判に対しては即時抗告ができることとされました(家事手続216条2項)。
「申立人は、遺留分の放棄を求めて申立てをしたものであるから、その申立てを却下された場合は、不服を申し立てることができるものとするのが相当である」からです(『逐条解説』670頁)。
一方で、申立ての許可する審判に対する即時抗告はすることができません。
「遺留分の放棄を許可する審判については、申立てどおりの審判がされたものであり、また、その判断を独自に争わせるだけの固有の利益を有すると認められる第三者は想定されない」(『逐条解説』670頁)からです。
許可審判の取消し
遺留分放棄の許可審判も、審判をした後にその審判が不当と認められるようになったときは、家庭裁判所は、職権でこれを取消し又は変更することができます(家事手続法78条1項)。
この取消し又は変更は、審判が確定した日から五年を経過したときには、原則としてできなくなりますが、事情の変更、すなわち審判の基礎となった客観的事実関係が変化したことによりその審判が不当と認められるようになったときには、五年を経過した後でもこれを取消し又は変更することができます(同条2項)。
なお、旧家事審判法の下においては、前記後者の場合に遺留分放棄者に申立権があるかどうかについて、これを否定するものと(仙台高決昭56・8・10)肯定すると解されるもの(東京高決昭58・9・5)とに分かれていました。
また、取消しの時期に関しても、従来の遺留分放棄許可審判を取り消した審判例も、いずれも相続開始前のものでしたが、前記仙台高裁の決定は、その理由中で、相続開始後であっても、家庭裁判所が職権で許可審判の取消しができるとしていました。
取消し、変更は、当該審判をした裁判所が一般の審判手続に従い、審判によってすることになります。
遺留分の放棄の効果
遺留分の放棄は、相続の放棄(民939条)ではないため、相続開始後は相続人となることに変わりありません。
代襲相続の場合に、被代襲者が遺留分の事前放棄をしておれば、代襲相続人は、被代襲者の有していた権利しか取得できないのですから、遺留分はないことになります。
遺留分を放棄すると、遺留分を侵害する遺贈又は贈与がなされても、その侵害額請求をすることができなくなります。
しかし、相続権を有していますので、遺産分割により遺産を取得することはできます。ある遺留分権利者が遺留分を放棄したからといって、他の共同相続人の遺留分が増加しそうですが、増加はしません(民1049条2項)。被相続人の自由に処分できる財産(自由分)が増えるだけです。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
中小企業の経営者が、長男等の後継者に自社株式や事業用資産を承継(贈与)しても、他の相続人から遺留分侵害額の請求権を行使され、その結果、これらの売却を余儀なくされ、後継者が会社を経営するのに必要な議決権や事業用資産を確保できない事態が想定されます。
これを防ぐ方法として、これまでに説明をしました、他の相続人から事前に遺留分の放棄をしてもらうことができますが、これには各相続人が自分で家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立てをしなければならず、負担が大きく、また、家庭庭裁判所の許可・不許可の判断が異なる可能性もあり、実際的に利用しにくい面がありました。
そこで、中小企業(※1)における経営の承継の円滑化に関する法律は、先代経営者が個人で保有する自社株式及び事業用財産を、後継者(※2)が円滑に承継することができるように、遺留分に関し民法の特則を定めています。
これによれば、同法の定める特例中小企業者の先代経営者の推定相続人は、そのうちの一人が後継者である場合には、
- 1全員の合意(※3)により、
- 2書面で、
- 3後継者が先代経営者からの贈与等により取得した中小企業者の会社株式(持分も含みます。)又はその他の財産を、遺留分算定基礎財産から除外することを定め、また、前記事項に併せて、非後継者が贈与等により取得した財産について、遺留分算定基礎財産から除外することを定めるなどし、
- 4その日から一か月以内に、
- 5後継者が経済産業大臣に対し、確認の申請をして、経済産業大臣の確認を受けた上、
- 6確認を受けた日から一か月以内に家庭裁判所に対し、許可申請をして、家庭裁判所の許可を受けることにより
遺留分に関し民法の特例の適用を受けることができるようになりました。
この制度は、平成21年3月1日から施行されました。また、平成27年改正経営承継円滑化法(平成28年4月1日施行)により,後継者が推定相続人以外の者(親族外承継)でもこの特例の対象となりました。
※1
「遺留分の適用に関する民法の特例」の適用を受ける「中小企業者」とは、合意時点において、3年以上継続して事業(経営承継円滑化法施行規則2条)を行っている、経営承継円滑化法2条、同法施行令で定める非上場会社(個人事業主は含まない。)です(経営承継円滑化法3条1項)。例えば、小売業でいえば、資本金の額又は出資の総額5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社です
※2
①先代経営者から中小企業者の株式等の贈与を受けた者(以下「特定受贈者」という。)又は当該特定受贈者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、②当該特例中小企業者の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、③当該特例中小企業者の代表者であるものをいいます(経営承継円滑化法3条3項)。
※3
ここで合意は、除外合意や固定合意をすることが通例です。
まず、除外合意とは、推定相続人及び後継者全員の合意により、後継者が先代経営者から贈与された特例中小企業者の株式等(又は特定受贈者からの相続、遺贈、若しくは贈与により取得した特例中小企業者の株式等)の全部又は一部につき、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこととする制度のことです(中小経営承継法4①一)。
遺留分の放棄の制度との違いは、遺留分の放棄が、遺留分全ての放棄であるのに対し、除外合意は、特定の財産のみを遺留分算定の際の基礎となる財産から除外するものである点にあります。
他方で、固定合意とは、推定相続人及び後継者全員の合意により、後継者が先代経営者から贈与された特例中小企業者の株式等(又は特定受贈者からの相続、遺贈、若しくは贈与により取得した特例中小企業者の株式等)の全部又は一部につき、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、その「合意の時点における価額」とする制度のことです。
そして、「合意の時点における価額」というのは、推定相続人及び後継者が勝手に決定できるものではなく、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人が、その時における相当な価額として証明したものに限ります(中小経営承継法4①二)。
結論
それでは、事例の回答にうつります。
畳屋のお父さんが、長男だけに相続したいというお話でした。
現行民法では、被相続人の生前に相続放棄をすることは、認められていませんから、お父さんの希望をかなえるためには、被相続人であるお父さんが「全遺産を長男に遺贈する」という遺言をするとともに、長男以外の相続人である子全員に遺留分を放棄してもらうことが必要です。
次男、弟、妹が、家庭裁判所に放棄の申立てをして、許可を得ることができればいいのです。
平成20年5月16日に公布された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律により、生前に、遺留分権利者全員の合意があれば、所定の手続きを経ることにより、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した特例中小企業者の会社株式又は持分やその他の財産を、遺留分算定基礎財産から除外、またそれに併せて、非後継者が贈与等により取得した財産について、遺留分算定基礎財産から除外することなどができるようにうなりましたので、それを活用するのも一つの手でしょう。
円滑な事業承継を行うためには専門家の手を借りることが何よりも大事です。
遺留分についてお悩みの方へ
遺留分額の計算から協議、まとまらない場合は遺留分侵害額請求訴訟まで、ご依頼者様の意向を汲み取りながら、プロの弁護士が適正に解決を図ります。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
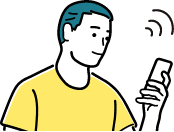
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


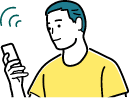


 メールで
メールで