
columns
弁護士コラム
遺贈における課税について解説
- 相続税・事業承継対策
- 投稿日:2022年07月22日 |
最終更新日:2024年03月14日
- Q
- 遺贈に対する課税は、どのようになされるのでしょうか?
- Answer
- 一口に遺贈と言っても様々なケースがありますので、詳細については解説をご覧ください。
相続人に対する遺贈
遺贈とは遺言による贈与のことであり、相続人にすることも、相続人でない者にすることもできます。
しかし、実務上は、相続人に対しては遺贈ではなく「相続させる」という文言が使われます(最高裁判所平成3年4月19日判決は、「相続させる」という文言について、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続させるために遺産分割の方法を指定したものであると解釈しています)。
したがって、ここでは相続人でない者に対する遺贈を念頭にして検討することにします。
個人に対する遺贈
遺言によって遺贈や遺産分割方法の指定がなされると、受遺者(遺贈を受けた人)や分割方法を指定された相続人は、遺言者の死亡時に直ちに当然に遺産を取得することになります(大審院大正5年11月9日判決、最高裁判所平成3年4月19日判決)。
相続税法による財産取得の時期についても、明文の規定はありませんが、民法の解釈を受けて相続の開始時(遺言者の死亡時)であると解釈されています。
そして、相続人や受遺者が負担する相続税の具体的金額は、相続税の総額を計算した上で、相続又は遺贈によって得た財産の価額に応じて相続税の総額を按分するという方法で計算します。
したがって、遺言者の死亡によって遺贈や遺産分割方法を指定する遺言の効力が発生すると、遺産分割方法を指定された相続人や遺贈された受遺者は遺産を直ちに取得することになり、取得した遺産の価額に応じて遺産を取得した相続人や受遺者が負担する相続税額が決まり、各人に対して相続税が課税されることになります。
なお、受遺者が遺贈者(被相続人)の配偶者ないし1親等の血族でないときは、受遺者の相続税額は通常の相続税額の2割増しとなります(相続税法18条)。
停止条件付き遺贈
停止条件付き遺贈とは、ある条件が成就することによって遺贈の効力が発生するというものです。
例えば、借地権の譲渡には賃貸人の承諾ないし裁判所の許可が必要であることから、建物と借地権を遺贈するときは「借地の賃貸人の承諾又はこれに代わる裁判所の許可があることを条件として」遺贈することになります。
条件成就前に相続税の申告をするときは、停止条件付き遺贈の存在は無視し、相続人が法定相続分に従って取得したものとして相続税を計算して納税することになります(相続税基本通達11の2の8)。なお、条件成就後に受遺者が遺贈された財産を取得したときは、相続人は、条件成就を知った日の翌日から計算して4か月以内に更生の請求をすれば相続税が還付されます(相続税法32条1項6号・相続税法施行令8条2項3号)。
条件成就によって遺贈された財産を取得した受遺者は、条件が成就した日の翌日から計算して10か月以内に相続税の申告をしなければなりません(相続税法27条、30条1項、31条1項)。なお、この場合の相続税評価額は、条件成就時の価額ではなく相続開始時の価額になります(相続税基本通達27-4(注)参照)。
これらの修正申告や更生請求は必ずしも行う必要はありません。納付済みの相続税はそのままにして、相続人と受遺者で協議して当事者間で清算することにしても構いません。
負担付き遺贈
負担付き遺贈とは、受遺者が一定の負担をすることを条件として遺贈するというものです。
例えば、特定の不動産の遺贈を受ける代わりにその不動産の銀行ローンの債務残高を完済して遺言者の相続人に支払いの責任が及ばないようにすることとか、特定の遺産の遺贈を受ける代わりに遺言者の妻の生活費として毎月最低●万円を支出することといった一定の条件を付けた上で遺贈するものです。
受遺者が負担する相続税の計算は、遺贈された財産の相続税評価額から負担額を控除した価額を取得したものとして計算することになります。
なお、負担額は遺贈時に確実であると認められる金額に限られるため(相続税基本通達11の2-7)、具体的な金額として評価することができない負担(例えば、受遺者が特定の相続人の面倒を見るといった金銭的負担が明確ではないもの)は控除の対象にすることができません。
負担の履行は停止条件ではないことから、受遺者が負担を履行しなくても遺贈の効力は発生します。
そのため、相続税の申告時期は、負担のない遺贈の申告時期と同じです(相続開始を知った日の翌日から計算して10か月以内)。
なお、受遺者が負担を履行しないときは、相続人は、負担の履行を催告した上で、家庭裁判所に対して遺贈の取消しを請求することができます(民法1027条)。
遺贈の取消しが認められた場合に更生の請求ができるかどうかについては明文の規定はありませんが、相続税法32条1項6号・相続税法施行令8条2項3号を適用ないし準用して更正の請求ができるという考え方があります。
そして、負担額に相当する金額については、負担の利益を受ける者に対して遺贈があったものとして相続税が課税されることになります(相続税基本通達9-11)。
ちなみに、受遺者が遺贈された財産を将来売却したときは、負担額は取得価額に含まれません。受遺者の取得価額は、遺贈者の取得価額と取得時期を引き継いだものとして計算されます(所得税法60条1項)。
包括遺贈
包括遺贈とは、遺産の全部又は一部について、一定の割合を示して行う遺贈のことです(民法964条)。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)、遺言者の一身に専属する権利を除き、遺言者の権利義務の全てを承継することになります。
なお、他に包括受遺者や相続人がいるときは、それらの者と遺産を共有することになります。
そのため、相続税を計算する際も、基本的には相続人と同様に取り扱われます。
とはいえ、包括遺贈者は相続人ではないことから、相続人のために設けられた各種優遇措置(基礎控除、生命保険金や死亡退職金の非課税額等)は適用されず、受遺者が遺言者の配偶者や1親等の親族でないときは相続税額が2割加算されることになります。
法人に対する遺贈
法人に対する遺贈をすると、大変な税負担を覚悟しなければなりません。
まず、受贈者である法人には法人税のみが課税されます(法人には相続税は課税されません)。
そのため、遺贈された目的物の時価(相続税評価額ではありません)を益金に参入し(法人税法22条2項)、事業収益等と合算して法人税の課税対象となります。
これに対し、遺言者には、遺贈した目的物を時価で譲渡したものとして譲渡所得税が課税されます(所得税法59条1項1号)。そのため、相続人は、相続開始を知った日の翌日から計算して4か月以内に準確定申告をし(所得税法125条1項)、譲渡所得税を納税しなければなりません(この譲渡所得税は、相続債務として相続税の課税対象額から控除することができます)。
まとめ
このように遺贈には様々なものがありますが、個人に対する遺贈には相続税が課税され、法人に対する遺贈には法人税が課税されることになります。
ただし、法人に対する遺贈には重たい税負担が発生することに注意が必要です。
相続税・事業承継対策についてお悩みの方へ
相続税・事業承継においては、ご自身にとってどの方法が効果的な対策となるのか、見極めることがまず大事です。トラブル防止の観点からも最適な対策・進め方ができるよう、プロの弁護士が専門家とも連携して安心のサポートをいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
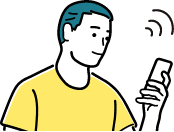
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


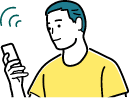


 メールで
メールで