
columns
弁護士コラム
相続における使途不明金と不当利得返還請求の時効・起算点を解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年12月19日 |
最終更新日:2025年12月19日

- Q
-
1年前に亡くなった父の相続手続きを進めていたところ、長年父の預金口座を管理していた弟が、生前から多額の引き出しをしていたことが分かりました。
弟は「父の生活費に使った」と言っていますが、具体的な使途を明らかにしようとしません。中には5年以上前の引き出しもあり、もう時効で請求できないのではと不安です。
弟が使い込んだお金を取り戻すには、どのような法的手段があるのでしょうか。
- Answer
-
相続人の一人が被相続人(亡くなった方)の預金を無断で引き出していた場合、他の相続人は「不当利得返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」によって返還を求めることができます。どちらを選ぶかによって、時効や証明すべき内容が異なります。
不当利得返還請求権の時効は「使い込みを知ったときから5年」、または「使い込みがあったときから10年」です。
一方、不法行為に基づく損害賠償請求権は、「使い込みがあったこと及び使い込んだ人を知ったときから3年」、または「使い込みがあったときから20年」で時効となります。
この記事では、使途不明金の返還請求において必要となる要件事実や時効の考え方、返還請求を成功させるための実務ポイントについて、詳しく解説します。
監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
相続手続きの中で「被相続人の預金がいつの間にか減っている」「家族の誰かが使い込んだかもしれない」といった使途不明金の問題が発覚することは珍しくありません。
この記事では、相続人による無断引き出しや使い込みに対して、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」を検討している方に向けて、請求を成立させるために必要となる要件事実や時効の考え方、実際の裁判例について、わかりやすく解説します。

目次
不当利得返還請求の時効と起算点

不当利得返還請求とは、法律上の理由なく他人の財産や利益を得た者に対して、その返還を求める制度(民法703条)です。
被相続人の預金を相続人が無断で引き出した場合には、他の相続人は不当利得返還請求権を行使することができます。
不当利得返還請求権には消滅時効が定められており、現行民法(166条)では次のように規定されています。
- 不当利得返還請求権を行使できることを知った時から5年
- 不当利得返還請求権を行使することができる時から10年
つまり、被相続人の財産が「引き出されていた事実を知ってから5年」、または「引き出し自体が行われた時点から10年」が経過すると、原則として請求できなくなります。例えば、亡くなった親の通帳を整理して初めて使途不明金が判明した場合、その判明時から5年以内に請求を行う必要があります。
しかし、現行民法の施行日である令和2年4月1日より前に発生した権利関係については、改正前民法が適用されます(改正附則第10条第4項)。すなわち、引き出し行為が令和2年3月31日以前に行われた場合、不当利得返還請求権の消滅時効は改正前民法の規律に従い、権利を行使できるときから10年となります(改正前民法第166条第1項・第167条第1項)。
実際の消滅時効に関する判断では、権利の発生時期(引出しの時期など)に応じた新旧両方の法律の使い分けが重要です。
時効の完成が迫っているときは、内容証明郵便の送付や訴訟提起などにより時効の完成を猶予することが可能です。
不当利得と不法行為の時効の違い
使途不明金の返還を求める場合には、「不当利得返還請求」と「不法行為に基づく損害賠償請求」のいずれを選ぶかによって、時効期間が異なります。
- 不当利得返還請求権
- 使い込みを知ったときから5年、または使い込みが行われたときから10年(民法166条)
- 不法行為に基づく損害賠償請求権
- 使い込みによる損害及び使い込みをした人を知ったときから3年、または使い込みが行われたときから20年(民法724条)
いずれの請求も、一定の期間を過ぎると法的に請求できなくなるため、使い込みに気づいたら速やかに行動することが大切です。
訴訟を検討する際には、まず時効が完成していないかを確認し、必要に応じて内容証明郵便の送付や訴訟提起による時効の完成猶予を行うことが求められます。
不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実

相続人による「使途不明金返還請求訴訟」では、法的な請求根拠として「①不法行為に基づく損害賠償請求」「②不当利得返還請求」「③委任契約上の債務不履行による損害賠償請求」などが考えられます。
このうち「不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)」は最も主要な法的構成であり、請求を成立させるためには以下の5つの要件事実を主張・立証する必要があります。
- 1原告の権利又は法律上保護される利益があること
- 2被告が①の権利又は保護法益を侵害したこと
- 3被告が②について故意又は過失があること
- 4原告に損害が発生したこと及びその数額
- 5②と④に因果関係があること
これらは一般的な不法行為の要件ですが、使途不明金の場合には、「引き出しが被相続人の生前」か、「死亡後(相続開始後)」かによって、立証すべき事実が異なります。
被相続人の生前の引き出し
被相続人の生前に、相続人の一人が無断で預金を引き出した場合には、その行為が不法行為(民法709条)に該当するかが問題となります。また、被告の不法行為により損害賠償請求権を取得するのは被相続人であり、原告は相続によりこの請求権を取得しているため、相続があったことについても主張・立証する必要があります。
この場合に、原告(他の相続人)が主張・立証すべき要件事実は、以下のとおりです。
- 1被相続人の預金債権が存在していたこと
- 2被告により①の預金が引き出されたこと
- 3(被告は①の預金につき引き出し権限がなかったこと)
- 4被告には、被相続人の預金債権を侵害した行為について故意又は過失があったこと
- 5原告は、被相続人の被告に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を相続分に従い相続したこと
なお、③の「被告に引き出し権限がなかったこと」については、原告が立証すべきではなく、被告が「引き出す権限があった」と抗弁として主張・立証すべきとするのが有力な見解です。したがって、原告は上記の➀②④⑤を中心に証拠を整えることが重要です。
なお、⑤は不法行為に基づく損害賠償請求権自体の要件事実ではなく、原告が被相続人から損害賠償請求権を取得したことを主張するための要件事実です。
実務上は、引き出し時期や金額・被相続人の判断能力・出金の使途などを示す通帳や明細・医療費や介護費等の領収書などを可能な限り収集し、「被相続人の意思によらない引き出し」であったことを具体的に示すことが求められます。
被相続人の死亡後(相続開始後)の引き出し
被相続人が亡くなった後に、相続人の一人が他の相続人の同意なく預金を引き出した場合にも、不法行為(民法709条)として損害賠償請求を行うことが可能です。
この場合に、原告(請求をする相続人)が主張・立証すべき要件事実は、以下のとおりです。
- 1被相続人の預金債権が被相続人死亡時(相続開始時)に存在していたこと
- 2原告は、その預金債権を相続し、預金債権について準共有持分を有していたこと
- 3①の預金につき被告が引き出したこと
- 4(被告は①の預金につき引き出し権限がなかったこと)
- 5被相続人の預金債権について原告が有する②の準共有持分を侵害した行為につき被告に故意又は過失があったこと
ここでも④の「引き出し権限があったかどうか(権限の有無)」は、原告ではなく被告側が抗弁として主張・立証すべきとするのが有力な考え方です。したがって、原告は上記の①②③⑤を中心に事実関係を整理すればよいと考えられます。
相続開始後の預金引き出しについては、引き出しをした相続人以外の相続人全員が同意すれば、民法906条の2(みなし遺産)の規定により、遺産分割の中で処理することも可能です。
しかし、引き出しをした相続人以外の他の相続人の同意が得られない場合や、引き出しの有無・使途を巡って争いがある場合には、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟によって解決を図るのが一般的です。
遺産分割手続きと使途不明金訴訟の関係

遺産分割がすでに終了した後に、新たな通帳や取引履歴が見つかり、被相続人の預金に不明な引き出しがあることが判明するケースがあります。このような場合でも、原則として使途不明金の返還を求める訴訟を提起することは可能です。
なぜなら、「不当利得返還請求権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」は、遺産分割の対象となる遺産そのものではなく、被相続人の財産を無断で引き出した相続人に対する独立した債権だからです。
そのため、遺産分割が終わっていても、使途不明金が後から発覚した場合には、改めて返還請求訴訟を起こすことができます。
遺産分割の対象となる遺産の原則
遺産分割の対象となるのは、相続開始時に存在し、分割時にも現存している財産です。この原則により、すでに処分されてしまった財産や、存在が確認できない財産は、原則として遺産分割の対象には含まれません。
例えば、相続人の一人が被相続人の生前に預金を引き出していた場合、その金銭は相続開始時点ではすでに遺産の中に存在しないため、他の相続人との間で遺産分割の対象とすることはできません。引き出した相続人がその金銭を遺産に戻すことに合意しない限り、その預金は遺産分割の対象から除外されるのが原則です。
なお、生前の引き出しについては、被相続人が引き出しをした者に対して「不当利得返還請求権」又は「不法行為に基づく損害賠償請求権」等を取得しており、当該債権が相続されることになりますが、預貯金債権以外の可分債権は遺産分割の対象とならず、法定相続分に従って相続されることになります。
また、相続開始後に遺産の一部が火災などで滅失して生じた保険金請求権や、遺産の一部が処分されて売却代金などの形に変わった場合、これらは代償財産ではありますが、原則として遺産分割の対象外とされます。このような財産については、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」など、別の法的手段によって回収を検討する必要があります。
使途不明金訴訟が提起される背景
相続における使途不明金の問題は、遺産分割調停や審判の中でしばしば顕在化します。その場合、争いのある預貯金は、一旦、遺産分割の対象から除外しておくのが一般的です。そのうえで、争いのない財産について先に分割を成立させ、残された使途不明金部分について、別途「不当利得返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」として民事訴訟を提起して解決を図る流れが多く見られます。
一方で、引き出された預金について、被相続人が相続人に対して贈与したものであると争いがない場合には、それを「特別受益」として相続分の計算上で調整すれば足ります。
実際には、被告(引き出した側)が「被相続人のために使った」「被相続人自身が使った」などと主張し、無断引き出しや贈与の事実を否定するケースが少なくありません。このように、使途や権限の有無について当事者の主張が対立する場合に、最終的な判断を求めて訴訟が提起されることになります。
預貯金を遺産分割対象とした最高裁決定の影響
平成28年12月19日の最高裁決定は、それまでの実務に大きな影響を与えた重要な判断です。この決定では、被相続人の死亡時に残っていた預貯金債権について、「相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象となる」と判断しました。
この判例以前は、預貯金は相続開始と同時に法定相続分に応じて自動的に分割されると考えられており、相続人の一人が勝手に払い戻した場合には、他の相続人の持分を侵害したとして、不法行為または不当利得に基づく返還請求が容易に認められていました。しかし、本決定以降は、預貯金が遺産分割の対象財産とされたため、「分割が確定するまでは各相続人に固有の預金債権は存在しない」という構成が取られるようになりました。
この最高裁決定は、あくまで「死亡時に現に存在する預貯金債権」に限られます。したがって、被相続人の生前に無断で引き出された預金に基づく「不当利得返還請求権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」は、本決定の影響を受けません。
また、相続開始後に共同相続人の一人が無断で払い戻しを行った場合でも、他の相続人の準共有持分を侵害したとして、「不当利得返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」ができると解されています。
使途不明金(不当利得・不法行為)に関する裁判例

ここでは、相続における使途不明金をめぐり、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」が争われた実際の裁判例を取り上げます。
各事例について、概要・当事者の主張・裁判所の判断・実務上のポイントを整理し、どのような場合に返還請求が認められ、どのような事情で否定されたのかを具体的に解説します。
現金の存在や被告の利得が立証できず請求が棄却されたケース
被相続人が保管していた現金について金額が立証できないこと等から、不当利得返還請求を棄却した事例(東京地判令和4年4月25日・平成30年(ワ)36095号)があります。
この事例は、被相続人Aの子であるXらが、他の兄弟Yらに対し、Aの財産のうち約3,500万円分が使途不明であるとして、不当利得返還および損害賠償を求めたものです。
Xらは、Aが生前に約6,000万円の現金を金庫に保管しており、Yらがそのうち一部を引き出して費消したと主張しました。これに対し、Yらは「亡Aの金庫にあった現金は6,000万円もなかった」と反論し、Aが自ら現金を取り出して使っていた可能性もあると主張しました。
裁判所は、まずXらの供述のみでは、亡Aが実際に6,000万円の現金を保管していたと認めるには客観的な裏付けに欠けると判断しました。さらに、金庫の管理状況に関して、亡A自身も金庫のダイヤル番号を把握しており、自由に出し入れできる状態であったことが確認されたため、A自身が現金を取り出して費消した可能性を否定できないとしました。
その結果、裁判所は、Yらが現金を不当に取得したこと、またはAに損害を与えたことを認めるに足りる証拠がないとして、Xらの不当利得返還請求および損害賠償請求をいずれも棄却しました。
この裁判例は、使い込みに関して、財産の管理状況、特に被相続人本人がアクセスできる状況だったかどうかが重要なポイントになることを示しています。
立証困難な使途不明額の一部が不当利得と認定されたケース
使途不明金について、裁判所が民事訴訟法248条 (損害額の立証が困難な場合の裁量認定)を考慮して一部を不当利得と認めた事例があります(東京地判平成28年3月15日・平成26年(ワ)24344号)。
この事例は、相続人の一人である被告Yが長期間にわたり両親(被相続人A・B)の財産を管理していたところ、他の相続人原告Xから「Yが財産の一部を無断で費消した」として、不当利得返還請求が提起されたものです。
裁判所は、Yによる支出のうち葬儀費用・施設費・生活費・雑費などの正当な支出を控除した約424万円について、使途が明らかでない部分があると認定しました。
しかし、①管理期間が11年と長期にわたる、②被告に派手な生活の形跡がない、③他方で被告が収支記録を残していない、といった事情を総合的に考慮し、民事訴訟法248条の趣旨に照らし、裁判所は使途不明額(約424万円)の約半分(210万円)を不当利得額と認定し、Xの法定相続分5分の1に相当する42万円の返還請求を認めました。
この裁判例は、立証が難しい使途不明金であっても、裁判所が諸事情を総合考慮して一部を不当利得と認める場合があることを示しています。
紛争防止の観点からは、長期間にわたる財産管理において、収支の記録や領収書を残しておくことが重要です。
不当利得返還請求を成功させるための証拠と準備

使途不明金に関する返還請求を行う際には、証拠の収集と整理が何より重要です。特に、不当利得や不法行為に基づく請求では、「どの預金が・いつ・誰によって・どのような目的」で引き出されたのかを示す客観的な資料が求められます。
まず、銀行通帳・預金明細・入出金履歴を確認し、不自然な引き出しや大口の出金があった時期を特定します。また、銀行や金融機関への取引照会(取引履歴の開示請求)を行うことで、引き出しの日時や窓口担当者などの情報を確認できる場合があります。
そのうえで、介護費用・医療費・生活費などの領収書や明細を可能な限り集め、被相続人の生活状況と照らし合わせながら、使途が正当であったかを分析することが必要です。
さらに、家庭裁判所で行われた調停の記録や、他の相続人とのやり取りの記録(メール・メモ等)も、事実関係を裏付ける有力な証拠となります。
弁護士が関与することで、時効の完成猶予や証拠保全の措置を講じることも可能です。内容証明郵便により請求を送付したり、訴訟提起の準備を行うことで、消滅時効の完成を防ぎつつ、必要な証拠を確保できます。
不当利得返還請求の弁護士に相談すべきタイミング

使途不明金の問題は、家族間の感情が絡み合いやすく、当事者同士の話し合いだけで解決するのは容易ではありません。「相手が説明に応じない」「通帳や記録を見せてもらえない」などの状況が続く場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが大切です。
特に注意すべきは時効の問題です。不当利得返還請求権は「使い込みを知ったときから5年、または使い込みがあったときから10年」、不法行為に基づく損害賠償請求権は「損害および加害者を知ったときから3年、または行為時から20年」で時効にかかります。「あとで確認しよう」と放置しているうちに時効が完成してしまうケースもあるため、早期の対応が欠かせません。
証拠が十分に揃っていない段階でも、弁護士が介入することで、銀行照会や証拠保全の手続きを通じて必要な資料を確保できる場合があります。内容証明郵便による請求通知を送付すれば、時効の完成を猶予させることも可能です。
さらに、訴訟提起のタイミングや法的構成(不当利得・不法行為・遺留分侵害額請求のいずれを主張するか)について、専門家の助言を受けることで、不要なトラブルや手続きの重複を防ぐことができます。
使途不明金の問題では、「時効が迫っている場合」「相手が話し合いに応じない場合」「証拠が不十分な場合」などは、早期の対応が解決への第一歩となります。特に、引き出しの時期や使途不明金の発覚から時間が経過している場合には、できるだけ早く弁護士に相談して法的手続を進めることが重要です。
よくある質問(Q&A)

ここでは、使途不明金の返還請求を検討している方から寄せられる質問の中から、特に多いものを取り上げ、実務的な観点から簡潔に解説します。
- Q
- 不法行為で訴える場合、何を証明する必要がありますか?
- Answer
-
不法行為に基づいて使途不明金の返還を求める場合、立証すべき内容は、引き出しが行われた時期(被相続人の生前か、死亡後か)によって異なります。
【被相続人の生前に引き出しが行われた場合】
① 被相続人の預金債権が存在していたこと
② 被告(相続人など)がその預金を引き出したこと
③ 被告に、被相続人の財産を侵害する故意または過失があったこと
④ 原告が、その損害賠償請求権を相続によって取得したこと
【被相続人の死亡後(相続開始後)に引き出しが行われた場合】
① 被相続人の死亡時に被相続人の預金債権が存在していたこと
② 原告がその預金債権を相続し、共同相続人として準共有持分を有していたこと
③ 被告が、他の相続人の同意を得ずに預金を引き出したこと
④ 被告に故意または過失があったこと
いずれの場合も、被告の引き出し権限については、被告側が「引き出し権限を有していたこと」を抗弁として主張・立証すべきとされており、原告が無権限であったことまで証明する必要はないとするのが有力な見解です。
- Q
- 遺産分割協議が終わっていても、使途不明金の訴訟はできますか?
- Answer
-
はい、可能です。
被相続人の生前に生じた「不当利得返還請求権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」は、可分債権であり、遺産分割の対象となりません。預貯金債権以外の可分債権は、遺産分割をせずとも、各相続人が債権額を法定相続分で割った額を取得します。
このため、「不当利得返還請求権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」については、遺産分割を経ることなく、各相続人が法定相続分に応じた額を取得することになります。
また、被相続人の死亡後に使途不明金が生じた場合、遺産分割時に当該引き出された金銭は遺産に属していないため、民法906条の2でみなし遺産とされない限り、遺産分割の対象になりません。遺産であった預貯金債権は共同相続人の準共有となっていますが、それにも関わらず一部の相続人に無断で引き出された場合、他の相続人は自身の準共有持分を侵害されたとして「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」が可能になります。
したがって、遺産分割がすでに終了していても、別途訴訟を提起することができます。
東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所
相続をめぐる使途不明金の問題は、法律上の構成が複雑で「不法行為」「不当利得」「贈与」「特別受益」「遺留分侵害」など、複数の論点が絡み合うことが少なくありません。また、時効や証拠の有無によって、請求が認められるかどうかの結果も大きく変わります。
この記事で紹介した裁判例のように、一見似たような事案でも、支出の目的や被相続人の意思の有無によって結論が異なります。そのため、使途不明金の返還を求める場合には、早い段階で専門家へ相談し、最も適切な法的構成を見極めることが重要です。
直法律事務所では、相続における預金の使い込みや不当利得返還請求に関するご相談をはじめ、相続をめぐる紛争の予防から解決まで、一貫した法的サポートをご提供しています。お困りの方は、まずは一度ご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
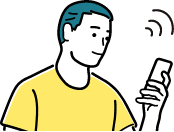
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


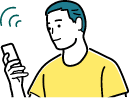


 メールで
メールで