
columns
弁護士コラム
財産管理委任契約とは?作成方法や任意後見との違いを解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年11月20日 |
最終更新日:2025年11月20日

- Q
-
最近は足腰が弱くなり、自分で銀行や役所まで行くのが大変になりました。認知症にはなっていませんが、物忘れも多くなってきたので、今後は近隣に住んでいる長女と「財産管理委任契約」を結び、預貯金の管理等の世話を頼みたいと思っています。ただ、遠方に住む長男から預貯金の使い込みを疑われるなどのトラブルになるのは避けたいです。
具体的な契約書の作り方や、委任できる範囲や内容、今後のためにできることなどについて教えてください。また、任意後見制度とはどう違うのでしょうか?
- Answer
-
財産管理委任契約と任意後見制度の主な違いは、①公正証書による契約が必要かどうか、②本人の判断能力の有無です。
財産管理委任契約は書面を必要とせず、本人(ご質問者様)が判断能力を保っている段階から、受任者に一定の財産管理を任せることができます。預貯金の管理のほか、要介護認定の申請、病院・施設の入所手続き、費用の支払いなどの療養看護に関する手続きも委任できます。
一方、任意後見制度は、判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人と支援内容を事前に取り決めておく制度で、能力低下後は家庭裁判所が選任する任意後見監督人による公的な監督を受けられます。
将来的に認知症などで判断能力を失った場合に備え、財産管理委任契約と任意後見契約を併用することも可能です。この場合、任意後見契約を含むため、必ず公正証書で作成する必要があります。
一般的には、本人の判断能力が低下した際は、受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、審判確定をもって財産管理委任契約が終了し、その後は任意後見契約へ移行します。これにより、判断能力が低下した後の財産管理は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで行うことが出来ます。
この記事では、財産管理委任契約の内容や手続き、判断能力の判断基準、デメリットや注意点、類似した制度との違いなどについて、詳しく解説していきます。
監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
「自分が少しでも元気ではっきりしているうちに、財産管理を誰かに任せたい」
このように悩んでいる方に向けて、身近で信頼できる人に財産の管理や療養看護の手続きなどを、裁判所の関与なく、自由に任せられる「財産管理委任契約」という方法をご紹介します。
本記事を読むことで、財産管理委任契約のメリット、デメリット、どんなことを委任できるのか、他の制度との違いが理解できるようになります。

目次
財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約とは、家族や親戚など信頼できる人物に自己の財産管理や療養看護を委任する民法上の契約です。具体的には預貯金の払い戻しや戸籍謄本の取得、要介護認定の申請など委任内容は様々で、与える代理権の範囲や内容は、当事者間で自由に決めることができます。
本人に判断能力が低下する前に契約する必要があり、本人の判断能力が十分な内から契約の効力を発生させることが可能です。このほか死後事務委任契約や任意後見契約と併用して契約できるなど、柔軟性が高いものです。
財産管理委任契約は民法上の「委任」の規程に基づく契約ですので、当事者間で合意があれば口頭や黙示の意思表示でも法律上は成立します。しかし、後のトラブル防止の観点から、契約書や公正証書で締結するようにしましょう。
財産管理委任契約が適しているケース
財産管理委任契約は、判断能力は残っているものの、身体的な事情により、本人で財産管理が困難となった方に適しており、主に以下のようなケースで利用されています。
- 怪我や病気により、長期入院や車椅子、寝たきりの生活が続いている
- 加齢で足腰が弱くなり、外出できるほどの体力がない
- 目や手が不自由で文字の読み書きが難しく、申請の手続きなどが困難
怪我や病気が完治するまでの期間、一時的に契約することも可能です。
任意後見契約や家族信託との違い
財産管理委任契約のほかに、任意後見契約や家族信託などの類似した制度が検討されることがあります。これらは、効力発生のタイミング・財産の名義人・公的な監督機関の有無などに違いがあり、それぞれ性質が異なります。
任意後見契約は、基本的に委任者の判断能力に問題がない時点で契約を締結し、判断能力が低下、もしくは失ったと判断された時点で契約の効力が発生し、任意後見監督人選任の申立てをするものです。任意後見開始には、任意後見監督人の選任申立てが必要であり、任意後見人は任意後見監督人の関与・監督を受けながら財産管理を行います。
このため、判断能力があるうちは財産管理委任契約を結び、能力が低下した後は成年後見制度へ「移行」する形の契約とするケースが多く見られます。
また、家族信託は信託法が適用される制度で、財産の名義人が本人(委託者)から受託者に移る点が大きな特徴です。これにより、委託者の破産等による財産散逸を防止できるほか、委託者や受託者が死亡しても原則として契約が終了しないといった特徴があります。
| 制度の種類 | 効力発生のタイミング | 財産の名義人 | 公的な監督 |
| 財産管理委任契約 | 契約締結後すぐ | 本人(委任者) | なし |
| 任意後見契約 | 判断能力低下後 | 本人 | あり (任意後見監督人) |
| 家族信託 | 契約締結後すぐ | 受託者 | なし |
財産管理委任契約の作成方法
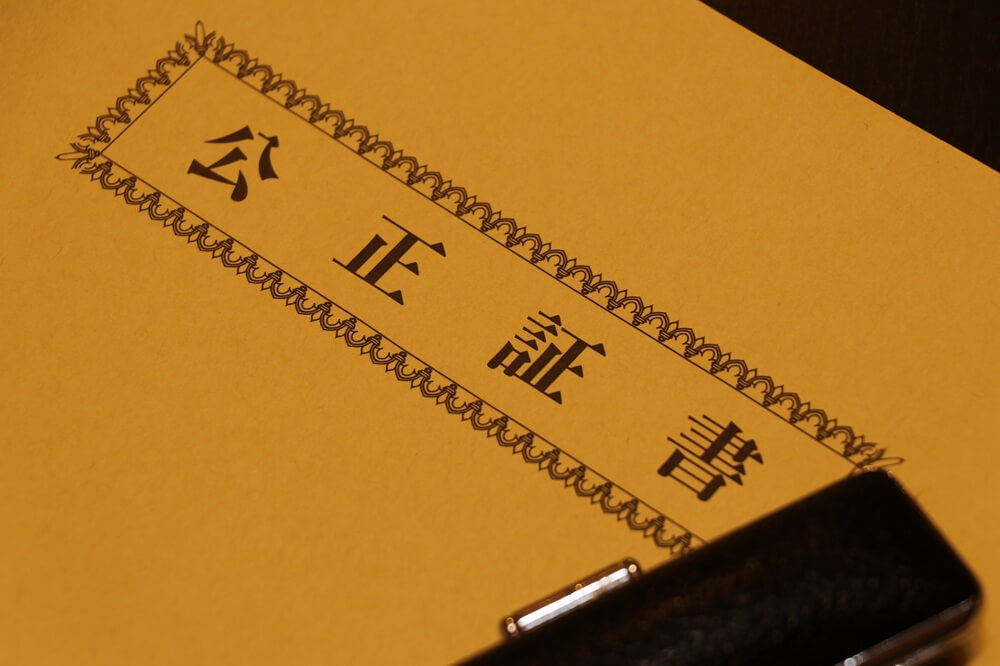
財産管理委任契約は、前述のように口頭あるいは黙示でも成立しますが、契約書を作成して締結すること、可能な限り公正証書で作成することをおすすめします。通常の契約書と公正証書は性質が異なります。
契約書は私人間で作成されるもので、私文書と呼ばれます。通常の契約書については、相手方から「そんな契約をした覚えはない」などと主張されてしまう場合があります。このような場合、合意したはずの契約内容を相手に実現させるためには、契約の締結やその過程から主張・立証する必要があり、相当な手間がかかります。
一方で公正証書は公文書と呼ばれ、当事者の意思をしっかりと確認しつつ、厳格な手続きを踏んで作成されます。その上で弁護士や検察官、裁判官として長年経験を積んだ後に法務大臣から任命された公証人によって正確に作成されます。契約内容の有効性などについては強い推定が働き、立証が容易となります。
契約や制度の種類によっては、公正証書による作成を法律で義務づけているものもあります。財産管理委任契約では公正証書の作成は義務づけられていませんが、トラブルを小さく抑える方法として前向きに検討しましょう。
財産管理委任契約書の書き方
契約書に特段の様式はありませんが、不備がないように以下の必要事項を基本として記載してください。
なお、委任内容は、当事者間で自由に増やすことができます。
- 委任者と受任者の氏名及び住所
- 契約の目的や趣旨
- 管理を委任する財産一覧
- 詳しい委任内容や財産の管理・運用の方法
- 記録や報告の方法などについて
- 発生する費用の負担は誰がするのか
- 受任者に対する報酬の有無・金額
- 受任者への報酬の支払い方法
- 代理権の消滅事由や契約の解除について
- 契約終了時の財産引継ぎについて(任意後見契約への移行型の場合は、任意後見監督人選任の審判が確定した時に契約終了する等)
公正証書にするメリットと費用
公正証書にするメリットは、以下の3点です。
- 公証役場が保管するため、紛失や改ざんのリスクがない
- 公証人には守秘義務があり、契約内容が外部に漏れない
- 文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働く
- 反証のない限り、完全な証拠力があるため、紛争の早期解決が期待できる
また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務について、以下の2点の記載がある公正証書は、金銭債務の不履行があったとき、裁判手続を経ずに、直ちに強制執行できます(執行証書)。
- 一定額の金銭の支払についての合意
- 債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述
なお、費用については、公証役場に収める手数料や印紙代などの実費が、約1万5000円から2万円程度です。
さらに、弁護士などの専門家に依頼する場合、専門家や事務所によって異なりますが、契約書の作成費用だけでも5万円程かかります。作成に関する相談料や公正証書にするための手続きの報酬まで含めると、総額で約10万円から20万円程度になるのが一般的です。
財産管理委任契約で委任できる範囲

財産管理委任契約では、主に以下のような内容について委任することが一般的です。
なお、内容については、公序良俗の範囲内で自由に決定することができます。
- 預貯金の出入金や振り込みの手続き
- 家賃収入や年金の管理
- 家賃・水道光熱費・納税などの支払い代行
- 要介護認定の申請
- 病院や介護施設の入所手続き・サービスの選定・契約締結代行
- 役所・金融機関・医療機関での手続き
- その他、日用品の買い物など
財産管理委任契約を契約書によって締結する場合には、上記のように委任事項を具体的に列挙することで、委任の範囲を明確にすることができます。しかし、家族・親族間で口頭や黙示的に財産管理委任契約が締結されている場合、委任事項が明確ではなく、包括的であることが多いです。
明確な委任事項がある場合でも、包括的な委任の場合でも、委任の範囲を超えた支出や本人の利益にならない支出は、受任者による使い込みが疑われ、問題視されやすくなります。
どのような支出であれば、委任の範囲と認められやすいのか、また、委任の範囲外であっても正当な行為と認められるのか、理解を深めていきましょう。
使い込みとみなされやすい支出
包括的な財産管理委任契約がある場合でも、委任者の明確な承諾がない支出は委任の範囲外と評価されます。
特に、以下のようなケースは典型例です。
- 本人の承諾がない支出
- 行為者(受任者)のみが利益を得る支出
例:管理を委任された口座から引き出したお金を、受任者が自分の孫の家賃補助に使用するケース
こうした行為は、権限外の行為として民法上の不法行為及び不法利得に該当するため、返還や損害賠償を求めて訴訟を起こされる可能性が高まります。
夫婦間で締結している場合
夫婦間で財産管理委任契約を結んでいる場合、以下の理由から、明確な承諾がなくても、配偶者による支出が使い込みには該当せず、正当と判断されることがあります。
- 婚姻期間中に生じる費用は、夫婦が資力に応じて公平に分担する義務がある。(民法760条)
- 単独で保有する部分を除き、夫婦が協力して築いた財産は共有として扱われる。(民法762条)
- 実質的に、夫婦共有財産が入っている夫名義の口座から、妻が生活費を引き出す程度であれば、問題になりにくい。
葬儀費用としての支出
包括的な財産管理委任契約の受任者は、委任者の死亡後に葬儀費用を相続財産から支出することはできません。
財産管理委任契約は、委任者の死亡によって終了するのが原則であり、死後事務委任契約を併用していない限り、受任者には委任者の死亡後の財産管理権限がないためです。
また、葬儀費用を誰が負担するのかについては、法律上明確な定めはありません。
被相続人が生前に承諾していたかどうかが重要になるため、相続財産からの支出が当然に認められるものではないのです。喪主が負担する場合や相続人が共同で負担する場合、あるいは条理や慣習に従うべきとする考え方など、様々な見解がありますが、最終的には相続人間で話し合いにより解決を図るべきものとして考えられています。
事務管理として認められやすい支出
委任契約がない場合や契約の範囲外の行為でも、本人のために行ったと評価できる支出であれば、民法上の「事務管理」(民法697条)に該当し、正当性が認められる場合があります。
事務管理は、本人を代理することはできませんが、本人のために自己名義で契約でき、その事務処理のために支出した費用の償還請求が可能です(民法702条)。事務管理として認められるためには、本人にとって有益な事務かどうか、そして、各支出が本人の意思に基づくかが判断基準となります。
有益と評価されやすい支出の例は、以下の通りです。
- 生活費(食費・電話代・光熱費・衣類費など)
- 医療費・入院費・介護サービス料・介護用品
- 所有不動産の維持管理費(固定資産税・修繕費など)
受任者だけで判断が難しい支出については、委任者本人から書面で承諾を得るほか、相続人や弁護士などの第三者と協議し、慎重に判断していきましょう。
裁判所による契約の有効性の判断基準

親族間で委任契約が締結されたような場合、口頭や黙示で契約締結の意思表示がされていることが多く、書面などの客観的な証拠がないことがほとんどです。
委任者が亡くなった場合、相続人間で、受任者の行為が委任を受けていたのかどうかが争われることが多々あります。また、委任者の判断能力が低下した場合も他の親族などと争いになることもあります。そのため、当事者間に包括的な委任契約が存在したか否かが重要となります。
包括的な委任があったことの認定が、単一の事実のみで判断されることはほとんどありません。口頭や黙示的な委任契約の有無や、委任当時において本人に意思能力があったかなど様々な状況証拠を総合的に考慮して、裁判所は判断することになります。
「包括的な委任」の有無
包括的な委任の存在を認定するに際して、裁判所は考慮すべき要素として以下の3点を重視しています。
- 委任者が受任者に対して、通帳などの財産を委託した経緯
- 委任者が受任者に対して、通帳などの財産を委託した状況(第三者の関与があったかなど)
- 受任者による委任者の財産管理の状況
これらの要素を総合的に考慮し、包括的な委任があったと認定されれば、財産の使い込みが疑われた場合にも、受任者側に有利に働くことがありますので、以下で解説していきます。
財産を委託した経緯と関係性
裁判所は、「なぜ」「どのような状況で」被相続人が財産の管理を委任することにしたのか、その経緯を重視します。
- 委任契約締結以前に、被相続人が自身でしっかり管理していたか
- どのような原因で心身の状態が悪化し、自身での財産管理が困難になったのか
- 長年同居し、献身的に介護をしてくれた家族など、財産を任せるほどの特別な信頼関係があったか(受任者との関係性)
このような委任者と受任者との関係性が、包括的な委任の有無を判断する重要な材料となります。
財産管理の状況と金銭の流れ
受任者が委任された財産をどのように管理していたのかについては、裁判所から厳しく問われる場合があります。受任者は、民法上の善管注意義務や収支報告義務を負っているため、管理の状況や金銭の流れについて矛盾なく説明できるかどうかが重要になります。
以下のような点が判断材料となります。
- 預貯金の出入金において、委任者からの指示があったか
- 受任者がどのように管理していたのか
- 従前の生活費や医療費の支払い額と一致しているか
- 高額な引き出しについて、その理由や使途を合理的に説明できるか
これらの点について、受任者側から具体的な反証が示されない場合、不当利得返還請求などを受ける可能性があります。
委任時の「意思能力」の有無
財産管理委任契約は、契約時点において委任者本人に意思能力(行為の意味を理解し判断する能力)があることが前提となります。そのため、委任当時の意思能力が争われる場合には、委任者がどの程度の判断能力を備えていたのかを、客観的資料から総合的に確認する必要があります。
裁判所が主に参考にする判断材料は、次のとおりです。
- 医師による診断名や検査結果
認知症診断や、長谷川式簡易スケール(HDS-R)などの簡易検査の点数は、意思能力の有無を判断するうえの重要な資料になります。 - 看護師・介護士によるカルテ・記録
日々の様子や会話の状況、見当識の有無など、医療・介護現場の記録も判断の参考にされます。 - 検査時の体調・精神状態
「認知障害」と記載されていても、診察当時が搬送直後で体調が極端に悪かっただけというケースもあります。カルテ記載を額面どおりに受け取らず、状況も併せて確認されます。 - 日常会話や意思表示の状況
診断上は認知症とされていても、表情や受け答えを通じてコミュニケーションが成立していた場合には、意思能力があったと評価されることがあります。
実際の裁判例でも、脳梗塞の影響で言葉が不自由な状態であっても、受任者との会話が成り立っていたことから意思能力が認められたケースがあります。 - 言動・行動全体からの総合評価
「意思疎通困難」と記録されていても、呂律が回りにくいだけで理解力は保たれている場合もあり、記録の表現と実態が一致しないことも少なくありません。
裁判所は、診断名や検査の点数だけで意思能力の欠如を判断するわけではありません。例えば、長谷川式簡易スケールで20点以下(認知症疑い)や15点前後の低い点数であっても、その点数のみでは意思能力を否定できず、検査時の精神状態や応答内容などが点数に反映されないため、他の資料と併せた総合判断が必要とされています。
また、意思能力が低下していた可能性がある場合には、委任の範囲が生活費・医療費・介護費など必要な支出に限定され、多額の引き出しについて包括的な委任があったとは認められないケースもあります。
財産管理委任契約のデメリットと注意点

財産管理委任契約には、以下のようなデメリットがあります。
- 受任者による財産の使い込みや、反対に使い込みを疑われるリスクがある
- 金融機関が財産管理委任契約に対応していない場合がある
- 委任者本人が締結した不利益な契約について、受任者には取消権がない
また、受任者に故意がなかったとしても、適切な管理方法が分からないまま対応してしまい、第三者から「使い込みをしているのではないか」と疑われる可能性があります。これにより、家族・親族間で感情的な対立が生じ、将来の遺産分割協議において、争いが生じる恐れもあります。
受任者による使い込みリスク
財産管理委任契約には、受任者によって財産を使い込まれるリスクがあります。成年後見制度や任意後見制度とは異なり、財産管理委任契約には受任者を監督する裁判所や監督人が存在しないため、基本的には受任者の知識や経験、そして良心に依存せざるを得ません。
家族や親族を受任者とする場合でも、使い込みが生じる危険や、反対に使い込みを疑われる危険があります。このようなトラブルを防ぐためには、複数の受任の選任し、管理する財産や手続きを分担させ、相互に監視できる体制を整える方法が考えられます。
また、専門知識と倫理観を備えた弁護士などの専門家を受任者とすることも、有効な対策の一つです。
さらに、財産管理委任契約に監督人を置くことも可能です。親族を監督人とすることもできますが、弁護士などの第三者を監督人に選任し、受任者に対して報告義務を課すことで、財産管理事務をより適正に行わせるとよいでしょう。
金融機関が対応しない可能性
財産管理委任契約に対応していない金融機関は少なくありません。成年後見制度のように裁判所が関与しているわけではなく、財産管理委任契約は私人間での私的な契約のため、法的根拠や社会的信用が十分でないことが理由とされています。そのため、親族や士業などの専門家であっても、受任者を代理人として認めず、本人確認や委任状がないと対応できないと方針を固める金融機関もあります。
代理人制度を設けているところもありますが、ATMを操作する程度しか認められておらず、受任者が窓口で多額の取引を行うことは、まだまだ難しいのが現状です。
利用したい金融機関が、財産管理委任契約に対してどこまで対応しているのかは、契約締結前に必ず確認するようにしましょう。また、契約書を公正証書で作成することで、契約の信用度を高めることができる場合もあります。
不利益な契約の取消権がない
委任者本人が自ら契約を締結した場合、その契約が不利益なものだったとしても、受任者には取消権がありません。取消権は、家庭裁判所によって成年後見人などに認められる強い権限であり、委任者の代理人に過ぎない財産管理委任契約の受任者には認められていません。
また、医療行為に関しても、受任者には同意権がなく、原則として本人の同意が必要です。不動産売買などの重要な取引では、不動産会社や司法書士から本人の同意や意思の確認を求められることが多く、実質的に受任者としての権限が意味をなさないケースもあります。
悪質で高額な訪問販売などの消費者トラブルを防ぐ観点からも、必要に応じて、任意後見契約への移行や法定後見制度の利用を検討することも選択肢の一つです。
財産管理委任契約を結ぶタイミングと注意点

財産管理委任契約は、委任者の判断能力が十分にある段階で締結することが重要です。判断能力の低下により契約が無効になるリスクや、契約終了の扱いについて誤解されやすい点も多いため、締結のタイミングと注意点を正しく理解しておく必要があります。
ここでは、契約締結の適切な時期、契約の終了事由、そして手続きの流れについて解説します。
判断能力があるうちに締結すべき理由
財産管理委任契約は民法上の契約であり、契約の締結には当事者に判断能力があることが必要です。そのため、委任者の判断能力が低下している場合には、そもそも契約を締結することができません。
また、契約締結時点では判断能力があったとしても、契約締結前から認知症を発症していた可能性がある場合には、「契約締結当時の委任者の判断能力」が争点となることがあります。したがって、委任者の判断能力が十分にある段階で契約を締結し、委任者自身が適切に監督できる時期から管理を開始しておくことが理想的です。
さらに、委任者の判断能力の低下後は、財産管理委任契約には監督機能がなく、受任者に取消権もないため、財産の適切な管理が難しくなることもあります。
判断能力低下後の取り扱いと契約が終了する場合
委任者が法定後見開始の審判を受けた場合には、財産管理委任契約は終了します(民法653条)。
もっとも、委任者の判断能力が低下したという事実だけで、契約が自動的に終了するわけではありません。また、任意後見契約が開始された場合も、そのこと自体によって契約が直ちに終了するわけでもありません。
このため、契約書には「委任者の判断能力が低下した時点で任意後見監督人の選任申立てを行い、審判確定時に本契約を終了させる」など、契約の終了事由を明確に定めておくことが推奨されます。
財産管理委任契約の手続きの流れ
財産管理委任契約が成立するまでの流れは、以下のとおりです。
- 受任者と相談し、選任する
- 家族・親族・弁護士などから適切な受任者を選任します。
- 委任する内容を決定する
- 預貯金管理・支払い代行・行政手続きなど、任せたい範囲を具体的に決定します。
- 契約書を作成し、締結する
- 可能であれば公正証書で作成し、契約内容を明確化します。
なお、受任者の選任前に、利用中(または利用予定)の金融機関が財産管理委任契約に対応しているかを確認し、必要書類を事前に用意しておくことで、代理人届出などの手続きをスムーズに行うことができます。
財産管理委任契約を弁護士に依頼するメリット

財産管理委任契約の受任者は、家族や親族だけでなく、弁護士に依頼する方法もあります。弁護士は法律や実務に関する知識や経験が豊富であり、高い職業倫理を保持している専門家であるため、安心して財産管理を任せやすい点が大きなメリットです。
弁護士を受任者とする場合には、通常、月額費用などの報酬がが発生しますが、不正行為のリスクは比較的小さく、家族や親族では対応が難しいような財産についても、適切な管理が期待できます。
また、委任者の判断能力が低下し、成年後見制度の利用や任意後見契約への移行が必要になった場合にも、弁護士であれば手続き面を含めて、手厚いサポートを受けることができます。
トラブルを防ぐためのチェックポイント
弁護士に依頼する場合でも、相談内容などを書面等で記録し、メールで相互に確認するなどして、確認内容の透明化を図ることが重要です。
また、以下のような点を確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
- 委任契約の背景や目的などが正確に伝わっているか
- 財産の種類・通帳・権利書・実印などの保管場所や管理方法
- 委任の期間や解除・終了事由
- 弁護士に対する報酬や実費の支払方法
- 弁護士からの報告の頻度や方法
- 受任者の判断能力低下時に、委任者がどのような対応をとるべきか
家族間での不信感を避ける方法
家族以外に委任すると、不信感を覚える家族がいるリスクが想定されます。「自分たちでは信用できないのか」「家族でやることに契約書や弁護士は必要ない」などという主張が出ることもありますが、その背景には自分たちが選ばれなかったことや相談されなかったことに不満を感じている場合もあります。
家族との関係にもよりますが、関係が良好であれば、事前に弁護士に依頼する目的や背景を伝えたうえで、依頼することが望ましいでしょう。
また、弁護士の連絡先や管理を依頼している財産の内容などを家族間でできるだけ共有し、定期的に報告を受けるようにすることが重要です。
当然、弁護士も委任者の家族間で対立しないように適切な配慮を心がけており、要望に応えられるよう最善を尽くしています。
よくある質問(Q&A)

- Q
- 任意後見制度や死後事務委任契約と併用できますか?
- Answer
-
財産管理委任契約は、任意後見制度や死後事務委任契約と併用することが可能です。
任意後見制度は、判断能力が低下する前に、「将来の後見人」と「支援内容」をあらかじめ契約で定めておく制度で、後見開始後は家庭裁判所が任意後見監督人を選任して公的な保護が及びます。
死後事務委任契約は、委任者の死亡後に必要となる事務(葬儀・納骨・遺品整理など)を、委任者の希望に沿って行うための契約です。
そのため、「委任者の判断能力が十分なうちは、財産管理委任契約」「判断能力が減退した場合は、任意後見契約へ移行」「委任者が亡くなった場合は、死後事務委任契約へ移行」といった形で、契約を組み合わせて締結することもでき、これらは同時に契約することも可能です。
身体の不自由や認知症がいつ発症するかは予測できません。また、死亡後には遺品整理や葬儀の取り決めなどの事務も必ず発生します。こうした事情から、これら3つの制度を併用して、将来に備えておくことが実務上推奨されています。
- Q
- 誰を受任者にできますか?
- Answer
-
基本的には、どなたでも受任者に選任することができます。配偶者や子どもを受任者とするのが一般的で、法律上の資格要件や人数の制限もありません。
配偶者に認知症などの懸念がある場合や、既に亡くなっている場合には、同居もしくは近隣に住む子どもを受任者に選任するケースが多く見られます。
ただし、委任者が亡くなった後に受任者が使い込みを疑われる恐れや、精神的・実務的な負担が生じる可能性もあることから、弁護士などの専門家を受任者として選任する方も増えています。
- Q
- 金融機関は対応してくれますか?
- Answer
-
財産管理委任契約に対応している金融機関は、実際のところそれほど多くありません。現状の金融機関では契約書を提示しても通用せず、その都度委任状を作成して、窓口に手続きしなければならない場合も多くみられます。
金融機関によって名称や必要書類は異なりますが、「代理人制度」を設けているところもあります。この制度を利用することで、あらかじめ登録された親族や専門家が、代理人として支払い等の手続きを行えるようになります。
メガバンクなど比較的規模の大きい金融機関では対応しているところが多いようですが、自分が利用したい金融機関がどこまで対応しているのかは、契約締結前に確認するようにしましょう。
東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所
財産管理委任契約は、判断能力があるものの、身体的な事情から財産の自己管理が困難になっている人に適した制度です。
委任者本人の判断能力が低下する前から締結でき、他の制度や契約との併用や移行がしやすいというメリットがあります。
一方で、「監督機関がない」「金融機関が対応していない」「公正証書にしないと安全性が担保されにくい」などのデメリットも指摘されています。
直法律事務所では、財産管理委任契約をはじめ、相続に関して豊富な経験を持つ弁護士が、幅広いご相談に対応しています。受任者との信頼関係が何よりも大切ですが、周囲に任せられる家族や親戚がいない場合や、判断に迷われる場合には、まずは一度ご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで