
columns
弁護士コラム
遺産の使い込み(使途不明金)の返還請求と時効とは?調査・立証方法を解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年10月31日 |
最終更新日:2025年11月19日

- Q
-
先日父が亡くなり、遺産分割することにしました。
生前、父と同居する妹に口座の管理を任せていたのですが、父の認知症が進んだ時期から、妹が多額の出金を繰り返していたことが分かりました。総額で数千万円は引き出したかと思います。妹は「父の生活費や入院費に使った」と反論しますが、肝心の領収書は持っていません。
調査や証拠収集を開始し、最終的には訴訟を起こすつもりです。父の認知症が進んだ時期がかなり前なので、時効があるのか心配です。
また、過去の裁判例などから、裁判所がどのように判断すると考えられるのか教えてください。
- Answer
-
まず、当事者間で交渉することが考えられます。
しかし、妹さんと話し合っても私的な使い込みを認めず、返還に応じてもらえないようであれば、遺産分割手続の中で解決することも考えられます。
それも難しい場合には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求、委任契約若しくは準委任契約に基づく善管注意義務違反による損害賠償請求権または受取物引渡請求訴訟などを提起して、使われた遺産を取り戻していくことになります。
しかし、いずれの請求権にも時効が設けられているため、時効期間内に催告や裁判上の請求等をするようにしましょう。調査・証拠収集としては、金融機関から被相続人の口座の出金履歴などを取り寄せることができます。弁護士に依頼すればスムーズに情報収集が可能ですし、妹さんとの関係で有利となりやすいです。
この記事では、遺産の使い込みについて具体的な調査方法や有効な証拠、裁判での立証方法、消滅時効などについて解説します。
監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
遺産分割のタイミングで、生前に被相続人から聞いていたよりも口座残高が少ないことをきっかけとして、不自然な出金や使途不明金が発覚する場合があります。
このような場合、相続人による私的な使い込みが予想されます。使途不明金を放置すると公平な遺産分割ができず、相続人の不満が解消されないため、遺産分割が長期化しやすくなります。また、相続税や贈与税の問題を税務署から指摘される可能性があります。
本記事では、使い込まれた財産を取り戻す方法や、裁判に発展した際の基礎知識について解説していきます。

目次
遺産の使い込み(使途不明金)とは?
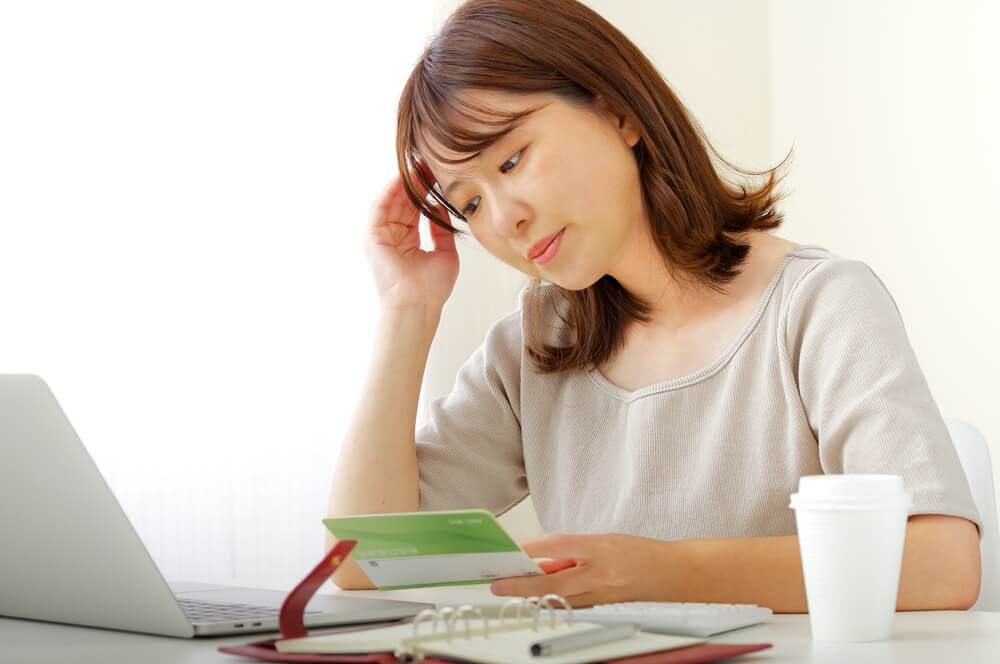
遺産の使い込み(使途不明金)とは、被相続人の生前または死後に、預金口座等から預金が引き出された痕跡があるものの、その使途や詳細が不明なままの金銭など、何に使われたのか不明なお金を指します。具体的には被相続人の預金口座から引き出されていても、目的や用途が分からないままのお金などです。
預金口座の残高が予想よりも減少していたような場合や、不自然な多額の引き出しが多いような場合で、その使い道に心あたりがない場合には、相続人による遺産の使い込みの可能性があります。
預貯金の無断引き出しなどの具体例
典型的な例として、被相続人と同居していた相続人が、被相続人の通帳やキャッシュカードを無断で持ち出して、預貯金を引き出し、個人的な生活費や遊興費に浪費していたケースが挙げられます。
また、介護をしていた相続人や親族が、その信頼関係を悪用し、管理されていた財産を流用するようなケースもあります。
被相続人が得ていた家賃収入・不動産・貴金属・株式の売却益・生命保険の解約金など、着服する財産は預貯金に限られません。
問題となる使い込みの3つの類型
使い込みのトラブルは、主に以下の3つの類型に分類されます。
- 被相続人の通帳などを無断で持ち出したケース(侵奪型関与)
- 被相続人に意思能力が欠如した状態で、有効な委任がなされないまま相続人等が引き出したケース(委託型関与その1)
- 有効に委任を受けたものの、受任者が引き出した金銭を委任の範囲を逸脱して個人的に使い込みをしたケース(委託型関与その2)
「侵奪型関与」は、被相続人の通帳やキャッシュカードを無断使用した引き出しです。
被相続人が入院を伴う病気や怪我などで財産を直接管理できない状況を悪用しており、悪質なケースといえます。
「委託型関与その1」は、被相続人の能力欠如を原因とした引き出しです。
認知症になると、被相続人本人は自身の発言や行為の意味を理解し、記憶するのが困難となります。法律ではそのような状態を「意思能力の欠如」と判断しています。意思能力が欠如した状態で財産管理を委任されたと主張しても、受託者には権限はないものとして扱われます。
「委託型関与その2」は、委託の範囲を逸脱した引き出しです。
被相続人が自身の預金口座など財産の管理を相続人に委託するケースがあります。
委任は正式に成立しているものの、被相続人としては生活費や医療費の支払いのために引き出してほしいところ、受託者が委託の目的・範囲・自身の権限を逸脱して、自己の利益のために財産を使い込むケースがあります。

実務では、使い込みの態様がどのケースに該当するかをできる限り正確に把握し、客観的な事実確認により解決を目指します。
使い込みの調査方法と返還請求に必要な証拠

遺産の使い込みが疑われる場合、使い込んだと思われる相続人に、いきなり直接問いただすのは得策ではありません。
最初から感情的に使い込みを疑ってかかると、本当に正当な支出だった場合に関係修復が困難となり、関係が断絶する恐れがあるため、証拠の収集などから慎重に進めていきましょう。直接的な証拠が得られない場合には、間接的な証拠・事実を積み重ねていくことが、立証の鍵となります。
調査では、以下の4点を目的としましょう。後に返還請求する場合に成否を分ける重要な点です。
- 1不自然な出金の有無を確認する
- 2出金した人物を特定する
- 3時期と金額を特定する
- 4使途を特定する
金融機関での取引履歴の取得
出金された事実を証明するためには、預貯金通帳の記帳内容を利用することができます。
もし預金通帳がない場合や、もっと昔の取引履歴を知りたい場合は、預貯金口座のある金融機関に出向き、取引明細書や引出履歴などを発行(開示)してもらうことが可能です。相続人の立場であれば、通帳を持っていなかったとしても依頼することが可能で、金融機関は拒否できないものとされています。
発行手数料が高額になる場合もありますが、最大で10年分の履歴を確認することも可能です。これにより不自然な引き出しや送金の存在を容易に明らかにできます。
認知能力が低下や長期入院などで本人が引き出しをしていたとは考えられない時期に引き出されたお金や、生活レベルに見合わない高額な支払いや振り込みがないか確認しましょう。このほか、払戻請求書等の筆跡や引き出したATMの時間や場所も、引き出した人物の特定に繋がります。
第三者による引き出し行為等の立証のための間接事実
直接的な証拠がなくても、間接的な証拠や事実から引き出し行為者を特定・立証することが可能です。
前述の通帳や取引歴のほかにも、被相続人と密接に関わっていた家族・介護者・友人の証言も時として証拠になり得ます。医療記録や介護記録に金銭の管理者として記載されている者があれば、引き出し行為者を特定するヒントがある可能性があります。
認知症の症状があった場合、認知症の症状の程度にもよりますが、被相続人が引き出しについて指示をすることや、引き出しの承諾をすることは困難な場合が多いです。有効な委任ができていなければ、引き出し者が権限なく引き出しをしたことが明らかとなります。
また、引き出しをした者が、通帳・印鑑・キャッシュカードを管理していた事実を証明できるようにしましょう。当該引き出しをした者が、当時、急に金回りがよくなったり、大きな買い物をしていた場合には、可能であれば当該引き出しをした者の預貯金口座を確認し、不自然な入金が被相続人の口座からの出金と、時期や金額が一致した場合には証拠となります。
使い込まれた遺産を取り戻すための法的手段と時効

預貯金の使い込みがあった場合、まずは当事者間での交渉による解決を目指し、次に遺産分割手続内での解決を検討しますが、これらが困難な場合は、調停・訴訟等による解決を図ります。
ただ、調停は最終的に当事者の合意がなければ成立しないため、対立が激しい場合に解決を見込むことが難しい手段です。そこで、実際に遺産を取り戻すための法的手段として、管轄の地方裁判所や簡易裁判所に訴訟を起こします。
使い込まれた遺産を取り戻すための法的構成としては、「不当利得返還請求」「不法行為に基づく損害賠償請求」「委託物引渡請求」が考えられます。これらのうちの一つ又は複数の請求を組み合わせて訴訟を提起します。勝訴すれば使い込んだ相続人に対して、裁判所が返還・賠償・引渡しを命令します。被告に支払能力があれば、使い込まれた遺産を取り戻すことができます。
しかし、いずれの請求についても消滅時効が設けられています。時効が完成している場合、時効を援用されると権利が消滅し、泣き寝入りせざるを得なくなります。時効完成までの期間は長いと思っても、相続関係のトラブルは数年単位の長期に渡るケースも少なくないため、使い込みに気づいたら、早期に対応しましょう。
返還請求の主な法的構成
被相続人の生前に預貯金を引き出された使途不明金の訴訟において請求する場合の法律構成は、主に次の3つがあります。
① 不当利得返還請求権(不当利得構成)
「不当利得返還請求」とは、委任や贈与などの法律上の正当な理由なく、他人の財産によって利益を得た者に対して、その利益の返還を求める請求です。
② 不法行為による損害賠償請求権(不法行為構成)
無断でした被相続人の財産(又は遺産)の使い込みや被相続人から委任を受けた権限を逸脱して遺産を取得する行為は、民法上の不法行為を構成します。
③ 委任契約条の受取物引渡請求権(受取物引渡構成)又は善管注意義務違反による損害賠償請求権(債務不履行構成)
被相続人から財産管理委任契約などで財産管理を委任されていたものの、委任範囲を逸脱した権限外の引き出し・使い込みがあった場合には、委任者が負うべき善管注意義務違反(善良な管理者としての注意義務を怠った)や金銭の引き渡しを求める(受取物引渡請求)ことができます。
いずれも、被相続人の生前に生じた使途不明金に関する訴訟であれば、被相続人が生前に有していた請求権(金銭債権)を相続開始によって各相続人が相続し、各相続人が行使できるようになったものです。この請求権は金銭債権であり、遺言で指定がない限り、法律上当然に相続分に従って分割されます。そのため、各相続人は自身の相続分の限度で請求ができますが、使い込んだ全額に対して請求できるわけではありません。
なお、相続開始後に相続人の一人が勝手に預貯金等を引き出して自己のために利用したような場合、引き出しをした相続人以外の相続人全員の同意があれば、当該使途不明金となった金銭を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(みなし遺産)。みなし遺産とされた場合、遺産分割協議の中で解決することが可能です。
各請求権の消滅時効
前述の①乃至③の請求権について、いずれも「権利行使ができることを知った時から」という主観的な時効が定められています。また、権利行使について知らなかった場合でも、出金が行われた時点や不法行為があった時点など「権利を行使し得る時を起算点とする」客観的な時効が定められています。
したがって、事案に応じてどの返還請求を選択するかで異なりますが、10年以上前の古い使い込みがあったとしても、損害または加害者を知らなかったような場合、不法行為構成をとった場合、時効は20年間完成しないため、請求できる可能性があります。
| 請求権の種類 | 消滅時効の期間 |
| 不当利得返還請求 | 権利を行使できることを知った時から5年間、かつ、権利を行使できる時(利益が相手方に帰属した時 [出金時など] )から10年間 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 損害及び加害者を知った時から3年間、かつ、不法行為の時(出金時など)から20年間 |
| 委任契約に基づく請求 | 権利を行使できることを知った時から5年間、かつ、権利を行使できる時(義務違反があった時または委任契約終了時 [被相続人の死亡時] )から10年間 |
遺産の使い込みを裁判で立証するためのポイント

使途不明金を巡る裁判(使途不明金返還請求訴訟)においては、いずれの請求においても主張・立証が最も重要です。
訴える側の原告が勝訴して請求を実現させるには、原告が被相続人の預貯金が出金された事実を主張し、証拠を用意し、事実を証明する責任(主張立証責任)を負います。被害を受けた上に証拠を揃えて立証しなければいけないことを理不尽に感じるかもしれませんが、訴える側が責任を負うのが裁判の基本となります。
原告側は、主に以下のような事実について証明していく必要があります。
- 被相続人が預貯金や口座を持っていたこと
- 被告が正当な理由なく引き出していること
- 場所・時間・金額などから被告による引き出しであること
- 損害の発生と、引き出し行為と損害との因果関係があること
一方で、被告側は、「贈与だった」「被相続人のために使った正当な支出だ」と主張して争うことが多いです。この場合、被告側がそれらの事実を主張し、証拠を提出して立証していかなくてはなりません。
家族・親族間での紛争においては、日々の支出についてまで細かく証明することが難しい場合が多いです。そのため、原告側は、通帳の出入金記録・医療記録や介護認定の調査票・引き出し口座の取引履歴などを元に、間接的に事実を立証していかなければならないこともあります。
裁判所は双方の主張と証拠を基に総合的に考慮し、合理性のある主張事実を認定し、判決を言い渡します。
請求する側と請求される側の立証責任
原告は、まず、被相続人の預貯金が引き出された事実について、金融機関の預貯金通帳又は取引履歴によって証明していきます。
また、被告によって預貯金が出金されたことについては、金融機関から払戻請求書の開示を受け、その筆跡により立証することや、ATMの防犯カメラの映像を入手することも考えられますが、このような証拠は入手が難しいことも多く、被相続人の身体状況や居場所、出金の場所や通帳等の管理状況などの間接的な事実を集めて立証活動を行うことになります。
被告側としては、当該出金は被相続人から生前に承諾や委任を受けてしたことや、贈与であること、引き出しはしたものの生活費や医療費などの被相続人に有益な正当な支出であったことなど具体的に主張・立証する必要があります。委任契約の公正証書や贈与税の申告書、医療費の明細、振込書などを用意し、委任や贈与を受けるだけの関係性や理由を証明する必要があります。
引き出した金銭を「いつ」「何に使ったか」を合理的かつ矛盾なく説明できない場合や、証拠を提示できない場合には、正当な理由による支出であったとしても、裁判所に「使途不明」と認定される可能性が高くなります。
引き出した側の典型的な反論パターン
使途不明金返還請求訴訟で、被告側から主張されることが多い反論には、以下の5つがあります。
■ 被告は関与していないパターン
自分は引き出し行為や財産の管理には一切関与していないという主張です。
このような場合、原告側としては、被告が被相続人の口座を管理していたことと、頻繁に被相続人を訪問するなどして管理しやすい状況にあったこと、被相続人が各引き出し時点において自己で管理できる状態になかったことなどを主張して証明していく必要があります。使途不明金について被告の関与が立証できなければ、原告側の請求が認められないことになります。
■ 被相続人を補佐したパターン
被相続人本人が引き出すのを手伝っただけという主張です。
被相続人本人の意思で預貯金を引き出し、被相続人の意思に従って利用したのであれば、被告が勝手に受領したわけではないことから、被告に返還請求することはできません。被告側は、被相続人から引き出しの補佐を依頼された経緯や理由、引き出しをする際の状況、引き出した金銭の流れなどの事実を主張・立証していきます。
原告側としては、被告側が主張する事実関係について反論していく必要があります。当時の被相続人の意思能力なども問題となることがあるため、その点の主張立証をしていくこともあります。
■ 被相続人に交付したパターン
被告自身が引き出したことは認めるものの、その全額を被相続人本人に渡したという主張です。
被告側としては、本人に渡した事実の主張・立証が必要です。
■ 被相続人から贈与されたパターン
引き出したお金は、被相続人から生前に贈与されたものとする主張です。
贈与税の税務申告を行っていたり、税理士に相談・依頼していれば、それらの資料を証拠とできます。しかし、贈与時点で、被相続人の認知症が悪化していると、贈与の意思が欠如していたと判断され、結果的に贈与があったと認められません。
■ 被相続人のために有用な用途で使用したパターン
引き出しをしたのは、被相続人のための費用等や相続人全体のための支出であるという主張です。
これらの他にも、実際には被相続人の預貯金ではないというパターン(名義預金等であり遺産ではないという主張)などがあります。
被相続人のための支出について裁判所の判断基準
では、被告が引き出し受領した金銭は被相続人のために使ったというような主張をした場合(被相続人のために有用な用途で使用したパターン)、どのような用途であれば被相続人のためであったと認められるのでしょうか。
ポイントとしては「被相続人本人の意思に基づいた、有益と判断できる支出であったか」です。
■ 医療費・介護費
被相続人の医療費や介護費の支払いに充てた場合、被相続人のための正当な支出と認められやすいです。領収書・医療明細書・病院や介護施設への振込書などによって、個別に立証する必要があります。
■ 生活費
日常的な金額・頻度・内容における出費についても領収書を保管することは珍しいですが、被相続人が自身で管理していた頃に引き出していた生活費と被告が管理するようになってから引き出す金額に不自然な差がなく、生活レベルに見合った相当な範囲内での金額や頻度であれば、被相続人の生活費を引き出した正当な支出であったと認定する場合が多いです。
また、総務省の家計調査等の統計資料から、被相続人の生活費を認定している方法もあります。夫婦は相互に婚姻費用分担義務を有するため、被相続人の預貯金といっても、配偶者の生活費としても使用することは当然許容されるべき範囲内と考えられています。
なお、被相続人へのお見舞いや介護のために使用した交通費などの実費について、相続人との関係性から、被相続人が負担することを黙示のうちに了承していた事実を立証できれば、引きだした金銭の受領が被相続人のためのものであったと認められることもあります。
次に、被相続人から贈与されたパターンでは、どのような主張や立証であれば贈与があったと認められるのでしょうか。
■ 贈与
贈与契約書や贈与税の申告書といった客観的証拠があれば、適正な支出と認定されます。しかし、証拠もなく遺言書や資産状況と矛盾するような多額の贈与であれば、安易に贈与があったものとは認められません。
証拠が提出できない場合には、贈与が認められるほどの事情や動機、被告と被相続人との関係、金額、贈与の時期、引き出しの頻度によって具体的に判断します。
遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット

遺産の使い込みが発覚したら、できる限り早めに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士ならでの能力や情報収集能力が、解決の鍵となります。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下の3点です。
- 証拠収集と調査のスピード感
- 相手方の典型的な反論への対応
- 裁判や調停を見据えた戦略的サポート
証拠収集と調査のスピード感
専門家である弁護士は、遺産使い込みのパターンに応じてどのような証拠収集をするべきかを把握しているため、迅速に証拠収集に取りかかることができます。
また、金融機関へ預金口座の取引履歴の発行を請求する場合に、どのような期間の履歴を取り寄せるべきかなどについて、経験に基づいて判断することができます。
なお、弁護士は「弁護士会照会」という制度を利用して情報収集を行うことができます。調査すべき金融機関等がわかっていれば相続人自身でも調査できる場合も多いのですが、預金口座がどの金融機関にあるのかわからないなど調査すべき範囲が広い場合など、弁護士会照会をすれば一定の範囲の金融機関から情報を収集することもできます。
しかし、使い込んだ相続人の口座の取引履歴などはプライバシーの関係で開示してもらえない等、限界がある点は注意が必要です。
相手方の典型的な反論への対応
基本的に使い込んだ相続人というのは非協力的であり、反論をしてくることが予想できます。
「生前贈与を受けていた」「借りていただけ」「被相続人のために使った」「亡くなって口座が凍結される前に引き出しただけ」などの様々な反論が予想できます。被相続人が亡くなっている以上、証明するのは困難です。
弁護士は交渉経験が豊富なため、冷静かつ客観的に対応することができます。そのため、相手方から有益な情報を引き出すなど、効果的な証拠収集活動が期待できます。
裁判や調停を見据えた戦略的サポート
最終的には調停や裁判によって解決を目指すこととなります。遺産の使い込みについて争いになっている場合、裁判で解決せざるを得ないケースが多く、遅かれ早かれ弁護士のサポートの必要性が高まります。
裁判に至るまでは用意するべき書類が多く、手続きも煩雑です。一般の方が調べて望んだとしても、状況に応じた対応が行えていないことがほとんどです。どんなに正当な真実であっても、しっかり主張・立証しなければ、事実と認められません。
相手方が弁護士に依頼している可能性も高いため、自身も早い段階で弁護士に相談し、面倒な手続きの代行や適切なサポート、アドバイスを受けることをおすすめします。
よくある質問(Q&A)

- Q
- 領収書など証拠がない場合でも請求できますか?
- Answer
-
領収書などの証拠を掴んで請求するのが理想ですが、なくても返還請求できる可能性があります。
使い込んだとみられる相続人の資産を調査し、預金通帳の取引履歴から大きな買い物や入金がなかったか、第三者の証言など、直接的でなくても間接的な証拠・事実が集まれば、交渉や裁判で有利に働きます。
- Q
- 兄弟が生活費に使ったと主張したら認められますか?
- Answer
-
兄弟が被相続人と同居しているような場合であれば、生活費に使ったという主張が認められるケースがあります。被相続人の利益のための支出は民法上の事務管理に該当し、正当な支出と認められる可能性があるためです。
生活費としての利用は領収書などが残っていない場合も多く、証明が難しいものですが、基本的には正当な支出と認められる傾向にあります。少額であれば、介護の労力をしてくれた兄弟へのせめてもの対価や謝礼として許容するのも円満解決には必要な考え方です。
- Q
- 遺産の使い込み返還請求には、どのくらいの費用や期間がかかりますか?
- Answer
-
事務所によって異なりますが、弁護士に依頼する場合、相談料・15~40万円程度の着手金・成功報酬として取り戻した金額(請求金額)に5%~20%を乗じた金額が費用としてかかるケースが多いです。また、%は取り戻した金額によって変動する場合が多いです。
なお、弁護士会照会を行うと1件あたり5,000円~1万円ほどかかるほか、訴訟期日には3~5万円の日当や郵送費などの実費がかかります。
相続関連では事情が複雑な案件が多いことから、事案の規模に応じて別途で見積もりという形を取る事務所やプラン別にしている事務所もありますが、使い込まれた金額が数千万円になる場合は、数百万円以上の費用がかかるでしょう。
期間については、初回相談から解決までに早くて数ヶ月、裁判になった場合には2~3年以上の年月がかかることもあります。
東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所
相続関係は親族間の感情的なトラブルを招きやすく、解決までに長い期間がかかる傾向にあります。特に遺産の使途不明金がある場合、親族間の争いが激しくなることが多いです。そのため、遺産の使い込みの疑いが出た時点で、迅速に弁護士などの専門家に相談し、調査や証拠収集を始めるようにしましょう。
ただ、何を証拠として収集すべきか、どのように証拠を収集するのかは、とても複雑で難しいものがあります。迅速かつ適確に請求を進めるためには、専門的な知識を有する経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
直法律事務所では、遺産の使い込みへの対応や相続関係について多くの経験を積んだ弁護士が親身にサポートいたします。遺産の使い込みに悩んでいる場合には、是非ご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで