
columns
弁護士コラム
「相続させる」遺言書と「遺贈する」遺言書の違いとは?効力は変わる?
- 家族信託・遺言書作成
- 投稿日:2025年03月07日 |
最終更新日:2025年04月12日
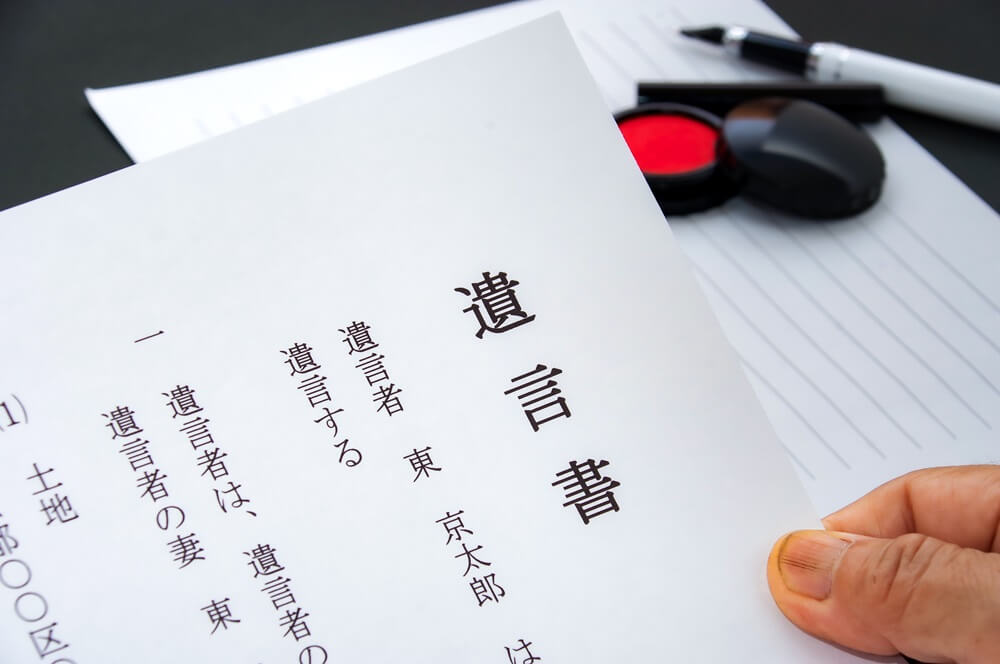
- Q
-
年齢を重ね、今後のことを考えて遺言書を作成しようと決心しました。事業用不動産は長男に譲り、他の子どもたちには預貯金や有価証券を分けたいと考えています。また、妻には老後の生活が安定するように配慮したいと思っています。
しかし、遺言書における「相続させる」と「遺贈する」の違いがよくわからず、どちらを使うべきか迷っています。それぞれの法的な違いや手続きへの影響について教えていただけますか?
- Answer
-
「相続させる」という文言は、相続人に対してのみ使うことができ、遺言者が亡くなった直後に遺産は相続人に相続されます。一方、「遺贈する」という文言は、財産の無償譲渡を意味し、相続人以外にも用いることができます。
しかし、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」には、法的効果の差異があります。例えば、借地権や借家権を「相続させる」旨の遺言によって承継させる場合には賃貸人の承諾は不要ですが、「遺贈」の場合には賃貸人の承諾が必要になります。また、代襲相続での取り扱いも厳密には異なります。
なお、登記申請については、「相続させる」旨の文言か「遺贈」かにかかわらず、相続人に対する所有権移転登記は相続人が単独で行うことができます。他方、相続人以外に対する遺贈の場合、登記申請は受遺者と相続人の共同申請で行わなければなりません。
この記事では「相続させる」と「遺贈する」の差異や、遺言作成時の注意点について、詳しく解説します。
この記事では、「相続させる」と「遺贈する」の法的な意味、および登記などの実務上の取り扱いの差異や、相続人および受遺者が遺言者より先に亡くなった場合の遺言の効力、遺言作成時の注意点について解説します。
これから遺言を書く方や、遺言の表現の法的な意味合いが分からず不安を抱えている方に最適な記事となっています。
目次
相続させる遺言と遺贈の基本的な違い

遺言書を作成する際、よく出てくる言葉に「相続させる」と「遺贈する」があります。これらの言葉はどちらも「特定の人に遺言者の財産を引き継がせる」という点で共通していますが、実は使い方や意味に大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの基本的な意味や使い方、そして法的な違いについて説明します。
相手による使い分け|相続人か非相続人か
「相続させる」という文言と「遺贈する」という文言の大きな違いは、財産を渡す相手が異なることです。
「相続させる」という表現は、相続人に対してのみ使うことができ、相続人以外には使うことができません。
一方、「遺贈する」という表現は相続人にも相続人以外にも使用することができます。
そのため、相続人でない友人や団体に対して「〇〇銀行の預金を相続させる」という表現を用いることはできません。一方、相続人にも「遺贈する」という表現は問題なく使用することができます。
法的性質の違い|遺産分割方法の指定と財産の無償譲渡
次に、「相続させる」と「遺贈する」の法的性質について説明します。
民法908条には、「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」とあり、「相続させる」という表現は、遺産分割の方法を指定する意味を持っています。
一方、「遺贈」については、民放964条には、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」とあり、法的には「遺贈」は財産の無償譲渡であるとみなされます。
このように、「相続させる」という文言は遺産分割の方法の指定、「遺贈する」は財産を無償譲渡することを示すという違いがあるのです。
しかし、従来、「相続させる」という表現の解釈は一つに定まっていませんでした。「相続させる」を遺産分割方法を指定する文言だと解釈すると、遺言に基づく遺産分割が必要になります。また、遺産分割をせず、直ちに財産の所有権が移転すると考える見方もありました。最高裁の平成3年4月19日判決によって、遺産分割方法の指定という見方に立ちながらも、遺言者の死亡により直ちに所有権転移の効果が生じるという判断が示されたため、「相続させる」と「遺贈する」は実務上おおむね同じ意味であるという結論になりました。
相続させる遺言と遺贈の効力の違い

「相続させる遺言」と「遺贈」では、効力が発生するタイミングやその後の手続きに違いがあります。
「相続させる遺言」の場合、特段の事情がない限り、被相続人の死亡時に直ちに遺産はその相続人に相続により継承されるとされています。
「遺贈」の場合も同様に、遺言者の死亡と同時に効力が発生しますが、遺言に停止条件が付されている場合、その条件が成就した時点で効力が発生します。
また、不動産登記、農地取得の許可、借地権・借家権の許可などで手続きの差異が生じます。この点について、以下で解説します。
不動産登記手続きにおける違い
「相続させる遺言」と「遺贈」では不動産登記手続きでの扱いが異なります。
「相続させる遺言」の場合、被相続人の死亡と同時に遺言書で指定された遺産はその相続人に相続により継承されるため、単独で所有権移転登記が可能です。
また、相続人に対する「遺贈」の場合、「相続させる遺言」の場合と同様、受遺者である相続人が、単独で遺贈登記の申請をすることができます(改正不登法63条第3項)。
一方、相続人以外の者に対する「遺贈」の場合、受遺者と法定相続人(遺言執行者が定められている場合は遺言執行者)との共同申請で所有権移転登記をする必要があります。そのため、法定相続人の協力が得られない場合、スムーズに登記ができないこともあります。
少し特殊なケースですが、遺言によって不動産を取得することになった者が所有権移転登記をする前に、他の法定相続人から法定相続分に相当する持分を譲り受けた第三者がその不動産について所有権移転登記をしてしまった場合の対応についても結論が異なります。
従来は、「相続させる」という表現を用いていた場合、所有権移転登記を行っていなくても第三者に対抗することができ、「相続させる」として相続した相続人は、当該不動産への第三者の所有権移転登記の抹消を求めることができました。
しかし、2019年に民法が改正され、相続分を超える部分の相続による権利の承継については、所有権移転登記などの対抗要件をそろえなければ第三者に対抗することができなくなりました(民法899条の2第1項)。そのため、「相続させる遺言」によって不動産を取得した相続人も、相続開始後、速やかに登記手続きを行わなければ、損害を被る可能性があり注意が必要です。
また、「遺贈」の場合、遺贈の登記をしなければ受遺者は第三者に所有権の取得を主張することはできないとされています。そのため、「遺贈」の場合も速やかに登記手続きを行う必要があります。
農地取得時の許可要件の違い
亡くなった方の農地を引き継ぐ場合、「相続させる」と「遺贈する」のどちらを用いても大きな差異はありません。それよりも「誰が引き継ぐか」によって手続きが変わります。
農地法3条には「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」とあり、農業委員会の許可が必要であると定められています。
しかし、相続人が相続や遺言で農地を取得する場合、農業委員会の許可は不要です。この際、「相続させる」と「遺贈する」のどちらの表現を用いても、引き継ぐ人が相続人であれば許可は不要となります。
一方、相続人以外の人が農地を引き継ぐ理由が、「包括遺贈」か「特定遺贈」かによって、農業委員会の許可が必要かどうかが決まっています。
「包括遺贈」とはすべての財産に対して割合を指定して財産を渡すことです。全財産全部を包括遺贈するケースや、全財産の一部を包括遺贈するケースもあります。一部包括遺贈の例としては、「全財産の3分の1をAに遺贈する」という遺言がある場合などです。このとき、農業委員会の許可は不要です。
「特定遺贈」とは特定の財産を指定して財産を渡すことです。例えば、「土地をAに遺贈する」という場合は特定遺贈に当たります。このとき、農業委員会の許可が必要になります。ただし、相続人へ特定遺贈を行う場合は、許可は不要です。
まとめると、農地の引継ぎでは「相続させる」と「遺贈する」に大きな違いはありません。
そして、引き継ぐ人が相続人である、または相続人ではないが包括遺贈で農地を引き継ぐ場合、農業委員会の許可は不要です。
引き継ぐ人が相続人でなく、特定遺贈で土地を引き継ぐ場合、農業委員会の許可が必要となります。
なお、許可が不要の場合でも届出は必要となりますので、注意が必要です。
借地権・借家権承継時の手続きの違い
借地権とは、建物所有を目的とした土地賃借権のことをいい、借家権とは賃料を払って建物を借りている借主の権利のことをいいます。
借地権や借家権の譲渡の場合、原則として地主ないし大家の承諾が必要です。
しかし、「相続させる遺言」の場合、被相続人の権利を包括的に承継するため、相続によって借地権および借家権を承継する際に、地主ないし大家(賃貸人)の承諾は不要です。
一方、「遺贈」の場合、賃貸人の承諾が必要です。借地権や借家権を遺贈する場合、この譲渡は売買や贈与などの一般的な取引に近いものとみなされ、原則通り地主・大家の承諾が必要となるのです。
なお、地上権を譲渡する場合は地上権設定者(地主)の許可は不要です。
相続させる遺言と遺贈の登記実務上の違い

「相続させる遺言」と「遺贈」では登記実務上の違いがあります。「相続させる遺言」では財産を引き継ぐ相続人単独で登記申請を行うことができるのに対し、相続人以外の者に対する「遺贈」の場合には遺言執行者と指定された相続人、または他の相続人全員との共同で登記申請を行う必要があります。
ここでは、これらの違いについて解説します。
単独申請か共同申請か
「相続させる遺言」の場合、前述のとおり、被相続人の死亡と同時に、遺言書で指定された遺産は相続により継承されるため、財産を引き継ぐ相続人が単独で登記申請を行うことができます。
相続人以外の者に対する「遺贈」について、遺言執行者が定められている場合、受遺者は、遺言執行者と共同で登記申請を行う必要があります。また、遺言執行者が定められていない場合は、受遺者は、他の相続人全員との共同申請を行う必要があります。
なお、遺言執行者は民法1012条に規定されており、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とされています。
他方、相続人に対する「遺贈」の場合、「相続させる遺言」の場合と同様、受遺者である相続人が、単独で遺贈登記の申請をすることができます(改正不登法63条第3項)。従前、相続人が受遺者であっても共同申請が必要でしたが、令和5年4月1日に改正不動産登記法が施行されたため単独申請が可能になりました。
なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)も、単独で所有権移転の登記申請が可能となりました。
登録免許税の違い
「相続させる遺言」と「遺贈」の二つの場合について、平成15年以前の登録免許税は異なっていました。「相続させる遺言」の場合は1,000分の6、「遺贈」の場合は、登録免許税は不動産の評価額の1,000分の25となっていました。
平成15年以降、相続による登記と相続人に対する遺贈による登記については、両者の登録免許税は統一され、現行の登録免許税は1,000分の4になっています。また、相続人以外への遺贈による所有権移転登記は1,000分の20となっています。
代襲相続における遺言の効力

代襲相続とは、相続人となるはずであった人が相続開始前の死亡や欠格事由に該当することや廃除によって相続権を失った場合に、その子などが相続財産を相続する制度です。被相続人の子に代襲相続の原因が発生した場合の代襲相続人は孫となり、孫にも代襲相続の原因があるときにはひ孫など順次下の世代が相続します。一方、相続人の兄弟姉妹の代襲相続は子のみに限られ、孫やひ孫などは含まれません。
遺言によって遺産を引き継ぐはずであった人が、遺産を引き継ぐ前に死亡した場合、遺産をどのように引き継ぐかについては長い間見解が分かれていました。「遺贈」については、受益者の死亡によってその効力を失うことが民法に明記されていますが、「相続させる」旨の遺言では、明文の規定が存在せず、この場合の対応については裁判所で争われてきました。
最高裁平成3年4月19日判決は、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続させるために遺産分割の方法を指定したものであると解釈しており、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」は異なるものと判断されました。また、最高裁は平成23年2月22日判決において、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である旨を判示し、代襲相続における遺言の効力について統一した見解が示されました。
ここでは、代襲相続における遺言の効力について解説します。
相続人が先に死亡した場合の違い
「相続させる」旨の遺言について、「特段の事情」がない限り特定の遺産を相続させようとした相続人が遺言者より先に死亡した場合、先に死亡した者の子に代襲相続は生じず(最判平成23年2月2日・民集第65巻2号699頁)、遺言のうち先に死亡した者へ相続する旨の部分が無効となります(東京地判令和3年11月25日・判時2521号84頁)。
他方、「遺贈」については、民法に明文の規定があります。民法994条によると、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」とあるので、受遺者が死亡した時点で代襲相続は発生しません。
また、受遺者が引き継ぐはずであった遺産について、民法995条では「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」とあり、原則として相続人に帰属することになっています。
特段の事情による例外
「相続させる」旨の遺言では、原則的に代襲相続は発生しません。しかし、「特段の事情」がある場合には代襲相続が認められることが、最高裁判所平成23年年2月22日判決で示されました。
ここでいう「特段の事情」は、「当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき事情」と説明されています。例えば、「〇〇銀行の預金をAに相続させる。ただし、Aが亡くなった場合には、Aの息子にさせる」などと、他の人へ相続させる意思が明示されていることが必要となります。
そのため、遺言に他の者に相続させる意思が表明されていない場合に代襲相続が発生すると、遺言書の当該部分は効力を失い、それぞれの相続人がそれぞれの相続分に応じて相続することになります。
遺言書作成時の実務上の注意点

ここまで、遺言における「相続させる」と「遺贈する」の表現の持つ法的な意味合いと、手続きの違いについて説明しました。この二つの文言に代表されるように、遺言では文言の選択が大きな意味を持つため、文言選択に注意することが必要です。
また、遺言書が遺言書として認められるためには、必要な条件があります。まず、遺言書は自筆で作成される必要があります。加えて、遺言のほかに日付、遺言者の氏名が記入されたうえで押印されている必要があります。このように、遺言書として認められるには形式を守る必要があります。
以下では、この留意事項に加え、正確に遺言の意図が伝わるために遺言書作成における注意点を解説します。
相続人への財産移転における推奨される表現方法
相続人に対して「相続させる」文言を使用する際には、相続人と相続財産を正確に記載することが必要です。例えば、土地を相続させる際には、「〇〇市の土地」というあいまいな表現ではなく、住所や地番まで正確に記載するとよいでしょう。解釈の余地が生まれないように、財産や相続人がはっきりと伝わる方法で指定する必要があります。
なお、「相続させる」文言でも「遺贈する」文言であっても、財産を受けるのが相続人の場合には単独で登記申請が可能です。
また、登録免許税についても相続または遺贈を受けるのが相続人の場合、差異がありません。課税関係でも相続人に対する場合、「相続させる」と「遺贈する」の間に差異はありません。
ただし、遺産が借地権または賃借権の場合、遺贈であれば賃貸人の承諾が必要となるため、相続人に対しては「相続させる」という表現が推奨されます。
非相続人への財産移転における推奨される表現方法
相続人ではない者に財産を引き継がせたい場合には、「遺贈する」という文言を使います。この際も同様に、相続人と相続財産を正確に述べることが必要です。
また、前述の通り相続人ではない者には「遺贈する」という表現しか用いることができず、「相続させる」という表現は用いることができません。誤って相続人ではない者に「相続させる」を用いた場合、被相続人の意思をどのように解釈するかが問題となります。遺贈として有効となることも多いと考えられますが、遺言の当該部分は無効となる恐れもあり、注意が必要です。
正確に遺言の内容を伝えるためには、二つの文言を使い分けることが必要です。
予備的条項の活用方法
予備的条項とは、遺言書を作成した後に一定の事由が発生する場合に備えて、当該事由が発生した場合には、別の効果を発生させる旨の条項を言います。
遺言書はいつでも撤回や書き直しが可能ですが、遺言者が遺言を書いてから認知症などにより遺言能力を喪失することや、遺言者が事情の変化に気づかないなどして、遺言の内容を変更することができず、遺言と自身の意図に差異が生じることが起こりえます。そのような場合に備え、予備的条項を遺言書に記載しておくことができます。
前述のとおり、遺言者の死亡の前に「相続させる」旨の遺言により遺産を受けるべき相続人が死亡した場合には、当該相続人に関する遺言部分は無効となります。これに備えて、別の人を新たな遺産を受けるべき者として指定することも可能です。具体的には、「〇〇銀行の預金をAに相続させる。ただし、遺言者の死亡以前、または遺言者と同時に死亡したときは、〇〇銀行の預金をAの長男Bに相続させる」と記載すればよいでしょう。このように記載することで、Aに関する遺言部分は無効とならず、Aの長男Bへ遺産を相続させることが可能となります。
よくある質問

ここでは、遺言に関してよくある質問にお答えします。
「相続させる」旨の遺言と代襲相続で注意することは?
「相続させる」旨の遺言で指定された相続人が遺言者より先に亡くなった場合、「特段の事情」がない限り、基本的に代襲相続は認められません。代襲相続が認められる「特段の事情」とは、先死した者の代襲者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき事情のことです。
どのようなケースが「特段の事情」に該当するのか、今後の判例の集積を待つほかありませんが、遺言者としては、相続人が先に亡くなってしまった場合も想定して遺言書を作成する必要があります。代襲者による相続を望む場合には、前述のような予備的条項を入れるようにしましょう。
なお、最高裁平成23年2月22日判決より前の東京高裁平成18年6月29日判決は、「相続させる」旨の遺言によって遺産を受けるべき相続人の死亡後、被相続人が代襲者も含めた遺産分割方法を指定した遺言を作成しようとしていたなどの事情を考慮して代襲相続を認めており、このようなケースが「特段の事情」に該当しうる可能性があります。
受遺者が先に死亡した場合はどうする?
「遺贈する」という表現を用いた場合、受遺者が遺言者より先に死亡すると遺言の当該部分は失効します。このことは民法994条に明記されており、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」とあります。
無効となった受遺者が受け取るべき遺産は民法995条に「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。」とあり、原則として相続人に帰属します。しかし、同条但し書きにおいて、「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」とあり、遺言書の別段の意思の有無や内容を検討する必要があります。
例えば、全遺産から遺贈または相続させるとした財産を「控除した残金及びその他一切の財産を配偶者に相続させる」などの文言がある場合、この文言は遺言者の別段の意思と解釈することができ、遺言者より先に亡くなった受遺者が受けるべき財産は配偶者に分配されます。
遺言を作成する際は、受遺者が遺言者より先に亡くなるリスクを考慮することが必要です。受遺者が先に亡くなった場合のための予備的条項を記載したり、包括的条項を加えて先死した受遺者が受け取るべき財産について言及しておくとよいでしょう。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
遺言書における「相続させる」と「遺贈する」の違いは、法的な取り扱いや実務上の手続きに影響を与える重要なポイントです。これらの表現を正しく理解し、適切に使い分けることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
しかし、遺産相続には複雑な法律や手続きが絡み、専門知識が必要です。また、遺言書の表現や効力の違いによっては、思わぬトラブルを招く可能性もあります。そのため、遺産相続や遺言書の作成に関して不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
東京都千代田区にある直法律事務所では、相続問題に精通した弁護士が丁寧に対応します。ぜひ一度ご相談ください。
家族信託・遺言書作成についてお悩みの方へ
相続においては、「自分が亡くなったあと、どうしたらよいのか」とお悩みの方も多くいらっしゃると思います。当サービスでは、家族信託・遺言書の作成に関しても、ご依頼者様のニーズに沿った、適切な対策・アドバイス・サポートをプロの弁護士がおこないます。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで