
columns
弁護士コラム
使途不明金の調査方法とは?証拠収集から弁護士会照会まで解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年11月05日 |
最終更新日:2025年11月13日

- Q
-
先日、母が亡くなり、財産管理をしていた姉に預金額を開示してもらいました。すると、亡母の預金額が想定より遥かに少ないことがわかりました。そこで、銀行から取引履歴を取り寄せたところ、母が認知症で入院していた期間に、連日、ATMから限度額まで現金が引き出されていたことが判明しました。姉に問いただしても、自分は知らないと言い続けています。
姉による使い込みの事実を証明する方法はありますか。「弁護士会照会」や、裁判になった場合の「調査嘱託」という手段があると聞いたことがあるのですが、どのような場合に利用でき、また、何ができるのでしょうか。
- Answer
-
姉が被相続人の口座から金銭を引き出していたことを突き止める直接の証拠がない場合でも、当時、姉が被相続人の通帳やキャッシュカードなどを管理していたなどの事実や、姉以外に引き出しをできた者がいない事実を立証できるような資料があれば、姉が被相続人の口座から金銭を引き出していた有力な証拠となります。
また、弁護士に依頼することで、弁護士法に基づく弁護士会照会を利用して、払戻しをした人物に関する情報を金融機関に照会することも可能です。過去にはATMの防犯カメラの映像の記録を取得したケースもあります。
さらに、訴訟手続きの中で裁判所を通じて調査嘱託をすることも考えられます。これらの手続きにより、ATMの防犯カメラの映像の記録を取得できれば、誰が被相続人の口座から引き出したのか明らかになります。
また、窓口での払戻しをしたような場合は、払戻請求書の開示を受け、署名や手続きの詳細などを確認し、不正な使い込みを立証できる可能性もあります。
この記事では、遺産の預金が想定より少ないとお悩みの方や、家族による使い込みの証拠収集方法でお困りの方が、自身の権利を回復するために必要な使途不明金の調査手続きについて、証拠の集め方から弁護士会照会や調査嘱託といった専門的な法的手法まで、分かりやすく解説します。
監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
使途不明金の問題をそのままにしておくと、決定的な証拠が時間とともに失われるリスクがあります。
この記事では、遺産の不正流用を疑う方が、リスクを回避しつつ、証拠を合法的に収集するための具体的かつ段階的な法的手順について解説しています。最後までお読みいただくことで、調査開始から最終手段までを理解し、公平な分配を実現するための知識が得られるでしょう。

目次
なぜ相続で使途不明金の調査が必要なのか?

相続における使途不明金とは、被相続人の預金口座から引き出されたものの、何に使われたのか不明確な金銭のことです。使途不明金は、相続人間の深刻なトラブルの原因につながります。遺産分割において、特定の相続人が遺産を使い込んでしまい、その結果、遺産が思ったほど残っていないというケースは少なくありません。
例えば、ATMからの出金は、キャッシュカードと暗証番号さえ知っていれば、同居の相続人などが書面を作成することなく預金を引き出すことができるため、使途不明金トラブルに発展する典型例といえます。
「誰が」「いつ」「何のために」お金を引き出したかが不明確なままだと、遺産分割協議が進まないだけでなく、「相談なしに勝手に使い込んだ」「裏切られた」という感情的な対立により、相続人間の信頼関係が崩壊するリスクがあります。
使途不明金の返還を求めるには、単なる憶測で他の相続人を追及するのではなく、出金記録・使途の合理性の欠如といった客観的な証拠に基づいて、誰が不正に引き出したかを立証する必要があります。相続で使途不明金の調査が必要なのは、この法的な立証作業を通じて、不明な金銭を遺産総額へ回復させ、全ての相続人に対する公平な分配を実現するためです。
なお、使い込んだ相続人に対しては、不当利得返還請求または不法行為による損害賠償請求等を行うことができます。
使途不明金の放置が招くリスク

使途不明金の調査を先延ばしにすることは、法的な権利を失うという深刻なリスクを招く可能性があります。
まず、使途不明金の返還請求権には消滅時効が存在するため、調査を先延ばしにすると、たとえ後から使い込みの事実が判明しても、法的に返還を求める権利を失ってしまう可能性があります。「権利を行使できることを知ったときから5年」で時効が完成してしまう請求権もあり、相手が時効を援用した場合には請求することができなくなってしまうのです。
また、時間が経過するほど、金融機関の資料保管期間が過ぎてしまい、重要な証拠が失われるリスクがあります。
例えば、先に紹介したATM出金の事例では、防犯カメラの映像は1ヶ月〜数ヶ月程度で上書きされてしまうのが一般的です。この場合、いざ調べたいと思った時には該当日の映像が残っておらず、誰が出金を行ったかの立証が極めて困難になるでしょう。
さらに、証拠がないまま他の相続人を追及すると、感情的な対立が深まり、遺産分割協議が頓挫するだけでなく、本来円満に解決できたはずの遺産分割全体が「争続」に発展してしまう危険性があります。
冷静かつ客観的な証拠に基づく調査こそが、紛争の長期化を防ぐことにつながります。
使途不明金調査の第一歩|金融機関での資料収集

使途不明金の調査は、憶測ではなく客観的な証拠に基づいて立証しなければなりません。具体的には、取引履歴(入出金明細)や残高証明書の取得が有効です。
ここでは、これらの書類の取得方法について解説します。
取引履歴(入出金明細)の取得
使途不明金の特定は、相続人が金融機関の窓口で、被相続人名義の口座の取引履歴(入出金明細)を取得することから始まります。通帳を管理している相続人が開示を拒否した場合、この手続きが重要となります。
この手続きを行う際、相続人は自身が相続人であることを証明するために、戸籍謄本や法定相続情報一覧図などの書類を提出する必要があります。金融機関は少なくとも過去10年分の取引履歴を保管していることが多いため、これを取得することで、長期間にわたる不審な出金がないかを確認できます。
そして取得した取引履歴から、主に以下のような不審な点がないかを確認します。
- 時期:被相続人の入院期間中や認知症発症後など、本人が動けないはずの時期の高額な出金がないか
- 金額:生活実態に見合わない高額・頻繁な出金がないか
- 振込先:取引履歴に振込先が明記されている場合、その振込先が特定の相続人名になっていないか
もし取引履歴に特定の相続人への振込が確認された場合、その金銭が不当な使い込みではないと主張するためには、金銭を受け取った相続人側が立証責任を負います。具体的には、「被相続人に直接渡した」「被相続人の同意に基づいて振り込んだ」「被相続人のために使った」といった内容を、客観的な証拠に基づいて証明しなければなりません。
残高証明書の取得
使途不明金の調査では、取引履歴の確認と合わせて、被相続人死亡時など特定の時点での預金残高を正確に証明するために、残高証明書の取得が有効です。
共同相続人は被相続人の預金残高に法的な利害関係を有するため、金融機関は相続人からの残高証明書の発行請求に通常応じることが一般的です。これは、共同相続人が自身の法定相続分に応じた権利を預金債権について有することが判例(最判平成31年3月18日)によって示され、残高証明書の発行についてもその法的な根拠が裏付けられたためです。
残高証明書の請求手続きは通常、取引履歴と同様に、戸籍謄本や除籍謄本、または法定相続情報一覧図などで相続人であることを証明した上で、金融機関の窓口で行います。
金融機関が任意開示に応じない場合の調査方法

取引履歴は相続人であれば取得することが可能ですが、引き出した者を確認するために払戻請求書やATMの防犯カメラ映像の記録を取り寄せようとしても、金融機関はプライバシー等を理由に開示を拒否することが多いです。
そこで、弁護士会照会や訴訟手続き内の文書開示請求といった手段を用いて証拠を収集する方法を解説します。
弁護士会照会の活用
弁護士会照会は、弁護士が依頼を受けた事件について所属する弁護士会を通じて公的機関や民間企業などに情報開示を求める制度です(弁護士法23条の2)。
弁護士会照会を受けた者は原則として回答義務があります。ただ、弁護士しか利用できず、しかも事件を受任することが前提として必要です。なお、弁護士には守秘義務があるので、回答を受けた情報は適切に管理されます。
この制度を活用することで、相続人個人からの請求では開示されなかった払戻請求書やATMの防犯カメラ映像の記録などについても、金融機関が開示に応じる可能性が高まります。
ただし、弁護士会照会には、回答に応じなくても罰則などの定めがないため、金融機関が必ずしも開示に応じるとは限りません。
訴訟手続き内での文書開示請求
相続人個人による開示請求や弁護士会照会でも重要な証拠の開示が得られない場合、使途不明金に関する返還請求訴訟を提起し、その裁判手続きの中で証拠開示を求める方法を検討することになります。
訴訟を通じて裁判所という公的な権限を背景に証拠開示を促す手続きには、以下の2つがあります。これらは、裁判において「誰が、いつ、いくら払い戻したか」という事実を認定するための重要な手段となります。
- 文書送付嘱託(民事訴訟法226条)
裁判所を通じ、当事者が所持しない文書を第三者である文書の所持者から裁判所への送付を嘱託する手続きです。 使途不明金があったような場合、裁判所を通じて金融機関に対し、払戻請求書・預金口座開設時の資料などの提出を求めることができます。
ただし、文書の所持者(金融機関)が必ずしも応じるとは限りません。文書の所持者が提出義務を負っているのに提出しない場合には、文書の提出命令(民事訴訟法223条)が発せられることもあります。
- 調査嘱託(民事訴訟法186条)
事実あるいは経験則について、特別な人的・物的設備があり、専門的知識・経験がある団体に調査を求め、その結果を報告させる手続きです。裁判所が金融機関などの団体に対し、特定の事項について調査し報告を求めるという強力なものです。
これは、使途不明金による訴訟で事実の認定が難しい場合に特に有効です。
裁判手続きにおける最終手段「調査嘱託」とは

使途不明金による訴訟において、当事者の主張だけでは「誰が、いつ、どこで払い戻したか」といった事実認定が困難な場合、裁判所を通じて行う調査嘱託という手段を取ることになります。
調査嘱託とは、民事訴訟法第186条に基づき、裁判所が必要な調査を金融機関などの団体に依頼する強力な手続きです。この手続きを通じて客観的な事実を明らかにすることで、訴訟を有利に進めることが可能になります。
以下に、調査嘱託が特に有効となる代表的なケースと、具体的な申立て事項を解説します。
ケース1:無断払戻しが争われる場合
相続人の一人が被相続人の預金を無断で払い戻したかどうかが争点となる訴訟で、調査嘱託が活用されます。
このケースで裁判所が金融機関に調査を嘱託する具体的な事項の例は、以下の通りです。
- 窓口での払戻しの場合
各払戻手続きの際に窓口に来た人物は誰か、本人確認はどのような方法で行われたか、金融機関が提出を受けた払戻請求書等の書類一式の写しの提出
- ATMでの払戻しの場合
払い戻されたATMの場所・日時・金額、および防犯カメラ映像の有無とその写しの提出
ケース2:無断での口座解約が争われる場合
被相続人の預金口座が意思に反して無断で解約された疑いがある場合に、解約手続きの正当性を調査嘱託で解明できます。
このケースで裁判所が金融機関に調査を嘱託する具体的な事項の例は、以下の通りです。
- 解約手続きの経緯
解約手続きの際に窓口に来た人物は誰か、本人の意思確認はどのような方法で行われたか
- 手続きの証拠
金融機関が提出を受けた解約に関する書類一式の写しの提出
ケース3:キャッシュカードの不正作成・利用が争われる場合
被相続人が知らないうちにキャッシュカードが作成され、それを使って不正に預金が引き出されたと疑われる場合に、カードの不正作成・発行の経緯を明らかにするために調査嘱託が有効です。
このケースで裁判所が金融機関に調査を嘱託する具体的な事項の例は以下の通りです。
- カード作成・発行の経緯
キャッシュカードの作成申込日はいつか、キャッシュカードは誰に、いつ発行されたか
- 手続きの証拠
キャッシュカードの申込みから発行までの手続きの詳細、金融機関が提出を受けた申込・発行・受領に関する書類一式の写しの提出
調査費用・弁護士費用の目安

使途不明金の調査と返還請求には弁護士への依頼が必要となり、費用が発生します。これらの費用は、弁護士事務所・事案の複雑性・請求額によって大きく異なります。
調査費用などの相場については以下の通りです。ただし、あくまでも目安なので、詳細は弁護士事務所にお問い合わせください。
- 弁護士会照会費用:地域の弁護士会によって異なりますが8,000円~1万円程度
- 戸籍謄本等の取得費用:数百円~数千円
(複数金融機関で取引をしている場合は、複数必要になる場合もある。ただし、原本を返却してもらえるケースもある。)
- 取引履歴取得費用:数千円から数万円
(金融機関や取得期間によって異なる。複数の金融機関に請求する場合はさらに費用がかかる。)
- 使途不明金調査費用:相続財産調査全般を調査する場合は10~30万円程度なので、これより低額になる可能性もある。
弁護士費用は、主に依頼時に支払う着手金と、使途不明金を回収できた場合に支払う報酬金(成功報酬)の2つです。
着手金は、相手方に請求する金額の4~5%(税別)、あるいは定額でかかる場合があります。
報酬金は、返還請求をする経済的利益の金額や事案の煩雑さによって大きく異なり、相手から支払を受けた金額の4~30%(税別)というケースや、一定額又は相手から取得した金額の○○%のいずれか多い金額というケースが多いです。
弁護士に依頼する際は、複数の事務所から見積りを取得し、回収見込み額と発生する費用の総額を比較し、費用対効果を事前に検討することが重要です。
よくある質問(Q&A)

使途不明金の調査にかかるよくある質問と、その回答をまとめました。
- Q
- どのくらい前までの取引を調べられますか?
- Answer
-
金融機関は、通常、過去10年分の取引履歴を保管していることが多いため、基本的には10年前までの取引を調べることが可能です。
ただし、それ以前の取引については、金融機関によって保管期間が異なるため、直接確認が必要です。
- Q
- 家族が払戻請求書を隠している場合どうすればよいですか?
- Answer
-
家族が払戻請求書の控えを隠している場合、金融機関に開示請求することが考えられます。相続人からの開示請求であれば、合理的理由があれば開示に応じてくれることも多いのですが、金融機関によっては応じてくれないこともあります。
この場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会制度を利用するか、訴訟を提起した上で文書送付嘱託や調査嘱託といった裁判所を通じた手続きにより、金融機関から直接書類の開示を求めることが有効な手段となります。
- Q
- 弁護士会照会はどのくらいの期間で結果が出ますか?
- Answer
-
弁護士会照会は、照会先(金融機関など)の回答期間や弁護士会の手続きによって異なりますが、一般的に照会手続き開始から1ヶ月を目安とすると良いでしょう。
ただし、照会先に罰則などの強制力がないため、回答が遅れる場合や、情報の一部しか開示されない場合もあります。
東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所
使途不明金の調査は、時効による権利喪失や証拠の消失というリスクを避けるために迅速な対応が求められます。しかし、例えば不正に引き出したかを立証するために金融機関に提出された払戻請求書の開示を求めても、開示してもらえず、弁護士会照会や調査嘱託といった手続きで収集せざるを得ない場合もあるでしょう。
使途不明金の問題は、証拠収集が困難であるため、解決までの道のりがスムーズに進まず、また、紛争の長期化により、さらなる精神的・時間的コストがかかるというリスクも伴います。
そのため、ご自身の権利を守り、複雑な手続きを円滑に進めるためには、弁護士などの専門家に相談する方法が有効です。
直法律事務所では、遺産分割・預金の使い込み調査の実績が多数あり、調査嘱託・弁護士会照会を用いた証拠収集の経験も豊富です。証拠収集から、返還請求の交渉、調停・訴訟申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス
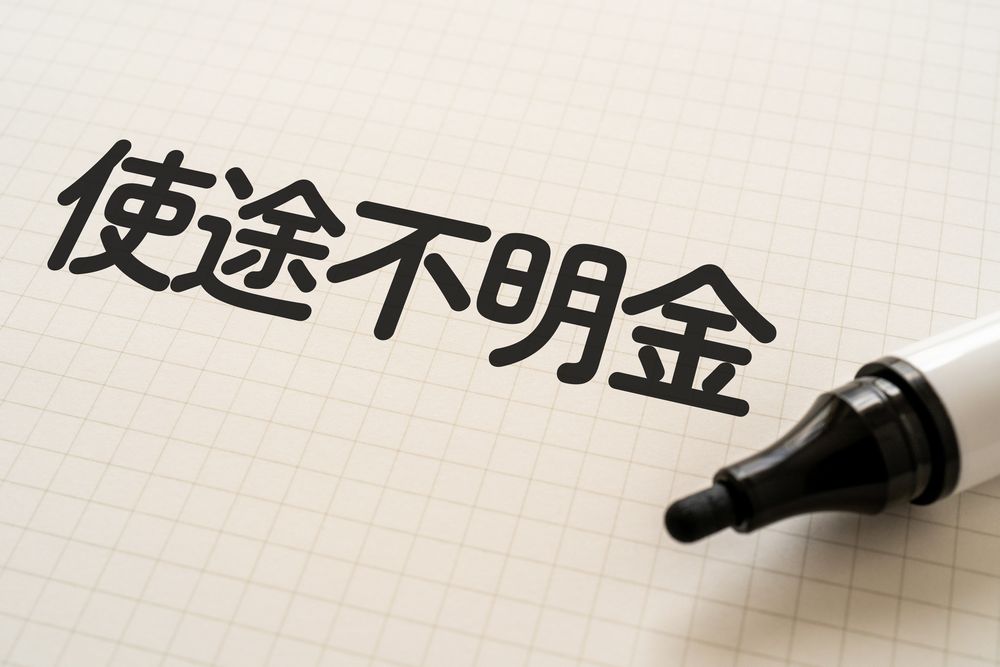




 メールで
メールで