
columns
弁護士コラム
相続財産調査はどうやる?不動産・預貯金・借金の調査方法と専門家に相談すべきタイミングを解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年10月03日 |
最終更新日:2025年10月03日

- Q
-
親が亡くなったけれど、どんな財産を持っていたのか全く分かりません。
どのように調べたらいいのでしょうか?
- Answer
-
相続財産には、不動産や預貯金といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金やローンといった消極財産(マイナスの財産)も含まれます。まずは登記簿謄本や預金通帳、郵便物などから手がかりを集めましょう。
相続財産調査は「相続を円滑に進めるための第一歩」です。
本記事では、相続財産の全体像から具体的な調査方法(不動産・預貯金・動産・有価証券・生命保険・借金の確認方法)までを解説し、専門家に相談すべきタイミングも紹介します。
目次
はじめに
相続財産調査がなぜ重要なのか
親や配偶者が亡くなり相続が開始すると、まず直面するのが「被相続人にどのような財産があるのか分からない」という問題です。
相続財産には、預貯金や不動産といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金やローンといった消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
つまり、財産調査は「どんな財産を受け継ぐか」だけでなく、「どんな負債まで背負うことになるのか」を把握するために欠かせません。特に近年では、ネット銀行や仮想通貨(暗号資産)といった、通帳や紙の書類からは発見しづらい財産も増えており、従来以上に調査の必要性が高まっています。
相続人が財産の全体像を正確に把握することで、以下のようなメリットが得られます。
- 相続放棄や限定承認の判断が適切にできる
- 相続税申告の漏れを防げる
- 相続人間の不公平を防ぎ、紛争を回避できる
財産調査を怠った場合に起こり得るトラブル
財産調査を怠ると、以下のような深刻なトラブルにつながる可能性があります。
- 隠れた不動産の発覚
相続登記を進めてから新たな土地や建物が見つかるケースがあります。その結果、遺産分割協議をやり直す必要が生じ、相続人間での対立が激化することもあります。
- 借金・ローンの発覚
相続人は、原則として被相続人の負債も相続します。相続開始後に多額の借金やクレジット債務が判明すると、返済義務を負うことになり、生活に大きな負担を与えかねません。
- 相続税申告漏れによるペナルティ
財産の一部を見落として申告した場合、加算税や延滞税といった税務上のペナルティが課されるリスクがあります。
- 相続人間の紛争
財産の全体像が不明確なまま遺産分割を進めると、「後から出てきた財産はどう分けるのか」といった争いに発展する恐れがあります。
このように、相続財産調査は「調べなくても大丈夫」ではなく、「最初にきちんと調べることでトラブルを未然に防ぐ」ために必須のステップです。
相続財産の全体像の把握
積極財産と消極財産
相続財産は大きく「積極財産」と「消極財産」に分けられます。積極財産と消極財産の両方を把握しなければ、正しい相続判断(単純承認・相続放棄・限定承認)ができません。
■ 積極財産(プラスの財産)
相続によって受け継ぐことができる利益になる財産です。代表的なものとして、以下が挙げられます。
- 不動産(土地・建物)
- 動産(現金・貴金属・自動車など)
- 預貯金や証券などの債権
- 有価証券(株式・社債・投資信託)
- ゴルフ会員権などの権利
- 知的財産権(特許・商標など)
- 仮想通貨(暗号資産)、ネット銀行口座
- 生命保険の死亡保険金請求権(特別受益に含まれる場合もある)
■ 消極財産(マイナスの財産)
相続人が背負うことになる負債や義務です。主なものは以下の通りです。
- 銀行など金融機関からの借入金
- クレジットカード債務
- 消費者金融からの借入
- 不動産に設定された担保(抵当権など)
- 被相続人宛ての督促状などで判明する債務
財産調査の基本的な流れ
相続財産調査は、以下の流れに沿って行うのが一般的です。
① 被相続人の保管資料や郵便物を確認する
預金通帳、固定資産税通知書、証券会社からの郵便、督促状などから財産・負債の手がかりを得る。
② 不動産の調査
法務局で登記簿謄本や公図を取得、名寄帳を確認。固定資産税納付通知書もチェック。
③ 金融資産・債務の調査
預貯金口座、証券口座、貸金庫の有無を確認。借入が疑われる場合は全国銀行協会や信用情報機関(CIC・JICC)へ開示請求。
④ その他の財産・負債の調査
知的財産権は特許情報プラットフォームで検索。仮想通貨やネット銀行口座はPC・スマホから確認。自営業者なら確定申告書や税理士への照会も有効。
⑤ 財産の全体像を整理し一覧化する
「財産目録」を作成し、積極財産と消極財産を区分してまとめることで、相続放棄や限定承認の判断に役立つ。

✅ 郵便物や書類は小さなものでも手がかりになるため、廃棄せずに保管する。
✅ ネット銀行・仮想通貨などは紙の通帳がないため見落としやすい。
✅ 不動産は市区町村ごとに名寄帳が分かれるため、複数自治体に照会が必要なことがある。
✅ 借金は登記簿の乙区や督促状から判明することも多い。
積極財産(プラスの財産)の調査方法
相続財産の調査において、まず把握すべきは積極財産(プラスの財産)です。これは相続人にとってプラスの利益になる財産であり、遺産分割や相続税申告の基礎となります。
この章では、代表的な調査方法を具体的に解説します。
不動産の財産調査(登記簿謄本・公図・名寄帳)
不動産の調査の基本は、登記簿謄本(登記情報)を法務局で取得することです。登記簿には所有者、抵当権などの権利関係が記載されています。
まず、申請には地番や家屋番号が必要であり、住所(住居表示)とは異なるため注意が必要です。住所しか分からない場合は、管轄法務局に地番照会を行うことができます。
さらに、共同担保目録を確認することで、別の不動産の存在が判明する場合があります。
なお、登記情報提供サービスを利用すれば、インターネットで登記事項証明書と同等の情報を取得可能です。
登記簿以外にも、公図(土地の位置関係を示す地図)や名寄帳(市区町村ごとの不動産一覧)を取得することで、相続人が把握していなかった土地・建物が見つかることもあります。ただし、名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、複数の自治体に照会する必要があります。
また、被相続人宛に届いていた固定資産税納付通知書を確認すると、不動産の存在や所在地が判明することがあります。
動産の財産調査
不動産以外にも、動産として価値のある財産が残されている場合があります。自宅内を調査すると、貴金属・美術品・骨董品などが発見されることがあります。
また、貸金庫を利用しているケースも多いため、契約書や銀行からの通知を確認する必要があります。貸金庫の開扉には、戸籍謄本や相続人全員の同意を求められることがあるため、手続きの流れを金融機関に確認しておきましょう。
預貯金・債権の財産調査(取引金融機関への照会)
預貯金は最も身近な相続財産の一つです。被相続人の預貯金通帳や残高証明書を確認することで、取引金融機関や支店を特定できます。
仮に通帳が見当たらなくても、銀行名や支店名がわかれば、取引明細を取得できます。金融機関名すら不明な場合は、被相続人と取引のあった銀行に直接照会する方法もあります。
その他、契約書や借用証書からは、被相続人が債権者となっている貸付金などが判明する場合もあります。
有価証券・会員権などの財産調査
被相続人が投資や趣味で保有していた財産も調査が必要です。
株式・社債・投資信託は、証券会社からの郵便物や配当通知で存在が判明します。上場株式であれば証券会社に照会、非上場株式なら発行会社に株主名簿の開示請求を行うことも可能です。
また、ゴルフ会員権は、会員証、郵便物、またはゴルフバッグの名札などから把握できることがあります。
知的財産権・仮想通貨など新しい財産の調査
近年は従来型の財産だけでなく、新しいタイプの財産にも注意が必要です。
知的財産権(特許・商標など)は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索可能です。
仮想通貨(暗号資産)やネット銀行口座は、通帳や郵便物が存在しないため見落とされがちです。被相続人が使用していたパソコン・スマートフォンを確認することでウォレット情報や取引履歴が判明することがあります。
生命保険の財産調査
生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡によって死亡保険金請求権が発生します。これは原則として相続財産に含まれず、受取人が固有の財産として取得します。
ただし、保険金額が大きすぎて他の相続人との公平を著しく欠く場合には、特別受益として遺産分割に考慮される可能性があります(民法903条)。
保険契約の有無は、保険証書や保険会社への照会で確認できます。

積極財産は「不動産・動産・金融資産・新しい財産・生命保険」と多岐にわたります。
どの調査も、手がかりは被相続人の保管資料や郵便物にあることが多いため、まずは書類やデジタルデバイスを丁寧に確認することが重要です。
消極財産(マイナスの財産)の調査方法
相続財産には、相続人にとって利益となる財産だけでなく、借金やローンといった消極財産(マイナスの財産)も含まれます。調査を怠ると「相続したはずが、実は多額の借金も背負っていた」という深刻な事態につながりかねません。
この章では、代表的な負債の調査方法を解説します。
金融機関等の負債
金融機関やクレジット会社、消費者金融に対する債務は、以下の照会制度を利用して調べることができます。
- 全国銀行協会(全銀協):被相続人の銀行借入状況を開示請求できます。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカード会社からの借入や分割払いなどの負債情報を照会できます。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融からの借入情報を確認できます。
いずれも、相続人であることを証明する戸籍謄本等の提出が必要です。
また、弁護士が代理で開示請求を行う場合には、相続人からの委任状(実印押印・印鑑証明書添付)が求められます。
不動産登記簿や契約書からの負債確認
不動産の登記簿謄本の乙区(担保権等の記載欄)を確認すると、抵当権や根抵当権などの設定状況から、被相続人が負債を抱えていたことが判明する場合があります。
ただし、登記簿の記載は「登記時点の内容」に過ぎず、その後に返済が進んで完済している可能性もあれば、逆に遅延損害金で債務が増えている場合もあります。したがって、実際の残債を把握するためには、判明した債権者に直接照会することが重要です。
また、被相続人が保管していた契約書や借用証書を確認することで、第三者からの借入が判明することもあります。
郵便物・督促状からの確認
被相続人宛に届いていた督促状・請求書・通知書は、負債を知る大きな手がかりになります。
特に以下のような郵便物には注意しましょう。
- クレジットカード会社や消費者金融からの請求書
- 保証会社や債権回収会社からの督促状
- 金融機関からの返済案内や残高通知
小さな封書一つからでも新たな債務が判明することがあるため、遺品整理の際には郵便物を安易に廃棄せず、慎重に確認することが大切です。

✅ 負債調査では、全国銀行協会・CIC・JICCへの照会が有効。
✅ 登記簿の乙区や契約書から担保設定を確認できる。
✅ 郵便物や督促状は、隠れた債務発見の重要な手がかり。
相続では、積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)まで含めて全体像を把握することが、トラブル回避の第一歩です。
補足的な財産調査の方法
相続財産調査の中心は、不動産・金融資産・負債といった主要項目ですが、それだけでは全てを把握できない場合があります。
この章では、見落としを防ぐための補足的な調査方法を紹介します。
確定申告書や税理士への照会
被相続人が自営業者やフリーランスであった場合、毎年の確定申告書に財産の手がかりが記載されていることがあります。
- 不動産の賃貸収入:賃貸物件の存在が判明
- 株式・投資信託の配当:金融資産の所在を把握できる
- 事業収入:取引先や売掛金の存在が明らかになる
確定申告書が見つからない場合でも、被相続人が税理士に申告業務を依頼していた可能性があります。その場合は、顧問税理士に照会することで財産情報を得られるケースがあります。
公証役場での遺言検索
被相続人が公正証書遺言を作成していた可能性がある場合は、公証役場に照会を行うことが有効です。日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用することで、公正証書遺言の有無を確認できます。
また、遺言書の有無や内容を確認することで、財産の分配方法や存在自体が明らかになることがあります。
郵便物や日常的な記録の確認
相続財産の手がかりは、意外にも日常の郵便物や書類に隠れていることがあります。
- 金融機関や証券会社からの通知:預貯金口座や証券口座の存在
- 保険会社からの契約更新通知:生命保険の契約有無
- 会員制クラブやゴルフ場からの郵便物:会員権の存在
- 督促状や請求書:借金・負債の有無
さらに、被相続人のパソコン・スマートフォンや手帳・日記といった日常的な記録にも、財産に関する情報が残されていることがあります。特に近年では、ネット銀行や仮想通貨など、紙の通知がなくデジタル記録だけで管理されている財産も多いため、デバイス調査は重要です。

✅ 確定申告書や税理士への照会は、自営業者の財産把握に有効。
✅ 公証役場で遺言検索を行うことで、遺言の有無や内容を確認可能。
✅ 郵便物・デジタル機器・日常記録は、隠れた財産を発見する重要な手がかり。
主要財産の調査に加え、こうした補足的な方法を組み合わせることで、より漏れのない相続財産調査が実現します。
専門家に相談すべきタイミング
相続における財産調査は、登記簿や預金通帳の確認といった基本的な作業から始められますが、すべてを自力で網羅するのは容易ではありません。
この章では、「専門家に相談すべきタイミング」を整理します。
自力での調査が難しい場合
- ネット銀行や仮想通貨などのデジタル資産
通帳や紙の通知がなく、パソコンやスマートフォンを調査しても手がかりが得にくい場合があります。専門家であれば、調査方法のアドバイスや、裁判所・金融機関への照会手続を代行できます。
- 信用情報機関への照会
全国銀行協会、CIC、JICCへの開示請求は、相続人本人が手続できるものの、書類準備や照会方法は煩雑です。弁護士に依頼すれば委任状をもとに代理で開示手続を行うことが可能です。
財産や負債が多岐にわたる場合
被相続人が長年事業を営んでいた場合や、不動産や投資商品を複数保有していた場合は、調査範囲が広くなります。
- 不動産が複数の市区町村に分散しているケース
名寄帳を自治体ごとに取得する必要があり、相続人が単独で対応するのは負担が大きいです。
- 事業関連の財産や負債があるケース
売掛金・設備・特許権といった事業用資産や、事業融資に伴う負債なども含めると、調査の抜け漏れリスクが高まります。
こうした場合は、弁護士・税理士が関与することで、効率的に財産目録を作成し、相続税申告や遺産分割協議まで見据えた整理が可能になります。
相続人間のトラブルが予想される場合
財産調査の段階で、すでに相続人同士の意見が対立することもあります。
「特定の相続人が財産を隠しているのではないか」
「死亡保険金や生前贈与の扱いをどうするか」
「借金の有無について見解が分かれる」
こうした状況では、感情的な衝突が法的紛争に発展しやすいため、第三者としての弁護士を介入させることが有効です。法律的な観点から冷静に調整し、調査結果をもとに公平な遺産分割を進めることができます。

✅ デジタル資産や信用情報機関への照会など、専門知識が必要な場合は弁護士への相談が安心。
✅ 財産・負債が多岐にわたり調査範囲が広い場合は、専門家が効率的に整理可能。
✅ 相続人間での対立が予想されるときは、早めに弁護士に依頼してトラブルを回避することが重要。
相続財産調査は「自分でできること」と「専門家に任せるべきこと」を見極めることが、スムーズな相続解決のカギになります。
まとめ
相続財産調査の全体像の振り返り
相続が始まったとき、まず取り組むべきは相続財産の調査です。不動産・預貯金・証券などの積極財産に加え、借金やローンといった消極財産まで、全体像を正確に把握することが相続手続の出発点となります。
調査方法としては、以下のようなステップを組み合わせることが基本になります。
- 不動産は登記簿謄本・名寄帳・固定資産税通知書の確認
- 預貯金は通帳や金融機関への照会
- 有価証券・会員権・仮想通貨などの多様な資産の調査
- 借金は信用情報機関や登記簿乙区、督促状からの確認
- 補足として確定申告書や郵便物・デジタル機器のチェック
積極財産と消極財産、双方の確認が必須
相続財産は「もらえる財産」だけではありません。積極財産・消極財産の両方を正確に把握して初めて、相続放棄・限定承認・単純承認といった手続の判断が可能になります。
もし借金を見落としたまま相続を承認すると、多額の返済義務を背負うリスクがあるため、積極財産と消極財産の双方の調査は必須です。
- 積極財産(プラスの財産):不動産、預貯金、株式、保険金など
- 消極財産(マイナスの財産):借金、クレジット債務、担保設定された不動産など
弁護士・税理士など専門家の活用のすすめ
財産の種類が多岐にわたる場合や、相続人間で意見が食い違う場合、専門家のサポートが極めて有効です。
- 弁護士:負債調査の代理手続や相続人間のトラブル調整を担当
- 税理士:相続税申告や財産評価の面でサポート
特に最近はネット銀行や仮想通貨など新しい資産も増えており、専門知識がなければ調査漏れが発生しやすくなっています。自力での対応に限界を感じたら、早めに相談することがトラブル回避の近道です。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
相続財産調査は、単に「財産を探す作業」ではなく、相続全体を円滑に進めるための土台づくりです。積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)を漏れなく把握し、必要に応じて専門家の力を借りることが、安心で公平な相続手続への第一歩となります。
不安な点があれば、是非弁護士へご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス

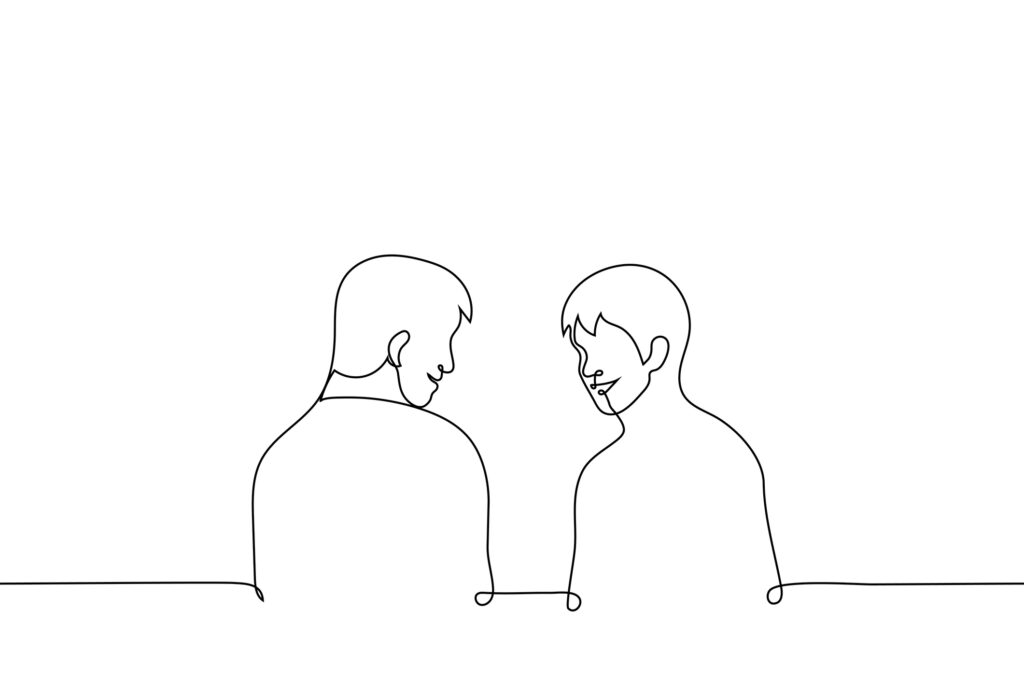



 メールで
メールで