
columns
弁護士コラム
相続不動産を他の相続人に勝手に売られた・担保にされたときの対処法を弁護士が解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年07月11日 |
最終更新日:2025年07月11日

- Q
-
遺産分割も終わっていないのに、兄が実家の土地を勝手に売ってしまいました。
これは違法ではないでしょうか?どのように対応すればいいのでしょうか?
- Answer
-
相続不動産は、遺産分割が終わるまでは全相続人の「共有財産」として扱われます。
他の相続人が単独で売却や担保提供を行うことは原則としてできず、法的に無効または一部無効とされる可能性があります。
被害を受けた相続人は、登記の是正、損害賠償請求、使用料相当額の請求など、複数の法的手段によって対応が可能です。
相続をめぐるトラブルの中でも、特に深刻なのが「不動産を他の相続人に勝手に処分されてしまった」というケースです。
遺産分割が終わっていないにもかかわらず、相続人の1人が不動産を第三者に売却したり、抵当権を設定してしまった場合、残された相続人は大きな不利益を被ることになります。
本記事では、こうした「無断処分」が起きた場合に、どこまで法的に取り戻せるのか、どのような主張や手続きを講じるべきなのかについて、実務に即して丁寧に解説します。
トラブルに直面している方も、予防策を知りたい方も、ぜひ最後までお読みください。
目次
はじめに
相続トラブルにはさまざまな種類がありますが、中でも特に深刻なのが「相続不動産の無断処分」にまつわるトラブルです。
たとえば、「まだ遺産分割協議も終わっていないのに、他の相続人が実家の土地を勝手に売ってしまった」「知らないうちに相続不動産が担保に入れられていた」といったケースは、被害を受けた側にとって精神的にも大きなショックとなるだけでなく、法律的にも複雑な対応を迫られる事態となります。
本来、相続財産は「相続人全員の共有財産」として扱われるため、勝手に処分することは許されません。
しかし、現実には遺産分割が済んでいない段階で、他の相続人が単独で売却・担保設定をしてしまうというケースが後を絶ちません。
しかも、それが登記まで済んでしまっていた場合、取り戻しや修正の手続きには大きな手間と費用がかかることもあります。
このような状況に直面した相続人の方に向けて、本記事では以下のような疑問や悩みに答えていきます。
• そもそも、他の相続人が勝手に不動産を売ったり、担保に入れたりすることはできるのか?
• 売却や担保設定があった場合、どこまで取消しや修正ができるのか?
• 第三者(買主や金融機関)が関わっている場合の対応はどうすればいいのか?
• 自分の権利を守るために、具体的にどんな法的手段があるのか?
本記事は、他の相続人に相続不動産を無断で処分された方=被害を受けた相続人を主な読者として想定しています。
ぜひ、あなたの状況に照らして、本記事を参考にしていただければ幸いです。
相続不動産は「共有状態」にあるという前提
相続トラブルの中で、不動産の「無断処分」が問題になる背景には、相続開始後の相続不動産が法律上“共有状態”にあるという点を理解しておく必要があります。
これは、無断で売却・担保設定された相続人が、自らの権利をどのように主張できるかを考える上で極めて重要な前提です。
相続開始後、遺産分割が終わるまでは相続人全員の共有状態(民法898条)
民法第898条は、以下のように定めています。
「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
つまり、被相続人が亡くなった時点で、その財産(たとえば実家の土地や建物、預貯金など)は、遺言などによる特別な指定がない限り、相続人全員の“共有財産”になります。
この「共有」とは、単に「仲良く使いましょう」という意味ではなく、民法249条以下に定められた厳密な法律概念であり、個々の相続人は、不動産全体に対して「持分割合に応じた権利」を持つということを意味します。
そして、重要なのは、この共有状態は遺産分割が確定するまで続くという点です。
誰か一人が「この家は自分のもの」と思っていても、遺産分割協議や審判で正式に決まらない限り、それは法的に認められた「単独所有」ではありません。
共有物の法的処分には原則として全員の同意が必要
不動産の「法的処分」とは、売却や担保設定(抵当権設定)など、所有権を大きく動かす行為のことを指します。
このような処分については、民法の明文規定ではありませんが、判例および学説上、共有者全員の同意がなければ有効にできないとされています(最判昭和42年2月23日など)。
理由はシンプルです。
たとえば、3人で共有している土地を1人の相続人が勝手に全部売ってしまった場合、他の2人の「持分」まで勝手に処分されてしまうことになります。
これは、他の共有者の権利を重大に侵害する行為であり、当然ながら全員の合意がなければできないとされるのです。
なお、共有者の1人が「自分の持分だけ」を処分する(たとえば売却や担保に入れる)ことは可能です。
つまり「共有物全体の処分」か「自己の持分のみの処分」かによって、要件が大きく異なります。
相続人の1人が単独で動いた場合、それは「無権限の処分」となる
したがって、遺産分割が終わっていないにもかかわらず、相続人の1人が単独で不動産の売却や担保提供を行った場合、それは他の相続人の持分についての無権限の処分=法的に効力が否定される行為となります。
しかし現実には、登記の力によって外形的には処分が成立してしまっているケースも少なくありません。
この場合、被害を受けた相続人としては、「自己の持分についての一部抹消登記請求」などの法的手段を用いて、状況を回復していく必要があります。
この点については、次章以降で詳しく解説していきます。
無断処分の典型例とその法的評価
相続不動産を他の相続人が無断で処分してしまった場合、法的にはどのように評価されるのでしょうか。
ここでは、代表的な2つのケースについて、それぞれの法的扱いや、被害を受けた相続人が取れる手段について解説します。
不動産を勝手に担保提供されたケース(抵当権設定)
他の相続人の同意なく設定された抵当権の効力は?
たとえば、相続人Cが、遺産分割が終わっていない状態で、相続財産である土地を自己の借金の担保として使い、金融機関Dに抵当権を設定した場合を考えてみましょう。
このとき、他の相続人Bの同意は得ていなかったとします。
このようなケースでは、抵当権の設定がされた対象が「不動産全体」であるか、「共有持分の範囲」にとどまるかで法的評価が大きく異なります。
民法上、相続不動産は全相続人の共有物ですから、共有物全体に抵当権を設定するには相続人全員の同意が必要です(最判昭和42年2月23日)。
よって、Cが単独で行った抵当権設定は、その「不動産全体」に対する抵当権としては無効となります。
ただし、注意が必要なのは、C自身の持分については自由に処分が可能であるという点です。
つまり、Cが自己の共有持分について抵当権を設定すること自体は有効です。
したがって、この場合、抵当権の効力はCの持分に限って認められることになります。
無効を主張できる範囲とできない範囲
被害を受けた相続人Bは、「自分の持分にまで抵当権が設定されたような登記」がなされた場合、その部分については抵当権設定登記の一部抹消(更正)を求めることができます。
しかし、抵当権設定契約自体を全面的に無効と主張することはできません。
このように、持分を超えた処分部分については否定されるが、持分内での処分は有効というのが、現在の裁判実務の基本的な考え方です(最判昭和38年2月22日参照)。
不動産を勝手に売却されたケース
売却行為は有効か?他人物売買になるとは?
次に、相続人Bが他の相続人Cの同意を得ることなく、相続不動産(甲土地)を第三者Dに対して売却してしまったケースを考えましょう。
この場合、Cは売却に関与していません。
このような場合でも、売買契約自体は債権的には有効とされます。
これは、Bが「自分の持分を売ったこと」までは合法であるためです。
一方で、BがCの持分まで含めて売却していた場合、その部分はBにとって「他人の権利を勝手に売った行為(=他人物売買)」となります。
民法561条により、D(買主)は、B(売主)に対して「Cの持分を取得して自分に移転せよ」と請求できます。
移転がなければ、代金の減額や損害賠償、契約の解除といった手段を取ることができます。
持分超過部分の登記抹消や使用排除請求の可否
被害を受けたCは、Dが取得した登記について「全部抹消せよ」と請求したくなるかもしれませんが、裁判所はこれを認めていません。
判例(最判昭和38年2月22日)によると、Bの持分についての売却は有効であるため、Dが受けた登記のうちCの持分に関してのみ登記の抹消(更正)を請求することができるにとどまります。
さらに、Cが「Dは不法に占有している」として土地の明渡しを求めた場合も、Dが有効に持分を取得している以上、共有者として使用する権利があるため、原則として明渡し請求は認められません。
ただし、Dが自己の持分を超えて使用している場合、CはDに対し使用料相当額の支払いを請求することができます(民法249条2項)。
このように、不動産の無断処分には厳しい制限があるものの、全面的に無効になるわけではなく、部分的に有効性が認められる範囲があることが、相続人としての対応を複雑にしています。
実際に取れる法的手段
相続不動産を他の相続人に勝手に処分されてしまったとき、「もう取り戻せない」と諦める必要はありません。
状況に応じて、いくつかの法的手段を講じることが可能です。
本章では、被害を受けた相続人が実際に取りうる手段として、登記の修正や使用料の請求、損害賠償などを具体的に解説します。
自己持分についての一部抹消登記請求(更正登記)
判例(昭和38年2月22日最判)に基づく実務的手法
不動産を無断で売却または担保設定された場合、処分者の持分については原則として有効ですが、他の相続人の持分にまで及んでいる登記は、実体に合致しない登記として更正の対象となります。
この点について、最高裁昭和38年2月22日判決は、「他の共同相続人の持分については登記の全部抹消ではなく、一部抹消(更正)登記による対応が適切である」と判断しています。
つまり、自己の持分を侵害された相続人は、「自分の持分に関する限度での抹消(更正)登記」を請求することができるのです。
手続の流れと必要書類
- 1登記事項の確認:法務局で登記事項証明書を取得し、現状の登記内容を確認します。
- 2法的検討:登記内容が他の相続人の持分まで含めて処分されていることを証拠化します(例:登記原因証明情報や売買契約書など)。
- 3協議・交渉(任意更正):相手方と協議のうえ、任意に更正登記が可能な場合はそれに越したことはありません。
- 4訴訟提起(更正登記請求訴訟):任意に応じない場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所にて「登記更正請求訴訟」を提起します。
必要書類には、登記事項証明書、相続関係説明図、戸籍謄本類、処分の経緯を示す証拠資料(契約書、遺産分割未了であることの立証など)が含まれます。
使用排除はできるか?
土地を勝手に使われている場合の明渡し請求の可否
たとえば、不動産が第三者に無断で売却され、現在その者が土地を使用している場合、被害を受けた相続人は「出ていってほしい」と考えるのが自然です。
しかし、第三者が処分者の持分を取得している限り、その人物は共有者の一人という立場になります。
民法249条1項により、共有者は共有物の全部について持分に応じて使用できるとされています。
そのため、原則として共有者である第三者に対して土地の明渡しを求めることはできません。
使用料相当額の請求という別のアプローチ
ただし、明渡しはできなくても、相手が持分を超えて専有的に使用している場合には、使用料相当額の支払いを請求することが可能です(民法249条2項)。
この「使用料相当額請求」は、相手が占有している面積や利用状況、地域の相場等をもとに金額を算出します。支払いを受けることで、経済的な不公平の是正を図ることができます。
損害賠償請求・契約解除
善意の第三者買主への対応
もし第三者が、無断で売却された不動産を「売主が単独所有者である」と信じて善意で購入していた場合でも、登記に公信力はないため、他の相続人は自らの持分を主張できます(最判昭和38年2月22日)。
とはいえ、登記があることで実務上の交渉や証明が複雑になることは避けられません。
そのため、早期に法的手段を取ることが肝要です。
なお、第三者買主は、売主に対して以下のような請求を行うことが可能です(民法561条以下)。
• 他相続人の持分の取得および移転請求
• 代金減額請求
• 契約解除
• 損害賠償請求
善意の第三者に対する損害賠償は難しい一方で、契約上の相手方である相続人には責任を追及できます。
売却した相続人に対する責任追及
無断で売却・担保設定を行った相続人に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求(民709条)を行うことができます。
たとえば、登記の回復や裁判対応に要した費用、使用料相当額、精神的損害などが賠償対象となり得ます。
また、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の場でも、相手の違法行為を考慮して、公平な遺産分割を主張することも重要です。
このように、無断処分に対しては、登記の是正、使用料請求、損害賠償、さらには訴訟提起など、状況に応じて多様な法的対応が可能です。
どの手段が最も適切かは、登記の有無や第三者の関与状況など、事案ごとの事情により異なります。
迷った場合は、早めに弁護士に相談し、適切な手段を選択することが重要です。
遺産分割との関係と実務上の留意点
相続不動産を他の相続人に無断で処分された場合、その行為が法的に無効・一部無効とされるにせよ、現実には不動産の一部が第三者の手に渡っていたり、登記が動いてしまっているケースも少なくありません。
こうした場合、遺産分割にどのような影響があるのか、またどのような主張を行うべきかを理解することが重要です。
無断処分が遺産分割協議に与える影響
原則として、遺産分割協議は、相続財産が現に相続人全員の共有状態にあることを前提に行われます。
したがって、その相続財産(たとえば不動産)がすでに一部処分されていた場合、協議の前提が崩れてしまうという問題が生じます。
実務上は、次のような2つのケースに分かれます。
ケース①:処分された不動産が相続財産として残っていない場合
たとえば、相続人Bが不動産を勝手に第三者Dに売却し、登記まで移転されてしまった場合、不動産そのものはもはや遺産分割の対象からは外れてしまいます。
しかし、「不当な処分があった」という事情は、他の財産の配分に影響を与える事情として考慮されます。
たとえば、他の財産を多めに取得することで帳尻を合わせるといった調整が可能です。
ケース②:処分されたのが自己持分の範囲にとどまる場合
たとえば、相続人Cが自己の持分のみ担保に入れたというような場合、不動産自体は共有状態として遺産分割の対象に残っているため、そのまま協議や調停・審判を進めることができます。
ただし、担保の存在は分割方法に制約を与える可能性があるため、協議にあたっては調整が必要となることが多いでしょう。
遺産分割調停や審判で主張すべきポイント
被害を受けた相続人として、遺産分割調停や審判の場で主張すべきポイントは次のとおりです。
処分が無断で行われたこと
まず、遺産分割前に他の相続人が単独で不動産を処分したことが違法であることを明確に主張します。
可能であれば、処分が行われた経緯や、遺産分割協議書の偽造等があればそれも指摘しましょう。
処分の効果が限定的であること
たとえば、売却であっても「処分者の持分を超える部分は他人物売買であって無効である」ことや、「登記があっても自己の持分については対抗できる」など、法的評価の整理を主張します。
遺産分割上の不公平としての調整を求めること
遺産分割の場では、不公平な処分行為があったこと自体を考慮要素として主張することで、他の財産配分に影響を与える余地があります。
民法906条の2に基づく主張可能性(東京地判昭和63年12月27日)
令和5年の民法改正により新設された民法906条の2は、以下のように規定しています。
「共同相続人のうちに、相続財産の一部について、その共有持分を第三者に譲渡した者があるときは、他の共同相続人は、当該譲渡がなかったものとみなして、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができる。」
この条文は、たとえば無断売却などにより相続不動産が第三者の手に渡ったとしても、あくまで「遺産としての性質を残す」ことを前提に分割請求ができると定めたものです。
この趣旨に近い判断として、東京地裁昭和63年12月27日判決は、相続人が持分を第三者に譲渡した場合でも、家庭裁判所での遺産分割調停の場では「譲渡がなかったもの」として取り扱うことができるとしています。
つまり、無断処分されたとしても、被害を受けた相続人は「本来遺産として存在していた不動産が持分処分されたにすぎない」ことを前提に、調停や審判の中で分割対象財産として主張することが可能なのです。
実務上のポイントまとめ
- 無断処分は、他の相続人との信頼関係を大きく損ねる重大行為である。
- 法的には一部有効(処分者の持分範囲内)となるが、登記や実体関係に齟齬が生じている場合には早期に是正が必要。
- 遺産分割調停・審判では、処分行為の違法性や不公平性を十分に主張し、民法906条および906条の2を活用して、正当な相続分の回復・実現を目指す。
事前・事後の予防と対応策
相続不動産の無断処分は、発覚したときにはすでに登記が動いていたり、第三者に渡ってしまっていたりと、取り返しがつかないように見えるケースが多くあります。
しかし、適切な事前対策と、初動の早期対応によって、法的な被害の拡大を防ぐことが可能です。
ここでは、相続における無断処分を未然に防ぐための方法と、実際に被害が発生した後の対応策を整理しておきます。
生前の共有対策(遺言・信託など)
もっとも効果的な予防策は、被相続人が生前に明確な意思表示をしておくことです。
遺言の活用
公正証書遺言などにより、「〇〇不動産は長男に相続させる」などと明示しておけば、相続開始後の不動産の共有状態を避けることができます。
共有状態がそもそもなければ、無断で売却や担保提供されるリスクも発生しません。
また、遺言には遺言執行者を指定しておくことも有効です。
執行者がいる場合、相続人が勝手に不動産を処分することはできません。
民事信託の活用
不動産を信頼できる家族に信託しておくことで、相続が発生しても不動産の法的主体は動かず、無断処分のリスクを回避できます。
いわゆる「家族信託」は高齢期の資産管理・承継に有用な手段として注目されています。
無断処分の疑いを持ったらすぐにすべきこと
被相続人が亡くなった後、不動産の登記状況などに不審な点があれば、すぐに確認と対応を行うことが肝心です。
登記情報の確認
まずは、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産に売買や抵当権設定の登記がされていないかを確認しましょう。
他の相続人や第三者とのやりとりの記録化
無断で処分された可能性がある場合、メールやLINE、書面等でのやりとりは証拠として必ず保存しておきます。
後に登記の更正や損害賠償請求を行う際に重要な資料となります。
金融機関や不動産業者への照会
処分の相手方(銀行・買主など)が判明している場合には、可能な限り情報開示を求め、事実関係の把握に努める必要があります。
弁護士への早期相談がおすすめ
相続不動産の無断処分が疑われる場合、登記の有無、処分者の意図、第三者の関与、遺産分割との関係など、法律的に検討すべきポイントが多数あります。
これらを個人で判断することは困難であり、対応が遅れることで被害が拡大したり、法的回復が困難になるリスクもあります。
弁護士に早期に相談することができれば、登記の差止仮処分、登記更正請求、遺産分割調停・審判との連携など、最適な法的対応を的確なタイミングで行うことができます。
何より、感情的対立を法的に整理し、冷静な解決へと導くうえで、弁護士の関与は不可欠です。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
本記事で紹介したように、相続不動産の無断処分には明確な法的制約があり、登記や使用状況の是正、損害賠償の請求、遺産分割での調整など、多様な手段が用意されています。
大切な財産を守るためにも、そして、将来の円満な相続を実現するためにも、早期に事実を確認し、必要に応じて法的専門家の支援を受けることが、最も確実な解決策といえるでしょう。
直法律事務所では、相続不動産の管理・賃貸・分配に関する法的サポートはもちろん、相続全般に関するご相談を随時承っております。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス

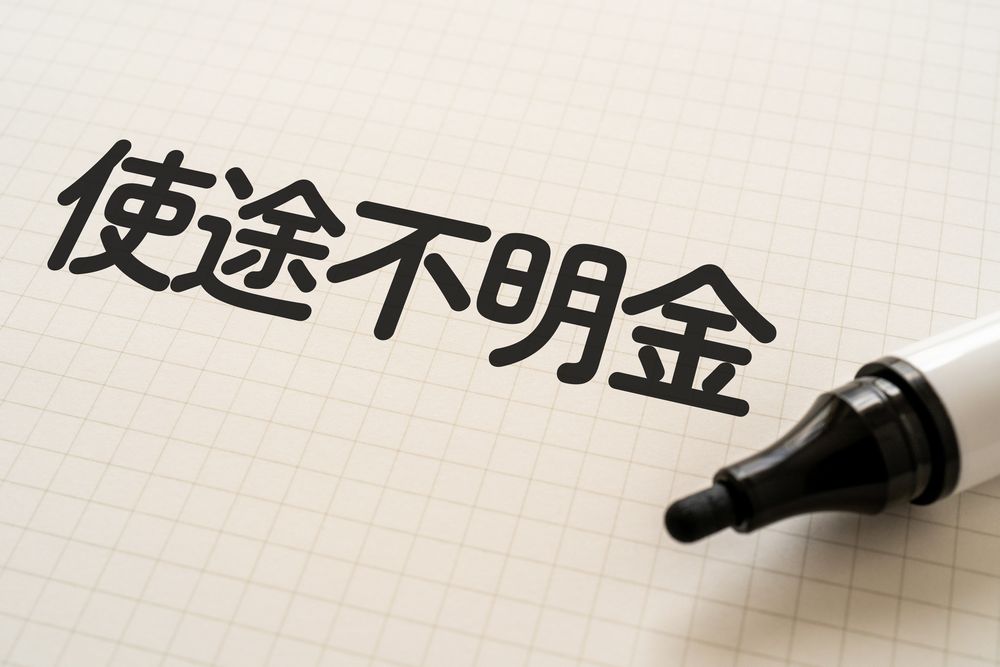



 メールで
メールで