
columns
弁護士コラム
相続した不動産はどう管理・処分する?よくあるトラブルと対処法を弁護士が解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年07月10日 |
最終更新日:2025年07月10日

- Q
-
親が亡くなり実家を相続しましたが、兄弟間で意見が割れて不動産の扱いを決められません。
どうすればよいでしょうか?
- Answer
-
相続不動産は、法的には相続人全員の「共有物」となり、売却や賃貸などの処分には原則として全員の同意が必要です。
現金や預金とは異なり簡単に分けることができないため、相続人間で深刻なトラブルに発展するケースが少なくありません。また、感情や利害が対立しやすいこともあり、早期の合意形成や、状況に応じた法的手段の選択がカギとなります。
本記事では、「相続不動産の管理・処分」をめぐる典型的な対立構造や、共有関係の整理方法、所在不明者への対応、トラブルを未然に防ぐための実務的アプローチまで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
相続後の不動産問題に直面している方、または将来に備えたい方にとって、必見の内容です。
目次
はじめに
相続不動産をめぐる典型的なトラブルとは
相続が発生したとき、相続財産の中に「不動産」が含まれている場合には、相続人の間でトラブルが生じやすくなります。
不動産は、現金や預金のように簡単に分けることができず、特定の相続人が単独で処分することも難しい資産です。しかも、固定資産税や維持管理費といった「負の財産」も一体でついてくるため、扱い方についての意見対立が表面化しやすいのです。
たとえば次のような典型例があります。
- 相続人の一部が「売却して分配したい」と考えているが、他の相続人は「思い出の詰まった実家なので残したい」と主張している。
- 兄が勝手に不動産を第三者に賃貸し、妹がそれに反発して紛争に発展。
- 相続人の1人が海外や遠方に住んでいて意思確認が困難。連絡が取れない。
- 他の相続人の了解を得ずに登記手続やリフォームなどを進めたことで、信頼関係が破綻した。
このように、不動産をめぐる感情的・経済的な対立が、親族間の長期的な確執にまでつながってしまうことは珍しくありません。
なぜ「管理・処分」が相続人間の火種になるのか
不動産を「どう管理するか」「いつ処分するか」「いくらで売却するか」「誰が住むのか」などの判断には、相続人それぞれの立場や思惑、そして感情が強く反映されます。
不動産は共有状態のままになりやすく、遺産分割が終わっていない段階では、相続人全員が共同で所有する法的状態(遺産共有)にあります。この状態では、不動産(共有物全体)の処分や借地借家法の適用される賃貸契約をするには、原則として相続人全員の同意が必要になります(民法251条、252条など)。つまり、1人でも反対すれば、処分はできません。
さらに問題となるのは、相続人の中に所在不明者がいたり、連絡を拒否する者がいるケースです。このような場合、不動産の適切な管理・処分が滞り、固定資産税や老朽化リスクだけが増していく「負の遺産化」が起こります。
また、不動産の利用や収益の偏在も火種となります。たとえば、ある相続人がその不動産に住み続けているのに、他の相続人には賃料が支払われていないような場合、「不公平だ」「占有料を支払うべきだ」といった不満が噴き出します。
このように、相続不動産の「管理」と「処分」は、感情・経済・法律が交錯する難題であり、専門的な知識や冷静な調整が求められる分野なのです。
相続した不動産は誰のもの?
遺産共有と物権法上の共有の違いはある?
相続人が複数いる場合、相続財産はすぐに個々の相続人のものになるわけではありません。民法第898条は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定めています。
つまり、相続財産は一時的に「相続人全員の共有物」として扱われるのです。この状態を遺産共有といいます。
では、この「遺産共有」は、たとえば兄弟や夫婦などが共同で購入した不動産に適用される「物権法上の共有」とは何か違うのでしょうか? 実は、最高裁昭和30年5月31日判決(民集9巻6号793頁)は、「遺産共有も物権法上の共有とその性質を異にするものではない」と判示しており、法的にはほぼ同じ取り扱いを受けます。
ただし実務上は、性質や目的の違いから「遺産共有」はより慎重に扱われます。物権法上の共有は、たとえば共同で購入した土地を自由に売買・処分できる一方、遺産共有では自身の法定相続分を超える割合については「遺産分割が完了するまで相続人全員の同意が必要」という大きな制約がつくのが特徴です。
遺産分割が完了するまでの法的状態
遺産分割がなされるまでの間、相続財産は相続人全員による「共有物」として存在し、相続人はその一部(=持分)を有しているにすぎません。たとえば、3人兄弟が実家を相続した場合、実家の不動産は3人で法定相続分に応じた共有状態になります。
この段階では、不動産の名義変更(登記)も共有名義で行われることが原則で、登記の変更にも相続人全員の協力が必要です。
また、相続人の1人が勝手にその不動産を使用したり、貸したり、売却しようとしたりすると、他の相続人の権利を侵害することになります。たとえば、兄が勝手に相続不動産を第三者に賃貸し、賃料を独り占めしていた場合には、他の相続人から不当利得返還請求や占有料相当額の請求がなされることもあります。
相続人全員で合意しないとできないこと
遺産共有状態にある不動産について、次のような行為を行うには相続人全員の合意が必要です。
- 不動産の売却(処分行為)
- 建物の大規模な修繕や改築(変更行為)
- 民法252条4項の期間を超える長期の賃貸契約、又は、借地借家法の適用のある賃貸借契約の締結
これらは、民法251条における「共有物の変更」に該当し、裁判例(最判昭42・2・23、裁判集民86・361など)でも「共有者全員の同意」が必要であることが繰り返し示されています。
したがって、「自分の持分があるのだから自由に使ってもいい」という感覚で相続不動産に関わることは、他の相続人との深刻なトラブルの原因になります。

相続が発生し、不動産が遺産に含まれていた場合、遺産分割協議を早期に進めることがトラブル防止の鍵となります。遺産分割協議には、原則として相続人全員の合意が必要であり、たった1人でも協議に応じない相続人がいれば手続きが進まないという厄介な側面があります。
もし連絡が取れない相続人がいる、あるいは感情的な対立が激しいといった状況であれば、早めに弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
共有不動産の処分はどう決まる?
「法的処分」にはなぜ全員の同意が必要なのか
共有不動産を売却したいと考えたとき、たとえ自分が過半数の持分をもっていたとしても、勝手に売ることはできません。その理由は、民法251条に定められた「共有物の変更」には共有者全員の同意が必要とされているからです。
不動産の売却、抵当権の設定、民法252条4項の期間を超える長期賃貸などの「法的処分」は、他の共有者の持分権を根本的に変動させる重大な行為です。
たとえば、土地を売却するという行為は、自分の持分だけでなく、他の共有者の権利部分も市場に出してしまうことになります。これは他人の財産を勝手に処分するのと同じことです。
このような理由から、法的処分=共有物の「変更行為」と解されており、民法251条の「全員の同意」の要件が適用されるのです。
一部の相続人が勝手に売却・賃貸したら?
相続人のうち1人が、他の相続人の同意を得ずに共有不動産を第三者に売却したり、長期の賃貸借契約を結んだ場合、その行為は他の相続人の共有持分権の範囲では無効になる可能性があります。
たとえば、3人兄弟で共有している土地を、長男が自分の判断だけで売却してしまったとします。このようなケースでは、他の共有者が「自己の持分について処分したのではなく、共有物全体を処分した」と主張し、他の共有者の持分に関し、売却の無効確認訴訟を提起することができます。裁判所は、共有者全員の同意がなかった以上、当該共有持分権の範囲に関し売却行為は無効とする判断を下す可能性が高いでしょう。
また、相手方(買主や借主)が善意であっても、共有者の1人の単独処分である以上、法的に完全な権利を取得できないことがあります。つまり、買主側も不安定な権利しか得られないため、実務上は登記や契約時に「全員の同意」を必ず確認するのが通例です。
管理行為との区別とその法的意味
共有物に対する行為には、「変更行為」や「処分行為」以外にも「管理行為」という概念があります。これらは法的な意味で明確に区別されており、それぞれに必要な同意の要件も異なります。
民法252条1項は、次のように定めています。
「共有物の管理に関する事項は、共有者の持分の価格の過半数で決する。」
つまり、不動産の修繕や維持管理、賃貸借契約(※短期に限る)などの「管理行為」については、全員の同意は不要であり、持分価格の過半数で決定することができます。
【保存行為と管理行為と変更・処分行為の比較】
| 行為の種類 | 内容の例 | 要件 |
| 保存行為 | 雨漏りの修繕、草刈りなど | 各共有者が単独で可能 |
| 管理行為 | 民法252条4項の期間を超えない短期賃貸契約など | 持分価格の過半数 |
| 変更・処分行為 | 売却、抵当権設定、民法252条4項の期間を超える賃貸借、又は、借地借家法の適用がある賃貸借契約など | 共有者全員の同意 |
特に注意すべきなのが、借地借家法が適用されるような賃貸借契約(例:建物所有目的での土地賃貸など)です。
これらは契約上の期間が短くても、更新により長期化する可能性が高いため、「管理行為」ではなく「処分行為」とみなされる傾向にあります。

不動産の売却や賃貸を検討する際、「管理だから」「名義に自分の名前があるから」と安易に行動してしまうと、後から他の共有者との法的トラブルに発展するリスクがあります。
自分の意思だけでできることと、全員の同意が必要なことの線引きを誤らないようにしましょう。
処分・変更・管理の違いを正しく理解し、行動する前に弁護士などの専門家に確認することが非常に重要です。
相続人の中に「所在不明者」がいたら?
売却を希望しても進められないケース
相続財産に不動産が含まれている場合、相続人全員で「売却して現金化し、分配したい」と考えるのは自然な流れです。しかし、相続人の中に連絡のつかない者(=所在不明者)がいる場合、そうした希望は一気に行き詰まってしまいます。
たとえば、兄弟姉妹の一人が海外に移住して音信不通になっていたり、戸籍上は生存しているものの、現住所や連絡先がまったく不明というケースでは、その相続人の同意を得ることができず、不動産の処分ができません。
不動産の売却や長期賃貸などは「処分行為」「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となるため(民法251条)、所在不明者の存在が致命的なボトルネックになります。
長年にわたり手をつけられないまま、固定資産税や管理費だけが発生し続ける「塩漬け不動産」と化してしまうことも少なくありません。
令和3年改正による救済制度:民法262条の3【所在等不明共有者】
こうした状況に対応するため、令和3年の民法改正によって新たに導入されたのが民法262条の3「所在等不明共有者の持分の譲渡に関する裁判」という制度です。
この制度では、以下のような要件を満たせば、裁判所の判断を経て「所在等不明共有者の持分も含めて」不動産全体を売却できるようになります。
- 他の共有者の所在が不明であり、合理的に調査しても見つからないこと
- 申立人以外の全ての共有者が、特定の第三者に持分を譲渡することに合意していること
- 譲渡対象が不動産全体(共有持分を合算したもの)であること
この手続をとることで、所在不明者の持分を「譲渡する権限」が裁判所から与えられ、他の共有者と一緒に不動産全体を売却することが可能となります。
手続の流れとしては、
裁判所への申立 ➡ 公告・供託 ➡ 異議申立期間経過 ➡ 譲渡権限の裁判 ➡ 登記手続
と進みます。
なお、譲渡価格に相当する金額は供託し、後日所在不明者が現れた場合の権利を保全する形が取られます。
遺産共有の場合は「相続開始から10年経過」が要件になる点に注意
注意が必要なのは、対象不動産が「遺産共有の状態」にある場合です。すなわち、相続が発生し、まだ遺産分割が完了していない状態の不動産については、所在等不明共有者が「共同相続人」であることになります。
この場合、民法262条の3第2項により、相続開始から10年が経過していないと、譲渡権限を得るための裁判を起こすことができません。これは、相続人間の「遺産分割の機会」を保障するための制度的配慮です。
たとえ他の相続人が売却を望んでいても、相続開始から10年が経過するまでは、この制度によって不動産全体を処分することはできません。
そのため、遺産分割協議を早期に行わなかったり、所在不明者に対応しないまま年月が経ってしまうと、長期間にわたって手詰まり状態に陥ってしまうこともあります。
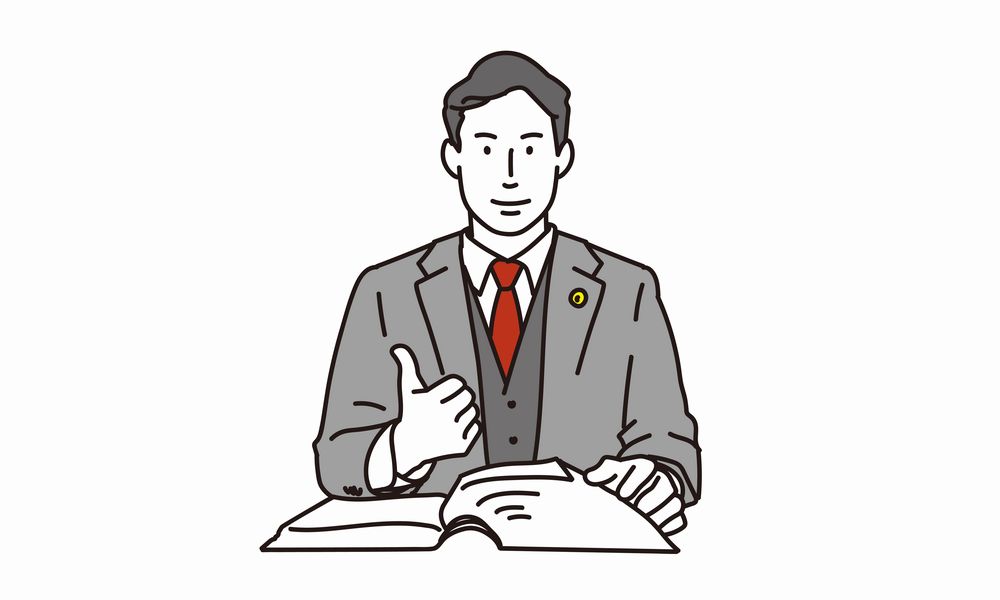
所在不明者の存在が不動産の売却や活用を阻んでいる場合、以下のような選択肢が考えられます。
・ 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所で申立て)
・ 共有物分割訴訟の提起(共有関係の解消を目的とする)
・ 民法262条の3による裁判手続の活用(所在等不明共有者の持分を譲渡)
どの方法を選ぶべきかは、状況や目的によって異なります。相続開始からの経過年数、他の相続人との関係、譲渡先の有無など、様々な条件を総合的に検討する必要があります。
所在不明の相続人がいる場合、手続きを一歩でも前に進めるには、法律の専門家による調査と戦略的な手続選択が不可欠です。
早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことが、将来的な損失を防ぐ鍵となります。
不動産の賃貸・使用貸借・地上権・地役権の設定はできるのか?
相続不動産が共有状態にある中で、「誰かに貸したい」「暫定的に使用させたい」と考える相続人が出てくることは珍しくありません。ですが、不動産に関する利用契約は、法的に「処分行為」(法律上の「管理行為」)とみなされる場合があり、勝手に行うと深刻なトラブルに発展します。
本章では、賃貸借・使用貸借・地上権・地役権設定などの契約が、相続人単独で可能かどうか、法的な判断基準を見ていきます。
借地借家法の適用がある場合
たとえば、建物を建てる目的で相続不動産を他人に貸す場合、その契約は借地借家法の適用を受けることになります。借地借家法が適用される賃貸借契約は、更新が保護されており、一度契約すると長期間にわたり当該不動産の利用権が他人に移転するという効果を持ちます。
このような契約は、単なる管理行為(民法252条)ではなく、「処分行為」または「変更行為」(民法251条)に該当すると解され、共有者全員の同意がなければ有効に成立しません。
実際の裁判例でも、「借地借家法の適用を受ける賃貸借契約を締結するには、共有者全員の同意が必要」とする判断が多数示されています。共有者の一部が勝手に契約しても、その契約は共有物全体には及ばず、無効または持分部分に限られる可能性が高いのです。
使用貸借も「無償ゆえに重い」? 管理行為とならない理由
「お金を取らないなら問題ないのでは?」と思われがちな使用貸借契約(無償で貸す契約)も、実は油断できません。
東京地裁平成18年1月26日判決は、使用貸借契約についても、共有者の使用収益権を一方的に制限する無償行為であるため、管理行為ではなく処分行為にあたるという判断を下しています。すなわち、補償もなく他の共有者の権利を減殺することになる以上、共有者全員の同意が必要だというのが有力な見解です。
この点、明確な法律上の規定はありませんが、実務でも「使用貸借=処分行為」とみなして、慎重に扱うのが一般的です。
地上権や地役権の設定契約も「期間の長さ」が鍵
不動産を貸すのではなく、一定の利用権を設定する方法として地上権・地役権があります。たとえば、他人の土地に建物を建てる目的で設定するのが地上権、通行や配管のために設定するのが地役権です。
令和3年の民法改正により、これらの権利設定契約についても「管理行為」か「処分行為」かの判断基準が明確化されました。具体的には、民法252条4項にそれぞれの目的ごとに期間が定めてあり、一定の年数(10年または5年等)を超える場合は処分行為に該当し、共有者全員の同意が必要になります(民法252条4項)。
※ 実務上は、5年以内・10年以内の短期設定は少なく、多くのケースで「処分行為」となります。
定期借家・一時使用などの例外もある
ただし、すべての賃貸借契約が自動的に「処分行為」となるわけではありません。例外として、一定の条件を満たす契約については「管理行為」とみなされる余地があります。
借地借家法では、以下のような短期契約について明確な特例が設けられています。
- 定期建物賃貸借(借地借家法38条)
書面で契約し、更新をしない旨を明記したもので、契約期間は自由。
→ 3年以内であれば管理行為とされる可能性あり。
- 取壊し予定建物賃貸借(借地借家法39条)
建替え等を目的とする短期契約。
→ こちらも期間と契約目的によっては、全員の同意不要となる場合あり。
- 一時使用目的賃貸借(借地借家法40条)
住居や事務所利用以外の、明確な短期利用目的がある契約。
→ 一時的であれば、処分性が低く、管理行為と評価されやすい。
これらの例外は実務的に非常に有用ですが、形式や契約書の内容によっては処分行為とみなされる可能性もあるため、契約書の設計段階から専門家の関与が不可欠です。
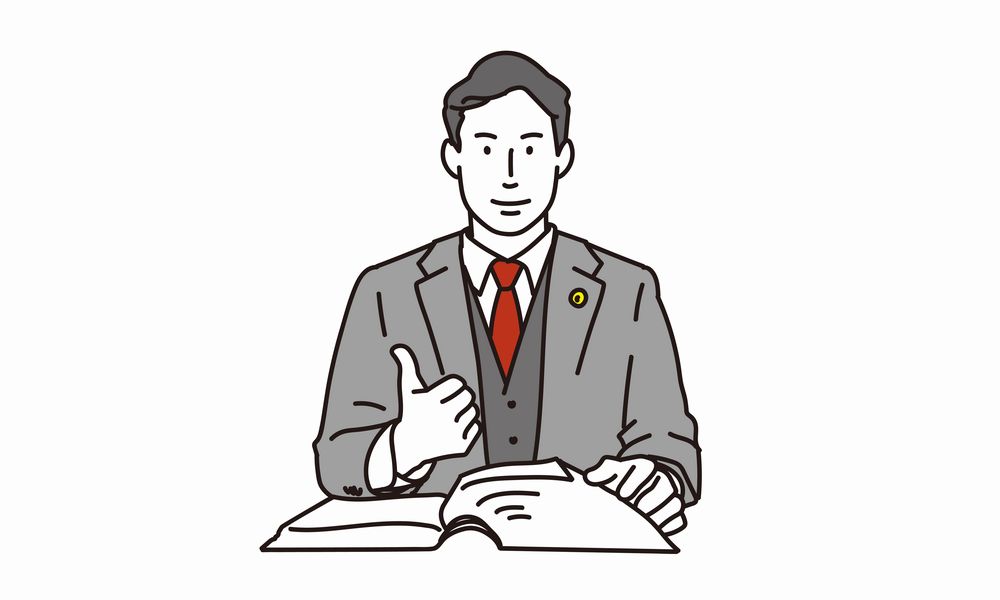
不動産の賃貸や利用許可について、「短期間だし、収益もないから大丈夫」と思い込みで進めることは禁物です。共有状態にある不動産では、自分の判断だけで契約することが他の相続人の権利を侵害するリスクを常に伴います。
契約期間、内容、法的性質を慎重に見極めたうえで、全員の同意が必要かどうかを判断し、必要に応じて遺産分割や共有解消の手続も視野に入れて動くことが重要です。
共有状態を整理・解消するための対処法
相続によって不動産を共有している状態では、「売却したい」「自分の持分を整理したい」と考えても、全員の合意が得られなければ動き出すことができません。特に、共有者の中に所在不明者がいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、実務的な対応が必要となります。
本章では、そうした状況への対処法や、共有関係を整理するための選択肢について具体的に解説します。
所在等不明共有者への対応
前章で触れたとおり、令和3年の民法改正により、所在等不明共有者がいる場合に不動産の処分が可能となる制度が整備されました。民法262条の3に基づくこの制度では、他の共有者が裁判所に申し立てることで、所在不明者の持分を含めた不動産の売却が可能となります。
この手続では、以下のような流れが一般的です。
- 1所在不明者の調査と疎明(戸籍・住民票等)
- 2裁判所への申立て
- 3公告期間(異議申立期間)の経過
- 4裁判所による譲渡権限付与の決定
- 5売却と同時に代金相当額の供託
この「供託」とは、所在不明者に代わって売却代金相当額を法務局等に預けておく制度です。これにより、将来その者が現れたときに権利を主張できるよう、実質的な保護がなされる仕組みになっています。
なお、相続不動産(=遺産共有状態)でこの制度を使う場合は、相続開始から10年が経過している必要があります(民法262条の3第2項)。そのため、10年未満の場合には、次に紹介する「不在者財産管理人」の制度などを検討する必要があります。
不在者財産管理人を選任すべき場合
相続人の中に「生きてはいるが連絡が取れない」「居所が不明である」といった者がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任するという方法もあります(民法25条以下)。
不在者財産管理人は、所在不明者に代わってその財産を管理・処分する法的権限を与えられた者であり、以下のような手続が可能になります。
- 遺産分割協議への参加・同意
- 不動産売却への承認申請
- 管理費・税金の支払い代行
ただし、管理人は「不在者本人の利益を守る」立場であり、自由に売却や処分ができるわけではありません。
たとえば、不動産の売却を進める場合には、家庭裁判所の「処分許可」を別途得る必要があり、手続の負担や費用(報酬や供託金など)も考慮しなければなりません。
そのため、所在等不明者がいるが相続開始から10年が経過していないというケースでは、有力な手段として検討されます。
共有物分割請求・共有持分の買取・信託の活用等の代替手段
共有関係を解消したい、あるいは不動産を自分の判断で活用できるようにしたいという場合には、以下のような方法も選択肢となります。
① 共有物分割請求(民法258条)
共有状態が続き、協議での解決が困難な場合には、家庭裁判所に共有物分割訴訟を提起することができます。裁判所は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかの方法で判決を下し、共有関係を強制的に解消することが可能です。
② 他の共有者から持分を買い取る/売却する
共有状態のままでは柔軟な運用ができないため、他の相続人の持分を買い取って単独所有にすることも現実的な選択肢です。逆に、自分の持分を第三者に売却することも可能ですが、トラブルの種になることもあるため注意が必要です。
なお、最近は「共有持分の買取専門業者」も存在しますが、買い叩かれたり、後に紛争化したりするリスクもあるため、事前に弁護士への相談が推奨されます。弊所でも多数この手のトラブルについて扱ってきましたが、後日、訴訟において権利濫用を理由に売却行為の無効を主張し、認められた事例が存在します。
③ 家族信託(民事信託)を活用する
複数の相続人で不動産を運用しながらも、管理・処分の権限を一人の信託受託者に集中させる方法です。特に高齢者の相続人がいる場合や、不動産の収益化を円滑に進めたい場合に活用されます。
契約によって自由に設計できる反面、税務上や登記上の手続が複雑な場合があるため、専門家(弁護士・司法書士・税理士等)の関与が不可欠です。
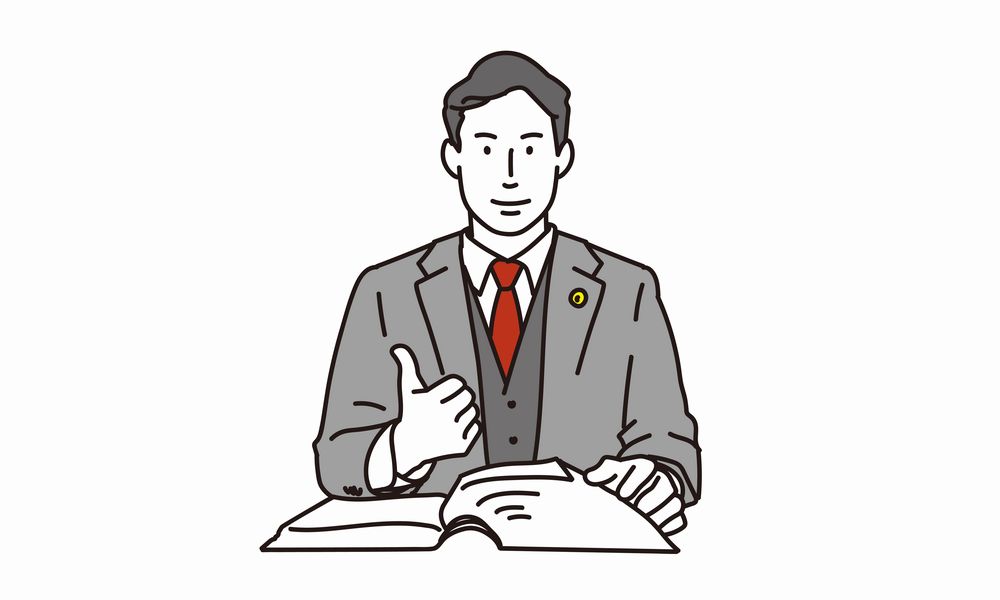
共有不動産に関する問題の多くは、「何も動けないまま年数が経ってしまった」ことに起因します。放置すればするほど、他の相続人が亡くなってさらに相続人が増え、関係が複雑化していきます。
「所在不明者がいる」「話がまとまらない」「名義が放置されたまま」といった場合には、自分が主体となって法的手段を講じることが共有解消の第一歩です。
それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあり、個別の事情によって最適な手段は異なります。まずは専門家に相談し、「動かすべきか」「待つべきか」を一緒に判断していくことをお勧めします。
トラブルを未然に防ぐためのポイント
不動産を含む相続には、法的な手続きの複雑さに加え、相続人間の感情的な対立という大きなリスクが潜んでいます。こうしたトラブルを防ぐためには、「争いになってから対応する」のではなく、「争いになる前に備える」ことが最も重要です。
この章では、相続不動産にまつわる問題を未然に防ぐための3つの実践的ポイントをご紹介します。
生前の不動産対策(遺言・信託など)
相続トラブルを避けるうえで最も有効なのが、被相続人の生前対策です。とくに不動産のように分割が難しい資産については、遺言書や家族信託を活用して、あらかじめ誰にどのように引き継がせるのかを明確にしておくことが有効です。
- 遺言書の活用
自筆証書遺言や公正証書遺言により、「不動産は長男に相続させ、代償金を他の相続人に支払わせる」などの具体的な分配内容を記載しておけば、相続人間の争いを大幅に抑制できます。
- 家族信託(民事信託)の活用
高齢になった親が認知症になる前に、不動産の管理・処分権限を子に託すことができます。信託契約によって、誰が管理し、誰に利益を分配するのかを柔軟に設計できる点が大きな特徴です。
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続が発生すると状況は一変します。法的効力を持つ書面による意思表示が、最も確実な予防策です。
相続開始後、早期に不動産の方針を合意形成する重要性
相続が発生した後、遺産分割協議をせずに不動産を「共有状態」のままにしておくと、年月が経つほど協議が困難になる傾向があります。
- 共有者の1人が死亡し、さらに相続人が増える
- 利用状況や費用負担に差が生じ、不満が蓄積する
- 時間の経過で感情的な対立が深まる
こうした事態を避けるためには、相続開始後なるべく早い段階で「この不動産をどうするか」を全員で話し合うことが重要です。売却、賃貸、共有継続など、いずれの方針を取るにしても、早期の合意形成がトラブル防止の鍵となります。
相続人間で話し合いが難しいときは、早めの専門家介入を
「話し合いをしようとしても感情的になってしまう」「特定の相続人が非協力的で進まない」そんなときこそ、法律の専門家である弁護士の介入が効果的です。
弁護士が入ることで、以下のようなメリットがあります。
- 法的根拠に基づく冷静な説明が可能になる
- 公平な第三者として全員と対話できる
- 必要に応じて、調停・審判・訴訟へのスムーズな移行ができる
また、弁護士を窓口にすることで、感情的な対立が激化する前に話し合いをまとめるチャンスが生まれます。話し合いができなくなってからでは選択肢が狭まり、時間も費用も余計にかかってしまうため、「こじれる前に専門家へ」が大原則です。
相続不動産は「財産」であると同時に、「思い出」や「こだわり」が絡むため、感情的対立が起こりやすい分野です。しかし、争いによって放置され続けた結果、不動産の価値が下がり、税負担だけが残るという事態は本末転倒です。
資産を守り、活かすためには、法的な整理と人間関係の調整をバランスよく進める必要があります。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
相続不動産の処分は「法」と「人」のバランスがカギです。民法の知識や手続の選択肢を理解しつつ、それをどう実際の家族関係に適用するかは、法律の問題であると同時に「人の問題」でもあります。
- 書面を残すことで相手の不信感を防ぐ
- 弁護士を間に入れることで感情を冷却する
- 制度を正しく使って公平に進める
こうした工夫の積み重ねが、相続不動産を「争続」にしない最大のポイントです。問題が生じてから対処するのではなく、早めに備え、早めに動くことが、相続の成功の秘訣といえるでしょう。
直法律事務所では、相続不動産の管理・賃貸・分配に関する法的サポートはもちろん、相続全般に関するご相談を随時承っております。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで