
columns
弁護士コラム
共有物分割請求とは?流れやデメリット・注意点を解説
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2025年02月14日 |
最終更新日:2025年11月13日

- Q
-
亡き父名義の実家が、現在は母と弟と私の共有になり、維持管理費の負担や老朽化への対応で意見が合わず困っています。
弟は改修費用の負担を渋っており、将来的にどう扱うべきか決めきれません。母はまだ意思ははっきりしていますが、要介護で施設に入り、築50年の家を放置するのも心配です。
話し合いで解決したい一方で、共有物分割請求も視野に入れるべきか悩みます。具体的な手順や費用、法的手段に進む場合のリスクはどのように把握すればよいのでしょうか?また、母が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
- Answer
-
共有名義の不動産は、共有者全員が協力して管理する必要がありますが、意見の対立がある場合は解決が難しいことがあります。建物を維持するために修繕するような場合、保存行為として各共有者が単独で行うことができ、かかった費用について、各共有者はその持分に応じて負担することになります。しかし、不動産の価値を増加させるような改修をする場合、管理行為に該当し、共有者の持分価格の過半数の同意が必要になります。
不動産の管理・処分方法について弟との話し合いで意見が一致しない場合、共有物の管理・処分を適切に行うために共有物分割請求を検討するのは有効な手段の一つです。 これは話し合いや、場合によっては裁判所での判決をもとにして、共有状態を解消する方法です。不動産を売却し代金を分割する方法や、どちらかが相手の持分に相当する金額を支払い、単独所有にする方法があります。ただし、これには費用や手間がかかり、また親族間の関係悪化のリスクも伴うため慎重な判断が必要です。法的手段に進む前に専門家への相談をおすすめします。
共有物分割を行う前に母が亡くなった場合には、現在共有している母親の持分が遺産となり、遺産分割協議が成立するまで当該持分を相続分に従って共有する状態(遺産共有)となります。このような遺産共有の状態でも共有物分割訴訟を提起することができます。この方法では遺産共有状態の共有財産の分割は行われるものの、遺産共有状態自体は共有物分割訴訟で解決することができないため、遺産共有状態は依然として残ることに注意が必要です。
例えば、共有物分割訴訟において他の共有者が共有物を取得し、母親の持分権者(相続人ら)はその共有者から賠償金を受け取るという解決になった場合、この賠償金が遺産となり、遺産共有状態であるため遺産分割が必要となります。
この記事では、共有物分割請求がどのようなものなのか、共有物分割請求のメリットとデメリットや実際に手続きに必要な費用や期間についてわかりやすく解説します。
共有不動産の活用方法で意見が食い違い、前に進めないという状態に直面している方や、共有物分割請求の内容証明郵便が届き、不安を抱えている方にも最適です。共有物分割請求に関するトラブルの解決に役立つ情報をお届けします。

監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦
目次
共有物分割請求とは

共有物分割請求とは、土地や不動産などの共有財産の共有者の一人が、他の共有者に対して共有状態の解消を求めることです。分割請求の法的根拠は民法256条本文であり、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」とあります。
参考:e-GOV法令検索|第二百五十六条
この請求には法的拘束力があるため、共有解消に向けて対応することが必要となります。ここでは、共有物請求の目的や、実際に必要となるケースについて解説します。
共有物分割の必要性と目的
共有は、複数人が共同で一つの物を所有している状態をいいます。共有者には共有物への権利が与えられると同時に、その権利に対する制限も受けます。
例えば、共有者は共有不動産の全体について、共有持分に応じて使用する権利を持ちますが、不動産の取り壊しや売却には共有者全員の同意が必要となります。そのため、取り壊しや売却をめぐって共有者の間でトラブルが生じることがあります。また、共有物の管理にも共有者間の合意が必要となるため、思うように不動産を活用できなくなることがあります。
そのため、共有物分割によって共有状態を解消することで、売却などの意思決定に関するトラブルを防ぎ、管理の効率化を図ることができます。
共有物分割請求が必要となるケース
ここでは、実際に共有物分割が必要となるケースを紹介します。
まず、相続によって共有状態が発生する事例です。
例えば、父親名義の自宅の土地建物があり、父親の死後、母、長男、長女の三人でその土地と建物を相続し、母がこの自宅建物に一人暮らしするというケースを考えましょう。このとき、自宅の土地建物は母、長男、長女の三人の共有物になっています。相続の時点で遺産分割協議を行い、土地も建物も単独所有としておけばよいのですが、何らかの事情で共有状態で遺産分割協議を成立させることもあります。そのような場合、共有物分割請求を行い、自宅に住み続ける母が不動産を取得することで、不要なトラブルを防ぐことができるでしょう。(ただし、母が高齢の場合には、次の相続も考慮にいれて検討する必要がある点、注意が必要です。)
ほかにも、不動産を共同購入したのち、権利関係を整理する事例が考えられます。
例えば、友人二人が資金を出し合い、マンションの一室を共同購入した事例を考えましょう。その後、片方が海外転勤を理由に売却したいと考えたものの、もう一方が売却に同意しないという状況が発生したとします。このマンションの一室は二人の共有状態になっているため、売却には二人の同意が必要となり、このままではトラブルは避けられません。ここで、共有物分割請求を行うことで、マンションに対する権利を整理し、処分方法を決定することができます。
また、共有者の間で利用方法の対立が起こることも考えられます。ある不動産を二人が共有していて、一人はこの不動産を賃貸として貸し出そうと考える一方で、もう一人は自分の居住用に使いたいと考えている場合、この共有不動産の使用目的を決定することができません。この場合でも、共有物分割請求を行うことで、単独の所有者となった者が使用目的を決定できるようになるため、不動産を有効活用できるようになります。
共有物分割請求のメリット・デメリット
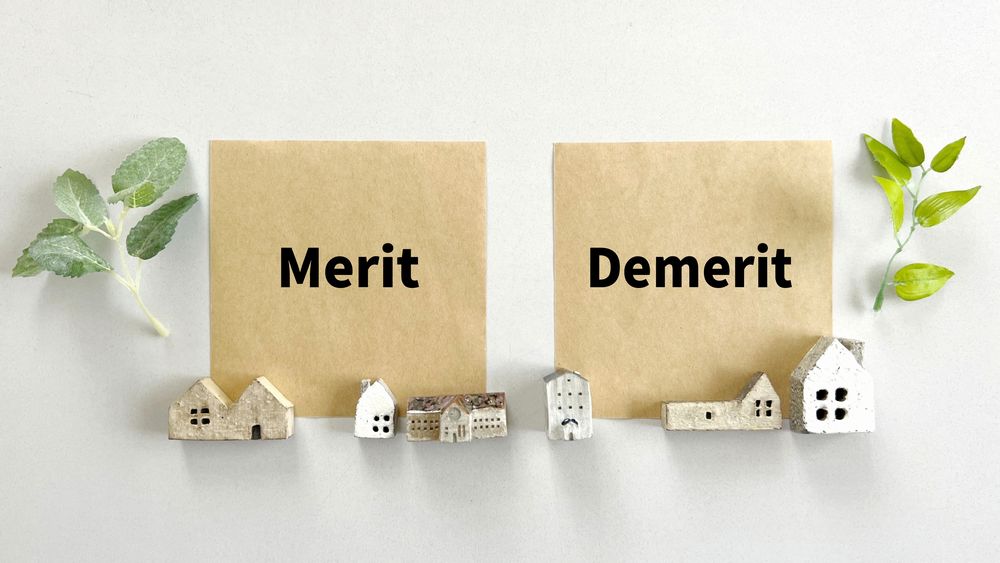
共有状態の解消は、単独所有になることでさまざまなメリットがあります。一方で、時間や費用、人間関係の面でデメリットが生じてしまう懸念もあります。
ここでは、共有物分割請求を行う上での判断材料を検討していきます。
メリット|共有状態の解消と紛争解決
共有状態の解消により、不動産の活用がしやすくなるというメリットがありますが、そのほかにも大きなメリットがあります。
以下では、適正価格で現金化が可能なこと、司法による解決が望めることの二点について解説します。
適正価格での現金化が可能
共有物分割請求で共有状態を解消しようとする場合、現物分割や売却・競売などによって換価して得た金銭を分けるといった方法が規定されていますが、単独所有者となる者が他の共有者の持分に相当する金額を代償金として支払う形(全面的価格賠償)によることが多いです。
この全面的価格賠償による解決を目指す場合、当事者間で共有物の評価額の見解が一致しなければ、鑑定人による評価を受けることもあります。共有物分割請求訴訟となっている場合、裁判所は、中立の不動産鑑定士等を鑑定人として選任して中立な立場で評価額を算定させ、鑑定書を裁判所に提出させることができ、裁判所はこれをもとにして独自に適正な金額を定めることができます。
法的手段による解決が可能
共有物分割請求は、民法256条に定められた手続きであり、当事者間での交渉による共有物分割が難しい場合には、裁判所に調停委員立ち合いのもとで行われる共有物分割調停を申し立てることができ、共有者全員が合意すれば成立します。ただ、実務ではこの手続きを利用することはあまりないようです。
また、調停における話し合いでもまとまる見込みがない場合、共有物分割請求訴訟を行うことができます。この訴訟は、裁判所に共有状態の解消方法を決めてもらうための裁判であり、判決には法的拘束力があります。このように、裁判所を利用するなどの法的手段によって共有状態を解消することができます。
デメリット|時間や人間関係への影響
共有物分割請求はメリットばかりではありません。共有物分割請求を行う場合、デメリットも含めて検討することが大切です。
ここでは、共有物分割請求のデメリットを3つ解説します。
手続きの長期化
共有物分割請求から共有状態の解消にいたるまで、スムーズに合意形成を行うことができれば、時間はそれほどかかりません。しかし、共有物分割訴訟まで進むことになると、判決が出るまでには相応の時間がかかります。
訴訟の判決が出るまでに、複数回にわたって口頭弁論が行われます。口頭弁論期日では、訴訟を提起した原告の主張や、相手方となる被告の主張が交互に行われます。主張や立証の準備の必要もあるため、口頭弁論期日は、おおよそ一か月ごとに行われます。そのため、判決による解決までは時間がかかるのです。状況によって異なりますが、半年から一年程度、それ以上の時間を要することもあります。
希望通りの判決にならない可能性
共有物分割請求訴訟を行っても、希望通りの判決にならない可能性があることにも注意が必要です。
例えば、ある不動産をめぐり、共有者の一人が不動産を単独所有したいと考えて共有物分割請求を行ったとしましょう。訴訟の末、「不動産を売却した金額を共有者で分けるものとする」という判決が出た場合、この共有者は不動産を単独で所有したかったのにもかかわらず、手放さなくてはならなくなります。このように、希望の判決が出ない可能性にも注意を払うべきでしょう。
共有者間の関係悪化の可能性
訴訟は法的な手続きであり、全員が訴訟の結果に納得していなかったとしても、その結果に従わなくてはなりません。そのため、共有者同士で不満が残ることや、険悪な空気になり今後の関係が悪化することも考えられます。状況にもよりますが、できるだけ話し合いによって解決することが望ましいです。
共有物分割請求の手続きと流れ

ここでは、共有物分割請求の開始から解決まで、プロセスの全体像を解説します。
共有物分割請求(協議の開始)
共有物分割を請求するには、他の共有者の全員に対して分割すべき旨の意思表示をすれば足ります。この意思表示をすることによって、他の共有者は分割の方法について協議し、分割を実行すべき義務を負うことになります。この共有物分割の意思表示は、口頭でも可能です。ただ、争いがある場合や、他の共有者がなかなか協議に応じてくれないであろう場合には、内容証明郵便などを用いて書面で通知することが多いです。
はじめは、共有している当事者同士での話し合いから始まると考えられます。例えば、長男と長女で二分の一ずつの共有となっている土地の共有状態を解消する場合に、長男が長女に土地の半額分の金銭を支払う代わりに長女の持っている土地の名義を長男へ変えることを提案するなどです。共有者間の関係性がよく、かつ提案した対価が十分なものであれば、協議はうまくいく可能性が高いでしょう。
一方、土地の使い道について対立がある場合、提案内容が一方的である場合などでは交渉が決裂する可能性が高まります。争いが予見される場合には、話し合いの前にあらかじめ弁護士に相談して、話し合いの方向性を決めておくと良いでしょう。
共有物分割調停の申し立て
共有物分割調停とは、調停委員の立会いのもと、裁判所で共有物分割へ向けて話し合いを行うことです。調停委員が当事者双方から話しを聞いて手続きを進めていくので、当事者同士が顔を突き合わせて意見しあう必要はありませんが、あくまで当事者間での話し合いであり、当事者間での合意ができなければ成立しません。
共有物分割調停では、まず申立書が必要です。また、実務上の取扱いとして、申立書(正本)と、その申立書の写し(副本)を相手方の人数分用意して提出します。その後、裁判所で調停委員の立ち合いのもと話し合いを行い、話し合いがまとまれば調停成立となり、調停調書が作成されます。
共有物分割請求には、調停前置主義は採用されていないため、訴訟提起前に共有物分割調停を経ることは必須ではありません。そのため、いきなり共有物分割訴訟を起こすことも可能です。共有者間の意見の食い違いが大きく、合意が難しい状況の場合、いきなり訴訟を提起した方がよいケースも多いです。
共有物分割訴訟の提起
共有者間で協議が調わない場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起します。裁判所に共有物分割訴訟を提起する際の必要書類は、「訴状の正本および副本」、「収入印紙」、「郵券代」、「当該不動産の固定資産評価証明書」、「当該不動産の全部事項証明書」になります。
この後、被告に対する訴状の送達、呼出状の送付が行われ、第1回口頭弁論期日に向けた準備を行うことになります。口頭弁論期日や弁論準備手続期日は、裁判所が判決を言い渡せるだけの審理が尽くされたと裁判所が判断するまで、約一か月ごとに繰り返されます。判決が確定した後は、判決に従わない共有者に対して強制執行などをすることが可能になり、判決の内容を実現することができます。
共有物分割の方法
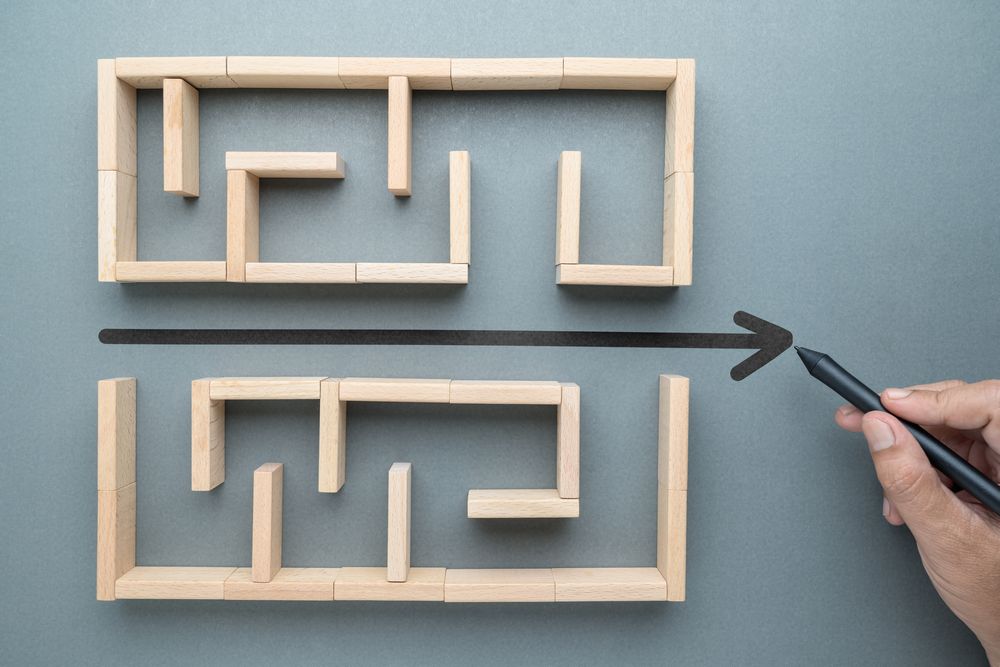
共有物を分割する方法は主に以下の3つがあり、裁判所がケースごとにいずれかの方法を選択します。
3つの方法は以下の通りです。
- 現物分割:共有している物を物理的に分割して共有者が単独所有できるようにする方法
- 代金分割:共有している物を売却して得られた代金を共有者で分配する方法
- 代償分割:共有者の1人が共有している物を取得し、その代わりに他の共有者に代償金を支払う方法
では、それぞれの分割方法の詳細について解説します。
現物分割|物を物理的に分割
現物分割は、物を物理的に分割し、各共有者が単独で所有できる状態にする方法です。
| メリット | デメリット |
| ・各自が単独所有可能 ・物の継続利用可能 ・税負担が少ない | ・不動産の場合は分筆費用が発生 ・分割後の価値低下の可能性 ・物理的制約がある |
【現物分割が適している主なケース】
- 土地面積が広く分割が容易な場合
- 各共有者が継続利用を希望する場合
- 建物がない更地の場合
現物分割は、共有者が引き続き当該物を利用したい場合に特に有効です。ただし、物理的な制約や分割後の価値低下のリスクを十分に考慮する必要があります。
代金分割(換価分割)|売却して代金を分配
代金分割(換価分割)は、物を売却し、その代金を共有者間で分配する方法です。
| メリット | デメリット |
| ・共有者間で公平な金銭分配が可能 ・手続きが比較的単純 ・清算が明確 | ・物件を手放す必要がある ・売却までに時間がかかる ・競売の場合は価格が低下 |
【代金分割が適している主なケース】
- 共有者全員が換価を希望する場合
- 物理的分割が困難な場合
- 共有者間で金銭的解決を望む場合
代金分割は、不動産を所有することを重視せず、現金化を優先する場合に適しています。非常にシンプルな分割方法ですが、不動産を手放すことになってしまうことに注意しましょう。また、販売方法が競売の場合、価格が低下する懸念があります。
代償分割(価格賠償)|共有者の1人が所有権を取得
代償分割(価格賠償)は、共有者の1人が物の所有権を取得し、他の共有者に代償金を支払う方法です。
| メリット | デメリット |
| ・物の一体性が保持される ・権利関係が明確になる ・迅速な解決が可能 | ・高額な代償金が必要 ・物を単独取得する共有者は資金調達が必要 ・価格算定で争いの可能性 |
【代償分割が適している主なケース】
- 特定の共有者に取得意思と資力がある場合
- 建物が存在し現物分割が困難な場合
- 共有者間の合意が得られやすい場合
代償分割は、共有者のうちの一人が不動産を保持し、他の共有者への金銭的解決を望む場合に最適です。ただし、代償金の額について共有者間で合意が得られることが前提となります。
共有物分割請求にまつわる費用と期間

共有物分割請求を進めるうえでは、手続きに必要な費用やかかる期間について理解しておくことが大切です。
ここでは、それぞれのポイントをわかりやすく説明します。
費用|弁護士費用、裁判費用など
共有物分割請求に必要な費用には、主に次のようなものがあります。
- 弁護士費用
弁護士に事件を依頼した場合に必要となる費用として、事件を依頼した段階で支払う着手金や事件が成功に終わった場合に支払う成功報酬のほか、実費、日当、手数料などがあります。着手金や報酬金は、弁護士が依頼者のために活動した結果、依頼者が得た経済的な利益を基準に算定されることが多いため、一概にこのくらい、という目安を提示することができません。そのため、無料相談などを利用して、具体的な内容の相談をした上で、見積をもらって金額を確認するようにしましょう。
- 裁判費用
裁判の手数料として訴状に印紙を貼付する必要があり、その代金や相手方に訴状の写し(副本)を郵送するための郵券の代金などが必要となります。印紙代は訴額を元に算定され、不動産の共有物分割請求訴訟の訴額は、建物であれば固定資産税評価額×持分割合×1/3、土地であれば固定資産税評価額×持分割合×1/6で計算されます。このように算定された訴額を基準に、手数料早見表などを参照して印紙代を算定できます。また、郵券は被告の人数にもよりますので、裁判所に直接確認して計算してもらいましょう。
- 鑑定費用
不動産の価値を専門家に評価してもらうための費用で、不動産により、また、鑑定士により異なります。さらに、裁判での不動産鑑定費用は、より厳密な鑑定が必要とされるため、高額になることが多いです。
これらの費用は、具体的な状況や依頼内容によって異なるため、法律事務所の無料相談の際に、鑑定や裁判となった場合の費用についても、具体的に確認するとよいでしょう。
期間|調停・訴訟にかかる時間
共有物分割請求にかかる期間は、選択する手続きや状況によって異なります。大きく分けて調停手続きと訴訟手続きの2つの方法があります。
調停手続きは、裁判所で調停委員を交えた話し合いによって解決を目指す方法です。一般的には6ヶ月から1年程度の期間を要しますが、共有者間で早期に合意が得られた場合には、より短期間での解決も可能です。
訴訟手続きについては、調停が不成立となった場合や、最初から訴訟を選択する場合に取られる方法です。この場合、通常1年から2年程度の期間が必要となります。
なお、訴訟手続を進めるうちに、裁判所の心証が開示されるなどして、勝てないと感じた当事者が妥協をすることで和解が成立することもあります。このような場合には、早期解決が実現します。
共有物分割請求に関するよくある質問

共有物分割請求について、多くの方が疑問や不安を抱えています。
ここでは、特に相談が多い質問について解説していきます。
内容証明郵便が届いたらどうすれば良い?
共有物分割請求をする場合、共有者全員に内容証明郵便を送付して協議の申し入れを行うのが一般的です。内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に・どういう内容の文書を送付したのかを証明できる郵便で、協議を行うための申し入れをしたという証拠として残すことができます。
共有物分割請求は法的強制力があるため、他の共有者は共有物の解消に向けて対応しなければなりません。そのため、内容証明郵便を受け取った場合、慌てずにその内容をしっかり確認し、共有物分割の協議に向けて準備を行いましょう。必要に応じて弁護士や専門家に相談することも考えておくとよいでしょう。
マンションなどの区分所有建物でも共有物分割請求はできる?
マンションなどの区分所有建物で共有物分割を行うことができるかどうかということについて、実は統一的な見解はありません。マンションなどの区分所有建物では、専有部分と敷地利用権が一体となり、原則としてこれらの分離処分が禁止されるという法的な制限があります。敷地だけの共有物分割は分離処分に当たるため、区分所有建物の共有物分割は禁止するという見方があります。
一方、敷地の共有物分割は分離処分に当たらないと考え、土地を実際に分割する現物分割を適用した判例もあります。しかし、敷地の共有物分割は現実的な支障を生むことがほとんどであると考えられるため、否定されることが多いでしょう。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
この記事では、共有物分割請求に関する基礎知識やメリット・デメリット、具体的な手続きの流れについて詳しく解説しました。共有不動産の管理や分割に関しては、共有者間の意見の相違や手続きの複雑さが問題となることが少なくありません。適切な解決を目指すためには、専門知識を持った弁護士などの専門家に相談することが重要です。
直法律事務所では、共有物分割請求を含む遺産相続問題に特化した弁護士が親身に対応いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス





 メールで
メールで