
columns
弁護士コラム
相続の「熟慮期間」とは?熟慮期間に行うべき4つのことと開始タイミングの考え方
- 相続放棄
- 投稿日:2022年07月21日 |
最終更新日:2024年03月14日
- Q
- 相続には「熟慮期間」があると聞きました。熟慮期間とは、何をする期間でどれくらいの期間を指すのでしょうか?
- Answer
-
「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月間を、「熟慮期間」といいます。
したがって知らないうちに相続人になっているということはありませんので、安心してください。しかし、この熟慮期間中にしっかりと相続の方法を判断する必要があります。
目次
「熟慮期間」とは
相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類から1つを選ぶ
相続の方法には、「単純承認」「限定承認」そして「相続放棄」の3種類の選択肢があります。
「単純承認」とは、プラスの財産・マイナスの財産全てを相続する方法です。自己のために相続があったことを知ってから、相続方法を選択しないまま3ヶ月が経過すると、自動的に相続人は単純承認を選んだことになります。
「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い人にとってはこの限定承認を申請することが多いでしょう。また、限定承認を選択する場合、相続人全員での申請が必要です。
「相続放棄」とは、プラスの財産・マイナスの財産全ての相続権を放棄する方法です。相続放棄を選択すると、元から相続人ではなかったと判断されます。また、限定承認とは異なり相続人全員ではなく単独でも申請が可能です。
熟慮期間は相続方法を選び手続きをするための期間
何もせず熟慮期間が過ぎた場合は単純承認をしたとみなされる
上述の通り、相続人である事を知りながら3ヶ月間放置した場合は単純承認を認めたことになり、限定承認や相続放棄をすることは認められません。したがって熟慮期間中に相続方法を選ぶ必要があります。
熟慮期間は原則3ヶ月
相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)、すなわち被相続人が亡くなったことおよび自分が相続人であることを知った時から、3ヶ月以内に単純承認、限定承認または相続放棄のうちどれを選択するか決定し、家庭裁判所でその旨を申述しなければなりません。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間中に行うべき4つのこと
相続人の確認
熟慮期間中に行うべきことの1つ目は、「相続人の確認」です。
自分が実は相続人であった場合や、自分が思っていたよりも多くの人が相続人であった場合、財産分与でトラブルが生じる可能性があるため、相続人の確認は必要です。被相続人が亡くなる前や亡くなった時点での確認も重要ですが、亡くなった後の確認も重要です。なぜなら、相続放棄を選択する人が出てくる可能性もあるからです。
相続財産の調査
熟慮期間中に行うべきことの2つ目は、「相続財産の調査」です。
被相続人のプラスの財産やマイナスの財産が明確になっていれば問題はありませんが、把握できていない被相続人の財産があると問題が生じやすくなります。
たとえば、自分が知らないだけで被相続人が実はマイナスの財産を持っているような場合や、被相続人が価値のない土地を持っており、それを相続すれば管理費や維持費に多額のお金を支払う必要が生じる場合などが考えられます。
したがって、被相続人の財産状況を調査するのは大変重要なことです。調査で被相続人の財産状況を把握した上で、単純承認、限定承認または相続放棄の選択を熟慮期間中に行いましょう。そうすることで、自分の財産を守る事にも繋がります。
他の相続人との協議・調整
熟慮期間中に行うべきことの3つ目は、「他の相続人との協議・調整」です。
上記で述べた3つの相続方法のうち、限定承認を選択する場合は、独断で進めることはできません。相続人全員で申請する必要があるため、他の相続人との協議・調整が必要です。また、どのような相続方法を選択するにしても、相続を原因に揉めることが多いため、相続人間の関係を守るためにも、協議、調整をすることをおすすめします。
(相続放棄・限定承認をする場合)家庭裁判所に申述する
相続放棄または限定承認をする場合のみ、家庭裁判所に申述する必要があります。
家庭裁判所に申述をしないままでいると、相続放棄・限定承認を選択したいと考えていても、単純承認を希望したとみなされます。したがって、相続放棄または限定承認をしたい場合は必ず熟慮期間中に申述しましょう。
熟慮期間はいつから始まる?
被相続人が死亡した事実および自分が相続人であることを知ったとき
被相続人が亡くなった事実を知り、且つ自分が相続人であることを知った日の翌日から、熟慮期間が始まります。なお、翌日から起算されるのは、民法140条の原則どおり、熟慮期間の計算においても初日はカウントされないからです。
熟慮期間のカウントの具体例
例えば、他の相続人などから、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になっていることを知らせる内容の通知書が届いた場合、通知書を受領した翌日から、3ヶ月の期間が熟慮期間としてカウントされます。
配偶者や子供の場合、自分が相続人ではないと誤信することはまずありえないので、通常、被相続人が死亡した事実を知れば、同時に自分が相続人であることを知ります。そのため、熟慮期間は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から3ヶ月間となります。例えば、もし被相続人が亡くなったことを知った日が4月26日であった場合、その翌日の4月27日が起算点となり、7月26日までが熟慮期間となります。
第2順位の直系尊属(父母・祖父母など)や、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合で、先順位の相続人がいると誤信していたような場合、その誤信に気づいたとき、すなわち先順位者が存在せず、相続権が自分にある事を知った日の翌日から3ヶ月間が熟慮期間となります(仙台高裁昭和59年11月9日)。
熟慮期間の起算点を繰り下げることができる場合
繰り下げができる場合
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月が経過していても、①相続財産が全くないと信じ、②相続財産が全くないと信じる相当の理由があり、③相続財産有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識できる時が起算点となるとした判例があります。
この他にも、プラスの財産があるとは知っていたが、遺言や遺産分割協議により取得すべき遺産がないと信じた場合や、相続債務の存在は知っていたが、他の親族が返済すると信じていたような場合など、熟慮期間の起算点を繰り下げた裁判例も少なからずあります。
ただし、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めなかった裁判例もあります。どのような場合に繰り下げが認められるかについてはケースバイケースですので、専門家に相談して調べておくと安心です。
最判昭和59・4・27の判旨
「…3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうるべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
①被相続人に相続財産が全くないことを信じた
②①について相当な理由があったと認められた
③相続財産の有無に関する調査を期待することが著しく困難だったという事情
これらを鑑みて、熟慮期間の起算点を繰り下げる(この場合では、「相続財産」の存在を知ったときを起算点とする)ことが認められました。
しかし、この判旨からもわかる通り、相続開始原因と自己が相続人になったことを知った時点において、相続財産の調査を相続人に期待することが著しく困難だったとも言えない場合までも救済する趣旨ではないため、注意が必要です。最高裁判所の判例解説でも、この判例について、自己が相続人になったことを知らなかったということは、いわば熟慮前の問題であるため、期間の進行開始を否定すべきであるというのが確定判決の理由であるとすれば、相続の対象となるべき財産が皆無であると考え、またそう考えたことが客観的にみて相当であるような場合もまた熟慮以前の問題である、としています。言い換えれば、そのような状況でも、相続人に対してさらに相続の対象となる財産の有無を調査すべきことを要求することは、いささか非常識であり、相続人に対してあまりに酷であると認めたものであろう、としています。
一方で、一律に相続財産についての認識がない以上熟慮期間は進行しないという考え方によるべきものとすると、著しく法的安定性を害する恐れがあります。また相続財産の調査を怠って相続財産がないものと決めつけ、熟慮期間の3ヶ月を無駄にした人まで救済の対象となってしまうので、救済の考え方を何らかの限定もつけずに採用することは妥当ではないとしています。
繰り下げた場合の新たな開始タイミングはいつになるのか
熟慮期間の繰り下げが認められた裁判例
熟慮期間の繰り下げが認められた裁判として、1つ例を紹介します。
東京高等裁判所、昭和61年11月27日判夕645号198貢
概要:
元不動産業者の被相続人Aは、取引主任者の資格を活かして不動産業者Bに勤め、死亡する半年前まで働いていた。Aの相続開始後約10ヶ月後に、相続人である息子CとD(Cの妻、Aの養女)のもとに、Eから、死亡する約3年前にBが関与した不動産取引について、Aの取引主任者としての不法行為責任を相続人に言及する訴状の送達を受けたことから、直後に相続放棄の申述をし、受理された。
Eが提起した訴訟の中で、相続放棄の有効性が争われ、原審は放棄の有効性を認めたため、Eは控訴した。
問題となった事情:
Aは、Eとの取引当時85歳の高齢であり、一日に2.3時間事務所にいる程度の勤務であり、息子Cの所有家屋にCD夫婦と同居し、生活費もCに依存し時折小遣いを配偶者Dからもらっていた。
CDとAは普段は互いに仕事の話はせず、CはAが不動産屋へ行っていると聞いていたのみで、Bの名前を知ったのは、Aが死亡した後のことであった。
Aには死亡当時、預金その他の資産は全くなく、またCDらはAが債務を負担している事実を知らなかった。
判決の概要は以下の通りです。
相続人であるCDは、被相続人Aの相続開始の時から本件訴状の送達を受けるまでの間、相続財産が全くないと信じており、Aが死亡の前年まで不動産業者のもとで働いていたといえど、その勤務状況や年齢等からみて、自ら責任ある立場で不動産取引等に携わり、これに関連して債権を取得する、あるいは債務の存在の可能性をも調査することは相続人の落ち度ではないと考えられます。
したがって、このような相続人には相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続財産が存在しないと結論付けてしまうのに相当な理由があったと認め、熟慮期間は訴状送達の時から起算すべきであるとされました。
まとめ
熟慮期間の起算点と繰り下げの要件などについて述べてきましたが、例にあげた事例のように繰り下げできると判断されるとは限らず、知らなかっただけでは済まないようなこともあります。今一度自分の相続状況を見つめ直してみましょう。
相続対策はあらゆる人に必要です。相続の協議や調整などを被相続人が存命の時に行うのは失礼である、親不孝者だと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、将来的に残された人が不幸になる可能性をなくすためにも、相続について話し合うことは重要です。
ただ、協議が難しい状況も多々あるため、そのような時は専門家に相談することもおすすめします。
相続放棄についてお悩みの方へ
お悩みに対するアドバイスとともに、財産調査から必要書類の取り寄せ、
申立て手続きまで、プロの弁護士が一貫してサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。
 初回相談は
0
円
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください
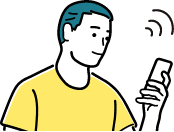
 事務所紹介
事務所紹介 アクセス
アクセス


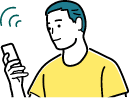


 メールで
メールで